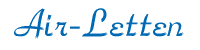
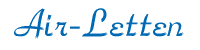
「あっ、あれは!」
思わず大声をあげ、ティータが怯えてミュラーに飛びついた。大声の元はそれ以上声を発することはなく、ただ水面を眺めている。
「あ!」
ティータも顔を上げてそちらをむけば、少年をしっかりと抱いているユリアが水面を漂ってきていた。
「ユリア大尉さーん!!」
また涙が流れてきそうになるのをこらえながらティータは手を振る。その声にユリアが反応し、手を振り返した。
「だいじょうぶ、ですかー!!」
大声を張り上げて少女が声をかけている。その横で、何かを言おうにも何もいえないミュラーがいた。
やがて点検の為作ってある水面への階段へたどり着き、少年を抱きかかえてユリアがゆっくりとあがってきた。
「トマスもこのとおり無事だ。早く親御さんのところへ連れて行こう」
滴る水を拭くまもなくユリアは関所への道をたどった。途中で後を追ってきた兵たちや親に出会った。
「トマス!!」
「大丈夫、水からあがった時に気が抜けて、気絶しているだけです」
父親にトマスを渡す。母親は涙を流してユリアに礼を言いつづけていた。
「当然のことをしたまでです、ご母堂。兵たちの救助が間に合わないと思ったら、勝手に体が動いていました」
「それでも、躊躇なく私たちの子どものために……ありがとう、ありがとう」
手を握って感極まった声を出す母親に少し困った表情をする。関所にいた人間のほとんどが自分の周りに集まってきていることに気がついた。助けを求めるようにティータとミュラーを探すがすぐ見つからない。騒ぎが大きくなってくれば自分を見知った人間が現れるかもしれない。そうなれば休暇が台無しになる。
「そこをどいてくれ!!」
後ろから男の声がした。兵や野次馬を掻き分けながらミュラーがユリアに近寄ってくる。
「……?」
首を傾げ、なんなのかを問おうとした瞬間に視界が閉ざされる。上から布をかぶせられていた。そのまま横抱きにされた。
「ミュラー殿!?」
「少し黙っていろ!」
よくわからないがその場から駆け出したらしい。どう走っているのか。せめて布を取ろうとするも、動くなと怒られる。仕方がないのでおとなしく男に抱きつくことにした。
「はあっ、はあっ、はあっ」
ようやく解放され、どこかに座らされる。布を取れば、肩で息をしている男が視界に入った。見回すと蒼いレンガ。
「……紺碧?」
「とにかく、あの場から、逃げたくなって。どこを、どう走ったかなど、俺もわからん」
「……多分、ルーアンの四輪の塔、紺碧でしょう」
「……とりあえず、その布で、体をふけ」
言われるままに濡れた部分をふき取る。服と髪だけはどうしようもない。
「なんで」
「え?」
「なんであんなことをしたんだ! 俺が飛び込んだって良かったではないか!」
「私では貴方と子どもの体重を支えることはできないですよ」
少し怯えた声で返す。
「貴方なら、私を支えてくれる。そう思ったから……」
「っ!」
自分を見上げる女の頭を力任せに懐に引き寄せた。
「俺を……信じてくれているのはいい。正直、悔しいくらい嬉しい。だが……もう無茶などしないでくれ!」
もごもごと腕の下で何かを言っているが聞き取りにくい。それより、ちゃんとユリアが生きていることを実感したい。
「……たい……す」
「お願いだ、お願いだから、俺の寿命を縮めるのはやめてくれ!」
ユリアの手がミュラーの体を激しく叩く。無視していたがあまりに酷く叩かれるので少し力を緩めた。
「っは!!」
真っ赤な顔をしたユリアが荒い息を吐いていた。
「痛い、です……息が……」
「す、すまん」
息を整え、顔を上げた。
「自分でも、治したいのです。とにかく体が動くこの性格を。……部下を持つようになってからは少しはましになったのですが……申し訳ありません……」
「貴女といると常に驚かされるが、今回は本当に洒落にならない。が……」
先ほどよりは力を緩めながら再び頭を引き寄せた。
「俺が傍にいない間はもっと無茶をしていそうだ。これは早急に、どんなことをしてもつれて帰るよう算段せねば、次に会う時は女神のお膝元、などということになりかねん」
「まさか。そこまで無謀では…………ないと思いたいです」
「いいや、もう信じないぞ。まったく、貴女という人は……」
「信じてください、気をつけます。貴方と共に生きたいから」
頭を締め付けていた力が抜けた。見上げると、怒っているとも嬉しそうともとれる表情でユリアを見ている。
「……今回だけだぞ」
「ありがとうございます」
微笑みながらミュラーの後ろになんとなく目をやると、大荷物でちょうど駆けてきたティータがあせりながら後ろ向きになるところだった。
「ティータ君、構わないよ」
ユリアの言葉にミュラーは慌てて振り向く。同じようにティータも振り向いた。
「えとえと、なんだか邪魔ばっかりしてるような気がして……」
「気にしなくていい。どうした、その荷物は」
「ユリア大尉さんたちの荷物です。探してたら水の跡がこっちに続いてきていたから……」
点々と続く水の跡をたどりながら、荷物を抱えてここまで来たのだ。
「ありがとう、ティータ君。先ほどの水門も」
「とんでもないです。あ、今まだすごい騒ぎですから、しばらく近寄らない方がいいと思いますよ」
「何でまたそんな騒ぎに」
「あの男の子、ユリア大尉さん探して大騒ぎなんです」
「おやおや……ユリア殿の崇拝者がまた増えたか……」
呆れ半分、笑い半分でミュラーが呟く。
「あははは。ミュラーさん、大変ですね」
「全くだ」
なにやら意気投合している。
「あの……そこで二人して私を責めないで欲しい……」
「あっ、そんなつもりじゃないです。それじゃ、そろそろわたし工房に戻りますね」
もっていた動力砲の調子を確かめる。人のいない方へ向けて試し撃ち。特に問題はない。
「良い休暇を過ごしてください!」
ぺこりと礼をして、来た時と同じように走っていった。ティータが置いていった荷物を取りユリアに渡す。
「ありがとうございます」
「……しばらくここにいるか。僅かだが、滝の音だろう? 最前から聞こえているあの音は」
「そうですね。そうか、ここからでも聞こえるのか……」
塔の中はどういう機構なのか水が流れているが、それとは違う遠い音がしているのに気がつく。
水泳にはまだ早かった。風が吹くと寒さを感じる。さきほど抱きしめられたおかげで落ちていた布を体に巻きつけた。
「……む」
ティータの登場で爆発し切れなかった感情が体にまだ少し残っている。下手に口を開けば何かろくでもないことになりそうだ。かといって、何も言わないのも不自然な気がする。どうしようかと考えていると、糸が切れたようにユリアが横たわった。
「どうした」
答えはない。深い眠りに落ちている。
「……水泳は、眠くなるものだが……しかし」
よくもまあ、親衛隊中隊長ともあろう人間が、外で無防備な寝顔を見せられるものだ、と心底思う。しばらくその寝顔を眺めているうち、ようやく波立った感情が落ち着いてきた。
あたりに柔らかい音が響く。エサを探していた獣が耳を動かし、そしてまたエサ探しに戻る。塔の入り口でミュラーは笛を吹いていた。上手く言葉に乗せられない感情を音に乗せ。眠るユリアの隣で、柔らかくかなで続ける。
あなたが そらを いくなら
わたしは つばさに なりたい
どんなに つよいかぜにも
けっしておれない しなやかなはね
いつか きっと もつから……
一心不乱に吹いていると、歌がそこに加わった。吹きながら様子をみれば、ユリアがまだ半分寝ているような表情でたどたどしく歌っている。
「……知っていたのか、この曲」
一通り吹いてから声をかける。
「……ついこの間、あのパーティーの時……オリビエ殿が教えてくれました……」
「オリビエの奴……」
「帝国の、ストリートミュージシャンが、歌っていたのだとか」
「そうだな。酒場でも軽く演奏されていた時期もあった」
「いい、曲、ですね」
「……ああ」
上半身を起き上がらせユリアはミュラーの手の中の笛をさした。
「それは、ミュラー殿の?」
頷く。
「では……王城から聞こえてきたのも貴方ですか?」
「確かに空中庭園で吹いていたが、聞いていたのか?どこで?」
「走り込みの途中、王城近くまでなんとなく行った時。てっきりオリビエ殿かと思っていました」
あの時、ユリアに届けばいいと願いながら吹いていた。だが、まさか本当に届いていたとは。
「楽器の演奏できる殿方というのは素敵なものですね。自分は楽器は完全に門外漢なので。うらやましい」
微笑みながら体に巻きつけていた布を取ろうとする。それを抑えて、怪訝そうな顔をするユリアを再び横にした。
「まだゆっくりしていればいい。怪しい天気だが雨はふらないようだ。俺もゆっくりしたい」
「すいません。私といればきっと概ね落ち着かないでしょう」
「まったくだ。だからこそ、今のこの時を大事にしたい。数少ない、貴女とゆっくりできる時間だ」
そう言われては何もいえない。青い壁を横目に見ながら、曇る空を見つめた。
どれほどそうしていただろうか。その間、何曲かミュラーの演奏を聞いていた。ほとんど知らない曲だったが、言葉に出来ない音たちだ。
「今から聞くことは、真昼の夢、とでも思ってくれ」
「ミュラー殿?」
突然話し掛けられてどきりとする。
「……貴女には、もうアルセイユという翼がある。……俺は、貴女の何になれる?」
「……」
しばらく質問の意味を取る為黙る。少し肌寒い風が二人の間を通った。寒さに肩を震わせ、ようやく自分が先ほど歌った歌詞にかけているのだと気がついた。
「アルセイユは、リベールの翼。私自身も、翼。私の翼は、まだ見つかっていません。まあ、翼に翼は必要ない気もします」
「……」
「けれど、ミュラー殿はそのままで。翼になろうなんて思わないでください。……そのままで、いいです」
言葉を選びながら、一言一言考えながらユリアは音にしていった。
「どうしても、というのならば……というか、言いそうなので先に言っておきます。私が欲しかったのは、私の背を守る人。何もかも任せて、存分に動ける人。……そして、無茶をしそうになれば、全力で止めてくれる人」
長い長い息を吐く。
「だからもう、貴方はそのままで、いてください」
「貴女の無茶を止めるのは、骨が折れそうだ」
軽口を叩きながら、ユリアをきつく抱きすくめたい気分だ。
「ところで、いつまで俺は「殿」などつけて呼ばれるのだ?」
「えっ!?」
女にとってあたりまえだが、男にはそうでもなかったらしい。
「二人の時は名だけで構わん。俺もそうしている。……一度失敗したが」
「え……でも」
口をぱくぱくさせて困る様子を見ていると、自分はどれだけおかしなことを言ったのかと不安になる。
「俺がいいと言っているんだ」
「……ど、努力します……」
真っ赤になって背を向けてしまった。