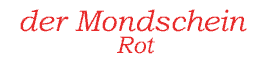
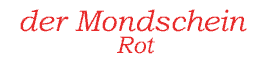
次の日は快晴だった。時計を見ると、普段よりかなり早く起きだしていることがわかった。とりあえず着替えるが、どうしたものかと見渡す。昨夜と同じように窓を開けると、さほど遠くない建物から声が聞こえてきた。
「?」
どうも練武場のようだ。興味を引かれ、部屋をでた。道行く給仕を捕まえ、練武場への場所を聞く。たどり着いた時、若い帝国兵たちが騒いでいた。
早朝訓練のようだが、軽く体を動かす程度の運動しか行っていない。まだ本格的に始まっていないのだろう。リベールでも一般兵は早朝訓練を行っているが、親衛隊は自主的な訓練時間としてある。城内を警備するだけではなく、それ以外の雑用もこなさなければならないので、全員が早朝揃うことは滅多にない。
「熱心なことだな。うちも、検討してみるか」
「おや、あんたは?」
呟くユリアの姿を見つけた兵士が近づく。
「みたところウチの人間じゃないみたいだけど。……ちょっとまて、その服装どっかでみたぞ?」
「自分はリベールのものだ」
「リベールって、あの南の……って、その服! 王室親衛隊じゃないか!」
驚く声に同僚が寄ってくる。
「リベール……?」
「うわ、ホントだ。なんでこんなところにいるんだ?」
ひそひそと囁く声が聞こえてくる。
「殿下に本国から書簡を持ってきただけだ。ただ、妙に早い時間に目が醒めたので、こうやって城内を散策させてもらっている。自分のことは構わず、訓練の準備をしてくれ」
そういってその場を辞そうとしたところ、最初に声をかけてきた兵士が引きとめた。
「なあ、あんた名前は? あ、俺はホルスト・ヴァイスって言うんだ」
「ユリア・シュバルツという」
「じゃあユリアさん、あんた、剣舞、ってできるか?」
「え?」
聞けば、最近上官が剣舞というものに凝りだしたらしい。しばらくリベールに行っている間に知り、戻ってきてからは訓練の合間に練習しているのだとか。仏頂面で練習する姿はある種の恐怖を感じるという。
「……まさかと思うが、諸君の上官は、ミュラー殿では?」
「あれ、よく知ってるな。向こうで会ったのかい?」
急に笑いがこみ上げてきた。仏頂面で舞う姿が容易に想像できた。
「あっはっはっは! なるほど、そうか」
「大丈夫か、あんた……」
「いやすまない。諸君の上官がミュラー殿なら、あの方に剣舞を教えたのは自分だ」
「えええっ!!」
再びざわめきが走る。
「たまたま自分が舞っているのを目にとどめられたらしく、な」
「じゃあ、本当はどんなもんなんだ? あんたが踊るなら俺見てみたい」
俺も、俺も、と兵たちが騒ぐ。あまりに騒ぎが大きくなり、舞わずにはいられなくなってしまった。
「何も自分じゃなくとも」
「少佐殿が不機嫌そうな顔でバタバタやってるのみたら、本当にそれが鎮魂もかねてるのかすっげぇ微妙なんだ。だから、本物ってやつをみてみたくて」
「そうそう、鎮魂というより強制浄化だよな、あれ」
「いやむしろ死んでる奴も目を覚ますだろ」
兵たちは言いたい放題だ。だが、嫌っている様子はない。それがなんとなくうれしかった。
「自分も本物の踊り手ではないが、かまわないか?」
「もちろん」
ホルストは一も二もなくうなずいた。
朝日の差す広い空間の中心にユリアは立つ。自分の剣は部屋に置いてきているので、模擬刀を貸してもらい携える。しばらく目を閉じ沈黙を保つ。近くの木から小鳥が飛び立ったのを合図に滑り始めた。
歩くというより滑るという表現が一番ぴったりくるだろう。一連の動作があまりに滑らか過ぎて、一つ一つの動きを見極めることが出来ない。兵たちが見とれている間にもユリアはあちこち動きつづけ、いつのまにか取り出した護身用の短剣と二つで舞っていた。
どうかこの兵たちが、無為な争いに巻き込まれ、散っていくことがないように。練武場を見守っているだろう、帝国の英霊たちに願う。兵役についている以上戦って散っていくことはある程度仕方がないし、ユリア自身もそれは承知している。だが、その争いの理由がくだらないものである時、それに従って散った者たちの虚しさはいかほどのものか。せめて、自国の誉れとして散っていけ。願いながら舞った。
舞い終わり、辺りを見回すとギャラリーが膨れ上がっていた。最初からいた兵たちはもちろん、遅れてきた兵士たち。騒ぎを聞きつけて集まってきた給仕たちや出入りの商人。
「なっ……」
周りにある人の壁に驚き、知らずあとずさる。一呼吸置いて、大歓声がはじけた。
「すっげぇ!! 少佐殿とは大違いだ!!」
「俺も舞ってみてぇ〜っ!」
「お前には無理だぞ」
「なんだとこの野郎!」
じゃれあう兵士たちに、何故かぼんやりとした表情でユリアを眺めている女性給仕たち。男性給仕たちはその姿をみて少し引き気味だ。
「いや、ほんとすごかったよ。無理言って悪かった」
ホルストが興奮した声で寄ってきた。
「こんなものだが、喜んでくれて何よりだ」
「こんなものなんてもんじゃないよ。みろよ周り。あんたの舞でみんな感激してる」
「……」
自分は普段と違ったことをしたのだろうか。グランセルの練武場でも良く舞いの練習はしたが、それほど注目されることはなかったはず。
「貴様ら、準備はどうした!?」
怒号が飛んだ。人垣が割れ、ミュラーとフライハイトが立っているのが見えた。
「うわ、まずい……」
ユリアの後ろで逃げ出そうとするホルストを捕まえ、頭に容赦なく拳を落とす。
「馬鹿者がっ!」
「申し訳ありません……すぐ準備にかかります……」
不服そうに頭をなでながら、ユリアにそっとウインクを送るホルスト。それに気がつき再び声を荒げるミュラー。
「いい加減にしろ! 自分の階級をわきまえろっ!」
「えっ、親衛隊の隊士殿では? リベールでは、親衛隊と言えど自分たちの階級とほとんど変わらないと聞いておりますが」
「確かに親衛隊所属だ。だが、隊士ではない。中隊長殿だ。階級は、大尉だ!」
「げっ……」
ホルストも、周りでやり取りを聞いていた兵たちも顔が青ざめている。それもそうだろう。どんな罰が下るか、知れたものではない。
「ミュラー殿、自分は特に気にしていません。皆もそんなに顔色を失わないでくれ。自分がきちんと言わなかったのが悪かったのだ」
どうか、罰などは与えないようにとくれぐれも念を押し、持ったままだった模擬刀をホルストに預ける。
「自分も気持ちよく舞えて楽しかった。ありがとう」
にこりと笑う。一瞬ぼんやりとしたホルストだが、上官がすぐ隣でいつにもまして仏頂面をしているので、急いで同僚たちの下へもどった。
「申し訳ない。訓練の邪魔をしてしまったようですね」
「いや……」
頭を下げるユリアに、落ち着かない様子のミュラー。
「そうだ、まだ挨拶をしていなかった。おはようございます、少佐殿」
「あっ、おはようございます……」
不意をつかれたのか、妙に丁寧な挨拶をしてしまう。対してユリアは、昨日思いを告げたためか、ここ最近で一番のすっきりした顔をしている。
「シュバルツ様、そろそろ朝食の準備ができます。一旦お部屋に戻っていただけませんか?」
今まで黙っていたフライハイトが口をはさみ、それもそうだと歩き始めた。と、振り返る。
「ミュラー殿、皆に罰など、お与えにならないようお願いいたします」
重ねて言うユリアに、わかったと言うように手をあげた。
「それにしても、先ほどの舞。私も詳しくは存じ上げませんが、一流の舞い手にも匹敵するのでは?」
「まさか。自分はまだまだです。まだ、舞の真髄は極めていない。それがわからない限り、舞い手などと呼ばれるわけには」
「ご謙遜を。だれがどうみてもシュバルツ様は一流です」
その証拠に、あの場の全員を魅了してしまわれたのだから。フライハイトは心の中で付け足した。
オリビエにつれられ、城内と帝都の視察などを行ったが、夕刻にはとくにすることもなく部屋で読書をしていた。夕方の光が窓から差し込んでくる。
「……夕方」
昨夜聞いた声を思い出す。試しに厨房へ行ってみようと立ち上がる。昼間一度確認したがとくに妙なことはなかった。ただ、厨房の勝手口と、城外への出口が近いことに気が付いた。と、どこかで爆発音がした。テーブルの上に置いてあった愛剣を掴み部屋から飛び出すと、不安そうな顔で給仕たちが話しこんでいる。
「何事だ?」
「いえ……ただ、西翼の方から妙な音がしまして……」
指差す方向へ走り出した。
「西翼には厨房があったはず」
嫌な予感がする。途中でホルストに出会った。
「大尉殿、どちらへ?」
「先ほどの爆発。気になる」
「では、自分もお供いたします」
彼も気になったからこそ兵舎から出てきていたのだろう。ホルストを従え、迷わず厨房へ駆け込んだ。
「!!」
夕餉の為の準備で忙しいはずの厨房。普段なら、活気と食べ物の匂いで溢れかえる場所。今は、血の海と鉄の匂いしかなかった。コックや給仕たちは残らず息絶えている。
「ひ、ひでぇ……」
「何事だ……一体……」
不意に、皇子派と宰相派の対立が思い浮かぶ。
「き、聞いてねぇよ……俺、こんなの聞いてねぇよ!」
「ホルスト?」
後ろで恐慌状態になっている兵に鋭い視線を投げかける。
「一体どういうことだ!?」
「ああ……俺、知ってたんだ。今日、襲撃あるって。だけど、皇族以外には手は出さないって……なんで……みんな死んじまって……」
「なんだと!」
ホルスト自身は宰相派でも皇子派でもないが、自分の身の安全は確保したい。噂という形で流れてきた今日のことを、半信半疑で意識していたのだと言う。
「それからの動きは?知らないか?」
「西翼は陽動だって……本命は、東翼から少人数で入ってくるって……」
「そうか」
それだけ聞けば用はない。急いでオリビエに知らせなくてはならない。
「な、なあ大尉殿……俺……俺」
「……」
不安そうに赤の海を見つめるホルスト。
「自分はこの国の大尉ではない。だから、不穏な人物を締め上げ、聞き出したことにしよう」
「!」
ユリアを見つめる顔が驚きと喜びでゆがむ。
「だが、その代わり走ってもらう。自分は今からオリビエ殿の下へ行く。お前は信頼できる人間に、東翼からの襲撃を食い止めるよう伝えてくれ」
「イエス、マム!」
敬礼し、その場から去った。ユリアも続いて走る。廊下を走っていては間に合わないので、中庭を突っ切る。いまや西翼のあちこちから悲鳴が聞こえていた。爆発音で兵たちもそちらに集まっていることだろう。
「あれは!」
視界の端で、いつか見た黒い剣が動いていた。
「ミュラー殿!」
彼の剣技は達人の域であるが、人数差が激しい。一なぎで二人は払い飛ばしているが多勢に無勢、いずれは落ちる。
それだけは、させるものか!
方向を変え、それまでよりももっと早く駈けた。
「どこから……こんなに!」
うかつだった。城内に待機していたわけではないだろう。そうであれば不穏な動きとして報告があったはずだ。
「くっ」
どこからともなく現れる新手に多少疲れを感じ始めていた頃。
「リベール王国親衛隊中隊長、ユリア・シュバルツ! 参る!」
凛とした声が聞こえ、直後に反乱分子が前のめりに倒れる。その後ろには剣を振り下ろしたユリアが立っていた。
「ユリア殿!?」
思わぬ人間の登場に、ミュラーは目を見開く。
「自分も戦います。ミュラー・ヴァンタール少佐、どうか、貴殿の兵の末席に自分も加えてください」
「いや、それは……」
「貴殿は以前、わが国の危機に力を貸してくれました。今度は自分の番です。共に、戦わせてください」
「……」
本来ならすぐに脱出させなければいけない、賓客である。だがユリアが頑固なのは、輝く環の事件でよく知っていた。断ってもこの様子では必ずついてくるだろう。それに。
再び、共に戦いたい。
男の中に、ふいにそんな欲求が生まれた。
「……心から感謝する。はぐれるな!」
「イエス、サー!」
いつかの空中庭園のように。二人は共に駆け出した。
「とにかくオリビエ殿の安全を!」
「わかっているが、西翼の奴らが……」
「西翼は囮です、本命は東翼から中央館を目指している!」
「何故、それを……」
「不穏な人間を締め上げ、聞き出しました。早く!」
促されるままに走るミュラーだが、僅かな疑いの心が芽生える。ユリアはそれに気がついたが、その場に行ってもらえば疑念も晴れる、そう信じた。
まだ中央館への通路には外敵は至っていない。一瞬はそう感じたが、早計だった。柱の影から数人の影が現れる。強い西日と、深く被ったフードのせいで顔はよくわからない。その動きは今までの敵に比べ、格段に腕が上であることを示している。
「やれやれ、ここを突破しなければオリビエのところにはいけないのか」
「そのようですね」
言いながらユリアは、立っていた鎧像から槍を引き抜いた。その重さと強度を確認し、気合を込めながら先陣を切る。華麗に槍を回し、数人に強烈な打撃を叩き込んだ。ミュラーはその様子を見、感嘆する。
「君はそのような戦い方もするのか」
「一応、一通りは武器の扱いを学びましたから。まだ何一つ、ものには出来ていませんけれどっ!」
足の運びや動きは舞を通じて学んだ。剣の扱い方は師であるカシウス・ブライトから学んだ。また、エステルの棒術は、ユリアの中になにか新しい戦い方を見出せるのではないかと予感した。これらを融合させ、ユリアにしか出来ない戦い方をようやく見つけ出したところだった。
ミュラーも負けてはいられないと、漆黒の大剣を振り回し胴体をなぎ払う。あまり手ごたえがないのが気持ち悪いが、それでも効いていないわけではないようだ。
しばらく戦い、ようやく全員を倒したと思った頃、最初に昏倒したと思っていた敵が、ふらふらしながらも銃でミュラーを狙う。それに気がついたユリアは咄嗟にミュラーの背後に滑り込み、同時に護身の短剣を投げつけた。だが、敵自身は沈黙したが、一瞬遅かったか、銃弾はユリアの左わき腹を貫通した。
「ユリア!!」
色を失ったミュラーが倒れたユリアを抱きかかえる。
「あ……ご無事、でしたか。よかった」
どくどくと血を流しながらユリアは微笑む。
「ユリア!! ユリア!!」
「自分は、幸せです。愛した人を守り、愛した人の腕に抱かれる。武人としては、少々、不本意、ですが、悔いは、ありません」
噛み締めるように呟く。
「ミュラー殿、行って、ください。貴殿の、守るべき人を、守る為」
「ユリア、逝くな! まだ、言いたいことがある!」
「……はい……努力、いたします……」
微笑んだまま黙る。心臓を直接わしづかみされたように震えあがったが、とりあえず気絶をしているだけのようだ。だが、この出血量は危険だ。
「少佐殿、ご無事ですか!!」
ちょうどそこへホルスト以下、彼の信頼できる部下が駆け込んできた。
「東翼の侵入者はなんとか食い止めています! って、大尉殿!?」
「ホルスト、衛生兵を呼んで来い! オットー、とりあえず止血をしろ!!」
「少佐殿は!?」
「俺は、オリビエのところへ行く! ……頼んだ。死なせて、くれるな」
『イエス、サー!』
仕えた人間を守ってこそ武人。軍人である前に武人であるミュラーは、同じく武人であるユリアの言葉に従うことにし、幼馴染がいる部屋への階段を駆け上った。