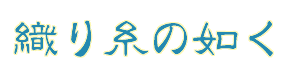
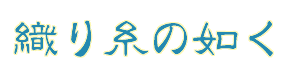
ひたすらにディーターは戸を叩きつづけた。いつか誰かは出てくれるだろうと信じて。一打に思いを込めて。ついでに大声も出しつつ。
「オリビエ−! ツケ払えーっ!」
数回叩いたところ、大声に参ったのか不機嫌そうな給仕が顔を出した。
「オリビエにあわせろ」
「……どちらさんですかね?」
不機嫌に不審が加わってディーターを一瞥。
「ディーターが来たと、オリビエかミュラーに伝えてくれたらわかる」
「ディーター……?」
つまみ食いをしに来ていた兵士がこちらへ来る。さっさと仕事に戻れと怒る給仕を避け、ディーターの前に立った。
「ああなんだ、ディーターさんか。お久しぶりです」
「あんたは前ウチに来てくれたな」
「ええ。落ち着いたらまた寄らせてもらうつもりですが、いつ頃から再開ですかね?」
給仕に大丈夫だと合図しながらディーターを台所に入れる。
「そうだな、まだしばらくは開店しても客が来ないしな。人も戻ってきつつあるんだが……」
しばしの世間話をしているとミュラーが顔を出した。給仕に呼ばれて引っ張ってこられたらしい。
「何をしているんだこんなところで」
「ツケ払え」
「……」
間髪入れず帰ってきた言葉に頭を抱えた。ツケには心当たりがあるが。
「お前あれから何ヶ月経ってるって思うんだ。一般人から搾取するだけしてあとはポイってーのは不義理じゃね?」
「いや、払わないとは言ってない。ただまだごたついてるから……」
「……よし。今日は勘弁しておいてやる。だけど次督促に来たときまだって言うなら、ペナルティとして一日俺に貸せ」
「何を?」
ニヤリと笑ってディーターが幼馴染に耳打ち。
「ユリアさんを一日俺に貸せ」
「なんだと!?」
突然の大声に台所にいた給仕や兵が驚いて二人を見た。注視されるわけには行かないのでそのまま勝手口から外に出る。
「何で貴様に一日あの人を貸さなければならんのだ」
十二分に皇城から離れたことを確認して憮然とした返事をする。
「だってあの人も俺のうちで飲み食いしたじゃないか。一日あったらいろんなことができるぞ」
「何をする気だ!」
「何って……教えてもらうんだよ」
ディーターはニヤニヤ笑いを崩さない。ミュラーは妙なことを言ったら馴染みだろうと叩き切ると心に誓って次の言葉を待った。
「……リベール風の味付け」
たっぷりと間合いを取って吐き出された言葉に心から安心した。
「あの人から話聞いて本格的にリベールに味修行に出てやろうと思っていたんだ。そんなところに妙な事態だろ? 俺の計画も見事頓挫で店は閑古鳥。リベールに行く旅費もない。だったら向こうから呼んで来ればいいし、いい感じに知り合いがいるし」
女坂をのんびり歩きながらディーターは上機嫌だ。
「なんかお前、変なことでも想像したか?」
「馬鹿が」
言い当てられたのでそっけなく吐き捨てる。
「てーわけで是非ご教授願いたいと頼んでおいてくれ」
「俺も漏れなく味見役について行く」
「……お前……目が据わってるぞ……」
他愛のないやりとりをしながらディーターの店までたどり着いた。封鎖は解かれているので人の数は一時期より増えてきているが、心なしか視線が冷たいような気がする。
「なあ……一体いつまで、こんな調子なんだろうな」
水を入れてもらい、適当に席につく。ディーターがぽつりと洩らした言葉が刺さる。人々の視線が冷たいのは気のせいではない。今この帝都にいる軍人は皇族内乱に関わっている人間であり、むしろ原因と同一視されている。今ディーターが洩らした言葉はそのまま帝都の民の言葉だ。
「お前に言っても仕方ないよな。オリビエに……さっさと終わらせてくれって、伝えてくれ」
「……わかっている」
歯切れ悪く答えを返すしか出来なかった。
城に戻る道のうち、男坂のほうが表になる。そしてその途中に、以前ユリアをつれてきた展望台があった。なんとなくそちらへ立ち寄ってみた。
この騒ぎが起きる直前のことなのに、大きく事態が動きすぎて記憶が遥か遠く。城を取り戻してから帝都封鎖が解かれるまでは捕らえたものの処遇に追われ、封鎖解除後は率先して兵を率いている。
「……もとよりこの手は血を吸っている。後悔はしていないが、空虚だ」
ヴァンダールの屋敷に戻っては当時の資料を当たり、そしてようやく見つけ出してきた名前たち。一番の責任者は一番に手にかけた。二番目、三番目と続けて手にかけていくにつれ、次第にもうどうでもいいと思うようになってきていた。昔読んだ本に、「怒りだけでは物事は続かない、怒り続けることは多大なる労力を伴う」という一説があったのを思い出すようになったのもこのごろだ。
日はまだ高い。城に戻ればまた今後どうするのか詳細を煮詰めなくてはいけないのだが、そうする気になれず近くの草むらに腰を下ろした。そのまま寝転がると空は以前と変わらず、のんびりと動いているようだ。
「……いかんな。公私混同だ」
いつのまにかオリビエと共にこの国を変えることが、ユリアを傷つけたものに相応の罰を返すことと結びついていたらしい。
「罰だと? 誰が誰に罰など下せるというのだ。馬鹿馬鹿しい」
自分が神にでもなったつもりでいたのか。あまりの傲慢さに笑いがでる。
けれど後悔は全くしていない。自分のしたことは自分の感情のためによかったと思っている。他の誰がなんと言おうと、ミュラーが今後もユリアの前で笑う為に必要なことだった。ただ、怒涛の如く過ぎていったこの数ヶ月に少し疲れた。まだ疲れている場合ではないのはわかるが、長丁場だからこそ少し気を抜けるならとも。
「……ここに貴女がいれば、もう少し俺はシャキっとするだろうか」
オリビエの前では滅多に見せない弱さを、ユリアにならば見せていいと思っている。弱く惑う情けない自分を見ても、彼女は動じもしないだろう。
「こればかりは、オリビエより確実に上だな」
オリビエにもそういう姿を見せていいのかもしれない。けれどしない。それが最後の一線だ。
「同じ立場の貴女ならば」
今は何をしているのだろう。自由に空を飛びつづけているのだろうか。そうだ、きっとそうに違いない。それがユリアに一番似合っている。ならば自分は、このゴタゴタがリベールに飛び火して、彼女が自由に飛べなくなるようなことを招かないようにしなければならない。もちろんオリビエのサポートもしながらだが。
「そうか。何も殺して回るばかりが方法ではない。むしろ、飛び火しないようにするほうがオリビエの目的にもかなっている」
何故こんな簡単なことに気がつかなかったのかと笑う。
「あくまでオリビエの目的が第一だ。でなければ俺は従者失格だ」
とはいえ迷うときもある。一様に生きることが出来ない、人としての性。迷う澱みから新しい芽を見つけるのも人。
「……少佐ー! 街にいっちまったのかーっ!」
上のほうから声が聞こえてきた。近衛長が自分を呼んでいる。
「どうした近衛長! 俺はここだ!」
しばらくして展望台に顔をだす、老年に差し掛かった男。
「ここにいたか」
ミュラーが座るその横にどかりと腰を下ろす。
「何かあったのか?」
「皇子さんが、手が空いたときでいいから執務室に顔出してくれってさ」
「諒解。ありがとう」
返事をしながらも腰を上げない。近衛長もそれを責めることはない。黙って二人で空を見上げる。
「少佐、悪い話を聞いた」
ややあって、近衛長が言いにくそうに口を開いた。
「この騒ぎについて……民衆からの不満が目に見えて大きくなってきてる。このまま行くと、帝都最大最悪のあの叛乱クラスの事態になりかねん」
「ああ、それは自分も感じている。ディーターの様子を見ていたらそう思った」
「ディーターって、街でメシ屋やってるあんちゃんか。お前さんと付き合い長いんだろ? もしかしたらつるし上げ食らってるかもな」
帝国の歴史は内乱の歴史。けれどほとんど一般人まで巻き込むことは無く、大体が皇室内のみ、無血開城のことが多い。けれど過去に何度かは一般人も巻き込んで、一歩間違えば焦土になるような争いが起きたことがあった。中でも現在の皇帝がまだその位につく前にあった内乱は、皇室の中でも、仕える兵や給仕たちにとっても、民衆にとっても忌むべき程だ。今でこそ誰も口に出しはしないが、特定の年齢以上の人間なら実際にその酷さを目の当たりにしている。
だれもはっきりしたことは教えない、帝国の忌むべき争い。けれど、風化してしまうことの出来ない、風化してはいけない記憶。実際を知らないミュラーですら、その凄惨さを伝え聞いているのが何よりの証拠だ。
「どうする気なんだ、今後は」
「……」
「俺たちは皇子さんの味方だ。だが長引けば長引くほど、そうでない奴も出てくる。争いは長くつづけるもんじゃない」
「……そうだな」
ミュラーの言葉を聞いた近衛長はごろりと横になった。
「いい空だな。なんだ、女のことでも思い出してたのか?」
はっとして振り向くと、図星だなと笑っている。
「こんな天気だ。女のことぐらい思い出したって悪くはあるまい。……ま、もっとも俺は常に思い出してるけどな」
大声で笑う姿に敵うものはない。その声を聞いてミュラーも少しだけ気分が晴れた。
「すまんな、用事をしていたら遅くなった」
結局夜遅くまで別の用事にかかることになり、オリビエの元にいけたのが深夜近く。起きているだろうと思ったら案の定、執務室には煌々と明かりが灯っていた。
「うんいいよ。ボクにもちょっと考えることがあったから」
いつに無く固い声に身が引き締まる。主の言うことを一言一句聞き漏らさないよう、体中に神経を張り巡らした。
「正直に聞くよ。ミュラーは、この先どうなると思う?」
「……現状維持のままだったら、ということか?」
「うんそう。例えばではあるけど、他の人の意見も聞いてみたくって。でもお抱え学者たちだと同じことしか言わないからね。耳の痛いことを言ってくれる人がいてくれるといいんだけど」
昔はいたのだが宰相派だった。ミュラーは深く追求することはせず、オリビエの言ったことを考える。
「……民衆蜂起だ。今はなんとかこの城の中で収まっている……とは言いがたいが、とにかく外に向かっての被害は目立っていない。だが、あちこちから不満が伝え聞こえてくる」
「だね。ボクもそう思う。でも事態収束宣言を出すのはもう少し無理みたいだ。第四皇子がつかまっていない」
「聞いた。最後の隠れ処にもいなかったのだろう? 後はどこにいることやら」
大本はきっと宰相。けれど、この内乱が始まってから表に出てくるのは第四皇子の名ばかり。どこからもオズボーンの名前は出てこないのだ。これでは手を出すことができない。
「本人は領地視察で、あっちの別荘で悠悠自適だっていうよね。なんか悔しいなぁ」
「悔しいって……そんな問題か?」
「悔しいものは悔しい。悔しいから、事が終わったら次の出仕日にあの髭全部そってみようと思う。少しは悪人顔脱却するんじゃないかな」
「何を言っているんだ」
机に座るなと手を振り上げれば慌てておりるオリビエ。いつものように。
「ふと思うんだ」
いつもと違う言葉。
「もはや皇族に、この国を治める力なんて全く残っちゃいないんじゃないかって」
「……」
昔々。武力に長けた一つの小さな北国が不凍港を求めて南へ進み始めた。その後ろに屍の山を築きながら、それ以上に泣く人間たちを残しながら。念願の不凍港を手に入れた頃、滅ぼした国や民族は数知れず。それをそのまま放置しておくことは出来ないと新たに上に立つことになったのが現在の皇帝一族。いくら善政を敷こうとも、国の成り立ちだけは消すことが出来ない。文字で残らずとも口伝される。一人語り部を殺そうともその百倍、聴衆が語り部となる。
「多様な人たちを治めるにはそれ相応の力と懐がいるんだ。ボクにはもちろんそんなものないし、父上だって無かっただろう。ボクの兄弟たちにだってない。宰相にだってもちろん無いだろうさ。皇帝家業は人の身には余るから、だから人であってはいけない。きっと歴代皇帝は、治めるべき広大すぎる自分の領地と、自分自身の力の無さに嘆いてきたんだと、今、そう思う。けれど民からもたらされる富は莫大で、必死になって裏がばれないように取り繕ってしがみ付いてるのが、今の皇族じゃないかな」
「……で、どうする気なんだ? それを改めて噛み締めて」
「そうだねぇ……みんなみんなやめちゃって、皆でコンサートしたいね」
真っ暗な窓の外を見ながら呟くオリビエ。その背は僅かに震えているようだ。自分に何も言えることはないが、その背を誰にも見せぬよう、扉の前に立った。
「アリシア女王陛下にね、言われた。人を治めるなら人ならぬモノになれって。覚悟はしてたけれど……」
声が途切れた。重苦しい沈黙がしばらく続くが、それを破ったのはオリビエ自身。
「そういえば昼にディーターが来てたんだってさ。何の用事だったんだろうね」
「ああ……ツケを払えと言って来た」
「ツケって、キミとユリア君が飲み食いしたときの?」
黙って頷くとオリビエの眉間に皺が寄った。
「キミが応対したのかい? なら払ったんだろ?」
「貴様にツケているからな。俺は払っていない」
「ちょっとちょっとミュラーさん、それはないよ。あの金額びっくりするぐらいだったんだから」
「アンテローゼの額よりかは安いだろう? そういえばあのときの保釈金、俺が立て替えていたはずだ。他にも色々と貴様がしでかした尻拭いで使った金もある。今すぐ耳をそろえて返してもらおう。ミラにしてざっと……」
「あーうー、ディーターには全てが終わってから返すって言ってたから、それで良いよネ?」
懇願するように上目遣いを始めた。それがうっとおしい事この上ないので邪険に手で払う。
「俺に聞くな。それにディーターは、ツケを払うよりもユリアに興味があるようだ」
「へえ。あの堅物がねぇ。今まであんまり浮いた話聞かなかったけど、ようやく料理より女性に目を向けるようになったか」
「……非常に俺としては嫌な言い方をされた気がするが」
「だってもしかしたらそうなるかもしれないじゃん。ディーターは料理一筋だけど格好良いと思うよ」
「ユリアは俺しか見てない」
「アーハイハイ」
急に悟ったような表情になってミュラーから離れた。冷え切ってしまっているお茶をカップに注いで窓際ですすっていたりする。
「おい、なにか反応しろ。こらオリビエ」
顔が熱い。妙なことを言うんじゃなかったと若干の後悔。
「ハイハイご馳走様。ところでなんでディーターが急にユリア君に興味もったんだろ」
「リベール風の味付けを一日中教えてもらうとか言っていたな」
「それはいい。ボクもぜひその場にお邪魔したいと思うね。どうせキミだって問答無用で行くだろう?」
当然だ。あまりに当然過ぎるので声に出す気も無い。なので頷くだけにしておいた。オリビエも満足そうに頷く。そしてまた窓を向いて、固まった。
「どうした?」
その気配に気づいて低く問い掛ける。
「いや、うん。第四皇子は、今行き場が無いよね?」
「まあそうだな」
「だったら、一番自分の身を守れそうなところに移動するよね?」
「……」
いいたいことはわかってきた。タイミングを計る。
「もしくは……自棄になって」
ミュラーはとっさにオリビエの襟首を掴み、窓際から引き倒した。ややあって窓ガラスが振動。そっと様子を窺うと、ヒビは入っていないが時間の問題だ。
「よかった、常に防御アーツを張るようにしてて」
窓の、外から見えないところにセットしてある戦術オーブメントを指す。防御アーツ一つしか再現できないランクの低いものだが、城に戻って全ての窓にこれを取り付けていたのだ。
「下でもやってるみたい。この城の防御は一体全体どうなってるんだ」
「空から来たようだ。途中まで飛行艇に輸送してもらって、上手く場所を狙って落下してきたのだろう」
階下から光が当てられた木に、落下時に使ったのか大きな布がはためいている。
「それはちょっと考えつかなかったな。空から来ることもあるのか。今後の課題」
「そのとおりだ。だがとりあえずはコイツで助けられた」
窓につけられたオーブメントを叩くミュラー。
「しばらくは進入できんだろう。今の内に城内の兵を集めて侵入者を捕まえるぞ」
「うん、そうだね」
駆け出していくミュラーに、ちょっとまってと鋭く声をかけた。
「何だ!」
「絶対にムリはしないで。今度は、ユリア君はいないよ」
「わかっている」
一瞬、虚を突かれた。一年近く前の襲撃を思い出し、しっかりと頷く。すぐ戻ると言い残して執務室を出て行った。
「……キミは死んではいけない。ボクも死んではいけない。そうだろう、女神様」
窓から離れ、机の一番下にしまい込んでいた導力銃の予備弾を取り出す。ずっと使っている愛用のオーブメントの点検をし、エネルギー切れにならないように幾つか導力補充剤をポケットに突っ込んだ。ふと思い至り、腹這いになりながら窓の傍へ。設置されてあるオーブメントに補充剤を取り付けた。
「うん、これで一晩は十分にもつ。窓突破はムリだよ侵入者さんたち」
酷薄な笑みを浮かべる。中途半端に彼を知った人間が見れば驚くほど気配が変わった。その言葉の直後に窓に衝撃が走るが、すぐにオーブメントが起動して何がしかの術を張りなおしている。
悠々と経ち上がり自分の机に戻った。わざとゆっくりと座り、後は待つばかり。机の場所は部屋の中央。周囲にあるものは全て自分で把握して、引出しにはしばらく篭城できそうなほどの物資が収納されている。この場所が一番安全で、そして一番絵になる場所だ。
「最後の最後まで自らの領地から動かず。なんと美しい話だろうね」
もしここで死ねば誰かが物語にして誰かが語るだろう。不思議と他人のことのように自分の立場を思い返す。そしてすぐ頭を振った。どうせ語るなら自分自身で語りたい。己の生き様を。
「オリビエ、入るぞ」
「うん」
真剣な表情のミュラーが戻ってきて何も言わず机に寄りかかる。ドアの外では数名の気配がした。
「この部屋で思い切り暴れるには二人が限界だ」
「まあね、確かに」
「給仕や女官たちには侍従長に従ってもらって食糧庫に入った。近衛たちは本館を固めてもらい、部下どもには出撃命令を下しておいた」
「レベルは?」
「最悪で。ただ、基本は生け捕り」
「……了解、そうしかできないね」
淡々と感情を殺して報告するミュラーに罪はない。もともとそうしろと言っていたのはオリビエ。だが一瞬だけ逡巡してしまった。
「……」
親友の方を向かず窓を眺める。下からの明かりがちらちらと動いているが、窓への振動はもうない。諦めたのだろうか。ドアの外はざわついていて何が起こっているのかはっきりとわからない。やがてノックの音。
「どうしたんだい?」
いつもと変わらない落ち着いたオリビエの声に伝令も焦りが少し抜けたようだ。
「は! 侵入者たちは一番に本館地下の牢へと向かい、囚人どもの解放を狙ったようです。ただ近衛長の指示でこちらにも兵を多数配備していた為、ほぼ被害なく捕らえる事が出来ました。現在一部屋にまとめて閉じ込めてあります」
「……陽動の可能性は? 他におかしな動きはなかったか?」
「現在の所は、本館への被害はそこだけです」
「東西の方はどうなんだろう。イレギュラーに伝令が来ないってことはたいしたことがない……ならいいんだけど」
伝令が部屋から辞した後ぽつりと呟く。そういえばあの大佐は海兵たちに人気があった、とミュラー。オリビエも思い出す。南方の領地を治める伯でもあったと。
「もしかしたら、彼を取り戻したいだけなのかもね」
「……」
親友は答えず、オリビエも期待はしない。ただ、これさえ凌げば。そうすれば今の事態は収束する。そんな気がしていた。次々に寄せられてくる定時連絡には侵入者の無謀ともいえる行動がありありとでていて、明らかに自棄で襲撃をかけてきているのだ。こちらもそろそろ持久力が尽きかかっているが向こうも同じ条件と思わせるほど。
「せめて、もうこれ以上街に被害がでないように」
力いっぱい手を握り締めた。
「ああ……そうだな」
しばらくの後付け足されたミュラーの言葉に不意に涙が出そうになる。悟られぬように深呼吸をしてごまかした。
「そういえばさ、ちょっと前に聞いたんだけど、今牢に入れてある遊撃部隊の面々」
「なんだ?」
「武器はともかくとして、支給した覚えがない戦術オーブメントも持ってたんだ」
「ほう」
「あんまり精度がいいものじゃなくて、ほとんど使い捨てみたいにして次から次へ、だったみたいなんだけど、これが例のシリアル無しの奴。で、しばらくは空中投下の形でそれが届けられていたみたいだ」
「そんな無茶苦茶な。その衝撃だけでも壊れただろうに」
「実際そうだったみたいだよ。ただ、途中からその供給がなくなった。最後の物資に『これ以上オーブメント提供不可、リベールライン壊滅』ってメモ。実際ボクもそれを見せてもらった」
「……リベールライン?」
怪訝そうに首を傾けるミュラーに軽く頷いた。
「他にもラインはいくつかありそうだけどさ、リベールラインが壊滅ってことは、作ってるところが見つかったってことだよね」
「……ユリアか」
「きっとね。……ねえミュラー、ボクたちの戦いは、いろんな人に支えてもらってるんだね」
支えてもらったお礼がしたい、と笑う。きっとそれも近いのだと、友と頷きあった。