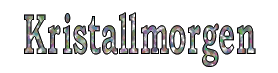
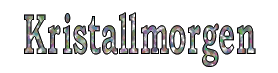
残響音を酷く大きく感じながら廊下を歩く。来賓を通すことを考えているこの廊下は、曇りの日でも明るく見えるような作りになっている。確かに窓は最大限に明かりを取り入れ、内装も明るいもので全て統一されていた。けれどもそこには本当の明るさはない。
置物についた汚れを拭きながらフライハイトはゆっくりと城内を見回る。毎日拭いている筈なのに必ずどこかは汚れている。まったく、と溜息をつきながら、それでも普段と同じことを続けられる暮らしに僅かながら安堵。目に付いた汚れを落とし廊下を眺める。
「……」
特別の来賓が来る時以外は誰かしかこの廊下にはいた。今のフライハイトのように掃除をしてまわる給仕たちであったり、立ち話をする城勤めたちであったり。不穏な会話がなされていることもあるが、それは関係ないとばかりに無視をするのが暗黙の了解だ。
「皆さんは大丈夫かしらね」
この廊下は中央館に続く。つい二月ほど前にはオリビエがそこにいたが、あの日を境にいる人間が変わった。唐突にやってきた海軍将校と遊撃部隊の動き。その意味に気がついたときには近衛も自分たちもまとめて兵舎に押し込まれた。白い大きな鳥に導かれて何人かは外に出られたが。
流石に給仕たち全員を押し込めていると生活が立ち行かないとみたか、数名が監視付きで料理人や掃除要員として出入りを許された。その後結局監視をつけることもなく給仕たちは城内を行き来している。とはいえ、中央館に続く廊下と、将校や遊撃舞台の多くが詰めている館自身には滅多に近寄ろうとしない。結局侍従長にその役が回ってきた。毎日決まった時間に巡回をし、なにか用事があれば黙って応じる。現皇帝が今だこの城にいた頃からの習慣だった。
「変わらないのだな、侍従長」
「私は同じことをするだけ。何か御用事でしょうか、大佐殿」
階段の上から海軍の将校が声をかけてきた。いつものことなので、いつものように返事をする。
「……いや、君たちも強情だなと。近衛は皇子派だからもう仕方がないと思うが、君たちは別にどちらでもないのだろう? 君が私たちにつくといえば全員ついてくるだろう」
「私はそれを判断するつもりはありません。この城の主はこの城が決めましょう。城が決めた主に我々は仕えます」
「……そうか。やはり平行線だな」
少し寂しそうに壮年の男は笑う。海軍は総じて宰相派だが、この大佐は熱心な宰相派ではなかった。部下たちに慕われ、戦場にいれば意気高揚の役を勤められる稀有な人材だと伝え聞く。軍の中のことは計り知れないが、こんな戦地に遊撃部隊のまとめ役として出てくる人間なのだろうかと、フライハイトは話をするたびに感じた。
戦死することを望まれてここにいるのかもしれない。良い指導者の死はいかようにも戦争では使えるのだから。
「他に御用事はございますか?」
「いや……ああ、食糧庫の件は申し訳ない。勝手なことをするなとしかりつけておいた」
その日、フライハイトは初めて心から笑った。
少しばかり足取り軽く食糧庫へ向かうと、庭師の何人かが手を振ってきた。
「侍従長、今日も食糧庫は無事だぜ」
「怪我した奴は大丈夫かい?」
「ええ。早くベッドから出たいと元気ですよ」
つい五日ほど前、遊撃部隊の何人かが食糧庫を占領しようと集団で押し寄せてきた。そのときに見張りに立っていた料理人や導力技師たちが怪我を負っていた。一時は給仕たちも皆殺しの目に会うかと思われたが、フライハイトと件の海軍将校のとりなしがありなんとか収まっている。
「ここだけは俺たちの一線だ。遊撃兵どもに譲り渡してなるものか」
当然ながらに、この城が占拠された当初、この食糧庫を解放しようとしてきた。帝都封鎖令を出す以上、外から食糧供給は見込めない。オリビエたちを封じ込めるために封鎖を行ったが、城の食糧庫を手に入れなければ先に消耗してしまう。帝都内の軍保管庫は全て網羅していたものの、城の備蓄量も入れての封鎖だ。
が、それらの管理は料理長が行っている。料理長を脅してはみたものの全く効果がない。給仕たちの軟禁が解かれたのはそこに理由があった。解かれたと同時に食糧庫の前には腕に覚えのある使用人たちが交代で見張りに立ち、遊撃兵たちとは一触触発の状態が続いていたのだった。
「大佐殿からの伝言です。申し訳なかったと。今後は無いようにするとのことでした」
「へぇ……軍のお偉いさんがオレたちみたいなのに謝るのか」
「あんまり軍人にはいい思い出はないけど、中にはいるんですね」
感心したと頷きあう庭師たち。
「あまりそういう偏見は持たないほうがいいですよ」
フライハイトがたしなめると相好を崩す。
「そりゃ侍従長くらいにまで達観できりゃ、そんな偏見も持たないだろうけど」
「下っ端の使用人だろうってよく無茶なこと言われたもんなぁ」
そうだそうだと頷きあう庭師たちをもう一度たしなめ、次の場所へ歩みを進める。中庭を横切りながら、ふと空が曇ってきたことに気がついた。
「……雨が降るのでしょうかね」
西翼にたどり着いた頃、細い雨が空から落ち始めた。静かに静かに。長い雨になるかもしれないと、濡れた体を軽く拭いて部屋を見回る。所々にやはり見張りの給仕たちが立っていて、一言二言言葉を交わし歩いていった。西翼は主に城に仕える人間の個室がある。各個人の部屋を荒らすことはフライハイトの中で最も許せないことであり、最初遊撃兵が学者の部屋を我が物顔に荒らしていた時には強烈な雷が落ちた。
「ここはあなた方の部屋ではございません。あなた方は客人です。客人は客人らしく、来賓用の部屋にいなさい!」
有無を言わせぬ口調とその内容に驚いた遊撃兵は慌てて部屋から飛び出したと、後で給仕の一人が語るほどだ。その後は荒そうという人間はいない。その代わり東翼の部屋は全て解放してある。中央館も、個人の部屋以外は全部侵入者たちが占拠していた。
「こういうことを守ってくれるのも、あの大佐殿が官を勤めているからこそですね……」
複雑な気持ちでとある部屋に入った。調度品らしい調度品はほとんどなく、小さい本棚には武に関するものばかりが溢れている。その中で変わったものといえば舞に関するものだろうか。机の上に厳重に封を施してある箱を見つけ、自然、彼女は表情を緩ませる。
「ふふふ、あの方にもこんなところがあるのが不思議なものです」
いつか、手紙の書き方を聞かれたときには驚いた。仏頂面で有名なミュラーがあんなにも表情豊かだったとは。久々に、誰かに話してみたいと思うほどに彼は表情を変えたのだ。
ミュラーのことは彼が城仕えを始めた頃から知っている。生真面目にオリビエの後をつかず離れず、時に困らされ、時に怒りながら、生真面目な少年は生真面目な青年になった。浮いた話も多少は聞いたがすぐ消え、何より本人がそんなことをおくびにも出さなかった。
「十数年お話をしていてあの顔を知ったのが初めて。本当に、人はいろいろなものを閉じ込めている」
どれだけあのユリアのことを思っているのか、口に出して言わずともすぐにわかるというものだ。少しだけユリアに嫉妬をしながら、ミュラーの母親のような気分になっていることに笑った。
「外国にはいろいろな方がいらっしゃる。……ええ、私もあの女性は好きですよ。良き方をみつけられました。不器用だと思っていましたが一応、やることはやっていたのですね」
手紙を入れてある箱に手を置きすぐにどける。他に置かれているものに触れないようにしながらテーブルや棚を拭く。ベッドもきちんとなっているかを確認し、ふと寒さを感じてテラスに出る大窓から外を眺めた。雨の勢いは変わらないが、しっとりと世界を濡らしていく雨だった。
「侍従長、知っていますか?」
近衛長の部屋を見回って出てきたところに、男性給仕の一人がそっと声をかけてきた。
「何がですか?」
「さっき、また敗走してきたそうです」
「……」
少し浮ついた気持ちを引き締めた。敗走の報告が入った日には必ず荒れる。東翼には近寄らないようにと皆に言わなくては。
「最近多いですね、敗走」
「……ええ」
なかなかどうして、あの末席皇子はがんばっているではないか。忘れ物は無事彼の手に届いたのだろうか。あの日、逃げ出す兵の手にとっさに押し付けたオリビエの忘れ物。
「とりあえず兵舎に戻ります。そろそろ近衛兵さんたちの食事を作らなくては」
「わかりました。自分は、この辺りにいるものに続けて連絡をします。それでは」
給仕と別れて兵舎へ。既に敗走の話は伝わっているらしく舎全体がざわざわとしていた。食堂の一角へ顔をだすと、近衛長が上機嫌で杯を重ねている。
「おうい、フライハイト侍従長。ちょっとまあこっちに来れば良いじゃないか」
「全く。こんな時間からお酒ですか?」
苦笑しながら隣に座る。
「いいじゃないか。どうせ俺らの仕事は今はない」
「もう少し位は緊張されても宜しくては?」
言いながら酒瓶を近衛長から遠く離す。それを取り返そうと体を伸ばしながら豪快に笑った。
「いいのいいの。たまには休まないといかん。部下どもも今ごろは部屋でゆっくりしているだろうよ」
「この間ストレスが溜まったとか称して、練武場でもないのにこの食堂で乱闘をしておりませんでしたか?」
じろりと睨む侍従長。それをものともせず取り返した酒瓶から直接呷った。
「そんなこともあったかもしれんが忘れた。もう年だからそろそろ引退したいんだ。引退するに当たって鍛えたい奴がいたんだが、今どうしていることやら」
誰のことを言っているのかは問わずともわかる。この男はミュラーを妙に気に入っているのだ。
「鍛える必要は無いほどの方と私は思いますがね。それに直接の部下たちが怒るかもしれませんよ?」
「俺が鍛えたいのは心のほうだ。どうもなぁ、生真面目すぎていかん」
「貴方に鍛えられると、それは豪胆にはなりましょうが……あの方は今のままで十分だと思いますよ」
「そうか?」
「生真面目すぎて何がいけませんか? きちんとするべきことは押さえているようですよ。何の問題もないかと」
「そうなのか。また今度聞いてみるか」
男は髭を撫でながら目を閉じる。フライハイトも黙って外をみた。雨は続いて降っている。
「……近々大荒れになるかもな。こんな静かな雨のときは余計にそんな気がする」
独り言のように近衛長は呟く。
「戻ってくるかい、末席皇子さんよ……」
夜になって霧がでた。底冷えのする夜、閉じていた目をゆっくりと開く。そこには一つの決意が見て取れた。
「朝になって、日が昇ると同時に男坂を上ろう。霧が晴れてようが晴れていまいが、ここにいるみんななら気にならないだろう?」
もちろんだと応じる。その様子にオリビエは大きく頷いた。
「今晩は寒い。ゆっくり休養を取ってくれ。明日はきっと長い長い一日になるだろうから。ディーター、お願いする」
「おうよ。備蓄全開放してやる」
腕を上げてその場から出て行く。司厨員数名が後を慌てて追った。
「じゃあ親方は武器の手入れをお願いするよ」
「ああ。折れ飛んだり弾詰まりなんかおこさしゃしない。鍛冶屋の名誉にかけてな」
言いながら彼も弟子を引き連れて出て行った。
「じゃあ自由行動で」
オリビエの言葉に集まっていた人間の大半が部屋を後にした。仮眠を取る者、手伝いに行く者、おしゃべりに興じる者。様々に行動しながら願うことは一つ。奇妙な感じがした。
「傷は大丈夫かい?」
「まあまあだ。しかし、こんな日を選ぶか? いくら男坂を熟知しているとはいえ、間者が潜んでいればすぐに対応できんかも知れんぞ」
少しの不安をにじませミュラーが応じる。
「それはボクも考えた。けど、多分明日の早朝が一番いい気がする」
「貴様の感覚だけが頼りか」
「良いじゃないか。ボクは運はいい方なんだ」
かもしれんな、と腕を組みなおすミュラー。
「朝のベッドに忍び込むのもそれはそれで素敵な始まりだと思うんだな」
「……何の話だ」
高まりかかっていた興奮が一気に萎える。その場に残っていた数名も脱力した表情をしていた。
「……とりあえず見張り小屋の様子を見てこよう。すぐ戻る」
「ん。諒解。気をつけて」
大きな作戦前だからこそ普段と同じように行動をしなくてはならない。城の動きをいち早く察知する為に男坂を見渡せる位置へ建てた小屋には常に何人かが詰めており、今ぐらいの時間にはミュラーも顔を出していた。報告を聞くためもあるが、何かをしていないと落ち着かなかった。
外に出ると霧。それほど濃くはないが見慣れた街が別世界だ。近寄れば何があるかはわかるので迷うことは無い。途中、詰所に寄って糧食を手に入れ小屋へ。監視を続けていたオットーに投げ渡した。
「ありがとうございます」
「様子はどうだ?」
「変わりません。動きがあればすぐに詰所、詰所から拠点へ向かいます」
「ああ」
覗き窓から道を見、そのまま城へ目を移す。
「少佐殿、宜しいでしょうか」
「なんだ?」
「今回は、殿下とともには出られないのですか」
「今の俺は手負いだ。残念ながらそれほどたいした働きはできんだろう」
「そうでしょうか。少佐殿の腕は誰よりもあると自分は思います。その程度の怪我でどうこうなるとは思えません」
オットーがいつになく真剣にミュラーを見ている。
「その慢心が自分自身にある。だからこそ、俺は残ることに決めた。それだけのことだ」
「……」
しばらく視線をかわしたがオットーが折れた。
「死ぬわけにはいかん。それもあるがな」
オリビエを護り、自分も生きる。それが守れなさそうなのだ。離れていることで護れないということはないのだから。
「どうして、それほどまでに生きることを?」
「お前は生きたくないのか?」
「……それは……けれど、軍人であるならば」
「そうだな。確かにそのとおりだ。死を厭わず、命令のままに死地に飛び込むものだな」
しばらく間をおいて続ける。
「だが、護るべきものを護り、尚且つ自分も生き残る。……その方が、ただ一度護っただけで死んでいくより難しいとは思わないか?」
「……ええ」
「死ぬことで護るのも一つの形。だが戦いはここでは終らんだろう。全て終る戦いで倒れるのならば悔いはないが、今はそういうわけにはいかん。まだ通過点だ」
「そう、ですね」
納得したというように頭を振る。
「あまり無理はするな。だが監視は怠るな」
「はっ!」
先程よりはスッキリした表情で敬礼を小さく返してきた。
朝が来る。行軍が始まる。全てを取り返せ。全てをひっくり返せ。陽気に歌い、笑いながら寄せ集めの兵たちは進む。
その先頭には皇子。この国を愛し、憎み、末席と言われては這い上がってきた皇子がいる。己の軍旗を掲げて、朝の霧を割って進む。
慌てて飛び出してきた遊撃兵たちと戦いながら、帝都にまた一つ傷をつけながら、それでも彼らは進む。薔薇に巻かれた黄金の軍馬の元に集って。
それを見送る親友がいる。背後から現れた刺客たちを仕留めながら、先を歩く友を思い、傍にいる部下を思う。皇子としての初陣がどうか成功であるようにと願う。その場に自分がいられないことを若干悔やみながら、それでも願う。これが終ればまた次が待っている。全ての戦いが終るまで願いつづけよう。
坂の上から狙われる道行き、上から降る矢や弾丸に何人かが道行きから脱落する。それでもオリビエはひるまず、一歩一歩登っていった。男坂は城へいたる為の正規の道。緩やかな女坂もあるがそれを使って帰ることはできなかった。ディーターにはそちらで帰ればいいと言われたが、オリビエの譲れない一線だった。
「せめて、こんな時くらい男坂を使ったほうがいいパフォーマンスになるよ。馬鹿な皇子の一人が馬鹿正直に正面から帰ってくる。失敗したら本当に馬鹿だけど、成功すればこれほどいい宣伝はない」
皇子としてこの坂を上がるのは正真正銘の初めて。自分は表舞台に出なくていい。女坂をゆっくりと登ればよかった、皇室の中を斜め下から眺めているだけでよかったはずなのに。
「殿下! 門が見えました!」
報告に黙って頷くオリビエ。差し出された旗を受け取り高々と抱え上げた。そして何かを噛み締めるように目を閉じる。ややあって目を開き、それほど大声ではないはずなのに妙に通る声で高らかと。
「開門せよ! 私は戻ってきた! ここに、この城に戻ってきたぞ!」