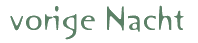
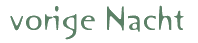
かつて、兄にこう聞いたことがある。
『自分は貴族制度を打破することに関わっている。それでも構わないのか』
と。
兄は笑って答えた。
『それも時代の流れならば応じる。だが先は長いぞ。貴族制を壊したとて、それがいいと思う人間がいるならばまた元に戻るものだ』
生半可では返り討ちにあう。せいぜい意識改変もがんばることだなと、少し寂しげになる。すぐにその表情は消えたが、ミュラーは未だに覚えていた。
オリビエは「美しくないから」と言う。確かに皇城の内外で彼の言う、美しいやり取りはなされていない。だがそれだけのことで全てを壊してしまっていいのか。皇族や貴族だけではない。彼らに仕える全ての人間、あるいは動植物も巻きこんで、ありとあらゆる暮らしを壊すこと。それを実行するだけの理由は。
『何もかもを信じてついていくだけが忠臣ではないぞ。時に離れ、冷静になりながら仕える相手を導くのも役目だ』
また、こうも言われたことがある。そんなことはわかっている。
「だがな兄さん」
音になったかどうかは知らない。
「俺は、兄さんの知らないあいつを知っているんだ」
その、兄の知らないオリビエが自分を繋ぎとめる。自身にも覚えはあるが、謀殺の対象になるというのは大変なことだ。おそらくヨハネスもそれを知っているからこそ強くは言わなかったのだろう。
誰を信じていいのかわからず、見るもの、出会うもの全てが自分を殺そうとしてくる。皇城の中にオリビエの居場所はなかったのだ。たった一箇所、彼のために作られたという図書室を除いては。が、いつしかそこも長兄、長姉たちに占領され。ミュラーが剣術の稽古をする際一緒に稽古をするようになったのはその頃からだ。
「もしかしたら、あいつは誰も信じていないのだろう」
よく笑い、よく泣き、よく表情が変わる。だからこそ惑わされてその底が見えない。かつて遊撃士のヨシュアが何かの折にそうこぼしていた。彼は人を見る目があると感心したことを思い出す。
「そりゃねぇと思う。少なくともお前だけは信じてるだろ」
「……」
ぼんやりとした思考に聞きなれた声が割り込んできた。誰かがそばにいるのはわかっていたが、目を開けるのが億劫で気にしないようにしていた。
「というか、態度見てりゃわかる。安心しなミュラー、お前だけはあいつの信用を勝ち得てるだろう」
「お前のほうも……信頼されていると思うがな」
「どうだろうかね」
視線を横に動かすと、椅子に座ってディーターが舌を出していた。
「……状況は?」
「どっちを聞きたい? 一つ、戦況。一つ、お前におこった事」
「……どちらでもかまわん」
「じゃ、戦況のほうから。といってもお前が倒れてからはほとんど進んでない。ただ近いから、オリビエとかはピリピリしてる」
「そうか。近いか」
「ああ」
何がと問うまでもない。近いといえば一つしかない。皇城奪還だ。第四皇子と戦うも、その後ろのオズボーンと戦うも、まずは自分の本来の拠点である皇城を取り戻さなくてはならない。
「んで次、お前のこと。ま、そんなに傷は酷くない。とっさに避けたのが良かったんだろうな。向こうにも迷いがあったっぽいし」
「迷い……」
「とりあえず何よりもお前疲れすぎ。あんまり無茶はするなよ、在庫の薬にも限界はあるんだからな、というのがお言葉だ」
「誰の」
「俺の」
つまらない冗談は体にこたえる。深く息を吐いて視線を天井に戻した。
確かにホルストの刃には迷いがあった。呟きながら自分に向かってきた時には背に嫌なものがはしったがそれほど勢いはない。ミュラーの技量であればかわし、反撃も出来たかもしれない。出来なかった理由は一つ、あの呟きにある。
「……今はどこに?」
「地下貯蔵庫に閉じ込めてある」
しばらく沈黙が部屋を支配した。ディーターが飽き、大きなあくびをしたところでミュラーはベッドから起き上がった。
「従業員用の第一階段右がそこだ。あんま無茶すんなよ」
「止めないのか? 仮にもけが人だぞ?」
「仮にも、とか言ってるあたりで自分はけが人と思ってないんだろ? なら俺が止める必要なし。自分の体は自分が一番よくわかってるだろうし」
「……なんてヤツだ。心配くらいしないのか」
「してるからここに今俺がいるんじゃないか。あ、もしかしてあの恋人のほうが良かったって? そりゃすまなかったな」
「……」
「だけどさすがにつれてくるわけにもいかないし。ここは俺の笑顔に免じて」
「もういい……オリビエが二人に増えたみたいだ」
部屋の中に何かをわめくディーターを残して廊下に出る。戸を閉める直前に大笑いを聞いた気がしたが気のせいということにした。
暗い貯蔵庫の中にホルストはいた。放り込まれてからどれだけの時間が経ったか。自分がしたことに思い至ってから眠くもならず、腹も減らず、ただただ目の前を見つめているだけ。時折体が僅かに震えるのは、目の前に、上司の本気があったから。
まだ戦場に出たことがないホルストは、本気で人が自分を殺しにかかってくる現場に遭遇したことがない。初めて明確に向けられた殺意が自分がよく知っている相手であり、それも絶対に敵わないと尊敬すらしていた上司だ。即座に体が動かなくなった。なぜかすぐにその敵意は消え、弾き飛ばされたナイフに気がついた周りに取り押さえられる。ミュラーもそのまま倒れたが手に重い感触はなかった。だからそう大した傷にはなっていないだろうと踏んでいる。
彼に刃を向けてどうしようとしたのだろう。それまでを振り返ろうとしても頭がはっきりしない。ただ、彼に何かがあればユリアが悲しむのは目に見えているのだ。それだけが彼の魂に刻まれているように揺らがない。
「入るぞ」
ホルストの答えを聞かずに扉が開く。廊下の明かりが内部を僅かに照らし出した。シルエットがホルストの足元まで届く。
「……少佐殿」
「ああ。暗いなここは。少し戸は開けるが構わんな」
「……」
逃げようと思えば逃げられるのかもしれない。目の前にいるのがミュラーでなければ。だが悲しいかな目の前の男は、自分がどんなに努力しても勝てないと思っている相手だ。そして手は拘束されている。
「一つ聞きたいことがある」
「……はい」
「ホルスト、貴様があの時呟いた言葉……覚えているか?」
黙って僅かに頷く。前後は今だ混濁しているがそれは覚えていた。
「大体の想像はつかないこともないが……誰のことだ?」
「シュバルツ大尉殿……です」
「そうか」
表情が読めない。構わずホルストは続けた。
「初めて会ったときから自分はあの方のことが……何の根拠もなく自分のほうを見てくださっていると考えていました」
「……わからなくもない。あの人は外では誰にでも同じ態度を取る。俺に対しても、多分貴様らに対しても……」
「そう……なのですか。けれどあの日。大尉殿がご帰国される際……たまたま自分が空港の見張りをしておりました。そうしたら……少佐殿と大尉殿が」
「あー、皆まで言うな。……まったく、どいつもこいつも……」
ミュラーの言葉に照れが混じった。いつも怒っているか仏頂面だった為、ホルストにはかなり意外だ。
「……とにかくあそこに自分もいました。もうなにがなんだか、その時期からわからなくなりました。ただずっと何かが頭に響いていたような、そんな気がします」
「頭に?」
小さく、はいと頷く。
「弱みに付け込んでの催眠か? 使いどころを踏まえれば薬でどうこうするより後に残らないからな……」
思索する上司に恐る恐る声をかけた。
「なんだ?」
「あの……自分はどうなるのでしょうか」
「……今はまだ何か聞こえるか?」
「いいえ」
「今でもまだあの人を思っているか?」
「!」
思いがけない言葉に呆然とした。この人は何をいいだすのだ。思っていないはずがない。初めて会ってからほぼ毎日、寝ても醒めてもユリアの笑顔が浮かんだ。同僚にも洩らし、思いがけず出会えたあの日からは大騒ぎもいいところだった。
「……はい」
「だろうな。俺だってそう簡単に諦められんだろう。そんな人だあの人は」
しばらく考えてミュラーがホルストに近寄った。手にはいつのまにか刃物が握られている。思わず目を閉じたが、切られたのは彼の腕を拘束する縄だった。
「……え」
「今度は刃物ではなく、別のもので向かって来い。その上であの人が貴様を選ぶのならば俺には何も言うことはない。……納得できんだろう、今のままでは」
「……」
「納得するまで好きなようにしろ。が、俺も負ける気はない。やっと見つけた人だ……」
「少佐殿……」
「もっとも、さしあたっては人手不足だ。ここで俺も貴様も死んだら、あの人を手に入れるどころの話じゃないぞ」
「は、はい」
ニヤリと笑うミュラーを、初めて身近に感じた。
整列をした兵が街道を進む。一個大隊並の人員が一部の狂いもなく進むその姿は、街道沿いの住民にとって見慣れた姿だった。が、見慣れているとはいえあまり見たくない光景である。またどこかで争いがある証に他ならない。
「……珍しいね。だいたい帝都から来るもんだけど、帝都に向かってる」
「確かに」
「あ、今帝都封鎖令でてるんだろ? この間来てた情報屋がここでがなりたててた」
酒場の一角で目の前を通っていった兵たちについてあれこれと隠居たちが噂する。マスターはそれを聞きながら、今は仕込みの時間だから本当は出て行って欲しいなと暢気なことを考えていた。
「あの章は……お、ありゃ宰相の直轄領にいるヤツラじゃないか?」
「どれどれ……本当だ」
帝都がなにやらきな臭いことになっているのは帝国中が知っている。その詳細を知るものはほとんどいないが、何かが変わるのではないかという気運が高まっていた。そこに持ってきて、宰相直轄領からの派兵。自然と隠居たちの酒のペースが落ちた。
「この国は、どこに向かおうとしているんだろうなぁ」
「ワシらはもう関係なくなるだろうが、若い人たちには大変な時代になるのかも知れんな」
「……そうだなぁ。ワシらにはもう何も出来ん。ここで飲んだくれるだけだ。……マスター、お代わりは?」
「ヘイヘイ」
まだ飲むのかよと口の中で悪態を付きながらいつもの酒を取り出した。
通り過ぎた街でそんなやり取りがなされているとは思わず、兵たちは相変わらず一糸乱れぬ行軍を続けていた。ただ、流石に帝都に近づけば近づくほど、宿場に兵が多くなってきているのには気がつく。誰も口には出さないがその多さには驚いていた。よく見れば自分たちより先に出た宰相の兵だったり、第四皇子領から同様に出てきているものであったり。何故帝都に入らないのだろうと心の中で首をかしげた。自分たちと同じ理由で召集がかけられているだろうのに。
「行軍停止」
止まれの号令が出され、一斉に足を停止する。高い高い壁が、帝都にたどり着いたことを意味していた。
昔、幾つかの部族がこの辺りには住んでいた。今の帝国を構築する人種がこの帝都をはじめに作ったが、他部族の侵入、侵略に耐えられるようにこの町の周りには高い城壁が作られた。が、今はその役割は若干変わっている。侵入、侵略に耐えられるようにという役割は変わっていない。今現在は、皇帝の、皇族の命を狙う輩から守っているのだ。
「何の用事だ」
門の前で押し問答が繰り返されている。
「開門を願う。帝都内での反乱鎮圧の為自分たちは召集された」
「駄目だ。どんな人間であっても、どんな命令を持っていても通すな。これが我々の受けている命令だ。例え陛下であろうとお通しは出来ぬ」
「何だと!」
「引取るか、この命令が解除されるまで待つか。好きなほうを選ぶがいい」
「……」
そこへ、また別の兵団がきた。同じように別の門番がやり取りをしている。よく見るとその兵団はオリビエの兵団だ。一気に門の前が緊張する。
「……回れ右。先程通り過ぎてきた宿場まで戻る」
「回れ右!!」
宰相の兵は舌打ちをしながら後退を始めた。それを門番が無表情に眺めている。
「一つ聞くが……」
オリビエの兵を率いてきた兵団長が門番に声をかけた。
「答えられる範囲でならば」
「君達に命を下したのはどなただ? 陛下か? それとも殿下か?」
一瞬考え込んだが門番は口を開いた。
「陛下でも、オリヴァルト皇子殿下でも、宰相閣下でもない。我らはヴァンダールの兵。なればこそ、我らは現ヴァンダール当主、ヨハネス卿の命にのみ従う」
言われて思い至った。『どこからに対しても壁であれ』。確か当主の訓の一つだったはず。現在、オリビエの専属護衛はヴァンダールのもの、しかも現当主の実弟だったはず。それでも自分たちを排除するのかと食い下がるがただ首を振るのみ。
ヴァンダールの命令系統は特殊である。帝都にありながら、帝都のルールに従わない唯一の事例だ。だからこそ内乱の際に一切揺らがない。
「ならば、帝都の中から逃げ出すものたちはどうなるんだ」
誰かが声を上げた。
「我々が受けた命はただ一つ。ここの門並びに壁を越えようとするものを許すな。一切の例外はない」
門番が抑えていた殺気が露になる。慣れてないものが浴びればそれだけで気絶してしまいそうな強烈な殺気。ヴァンダールの兵は超一流が揃っていると聞いていたが、実際にそれを実感する羽目になってしまった。よくよく探れば辺りに、姿は見えないが殺気だけはある。門番をきっかけに、潜んでいる者たちもその存在を知らしめているのだ。ここを通るならば、自分たちを相手にしていけと。
「……回れ右。最後の宿場まで戻る」
宰相の兵と同じように来た道を引き返す。その後姿を見送り、ようやく門番は殺気を消した。次いで周囲の殺気も霧散。
「ふう……何番目の団体さんだ?」
「忘れた」
あまり気分がいいものでもない。
「ヨハネス卿も難しい注文をしてくれるもんだよ。俺らなら出来るって……」
「でも上手くやってるじゃないか。この調子で行こう」
「楽観的だな」
もう一人の門番に仕方がないと笑う。
「さっさと終ってくれるに越したことはないがな」
「まあね」
いつ終るのだろうか。見上げた空は少しだけ曇っていた。
作戦室代わりの客室に入るとオリビエが感極まって飛びついてきた。まだ傷が治ってないと慌てて周りが引き剥がしにかかる。
「いやすまないミュラー。嬉しくてね」
「……貴様に先に殺されるかと思った」
「もう少し休んでいればいいんじゃないかい? ボクが手厚く看護するよ。それはもう昼も夜もそばについて、汗をかいてたら拭いて……」
「結構だ」
治るものも治らなくなると睨むと半泣きで離れた。その表情が不思議そうなものに変わる。
「あれぇ? 彼は」
「人手不足だ。処罰は後にする」
「……ふうん。キミがそういうならいいけど」
背後にいたホルストに視線が集まった。
「そんなことよりどういう状況だ?」
「今詰所奪還組の報告待ち。それが終ったらあとは男坂を上がるだけ」
「そうか。ならなおさら人手が要るな」
「まあね」
オリビエから視線をホルストにうつす。いつも元気が有り余っていた部下はただじっと黙って床を見詰めていた。
「ホルスト・ヴァイス上等兵!」
「は!」
唐突に呼んだミュラーに驚きつつ、それでも訓練の賜物か、即座に敬礼を返してきた。それに満足して口角を上げる。
「条件付で、戦時下特例措置を取る。貴様は俺の補佐に入れ。いいな!?」
「は、はい!」
近くに置いておけば何か動きがあったときすぐに対処できる。なにより、同じ女を愛したもの同士だ。根は自分と同じに違いない。
「オリビエ! 来た来た、報告だ!」
飛び込んできたディーターに部屋の中が静かになる。ややあってオリビエが先を促した。
「ああ。詰所奪還成功。今、残党は駆け登ってるってさ」
瞬間、部屋が歓声に包まれた。その中にあってオリビエは引き締まった表情をした。
「いよいよだな」
「そうだね。でも今のキミは連れて行けない」
「……」
言わんとすることはわかる。深手ではないとはいえ急所を狙われて傷を負った。手負いが突入してどうにかなる場所ではないことは自分が一番理解していた。
「なら……自分を同行させてください」
「ホルスト?」
「自分は少佐殿のように剣は振るえないし、他の何もかもが及ばない。けれど、殿下を命を賭して守ることは出来る」
「……」
ミュラーは黙ってオリビエを見た。決めるのは自分ではない、オリビエだ。
「うんわかった。じゃあお願いする。他にもキミが付き合いやすそうな人を選んでおいて。それがボクの周りにいる人ということにしよう」
「ありがとうございます!」
オリビエに礼をし、ミュラーに敬礼をした。自分も敬礼を返しながら兄の言葉を思い出した。
『時に離れ、冷静になり、仕える相手を導くのも役目』
一時離れる程度でどうこうなる絆ではない。互いにそれを理解してもう数年。そしてミュラーは、自分が前線から外されたにもかかわらず嬉しかった。
「オリビエが、人を信じようとしている」
誰も信じず、誰にも何も求めていない。こればかりはミュラーが何を言ってもどうしようも出来ない、オリビエの業。ようやくその業と向き合う気になった。
「そうだオリビエ。少しずつでいいんだ。信じてみろ。あの時の仲間のように」
リベールは人を変える。今、その言葉を妙に実感した。が、それは半分当たっていて、半分間違っている。リベールにいる、あの仲間たちに会えたからこそだ。
「そうして全てが終ったら、またあの国に出かけよう。貴様の仲間に会いに。全てが終ったことを分かち合いに」
口に出して言えばまたからかわれるので、今は胸中に納めることにした。