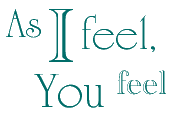
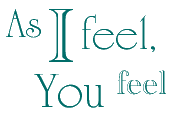
船影はもう見えない。動けないまま、ただそこに突っ立っているしか出来ない。けれども背後でなにやらボソボソと話し声が聞こえてくるので振り向けば、通路に座り込んでミュラーを伺っているオリビエとディーターがいた。
「……何をしているんだ」
「あ、見つかった」
「そりゃま、別に物陰にいるわけじゃないしなぁ……」
あ、そうかと手を打つオリビエ。
「何を納得している……」
先ほどまでの余韻が飛んで消えた。
「ボクたちもユリア君を見送りに来たんだけど……ねぇ」
「なぁ……あんなに見事に二人の世界を作ってるとは思わなかったから、声も掛けられやしなかった」
「キミはともかくユリア君は気がついてもおかしくなかったのに全然だしさ。あーあ、寂しいなぁボク。寂しいからすねちゃう」
「俺もだ。一人身にはきつい仕打ちだよ」
まったくだ、と二人頷きあう。
「……いつから後ろにいたんだ」
「んー? 『そろそろ出発だー』とか誰かさんが言ってたかな」
「案外にあのユリアって人も情熱的なんだな。それともお前に惚れきってるのか……昔から知ってると、なんでこんな奴にと思うんだが」
「だよね、だよね! 絶対ボクのほうが」
「いやそれは問題外だ」
ディーターのそっけない一言に「の」の字を書き始めるオリビエ。努めて感情を抑えようとしていたミュラーだが、握り締めた拳により一層の力が入った。
通路の真下、資材や機械を置いてあるところで一人体を震わせる兵。いつもならいる整備員たちも逃げ出してしまっており、あたりに人気のない中足元の木材を思いっきり蹴り飛ばした。長く、また見た目よりきっちりと積み上げられているそれは、一度蹴ったくらいでは崩れることもない。続けて蹴ってやろうと思ったが足の方が痛くなった。
「……へっ……最初から、眼中になし、か……」
リフトに寄りかかりそのままずるずると座り込む。もはや立つこともかなわぬほど、ホルストは忘我状態だった。
何がしかの兆候はあった。突然剣舞など始めたり、ユリアのことになると殊更にしかってきたり。微妙な間も多々あった。けれど気が付かなかったし、気が付こうともしなかった。自分を見てくれている。信じて疑わなかった。
「よくよく考えたら、そんなことないよなぁ。俺、全然頼りになんないもんなぁ。……この間だって、叱られたもんなぁ」
釣り合いは取れないのかもしれない。それはわかっている。だが。
「……よりによって、だよ……」
何故だ。何故ミュラーなのだ。恋人がいるなら知らない人間の方がよかった。筋違いなほどのイライラが募る。
いなかったら、いいのにね
どこかで音が響く。ああそうだな、と口の中でつぶやいた。
つぶやいた直後にはっとあたりを見回す。誰もいない。
「……気のせいか? あんな気のせいが聞こえるなんて、俺どうしたんだ……」
もしも今ミュラーに何かあれば最も悲しむのはユリアだ。火を見るより明らかなのに。けれど心は痛く、願っても掠らない思いがのしかかる。
「……」
どうしたらいいんだろう。どうこの状態を生き抜けばいいのだろう。日が入らない通路の下で、ただ地面に埋め込まれたタイルを眺めた。
「ねぇねぇ、痛かったよぅ」
「軍人の癖に一般人に暴力ふるうたぁどういうことだよ」
ホテルまで戻る間、一人ミュラーが先頭を歩き、後ろから追いすがるようにオリビエとディーターが駆けていく。幼いころからよくあった光景だ、とディーターは思った。大体オリビエが余計なことをして、彼がはやし立てて、それに対してミュラーが怒っていた。この構図は変わらないんだろうなと思う。
けれど痛いものは痛い。年季の入った大工が、ここだ、という一点を見極めてその槌を振り下ろすかのごとく、二人の頭の弱点めがけて渾身の一撃が振り落とされた。
「昔から知ってるってのも良し悪しだな。どこ殴れば一番効果的か心得てやがる」
「それはまあこっちにも言えるけどね。どうからかえば面白い反応してくるか、よーく知ってるもん。よーく、ね」
オリビエの想像している人物に自分も入るだろうな、と肩を竦めるディーター。
「確かにな」
イッヒッヒ、と笑い、先にホテルに入ってしまった幼馴染を追いかけようと向き直る。そこに。
「……うわっ」
「おや」
大きな白い鳥が舞い降りてきた。初見のディーターは驚き、馴染みのオリビエは何だろう、と首をかしげる。ジークの足にはいつものように通信筒。
「……お、おいオリビエ、これは」
「リベールの親衛隊の一員だよ」
「へ?」
信じられないと口を開ける男にジークが威嚇してくる。慌ててすまないと、小さく謝った。
「クローディア王太女殿下のナイトなんだ」
「へえ……こいつはハヤブサか?」
「うん、そう聞いてる。でもジーク、って名前があるよ」
筒から書簡を取り出しざっと目を通しながら続ける。
「ついでに言うと、ユリア君のナイトでもあるんだ。もともとユリア君が飼っていたらしいし、名前も彼女が付けてるって。だからミュラーとはほんとに反りがあわないみたいだね」
「はっはっは!」
いつもジークに空へ逃げられて、一方的にやり込められるだけだという話まで聞かされ、ディーターは大笑い。オリビエもつられて笑ったが、すぐにまじめな顔になった。
「……ジーク君、今日までありがとう。しばらくはクローゼ君やユリア君、他の誰かが言ってもボクのところにはこなくていいよ。約束してくれ」
小さく鳴き返す。それに頷いて少し笑うオリビエ。
「また落ち着いたらボクからちゃんとお礼を言いに行くよ。そのときにはまた頼む」
持っていた紙切れに、今言ったのとほぼ同じ事を書き付けて筒に入れた。そこへ、先に行ってしまっていたミュラーが戻ってきた。
「何をもたもたと……」
「ごめんごめん、ジーク君がね」
とたんにジークが戦闘態勢に入る。ミュラーも応じて身構えた。
「……お前、相当痛めつけられてるな……」
ディーターがあきれ、オリビエもうんうんと頷いていた。
「……ジーク君と二人きりに、してくれ」
「おおう、アヤシイシチュエーション!」
「馬鹿が! ……ディーター、ホテルに戻っていてくれ。馴染みの鍛冶工房の面子が来てくれているから、少しは安心だろう」
「了解。馴染みの鍛冶って……うわ、アドルフのとっつぁんかい」
曲がり角から覗いたディーターは肩を竦めた。昔よく叱り飛ばされたのが今でも軽くトラウマなんだけど、とつぶやきつつも、状況を見守りたがるオリビエの襟足を掴んで引きずっていった。
大人の足で十歩、距離を開けた位置にミュラーとジークはいた。ジークはその場に適当な木材を見つけ宿り、ミュラーは羽を収める様を眺めていた。
ややあってミュラーが口を開く。
「君が俺を嫌っているのはわかる。その理由もわかる」
ジークは気にも止めていないというように羽を繕い始めた。
「……不満なのか? あの人の傍に居られない俺に」
反応はしない。けれど男は話し掛けつづける。
「それでも俺はあの人を愛した。君にしたら新参者に過ぎない。けれど、その気持ちだけは君があの人を思うのと同じだと思っている」
初めてジークが反応した。けれど何の意味なのかははっきりわからない。
「先にあの人の騎士として共にあった君に、俺を認めて欲しい……」
出会ったとき、ユリアはすでに天涯孤独だった。ならば、もっとも身近にいるジークに認めてもらわないといけない。でなければ、何よりも誰よりも、ユリアが悲しむのは目に見えている。
「今は離れている。けれど、必ず生きてあの人を迎える。その覚悟で俺は今、この地に居るのだ」
ジークが木材から離れた。
「……」
高く高く舞い上がり、真昼の太陽に隠れてその姿が見えなくなった。ミュラーはじっと立ったままその場から動かない。構えを取るわけでもなく、目すら閉じず。好きにしてくれ、とあるがままに立つ。
けれどもその瞳は意志を秘めていた。他の部分が自然でも、そこだけ不自然なほどの力を持っていた。天から弾丸のように降ってきたジークがその瞳をめがけてきたときも、ミュラーは微動だにせず、まぶたも閉じず、微笑みすら浮かべていた。
一瞬だけの交錯。紙一重で目を抉り出されることはない位置。ジークの羽の感触が思い出される頬。魔獣すら屠る鋭い一撃は、僅かにそらされたのだ。不意に痛みを感じて頬に手をやれば、風圧で一筋の傷が出来ていた。手に僅かについた血を見てようやく安堵した。
この赤が目に入る。目を渡してもいい覚悟だった。その覚悟は今でもあるし、今後、形を変えることはあれど持ちつづけるだろう。それだけに、最後の最後でそらされたことが大きく感じる。
「だが……少しは、認めてくれたのだろうか」
軌道を変えることができるギリギリまで、ジークはミュラーに致命傷を負わせようとしていた。人も動物も同じだ。その目には確かに殺気があった。
「俺には彼の言葉はわからんが……その方がいいのかもな」
再び木材に舞い降りてきたジークをみながらつぶやく。あれで冗談だ、と言われたら一生ジークには認めてもらえない気がするから。
まだ多少の攻撃は受けつつも、それまでよりはましかな、と思いジークを見送った。次に会うのはいつだろうか、と考えて、必ずもう一度会わないといけない、と誓う。
ホテルに戻ればロビーが賑やかだ。外はゴーストタウンと化していたのに比べ、あまりに明るい。
「……とっくに封鎖令は発効されているというのに」
オリビエを中心にして馴染みの鍛冶職人、酒場の仲間、城から逃げ出してきたミュラーの部下たち。市場で顔見知りになった見習や店主、客もいた。
「お、戻ってきたか。どうだ、認めてもらえたか?」
ディーターに茶化される。
「僅かな前進といったところだ。ところでこれは」
「んー、ボクの人望」
「大体は、遊撃部隊の奴らに酷い目に合わされた奴らだ。宰相が何しようが俺らにはあんまり関係ないが、遊撃部隊は別だ。店休む羽目になった人もいるからな」
俺だ俺だ、と誰かが手を上げている。
「だからボクの」
「そーいう事態になることがわかってて部隊集めたんならもちろんだし、そうでなくても問い詰めたいわけだ。直訴しにいったって城門は閉まったままだし、ならこじ開けるさ」
オリビエが何か言おうとしていたが誰も聞いていない。
「……そうか」
一見オリビエを無視しているようだが、その実皆は気にかけている。本人もそれはわかっているようで、相変わらずの百面相をしながらも笑っていた。
皆オリビエの本当の身分は知っている。だがそういうことがわかる以前に仲良くなった人たちだった。
酒場に顔を出さなければ店主や歌姫が心配してディーターの所に来る。市場に珍しいものがあれば一番に買い、その場でなんともいえない幸せな表情を振りまき、周囲に伝染する。下町と呼ばれるところを闊歩し、持ち前の好奇心を武器に各所で騒動を起こしつつ、その憎めない性格に和まされてきた面々。
「ところでなんでオリビエちゃんが宰相と戦うんだい?」
果物屋の女将が疑問を発する。
「女将さーん、そりゃないよ」
わざとらしくオリビエが椅子からずり落ちる。ミュラーとディーターは顔を見合わせた。
「まぁさ、ボクと宰相殿の間には、相容れぬ因縁? があるんだよ」
「そうかい」
それだけのやりとりで会話は終了。また思い思いに雑談に興じ始めた。
「なんだ、愛されてるんじゃないか」
傍らの友のつぶやきが今の状態を的確に突いていると思う。下町の仲間が、何の因果か宰相と敵対している。なら、ちょっと手助けしてやろうじゃないか。それだけなのだ。
「俺たちもかわらんだろう」
「だな」
「……お前は、いいのか?」
「俺? 何を今更。お前らと友人やってるあたりで諦めたよ。親兄弟は街から出るよう言ったけど」
妹が産み月なんだ、と照れくさそうに続ける。
「カルラか? それは何よりだ。またゴタゴタが片付いたら祝いに行こう」
「オリビエと、ユリアさんも連れて来いな」
「後者はリベールから掻っ攫ってこないといかんが」
「大事件だそりゃ」
全くだ、と肩を竦める。
「それによ、これだけの面子がいて、料理人が俺一人じゃないか。メシもなくてどうやって戦うって言うんだ?」
「美味しいご飯は戦う為の必須条件だけど、ディーターだしねぇ」
オリビエが輪から出てきてかき回す。言われたディーターは気にしているふうではないし、
「これが終わったらもう帝都で17番やら16番やら言わせないぞ。俺のメシを食って闘争成功しました、って宣伝するからな」
とまで言ってのける。
「期待しておくよ」
とオリビエが言うのに不満そうだ。そのやり取りを眺めていたが、一段落ついたとみてミュラーがオリビエに状況を聞いた。
「ボクの私兵は帝都内のあちこちに残ってる。それを召集しないといけないんだけどね。さすがにこの人たちに丁丁発止してもらうわけにもいかないから。地の利を生かしての持久戦になったときに手伝ってもらうくらいかな」
大体が生まれも育ちも帝都だというメンバーばかりだ。それは確かに有利だろう。けれど戦いに素人なのは事実で、それでは宰相の私兵と前面衝突すればかなわない。
「ボクは正々堂々、正門から帰ることにする。城付近まで様子を見に行ってもらってるんだけど……」
「誰に」
「キミの部下で、オットーって居ただろ? 彼に。堅苦しいけど、その堅苦しさが見咎められないかな、ってね」
「……やや柔軟性に欠けるから、偵察には向かんと思っているのだが……」
そういう隙にオットーがもう一人と共に戻ってきた。
「殿下、ただいま戻りました。少佐殿、お疲れ様です」
「お疲れ様。どうだった?」
城から目抜き通りにかけてはずっと兵が巡回しています。こちら方面に向かってくる様子はないですが、昼前に襲撃があったとのこと、ご注意ください」
「うん、ありがとう」
礼を言いながら思索を始めた。
「貴様らはどうやって? 昨日は深夜警備だっただろう?」
「は! 白い鳥に通信を運んでもらい、一部は何とか脱出できました。けれども近衛長以下の近衛全員と、我が隊の若干名がまだ残っています」
「誰だ?」
報告を聞きながらも近衛長の顔が浮かぶ。大丈夫なのだろうか。
「それと……フライハイト侍従長殿より殿下に、と」
「?」
話を振られたオリビエは、オットーが仲間のところに行き、何がしかの荷物を手に取るのを眺める。
「こちらです」
丁寧に包まれた中から出てきたのは。
「軍旗……」
紫がかった深青の生地に帝国章が縫い取られている。通常のものとは違い、数箇所に赤い薔薇の刺繍があり、黄金の軍馬には薔薇の蔓が巻きつけられていた。
「これは、ボクの軍旗だ」
あの老婦人がこれを今、オリビエに渡してきたということは。
「応援されてるのかな、それともけしかけられてるのかな」
どちらにしても、これを掲げて城まで戻って来い、って事だろうね、と広げる。両手ほど幅はないが長さがそれなりにある。
「配色のシュミが悪いよね」
「何言ってるんだよ」
ディーターが軍旗を見ながら、ついでに軽く一撃お見舞いしながらあきれた。
「そんな問題で済まそうとするなよ」
逃げたらいけない一線がある。そこまで言う必要もないと、そこで言葉を切った。ミュラーも同感なので何も言わない。
「オットー、目抜き通りには兵が多かったんだな?」
「は! 基本順回路に20人、特対順回路に15人。おそらく城周りにはもっと配置されていたかと。ほぼすべてが遊撃部隊の人員で賄われておりました」
「そりゃまた暑苦しそうだね。普段は基本に5人くらいなのに」
「一般兵は? 見かけなかったのか?」
「はい……」
オットーが肩を落とす。兵舎に押し込まれたな、とあたりをつけた。
一般兵は宰相派、皇子派、どちらでもない派とさまざま入り乱れている。遊撃部隊の規模は私兵にしては多すぎ、一般兵の半分にまで膨れ上がっていた。それを受けて一般兵を締め出したのだろう。
「あいつら、ことあるごとに自分たちに敵対してきて。普通の兵に好きな奴はいないと思います」
「そのあたりは俺も理解している。だからといって、無茶に出たな……」
「何かあせってるのかもね。それが何かは、宰相殿のみぞ知る、と」
オリビエが軍旗をマント代わりにしながら歩き回る。とめようと思ったものの、周りの仲間たちが囃し立てるので声が届かない。
「じゃ、ボクたちも作戦らしいもの、考えてみようか」
一回りしてミュラーたちのところに戻ってきた。
「いいだろう」
「うぃっす」
頷いたとき、オリビエの目の端に何かが煌いたが、それを指摘するのはもっと後にしよう、とミュラーは思った。