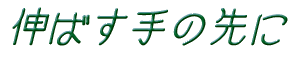
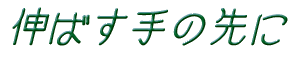
「これはまた大変なことになったねぇ」
「ああ……って何で貴様がここに」
「そっくりキミに返すよ、その言葉」
「……」
ミュラーとオリビエはヴァンダール家に泊まったがユリアは勧めを断ってホテルに戻っていた。早朝、モーニングコールで目を覚ましたが、そのとき封鎖令の話を聞いた。街道と空港が昼12時をリミットに完全封鎖されるという。
その話を聞き覚醒した。どうしようかと考えているところに二人が顔を出したのだった。というより、最初はミュラーだけしかいなかったのだが、いつのまにかオリビエも混じっていたのだ。
「とにかくさ、この大変な部屋。全部持って帰るのはちょっと事だね」
「そっちが心配なのか、この期に及んで……」
かろうじて寝台だけは確保されている部屋を見回しオリビエが笑う。
「昨日ホテルを通じて、貨物便の手配をしていますので……」
「ボクの愛を受け取ってくれてありがとうユリア君! ……はいはい、冗談だよ」
遠慮がちに声を掛けるユリアの手を取って熱っぽく語るも、どこからともなく流れる冷たい空気に肩をすくめた。
「なんで貴様までここにいるんだ!」
「だって城追い出されたもん。卿の所に居座るわけにも行かないしね。明らかにボクが目的だ。ボクの持つ玉璽が目的だ」
オリビエはまず城に向かおうとしたのだがヨハネスに止められていた。すでに宰相派に抑えられていると。
「卿のところを反宰相の詰め所にするわけにもいかないからさ」
「それは確かに……だがどこを拠点にする気だ?」
「ここ」
「……ホテルですか」
「結構要衝なんだな、このホテル。皇城の様子がよく見えるし、でもこの方角には城からは狙いにくいんだ。なにより帝都の構造が一番の難関だね」
皇城からは細い路地が多く、建物の向こうに見えているホテルに行くのに大回りをする羽目になってしまうのだ。
「支配人が断るだろう?」
「支配人はボク派なんだって。流石にそこまで手落ちな事はしないさ」
少し心外だというように口を尖らせる。
「う、うむ……」
「問題は空港からの侵入だけど、民間船はこの封鎖令で全部退避するしね。それだけでも大分脅威が減る」
ただ、封鎖令を出すということは宰相側は帝都の破壊もいとわない可能性がある。残りたければ残っていてもいいが、そのかわり何があっても文句はいわないように、と暗にこめている。それを知ってか、もとから帝都に住んでいた人間たちも逃げ出している。窓から通りをみれば家財道具を持って列を成している人々がいた。
「じゃあそういうことで。ドレスが汚れたりしないかなと心配したけど、貨物で先に送るならまあいいか」
「貴様はいったい何をしにきたのだ……」
「ボクを捨ててこっちに来た誰かさんの邪魔をしたかったんだ」
言い返すことが出来ずに立っていると、オリビエはそのまま部屋から出て行ってしまった。
部屋からドレス入りの箱がどんどんと持ち出されていく。その様子を何も言わずに男と女は眺めていた。最後の一つが運び出されユリアがサインをする。人足たちが出て行くと外の音が聞こえてきた。
「封鎖だ!! 空港封鎖するぞ!! 現時点から5時間以内に帝都内の外国人は国外退去せよ!」
窓の外では誰かが大声でがなりたてている。その声を聞きながら、でもここから離れたくないと考えている自分。できるなら、あのときと同じように傍で剣を振って戦いたいのだ。
だが。
「貴女は国に戻るんだ。いいな」
ミュラーはユリアにそう言い切る。
「しかし!」
「貴女にはやらなければならないことがあるはずだ。それに……これは、俺たちの問題だ。俺たちが起こしたことだ。だから、俺たちで決着をつけなければならないんだ」
厳密に言えばミュラーの言い方は間違っている。ヴァンダールの当主就任と結婚の儀で多少なりとも浮つく上流社会。その間隙を縫って封鎖に踏み切ったのは宰相派だ。けれど、そんな行動を起こさせたのは明らかに皇子派、オリビエの責である。
「だから、帰れ。いいな」
「……」
長い沈黙の後、不承不承と言った様相で、諒解、とつぶやく。少し俯いていたが、何かを決めたように顔を上げるユリア。
「でも、ぎりぎりまで、ここに居ても、いいでしょうか」
「……ああ。俺も、ぎりぎりまで居る」
「ならば、それならば。お願いを、聞いてくれませんでしょうか」
頬を染め、震える声で、わずかに体も震えていて。体の前で作ったこぶしがこれ以上ないとばかりに握り締められていた。けれど不思議と恐怖は無い。あれほど彼女を苛んだ痛みもない。今なら。今ならいい。この人ならいい。この人だからいい。
「それは却下だ」
けれど。そんなユリアの様子を見ようともせず、ミュラーは窓から様子をうかがいながら断じる。
「!」
何か言いたいのに言葉が見つからない。ここまで明確に拒絶されたことはなかった。心通じ合って、ともにいられるかもしれないと思ったユリアの直感は間違っていたのだろうか。
震えそうになる声を励ましながら言葉をつむぐ。
「なぜ、ですか? 理由を」
続けられない。嗚咽が何もかもを邪魔してくる。やっと、と信じたことが壊れる。そんな状態と知ってか知らずかミュラーは顔をユリアに向け、顔を覆い肩を震わせる己の恋人を見つめた。
「これ以上、俺を情けない男にしてほしくないから、だ」
言われた意味がわからずに顔をわずかに上げる。そこに、大きな手のひらが伸びてきた。
「貴女には前にも一度、言われているからな。ここでまた貴女から言われたりしたら、一体何を言われることやら」
「……どういう」
「まあ、男の沽券に関わるものだ。だから今度は俺から言わせてもらいたい」
男の親指がそっと眦の涙をふき取り、頬に触れていた手が背中に回る。されるがままにその腕に収まる女。
「ユリア。抱いてもいいか?」
いや、と腕に力をこめてくる。
「抱くぞ」
ユリアの答えを聞かないまま唇を合わせる。声で答えられない代わりにユリアは腕を背中に回し、しっかりと組む。入り込んできた男の舌を拒絶できない。いや違う。拒絶する気などなかった。
「ようやく、貴女を抱ける。いつか皇城で療養していた頃から。それよりももっと前、初めて舞っている姿を見てから。……俺は、ずっと抱きたかった」
「……ああ……ごめんなさい……ごめんなさい」
幼子のように泣きじゃくりながらユリアは抱きつく。このひと時だけでも離れるまいと。
「いいのだ。その時がくるまで待つと、貴女に恋焦がれたときから決めたのだから」
「ミュラー殿……」
「初めて会ったのは戦場だった。そして、貴女を抱くのも、戦いの火蓋が切り落とされようとしている今。……俺たちには、それはそれはふさわしい」
いやみのない、柔らかな笑み。誘われたユリアは男の唇をふさぐ。少し眉を上げた男だがそっと抱え上げて寝台へ。スプリングが軋んだ。
ユリアの部屋から少し離れた廊下でオリビエはにこにこしていた。ようやく自分の親友が幸せになれそうなのだ。自分のことのようにうれしい。
「ああそうだね。ヒトは、こんな気持ちになれるんだね」
一年前にリベールを旅したとき、ようやく思い出せた感覚だった。
「これは幸せだ。みんな幸せだ」
わずか一年、けれどずっと帝都で綱渡りを続けていると、本当の意味で人を思いやることを忘れてしまった。そんなことではいけない。どんな生活をしていようと、人とのつながりを消してしまうような社会はいけない。
「面白くないもんね」
面白いか面白くないか、それはオリビエの最後の判断基準だった。
「なにニヤニヤしてるんだよ」
「ん……? おおおっ! キミは!」
「誰だっけ、とか言うなよ。言われつづけて飽きた」
「言わないよディーター。久しぶりだね」
「お前の方に逢うとはな。城追い出されたんだろ?」
すぱっと言われて肩をすくめる。
「うん。だから今日からボクはホテル住まいだ。美味しい料理を取ろうかと思ってね。知ってるかい? 帝都の路地裏に、口は悪いけど結構腕のいい料理人がいるんだ」
「ほう。帝都で何番目の美味さだ?」
「そうだね、まあ16番目くらいじゃないかな」
「……ミュラーよりはましな評価か」
頭を掻きながらあたりを見回す。静かなもので二人以外の人気がない。
「ミュラーは?」
「あー。取り込み中だから。そうっとしておいてあげよう。今くらい」
「取り込み中?」
眉根を寄せるがすぐに意味ありげな笑いに変わる。なるほどなるほど、と妙に感心して頷く様子にオリビエが小首をかしげた。
「ほら、アレだろ? リベール人の恋人」
「なんだ、知ってるのか」
「この間ウチに来た。今日はその件だ」
「でもミュラーは今……」
言いかかるオリビエを制すディーター。
「ちがう、お前に用事だ」
「?」
虚を突かれた。
「さんざんウチで飲み食いしていって、お前にツケてることになってるんだ。だから支払い」
「なんだって?」
「支払いだ、支払い」
「……いくら」
すさまじいほどの理不尽さを覚えながらなんとなく値段を聞く。耳打ちされた金額に力が抜けていった。
「そ、そんなに……」
「そうだ。さっさと払えよ。「獅子が風に立つ前に」な」
「この騒動終わってからでもいい?」
「ダメだ……といいたいが仕方あるまい。しばらくついて回ってやるから覚悟しろ」
「……」
黙ったオリビエを残してディーターは階段を下りていってしまった。残ったオリビエは階段の一番上に腰掛けながらディーターの言葉を思い出す。
「……「獅子が風に立つ前に」か。これはまたやっかいなことだ」
昔から三人の間で使っていた隠語で、「自分にとって都合の悪いことが近々起こるからその前に準備をしろ」という意味を持っている。せめて逢瀬が終わるまでは静かだといいなと、口に出さずにつぶやいた。
静かだった。若干熱さの残る吐息を吐いた自分に驚く。直接顔を見るのは恥ずかしすぎて出来ない。だから黙って横になっていた。不意に背中で男が動く。眼をやると起き上がり、窓から外をのぞいている。
「……どうか、しましたか?」
「そろそろ最終便の時間か。皆ほとんど行ってしまったようだが……」
時々まだ一人二人が通りを駆けて行っている。
「……この際だ、もうひとつ。もしも子を成すようなことがあったら」
子ども。顔が熱くなる。一瞬だが浮かんだのだ。己と、ミュラーと、時折邪魔をしに来る仲間たちと、小さなゆりかごで眠る命。
「誰がなんと言おうと、生んでくれ。俺の子だ。俺と、貴女の子だ」
思わず上半身を起き上がらせたユリアは優しく抱き寄せられた。
「必ず。必ず迎えに行くから」
「……あ……」
その言葉に涙が出た。今日は泣いてばかりだと頭のどこかで笑っている自分がいるほどに。
「また……俺は貴女を泣かせたか」
「貴方は、ひどい人だ……」
「……そうか」
「一つ一つの言葉で、私をいつだって困らせる。いつだって、不安にさせる。いつだって……」
顔を上げて、まだ眦がぬれている様を見せながら、微笑む。
「いつだって、私を幸せにしてくれる」
「ユリア……」
「わかっています。わかって……」
それ以上は何もいえない。けれどとめることはできない。第一、自分自身が止められたら意地になるに決まっている。
「どうか、御武運を……」
生きてください。どんなに離れても、生きていればまた逢える。途切れた言葉の後に思いを乗せて、願った。
そのとき、どこかで不意に大きな物音がした。甘かった空気は霧散し同時に職業軍人としての厳しさになる。手早く身支度を整え外に飛び出した。
「どこだ!」
「下です!」
飛ぶように階段を駆け下りればオリビエとディーターが数人に囲まれていた。降りてきたミュラーとユリアに気が付いた侵入者が発砲してくる。が、慌てているのか見当違いな所に当たるだけだ。駆け下りてきた勢いのままミュラーが侵入者の一人に体当たりをすれば手から銃が放物線を描いて離れていく。下腹に拳を叩き込まれた男はその場でうずくまった。
二人の出現で浮き足立った何人かがオリビエたちから眼を離す。その隙にディーターが手近にあった花瓶をたたきつけた。後頭部に命中し、バランスを崩して振り返ったところにオリビエが銃で肩を打ち抜く。
「冷静さって大事だよね」
「まあな」
オリビエのつぶやきに近くまで来ていたミュラーが応じる。
「こいつの近くには俺がいる。それを知らぬはずは無いだろう!」
侵入者を恫喝する。
「……嘘ばっかり。ユリア君の近くにいたぢゃないか」
「黙っていろ」
後ろから聞こえてきた声に短く返しつつ、視線は侵入者に向けたまま。怒鳴りつけられた侵入者は自棄なのか勝算あってか、持っていた銃を構えようとした。けれどもそれはあらぬ方向から飛んできた銃弾に阻まれる。
左後方にユリアが銃を構えて立っているのが見えた。彼女の後ろには、ミュラーが逃していた侵入者たちが足から血を流しながら這いまわっている。
「やるねぇ。足を撃つか。ボクもそっちで行こうかな」
言いながらねらいを定める。残り一人になった侵入者は悔しいとばかりに歯を噛み締めていたが、何事かをつぶやくと突風が吹き荒れた。
「戦術オーブメント!」
ユリアがはっと叫び、同時にオリビエも打ち消すようにより大きな風を巻き起こす。合間にミュラーが床を蹴って男の顔を殴り飛ばした。追い風もあり、ロビーにあったソファにたたきつけられて沈黙した。
「怪我は無いか?」
振り返ったミュラーは、オリビエとディーターがニヤニヤしているのに気が付く。
「……」
「なんだいそんな厳しい顔して。ほらほら笑って笑って」
「さっきまで幸せだった人間のする顔じゃないぞ」
「……助けに来るんじゃなかった」
額に手をやりため息をつく。そのときユリアは、殴られて気を失っている男のそばに座り込んでいた。懐を探り、懐中時計に見える機械を取り出す。
「……これは……いや、しかし……」
操作と発動タイミングの短さからリベール製だと直感した。案の定、外側は帝国製を装っているが外蓋をこじ開けてみれば見慣れたリベール製だ。だがどこにもシリアルが無い。
当然といえば当然だが、国内で使用されるすべての戦術オーブメントにはシリアルが刻印される。持ち主と所属をはっきりさせるためで、無いものがあるのがおかしいのだ。
「……流れた……どこから?」
自分が持っているそれと見比べながら考え込む。
「どうしたんだい? 考え込んで。ディーターが血なまぐさいのが嫌だって言うから、どこかに移動しようと思うんだけれど……」
「あ……すいません。これをみていました」
覗き込むオリビエに見易い様持ち上げる。
「オーブメントだね」
「シリアルが、ないんです」
「……?」
「オリビエ殿、戦術オーブメントを見せていただけますか?」
はい、と渡されたオリビエのオーブメントには、裏にきちんとリベールのシリアルが刻まれている。
「これのことです。リベール製には必ず刻まれていますし、以前みた帝国製にも共和国製にもそれぞれの国のシリアルが刻まれていました。存在的に武器、兵器と変わらない位置にいるので、これだけはどの国でも統一しようと決めているはずなのですが……」
「そいつが持っているものにはシリアルが無い、か……」
「じゃあユリア君。それをもっていってくれたまえ。キミに任せるよ」
「しかし」
「今のボクには残念ながらそれを解明する時間も余裕も人もいない。悲しいかな、ね。だから任せるよ」
「……かしこまりました」
立ち上がって深謝。その後、手近な部屋を支配人に開けてもらい一息つく。
「ユリア君の部屋でもボクは一向に構わなかったんだけど」
「……」
「……ユリア殿のほうが構う。やめてくれ」
「だから今更「殿」なんかつけなくてもいいのに。ディーター、大丈夫かい?」
寝台の上で寝転がっている幼馴染に声をかけた。
「なんとかな。あれだけの血にお目にかかることは滅多に無いからなぁ」
寝返りを打ってうつ伏せになる。
「しかし、よくここにいるとわかったな」
「だってここ、姐さんがいたところじゃないか。オリビエが一番好きだった」
ミュラーの問いかけにくぐもった声で返す。そうか、と目を伏せた。
もともとこのあたり一帯は花街だった。空港が近辺に出来、風紀が悪いということで花宿は移動させられるか廃業に追い込まれている。そこで働いていた遊女の一人を、オリビエは姐さんと呼び親しくしていた。店が廃業する前に流行り病で死んだが、今でも命日には三人で墓に出かけていた。
「ミュラーは知らなかったかもしれないけどさ、あの宿の経営者がここのホテルのオーナーなんだ。そのつてもあって」
「ああ……そういうことか……」
「そういうこと。それにしてもディーター、なんでわかったんだい?」
「んー? 朝っぱらからちょっとやりあってな。夕べから居座ってた酔っ払いを追い出したときに」
グダグダといいつづける酔っ払いを店の外に放り出したとき、仲間らしき人間がやってきた。
「そいつらが言ってたんだ。ターゲットはホテルだってな。夕べからのグチで遊撃部隊の奴だってのはわかってたから……ついでに奴ら、俺に一発ぶちかまして行きやがった。さっき仕返しできてスッキリしたよ」
寝転がりつつ豪快に笑う。残りの男たちも笑った。
「さっきは息ピッタリだったね。みてたんだけどさ、あの銃綺麗にユリア君のところに落ちたもん」
銃も上手いんだねと続けると、オーブメントを前に考え込んでいたユリアが顔を上げた。
「あ……いや、一応訓練はしていますので……あまり射撃は上手い方ではないのです」
「そんなことない。ここにも一応軍人いるけど、彼よりもよっぽど上手いよ」
じろりと睨むミュラーも気にせず続ける。そこへ、グランセル行き最終便があと一時間後に出るとの知らせが入った。
「じゃあ、ボクたちはここにいるよ。荷物をまとめたり、別れを惜しんだりしてくればいいんじゃないかな」
ニコニコ笑っていったオリビエだが、そうさせてもらうと本当にユリアと一緒に出て行ってしまったミュラーをみて拍子抜けした。
搭乗手続きを済ませ、本来ならばもう機内に入っていないといけないのだが、そうすることも出来ずにユリアは通路に立っていた。すぐ隣には黙って恋人が立っている。
「……そろそろ出発だ」
「ええ……」
言われなくてもわかっている。けれど、服の袖を掴んだ手が開かない。そんなユリアの手を男の手が覆った。
「何、約束は守る。貴女は貴女の、出来ることをしてくれ。出所不明のオーブメントの件は頼んだ」
諭すようにささやき、こわばっている女の指を優しく外していく。
「そんな顔をされると俺の決心も鈍る。頼む」
困った表情で、でもその瞳の奥には得がたいほどの優しさを宿し、ユリアの手に口付けた。出発を知らせる合図が遠く響く。
「わかり、わかりました。ですが、約束を破ったときには、覚悟しておいてくださいね」
「貴女に泣かれるのには弱い。だから、泣かさないようにする」
見つめあい、そして手を離してユリアは甲板へ。係員が来て柵に鍵を掛けていく。振り向けばミュラーがまだ通路に立っていた。係員が何事かと言う表情をするのをよそに引き返し、柵越しに男に口付けをした。散見する見送りの人たちも係員も驚いて二人を見ているが、構わず口付けを続ける。機体が振動し、浮き始めたところでようやく唇を離した。
「この感触……貴方の手、体……忘れないうちに、必ず」
「必ずだ」
遠ざかる男を眺めているとリベール式の敬礼をしてきた。つられて敬礼を返す。見えなくなり、係員に怒られてもそのまま下を見つめつづけた。