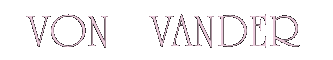
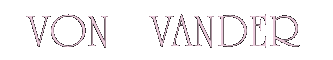
冗談は止せ、と思わずつぶやいてしまった。幸い、忙しく立ち働くホテル従業員たちがユリアのつぶやきに気がついた様子はない。代わりにどんどんとドレスを運び込んでくる。
「おい、もう部屋に入らないんだが」
「ちょっと待てよ……まだ二ケース残ってるんだけど」
廊下からそんなやり取りが聞こえてくる始末。部屋の中にいた従業員ですら苦笑いだ。
「……もう一度伺いますが、これはオリビエ・レンハイム殿からなのですよね?」
「はい。こちらに送り状が」
渡された紙には確かにオリビエの名。ドレスと、それに付随する小間物一式。それが数十着。いったいどうしろというのだ。
「どう……なされますか? まだケースが二つほど……」
「あー……もうそこまで持ってきていただいているんですよね。ベッドの上に置いてください」
これでドレスの海をどうにかしないと眠ることすらできなくなった。部屋に一人残され、周りを取り囲むケースを眺める。
「確かに型は違うのかもしれないがここまでとは……」
手近なケースの蓋を開けて中を見る。基本は白なのは以前と同じ。少し露出度は上がっている、ような気がする。正直なところはどう違うのかよくわからない。
「とりあえずベッドの上だけでもどうにかしなければ」
眠ることもできやしないのだから。
「冗談……」
二日後に改めてつぶやいたのがこれである。ホテルの前に着けられているのは馬車だ。それほど華美ではないが、見慣れていないユリアにはとてつもないものに見える。もっとも、道行く帝国人たちは気にしている風ではない。
「すまない、こんなことになって」
降りてきたミュラーが申し訳なさそうな表情でユリアの手を取った。
「少し早いが、構わないか?」
「……あっ……ええ……」
自分もそれに乗るということに思い至っておらず、問われて初めて気がつくありさま。連れて行かれるままに乗り込めばオリビエもいた。
「やあユリア君。よく似合っているよ。送った甲斐があるというものだ」
「あ、ありがとうございます……」
素直に喜べない。まだ他のドレスはユリアの部屋に置かれたままである。
「他のものはそのままお返し……」
「アレはユリア君にプレゼントだ。煮るなり焼くなり、好きにしてくれたまえ」
「……はあ……」
どうあっても返却を受け付けようとしない。ゆっくりと馬が足を進める音がする。
「帝国では、馬車が常用なのですか?」
ここ最近帝都を歩いたが見かけたことは無い。
「帝国では、というより貴族は、が正しい。帝都は結構狭いところが多いからあまり使われない。ただ、地方の領主たちはこれがないと生きていけないわけだ」
「リベールでは導力を使った移動用の車があるよね。けれど帝国にはそこまでの技術力がないんだ。最近ようやくそれに近づいてきたみたいだけど、まだまだ」
窓に掛けられている薄布を軽く持ち上げ、オリビエはゆっくりと流れる景色を見た。
「流石にね、門の前で『来ました』ってガンガンたたいて、そこから屋敷まで徒歩で行くのも格好悪いしさ」
大した距離は無いんだけど、と付け足して片目を閉じた。その言葉どおり、それからあまり間を置かずに馬車が止まる。ものものしい鉄の門扉の奥には広い庭園が見えた。
「話をつけてくる」
言い置いて馬車から降り、ミュラーが門番に近寄る。しばらくの間を置いて門が開き始めた。再び馬車が動き出し、ミュラーも乗り込んで息を吐く。
「これからがまた長いんだな……歩いていけば速いが」
「だからって、庭を縦断して、玄関につくころには疲れ果てているなんてイヤだよ、ボクは」
二人があきれた笑い声をあげているとき、ユリアにはその会話を聞く余裕が無かった。窓から見える景色が少し変わり、下から響いてくる音も変わった。いよいよだ、と思うと自然とうつむいてしまう。
「……」
そんな女の肩を抱き、驚いて見上げる顔に微笑んでみせるミュラー。オリビエはその様子を眺めたが、やがて両手をひらひらとさせる。
「ふー、参った参った。ミュラーがユリア君の隣にあたりまえのように座ったときも思ったんだけど、こりゃボク、お邪魔だよねー。すまないねユリア君、馬車は二台にしたほうがよかったね」
「あっ」
瞬時に顔が熱くなる。肩に置かれた男の手を外そうとするが、面白がっているのかミュラーは離そうとしない。逆にもっと力をこめてきた。
「ミュラー殿……あの……大丈夫です」
「そうは見えないが」
確かに、口で言うほど大丈夫ではない。表情も体もこわばってしまっているし、膝に手を置けば小刻みに震えている。
「でも、大丈夫です」
一瞬だけ何かいいたそうな顔をしたものの、今度は黙って抱いた手を離し、それを楽しそうにオリビエが眺めていた。
「オリヴァルト皇子殿下ご一行の到着です」
「お、来た来た」
給仕がヨハネスに知らせに来たので、心なしかうきうきしながら部屋に呼ぶように伝える。しばしの間を置いてノックの音がした。
「入ってくれて構わん」
最初の一声をどういおうかと悩んだ。浮き足立つ様が声に出てしまうと、当主としての威厳が足りないと思われるかもしれない。けれど、そんなにかたい人間でもない。
「入ります」
「なんだ、マルセルか」
「お言葉ですな。お客人です」
ミュラーかオリビエがくると思っていたところに老執事が顔を出した。一瞬がっかりするが、続けられた言葉に襟を正す。今度こそ、待ち人たちだった。
「やあヴァンダール卿、久しぶりだね」
「これはこれは、オリヴァルト殿下。その名では自分を呼ばれたとは思えないですな」
「なに、今日お披露目だろう? これからこう呼ばれるのだから」
「それは確かに。愚弟は元気で殿下の御身を守っていますかね?」
「本人に聞くのが一番さ」
握手を軽く交わし、オリビエが脇に寄る。続いてミュラーが見知らぬ女性を従えて前に出てきた。
「兄上、お久しぶりです」
「うむ、健勝そうだな」
いつものように大仰に挨拶をしてくるので、こちらもわざと大仰に返す。再会したときの冗談のようなもので、今回もひとしきり笑った。
「……で?」
「ああ、こちらがそうだ」
言いながら控えていた女性を前に押す。普段では見られない弟のいたわりの表情が、相手をどういう風に思っているかを如実に語っている。少しうらやましかった。
すらりと伸びた手足と細身の体。白く薄い、つややかな生地のドレス。装飾は最低限、比較的露出の少ない型。所々見える体は鍛えられており、細かく傷もあるようだ。ただそれは気になる、というものでもない。短く切られた髪は綺麗な髪だと思った。伸ばせばそれはそれで似合うだろうな、とも。控えめの化粧と、少し困ったように細められた瞳。だが強い意志を秘めていそうな厳しい瞳。
「は、初めまして。自分はユリア・シュバルツと申します」
少し不安そうに一礼をした。
「……ほう」
「……」
ヨハネスは目の前に立つ女を眺める。ユリアは緊張した面持ちでヨハネスの言葉を待っていた。
「弟から聞いていたが……こんなに美人だとは思わなかった。殿下が見込むだけのこともある」
「……え……」
「歓迎する。俺はヨハネス。ヨハネス・ヴァンダール。そこの仏頂面のヤツの兄だ」
笑いながら手を出せば遠慮がちにそれを握る。
「よかったねぇユリア君。お兄さんに気に入ってもらえて」
「貴様は口を開くな」
茶化しあいをする二人に困った視線を向けるユリア。
「うるさいのは放っておこう。それはそうと、貴女は軍人だとか。……疑うわけではないのだが、帝国に女性軍人はほぼ皆無なのだ」
「存じ上げております。けれど、これでも女王陛下に剣をささげる身です」
「だろうな。……ああ、立ったままで申し訳ない。殿下も一緒にこちらへ」
ソファに座るよう勧めヨハネスも座る。見計らったかのようにマルセルが飲み物を持って現れた。それぞれ手に取り、マルセル執事も下がったところで乾杯。
「卿、いきなり飲んで、演説のときに酔っ払ってたらいけないよ」
「すぐ醒めますよ。それに、マルセルはそんなに強い酒は持ってきていない」
半分ほど杯の中身を空にし、少しずつ飲んでいるユリアを見る。
「さてシュバルツ殿。こいつとのなれ初め、いろいろ聞かせてもらおうか」
「は、はい……。あれは一年程前でしたか……」
節目がちに話しはじめる女。所々オリビエに助けてもらいつつ、その、決して穏やかではない足跡をたどっていく。所々でユリアが頬を染めれば呼応してミュラーもわざとらしく酒をあおっている。なんとわかりやすい二人だ、と思っているうちに話が終わった。
「……と、このような感じでしょうか……」
「そうだね、ボクもそんな感じだったと思う」
「貴様がどれだけのことを知っているというのだ……」
胸を張るオリビエに一瞥をくれてヨハネスにミュラーは顔を向ける。
「で、満足か兄さん」
「満足も何も、夜はこれからだ。隠していることを聞き出すからお前は出ていろ。申し訳ないが殿下も今しばらく部屋の外でお待ちいただけないでしょうか?」
「ボクには依存はない。ミュラー、行こう」
「いや、おい……」
一瞬ユリアに手を伸ばしかかったが、オリビエが部屋を出て行くのを見て仕方がなく外に出て行った。後には不安そうなユリアと、やれやれ、と息を吐くヨハネスが残される。
「……シュバルツ殿」
「は、はい!」
知らず丸まっていた背中がぴん、と伸びる。
「俺の弟はあんなやつで、どうにも不器用な男だ。その疎さは、兄弟でも驚くほどに」
乾く唇を酒で湿らせため息。
「だが、決して悪い奴ではない」
「……ええ、よく存じ上げております」
「ありがとう。……ついでに言えば、やはりヴァンダールの名は奴について回る。望む、望まざるに関わらず。俺に何かあればあいつが当主なのだ」
「……」
「結構な確率でそれは発生する。リベールでもそうだろうが、帝国貴族は有事の際に先陣を切る。それこそが貴族の役割だ」
「ええ……はい」
「そのために戦争を起こすという噂まであるぐらいだからな」
自虐的につぶやいて一人笑う。
「有事の際、部下に任せきりで自分は安全な場所にいるままでは、部下の心はつかめません。上にたつものには、その下にいるもの達を守る義務があります。貴族という立場も、それと同じようなものと認識していますが」
「ああ、そうだ。……つまり、何がいいたいかというと」
当主は頭を掻き、ユリアから視線を外す。
「それでも、俺の弟を……ミュラーを見ていてくれるのかということだ」
貴族としての生き方を強いられるかもしれない。権謀術数渦巻くこの世界は、弱ければ弾き飛ばされてしまうのだ。それを知るから、かつての弟の想い人たちは姿を消した。口にも顔にも出さないが、深く傷ついていることは知っている。
だがユリアは即答した。
「もちろんです、ヴァンダール卿。あの方が許してくれるのならば、自分はずっと想っています」
「……ありがとう」
少し頬を染める女を眺め、ヨハネスは心底から感謝をした。
なし崩し的にパーティーに参加することになった。大半は壁際に立って、あちこちで話が盛り上がっているのを眺める。
「壮観だね、ここまで貴族がそろうというのも」
「そうなのですか」
「以前、ボク主催の晩餐会に出てくれただろう? あの時には来なかった人間も来ているから」
伸びをしつつ、オリビエが声をかけてきた。
「ボクの兄たちさ」
「……あ」
言われてみれば、オリビエによく似た面差しの男を数人見かけた。
「ヴァンダール家は基本中立だからねー。ボクもそうありたいと思うよ。みんな仲良くコンサート。これが一番だと思うのだが」
「ふふ、オリビエ殿らしい」
「もちろん綺麗どころのダンスも入れたいね。ユリア君も参加してくれるだろう?」
「それは……そのときに考えます」
「前向きにね、前向き。……お、来たよ」
前を向けばミュラーがグラスを持って歩いてきた。オリビエの姿を認めると肩をすくめた。
「居たのか。残念だが貴様の分は無いぞ」
「構わないよ。退散するから」
言いながらまたにぎやかな輪に戻っていってしまった。見送ってからミュラーはユリアにグラスを渡す。
「ありがとうございます」
ゆれる深紫の液体を眺め、先程合ったことを思い出した。
「そういえば……リカルダ殿にお声をかけていただきました」
「義姉さんが?」
「ええ、卿からお聞きになったのでしょうか、よろしくお願いします、と。確かまだ殿下と大してお年は変わらなかったはず。やはり、しっかりされた方が多いのですね、貴族には」
「そうでもない。俺は出奔したし、他にもただの放蕩息子としか言いようの無い人間もいる。それぞれだ」
「……時間が経てば、変わる事もありますよ」
見えないように笑い、グラスから液体を流し込んだ。しばらく黙っていたが、気分転換をしようというミュラーの言葉に従い外に出た。
月は沈みかかっている三日月。星の光の強い夜だった。
「無人とは行かないが……」
まばらに人の姿が見える庭園へ降りていく。何の花かは知らないが、真っ白な花弁が星の光を吸収しているかのように輝いている。
「それでも静かだ。その方がいい……」
繋いでいた手はユリアの腰に回されてくる。ユリアもより近くに寄り添い、広い庭を散策し始めた。すでに語らっているカップルを邪魔しないように気を使いつつ。
小さな噴水が作られているところまでくると、本館からやや離れているため人が居ない。あたりは薄く導力灯で照らされ、ぼんやりとその輪郭をあらわにする。ささやかな水音が聞こえる近くのベンチに腰掛けた。
「……歩いてみたかった、この庭。俺が思う、帝都のいいところの一つだと思っている。一番は皇城への道途中だが」
「ええ……リベール貴族でも、ここまでの庭を持っているところはそうそうないですね」
張り出してきている枝に手を添えてついている花を見る。祖国では見かけない花だ。
「北の方の花だ。たまたま献上品の中にあったと聞く。曽祖父の時代だそうだ」
説明を聞きながら枝と戯れているとミュラーに引き寄せられた。若干のけぞる形で腕に収まる。しばらくそのままでいたがそれ以上はない。だが。
「……」
妙な気配がある。視線をそっと動かすと男も軽く頷いた。またしばらく沈黙を保つ。じりじりと足が即時に動ける位置へ動いていた。ユリアもすそを掴み、いつでも引き裂き動けるように身構えた。
風と水音にまぎれて後ろの茂みがゆれた。ボソリと声が聞こえてくる。
「申し訳ありません」
「……ああ」
ミュラーが警戒を解いた。直後に気配は雲散。ユリアはまだ警戒したままミュラーの言葉を待っている。
「警備の人間だ」
「え?」
「おそらく兄の配下だろう。あの腕なら、一般の貴族は存在に気が付くまい。正直なところ、俺も真後ろに来るまでははっきりとわからなかった」
「私もすぐにはわからなかった。あのような方を部下にもたれているのですね、卿は」
「この家には俺よりも腕の立つ人間が山のようにいる。手合わせしようという気も起こらん。おっと……そう驚いた顔をしないでくれ。帝国ではあたりまえなのだ。宰相殿の屋敷や、直系皇子殿下たちの屋敷はもっとすさまじい」
「リベールでは……あまり考えられない事です」
「まあそうだろうな」
女から視線を外し、一際明るく輝いている星に目をやった。
「この国の歴史は内乱の歴史だ。己の身を守る為、貴族たちは金にあかせて腕利きを雇う。ただ、うちはそれだけではない」
「どういうことでしょうか?」
「中立であり続けるため。どこにも屈さず、どこも支配せず。『どこからに対しても壁であれ。そしてどこにとっても最後の砦であれ』。当主の家訓だ」
ヴァンダール家はどこからも資金援助を受けていない。複雑な関係の結果、他の貴族たちは何がしかの相互援助を行っているものである。だからこそ孤高を保つことができた。そんな芸当ができるのは、たまたま領地が豊かだったからだ、と付け加える。
「でも……こうやってミュラー殿はこちらにいらしています。それは、問題なのでは?」
「今回は特別だ。オリビエが公式に訪問しているし、俺は奴の護衛ということになっている。今日は帝国中の貴族がここに集まっていると言っても過言ではない。敵味方関係なくな。普段はほとんど意識しないが、こういうときは嫌というほど思い知らされる。自分の出自は、宰相殿とはまた違った意味で帝国で一目置かれる存在なのだと」
「そう……ですか」
薄い明かりでは表情はよくわからないが、とても寂しい声だった。ユリアは少し考え、体を伸ばし男の頬にそっと口唇を押し当てる。すぐに体を元に戻せば、抱いて来る手に力がこもった。
「……公式には滅多に来ないのだがな」
軽く笑う。
「非公式には何度か来ている。オリビエは妙に城から逃げ出すのが上手いから、多分ほとんど気づかれていない」
「大丈夫なのですか?」
「不本意ながら俺も同行している。段々、見張りをかいくぐる術が上達してきたのが嫌だ」
冗談めかした声には寂しさは無い。安心し、ユリアは肩を震わせて笑った。
「では、今度指南してくださいね」
「どうする気だ? まさかお忍びの漫遊でも?」
「それもいいですが、できるなら、逢いに来ますよ」
「ならみっちりと仕込もうか」
笑いあい、また静かに星明りの夜を楽しんだ。
帝都封鎖令が猶予付で発令されたのは、その早朝のことである。