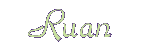
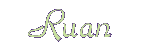
卓上灯の光度を最大にし、持ち歩いている小さめの本を手にとる。ソファーに座りながら目を通すものの頭には入らない。
体が熱いのは酒のせいなのか、それともシャワーを浴びたせいか。そのどちらでもないのだろう、とユリアは思う。
「今日は……怖い」
紺碧やエア=レッテンで怒る様子や、街道での出来事を思い出しては体を震わせる。
二部屋取っていたようで、ミュラーは別の部屋に戻っていた。怖さの奥でなにかを期待していることに気がつき、ユリアは自己嫌悪しながら立ち上がる。
「ここはどこの宿だろう」
ルーアンは観光に力をいれているためか、他の都市よりも宿泊施設が多い。ここもその一つだろうとは思うが、なにせ到着した時の記憶が無い。窓から外を見る。跳ね橋が明かりに照らされて美しい。
「……だめだ、わからない。基本的に跳ね橋が見えるように窓は作るはずだからな……」
濡れた髪は乾いている。少し身支度を整えて部屋から出た。静かだ。
ロビーまで来て鍵を預ける。すぐに戻るからと言い残してホテルから出た。少し歩くと左手に教会が、右手にギルドの看板が見える。
「……ギルド裏だったか」
正面のカジノバーからはにぎやかな声。教会に続く橋の上では若いカップルが語らっており、ユリアは足早に通り過ぎた。
まだこの街は眠っていない。工房や食料品店は閉まっているが、観光客相手の店はこれからだ。クローゼが王城に戻ってからルーアンには滅多に来なくなった。部下たちの慰安を兼ねてよく一日二日、逗留したことを思い出す。
振り向き、ホテルに戻ろうとすると、先ほど橋の上で語らっていたカップルがこちらに歩いてきていた。邪魔にならないように避け、見送る。
「……やはり、羨ましい……」
国家にとって望ましくない思いの行き場。せめて自分がただの一般兵ならと、どれだけ思ったことか。そうでありさえすれば、帝国へ行くことも躊躇わないのかもしれない。
「けれど、アルセイユに乗っていたからこそ、あの人に会えた……」
あまり深く考えるものではないな、と頭を振った。
「お? 元気になったか、大尉さん」
明るい声が頭上からかかった。見上げればジンが顔を出している。そういえばギルドの真横だったと合点がいく。
「すまんが休暇中だ。階級はやめてくれないか?」
「おう、わかった」
顔を引っ込める。しばらくすると勢い良く戸が開く音がした。
「?」
怪訝に思ってそちらへ向かうと、やってきたジンにぶつかりそうになった。
「おっとすまん。どうだい? 酔いは醒めたかい?」
「ああ。だが自分がどこにいるのかわからなかったのでホテルからでてきていた」
「そんなに悪くないホテルのはずだが」
悪くない、と頷くユリア。よかった、と豪快に笑う大男。
「迷惑をかけた。セーブしていたはずなのだが」
「いいってことよ。人間、なにか弱点が合ったほうが愛嬌があっていい。あんたは酒が注意だな」
「飲みなれていないわけではないのだが、どうもいかん」
苦笑して頬を掻く。そんな女を見ながらジンが少し付き合ってくれないかと呟く。何事だろうと目を見るも意図はわからない。
「何かあるのか?」
「あー、たいしたことじゃない。俺のヤボ用にちょっとつきあってくれないか? 手間はとらせん。そこの小間物屋まで」
「……わかった」
首をかしげながら小間物屋に入る。所狭しと女物のアクセサリが並べられていた。
「俺はこっちは門外漢でなぁ。ルーアンには舶来品が多いから、何か買ってきてくれと言われたはいいが、全くわからん」
「はあ……私もそんなに詳しいわけではないが」
「でも、あんただってこういうの嫌いじゃないだろ? 嫌いならそんなピアスはつけんだろう」
指され、確かにそうだと思い直す。
「つけるのはどういう人だ?」
「あー、これ見た方が早いな」
懐から一枚写真を出す。そこには淑やかな東方風の女性が写っている。
「ジン殿の思い人、か?」
「そういうのでもない。まあ昔馴染みだ」
写真とアクセサリとを見比べながら歩く。ひとつひとつ見比べては置き、また手にとる。ジンは店から出て、店の主人となにやら話し込んでいるようだ。
ふと、髪飾りの一つに吸い寄せられた。小さな丸い飾りが数個つけられて、動けばそれが揺れる。小さな七耀石がすべて使われており、光を通せばさまざまな色に変化した。これを、と思うが写真の女性にはどうにも似つかわしくない。また再び歩き始めるのだった。
「思ったより時間がかかったな。すまねぇ」
「こちらの方こそ優柔不断で、なかなか決められなかった。申し訳ない」
「そうなるだろうと思ったから店のオヤジと話をしてた。でもあんたが選んでくれた中から探すのは楽だった。選んでくれてた物も、どれもあいつに似合いそうでよかったよ」
「役にたてたのなら、光栄だ」
「これで怒られなくてすむ。……あんたも戻った方がいい。迎えがきている」
「迎え?」
一瞬部下がいるのかと思ったが違う。いつにもまして不機嫌そうなミュラー。
「すまんな。俺のヤボ用に付きあわせちまった。もう用は終わったから、つれて帰ってくれ」
「そうさせてもらう」
抑揚の無い声で応じユリアの腕を掴む。強く握られて鈍く痛んだ。
「じゃあな。いい夜を」
「ああ、そちらも」
男に引き寄せられながらユリアは大きな背中に返した。そのまま教会前の橋までつれてこられる。
「……」
握り締められた手は離され、水に映った爪月を眺めている。月は揺れる水面にゆがんで映っていた。
欄干にもたれてユリアに向き合う。ちょうど橋からの明かりが逆光になり表情はわからない。目を細めながら男の言葉を待った。だがミュラーは女の方を向いているだけで何も言わない。段々無言で責められている気がしてきた。
「責められることは……していないと思うのですが」
「今日、貴女が助けた少年に獲られることすら嫉妬している自分がいる。気心が知れているとはいえ、それなりの年の男と話していて、快くいられるとでも?」
「あ……」
すみません、と呟く。
「飲みなおしをしようかと貴女の部屋に行ってもいない。フロントで聞けばすぐ戻ると言った。が、待てど暮らせど戻ってこない。探しにくれば男と話している。……醜い嫉妬だ、これは」
頭を振りながら独白した。
「私も、嫉妬しますよ」
貴方の、守るべき方に。
私の知らない貴方を知る方に。
私より長い間、貴方と傍にいる方に。
ぽつりぽつりと語りながら俯く。
「どうしたって、どうやったって。……埋められない。嫌になるくらい、オリビエ殿に嫉妬している」
「……そうか」
「立場に縛られ、自由に飛ばすことも出来ないこの思い。……どこに、もっていけばいいのか、ずっと、悩んでいます」
地面を見て歯を食いしばる。確かに通じ合った思い。だが、そこからどこへ行けばいいのか。
「答えは、でているのですけれど、今の私には、まだそれを実行することができない……」
士官学校をでてからすぐに親衛隊に入るよう言われたのは、親衛隊は女王やクローゼの身辺警護をする関係上、女性が比較的多いからという意味合いもあった。帝国はもとよりリベールでも軍は男社会である。戦役時代の経験は、その後の生活の中で妨げにしかならない。
が、それを断ったのは他ならぬユリア本人。各地方分隊を転々とすることでトラウマを治そうと荒療治をした。ほとんどの人間に反対されたが強行し現在にいたっている。
「本当に、もっと早くに言っておけばよかった。……どこか、私のすることは抜けているようです……」
「それはいい。ゆっくりと治せばいい。治らなくても、できるだけかかえてみせる」
ホテルへの帰路につきながらミュラーが呟く。
「……俺たちは似ているな。立場とか、そういうものでなく、なにか根本的なものが」
「そうかも、しれませんね……」
息を吐きながらユリアも歩き出した。
「それにしても、一昨日はかなり積極的に俺に迫ってきたのに、今日は嫌におとなしい」
「そ、それは、夢見が悪くて」
「覆い隠す為に俺を求めた、か。そういう形もあるだろうが、俺はそういう抱き方はしたくない。本当の意味で通じ合うまで待つ」
だから、無茶に惑わさないでくれ。付け足された言葉に笑った。
突然の炸裂音。同時に臨戦体制になるが、ざわつくものの不穏な気配は無い。また何かが爆発する。戸惑っていると、誰かが花火だと叫んだ。
何も言わずとも思ったことは同じ。ホテルへ向かう足を方向転換し、街を貫く河の方へ。艀の上に数人の花火職人が乗っており、そこから打ち上げていた。一発打つごとに艀が揺れる為連発は出来ないが、滅多に見ることの無い炎の色に観光客は喜ぶ。
もうすぐ近くには寄れないが火の匂いはすごい。だが、自分達が今までなれた砲火とは違う。
「この火は、いい火だ」
「ええ。とてもいい火だ」
儚く落ちる火の欠片に、あの火は悔いは無いのだろうかと思う。
ただその一瞬だけ。その時だけ、輝く為に生まれた火。
「……」
黙って見上げている横顔を眺める男。今にも、頭上で展開されている花火と同様に、散っていきそうな横顔。本当に消えてはしまわないか、本当はもうここにはいないのではないか。
そんなはずは無いのに強烈な不安が消えない。そっと手を出し、しっかりとそこに在るのを感じ、ようやく安心した。
「どう、しました?」
「……なんでもない」
一つ一つ打ち上げられては大輪の花が散る。散ってくれるな、と思うことは己のエゴか。散るからこそ愛しいことはわかっていれど、そう思うことはとどめられない。
「人が多くなってきましたね。いつ終わるかわかりませんが、ホテルからでも見られるのではないでしょうか?」
「ああ、そうかもな。……もどるか」
「はい」
集まり始めた人間を掻き分けながら今度こそ、とばかりにホテルへ向かう。想像したとおり、部屋からも良く見えた。
「飲み直し、しないか?」
「え? 私は……」
「心配するな。さっきも言ったが、俺は眠る人に手をだす気はない。自分のペースでゆっくりといけ。ただ静かに飲み交わしてみたいだけだ」
それなら、とソファに座る。注がれたワインは白でもなく、赤でもなく。
「アガット君のお薦めだそうだ。どんな味なことやら」
「私が陥落している間、あちこち寄られたのですね」
「そうあちこち寄ったわけではない。食事をした酒場で売っていたから、買ってみた。貴女を背負って買い物はちょっと難しい」
「……すいません」
「それはもういい。いい加減にしないと、眠らないうちに手を出すぞ」
「……子守唄付きなら、歓迎しますよ」
「子守……おいおい」
戸惑いから呆れた笑いへ。透き通った音を立ててグラスが合わさった。
Ende
この二人はどこまでいくんだ、とルーアンへ。私にしては珍しく、酒に弱い女性なんて設定がついてます。いやー、少佐きっともんもんとしたに違いない(待て)。弱い、というかそれなりだけど、他が規格外だったという感じですね。スピリタスが寝酒なんてことが出来そうな野郎三人組(できません)。まー書いてる本人なーんも考えてません(笑)。
どうあってももぞらせる気はないらしい自分。すいません、一線越える寸前、というの、個人的に激しく萌えなんです(苦笑)。