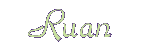
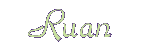
薄暗い道を降りていたところ、突如魔獣に囲まれた。少々慌て気味にエア=レッテン上層から戻ってきていたので気配を読み損ねていた。剣を抜きながらユリアはそっと舌打ちをする。間の悪いことに、等間隔にある灯がもっとも届かない位置だ。
「明かりを灯します!」
いいながら戦術オーブメントを操作する。ややあって、薄暗いが確かに辺りを照らすものができた。浮かび上がる魔獣たちを切り払いながらもっと明かりの強いところへ移動をした。
「ひ、ひいいっ!」
「!」
老人の悲鳴を聞き二人はもと来た道をとって返す。先ほど冷やかしてきた老人が腰を抜かして地面に座っており、その回りには浮遊する魚のような魔獣が数体。
「俺は右から回る。貴女は左から」
「承知」
いいながらすでに一体を切り裂くミュラー。負けないようにユリアも切っ先を突き出す。それほど数が多くないこともあり、数分で辺りは静かになった。
「ご老人、立てますか?」
聞くがまだ恐慌状態。よく見れば、足から血を流していた。
「申し訳ないがミュラー殿、エア=レッテンまで行って、誰か呼んできてはくれないでしょうか。私が手当てをしますので」
「……ああ」
ユリアが関所に行った方がいいだろうが、知った人に見つかるのを嫌がる様子を思い出して頷いた。
関所の看板がでているところまで来ると、見張りらしき兵が二人何かを話していた。とくに気にするともなく聞き流して歩くが、
「ユリア大尉」
の、単語でその場に立ち止まる。
「だから、アレ、王都に常駐してる親衛隊の隊長だと思う」
「ほんとかよ。俺はよく知らないからなぁ。王都常駐って言ったらアルセイユ組がほとんどだろ?あそこの噂はいろいろだが……。前に血も涙も無い鉄の女って聞いた」
「それは違うぞ。親衛隊に知り合いいるから聞いたよ、確かに厳しいけどいい上司なんだってさ。オレ前王都駐在だったんだ。ほら、あのよくわからんものが湖の上に浮いてた頃」
「ああー。忘れようにも忘れられんな。上からデカブツが降ってきて、よりによって出水口付近だったもんだから、俺まで撤去に狩り出されたんだっけ」
「お前の思い出話なんかどうでもいいんだ。それより子ども助けたあの女だ」
「……結構酷い奴だよな、お前」
左側に立つ見張りが呆れたが、右の兵は気にせず話を続ける。なんとなくミュラーも水面を見る振りをして会話を聞く。
「とにかく、あれが壊れて落ちてきた頃、王都前広場にでかい生物とアルセイユが下りてきたんだ。そのとき、艦長って呼ばれてた人にすっげー似てるんだ。それに、前に写真でたぜ」
「まさか。メチャクチャ嫌がってるって噂だぞ?」
「ふっふーん、リベール通信に載ったんだ」
得意そうに胸をそらす右の兵。
「一瞬にして売り切れた、例の号だ」
「あ! 店に置くなり消えて、本社の方にすら在庫が無くなった号か!」
「仕事サボって本屋開くの待った甲斐があるってもんよ。もっともそれが目的じゃなくて、デカブツが浮いてた真相が報道されるっていうからそっちが読みたかったんだ。そうしたらその中にあったんだな」
「っくー! おい、俺にも読ませてくれ!」
「今はもってないぞ。ロレントの実家に置いてある」
残念そうに足を踏みしめる左の兵。
「落ち着けよ。今はその話じゃなくて、昼の女の話だ」
「そこに戻るか……でもよ、もしその女が大尉だったとして、お前それでどーする気なんだ?」
「俺ファンなんだ」
「……全然聞いたことなかったぞ」
渋面で隣の同僚を見る。
「だからサインを」
「お前なあ……でもさ、昼の女、男連れだったぞ? あの女がカーテン巻きつけて窓から飛んだとき、端持ってた奴はこの辺では見ない顔だった」
「野郎の顔なんか見ちゃいねーもん、俺」
「わかりやすい奴だ」
呆れつつも笑いが出てくる。
「お前だって、野郎と女がいたら、女しか見ないだろ?」
憤慨して強く言い返す。わかったわかったと手をあげた。
「はー、戻ってくるかなぁ。戻ってきたら全員で最敬礼でお迎えするのに」
一転、うっとりするような目で爪月を眺めている。もうダメだと左の見張りが首を振ったとき、ミュラーは何故自分がここにいるのかを思い出した。その場を離れて建物内の兵に怪我人が出たことを伝えた。
衛生兵を二人ほど連れてもとの場所へ戻っていると、老人がユリアに支えられながらゆっくりと降りてきていた。
「見た感じでは深く切ってはいないようだが、どこか神経を痛めてはいないか心配で。どうかよろしくお願いします……」
兵に老人を頼み頭を下げる姿。それを見て、関所の兵やアルセイユの面々がユリアを慕う意味がわかった気がする。それなりに階級が上がるとどうしても下に対して横柄になる。自身にも覚えがある。そうでないから兵たちに愛されているのだ。
「見習わなければな」
「なにか仰いましたか?」
「いや。それはそうと、今晩はどこで泊まる?」
「エア=レッテンでも泊まれます。そのつもりだったんですが……」
「が?」
「多分今日は、戻ったら騒がれそうですね。あの親子が泊まってるかもしれませんし」
「ティータ君の言うとおりなら、きっと貴女を離さないだろうな。貴女を子どもとはいえ男にとられるのは俺も許せない、かも知れない」
「またそんな……」
お戯れは、ほどほどに、と笑いかけた。
「そうですね。ここからルーアンまではそれほど距離は無い。ルーアンで宿を求めましょうか」
「いきあたりばったりも極まれりだ」
「そういうものですよ。柔軟が一番」
歩き出した背中を追う。後ろから見れば華奢な双肩。その背を守る人が欲しかったと語った。だが、どんどんと離れていく背に、自分は本当にその守り手に値するか問われている気がする。
「そばにいることが出来ず、一体何を守れる?」
自然と歩みは遅くなり、ユリアの背は離れる。立ち止まり、明かりで出来た自分の影を眺めた。
「どうかされましたか?」
歩みが止まっていることに気がつきユリアが戻ってきた。心配そうにミュラーの様子を見ている。なんでもないと言おうとしたところに話し声が聞こえてきた。
「……!」
ユリアの手を取り急いで木立の下へ。木にユリアの背を押し付け挟むようにミュラーが立つ。
「な、何を!」
文句をいおうとした口を塞ぐ。
「こ、こん……な……ところで!」
ユリアも人が来ているのはわかっている。カルデアとは訳が違う。精一杯抵抗をするが押さえ込まれ。いつもとは違う様子に若干の恐怖を覚える。
その間に数人、集団が通っていく。押さえようとしても出るユリアの僅かな喘ぎに下卑た笑いを浴びせ、だがこちらに近寄るような真似はせずに去っていく。十分去ったところでミュラーはユリアから体を離し、集団が去った方向を見た。
「……くっ、一体何をしに来た、宰相の腰巾着め」
帝国の、宰相寄りの一般臣民にすら評判の悪い文官だ。
「リベールに別荘を持っているとは聞いていないな」
嫌な気分だがこの国を帝国の都合でかき回すような真似はしたくない。体に沸く憤りをどうにか押さえ、ユリアの方を振り返れば、目線にいない。下をみるとへたり込んでいる。
「どうした?」
「どうした、ではありません!」
珍しくミュラーに対して声を荒げる。半分涙目で顔は赤いようだ。
「なんですか! こ、こ、こんなところで!」
「……ああ……」
顔を見られないことだけを考えていたので意識しなかったが、どうも普段より激しい口付けを送っていたらしい。
「ああ、ではありません!!」
先ほどと同じように声を荒げた。
「すまない。顔を見られたくなかったので咄嗟だった」
「だからといって……ふう」
何かを言おうとしたがあきらめて頭を振る。顔がほてるのか自分で頬に手を添えては扇ぐ真似をした。
「とにかくルーアンまで行きましょう。あまり遅くなると酒場も閉まる」
明らかに動揺を隠しているがそれについては何も言わず、ただわかったと応じた。