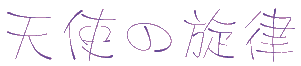
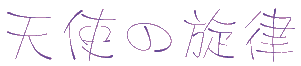
「これは王室からの厳命だ。しかと、承るように」
ウルリッヒから言い渡された命令に意識が凍りついた。
「な、なんで私が…」
「それだけ王は貴女のことをかっているのだ…恐らく」
取ってつけられたような恐らく、というのが引っかかったが、そこまで言われればやるしかない。
「わかりました…。でも、本当にどうなるか…保障できませんと、お伝え願えますか?」
「……では、そのように伝えておこう。ついてはその場所だが」
と、地図を机に広げ、国境付近の場所を示す。
「ここで行ってもらいたい」
「ここ…ここってシュミッツの草原より奥じゃないですか!」
「そうだ。この計画、ザールブルグ内で行うわけにもいかぬだろう」
「そりゃそうですけど…お店…」
「その間のドルニエ殿、イングリド殿、ヘルミーナ殿、ならびに雇っている妖精達の生活費と雇用費はある程度まで王室で負担する。それだけ、今回の件には力が入っているのだ」
「はぁ」
内心滝のような涙を流しながらリリーは応えた。しかも、ある程度までというのがなんとも哀れだ。
「もしかして、どんどん深みにはまってる?私…」
「今回は特別に私も同行しよう。他に連れて行きたいものがあれば、遠慮なく言うがいい」
「はぁ…」
ウルリッヒがついてきてくれるのはいいのだが、問題の依頼内容のせいで頭が急に痛くなってきた。
王室主催の芸術祭が開かれるのは三ヵ月後。その中には歌唱の部があった。そこに、何を思ったのかゲルハルトが参加表明したのだ。彼の殺人的な声は王室にまで耳に入るほど有名で、もしも彼がそのまま出たら、気の弱い貴族の人間はその場で卒倒してしまうだろう。それを避けるためにリリーが指名された。
「錬金術の力で、ゲルハルトの歌声をどうにかして欲しい」
これがウルリッヒ、ひいては王からの依頼だった。
「そんなの…一体どうしろって言うのよ…」
聖騎士が去った後、彼女は痛む頭を抑えながら参考書をめくる。しかし、当然ながらどこにもヒントになるようなことは書かれていない。
「……とりあえず、超高性能耳栓はいるわね…」
泣きそうになりながら器具を手に取った。
「リリーっ、いるーっ?」
カリンが工房に顔をだしたが、主は居らず少女達と妖精たちが輪になって踊っていた。
「…なにやってんの?」
「あ、カリンお姉ちゃん」
「先生は今いませんよ。ウルリッヒ様と、ゲルハルトのお兄さんと一緒に出かけてます」
「採取?いつ戻る?」
そういえば最近武器屋休みだったな。そんなことを思う。少女達は首を傾げてカリンを見た。
「いや、今回なんだか特別な用事だって言って…」
「泣きながらレナフォルテ背負って出て行きました」
「れなふぉるてぇ?」
楽器の王様といわれる代物だ。音はすこぶる良く、弾きこなせばどんな音楽も生み出せる。ただ、巨大で重い。
「なんなのよ」
「なんでも今度の芸術祭がらみだとは言ってましたけど」
「ふーん」
「あ、なにかご依頼でしたか?」
「あたし達でも作れるものなら…」
「いや、グラセン鉱石が欲しかったんだけどね」
その言葉にヘルミーナは、今工房にあるもののリストをめくる。
「あー。この間使い切っちゃったんだ…」
「そう。仕方がないね。それにしても参ったなぁ。すぐ欲しいんだけど…。そうだ、リリーどこにいったか知ってる?場所によったらすぐ分けてもらえるかもしれないし」
「あ、確か」
シュミッツの奥の名もない土地だと答えた。
「…無理かなぁ」
考え込むカリン。
「あ、そういえばおねーさん、自分の道具袋に入れっぱなしにしてた分があったと思う」
妖精の一人が思い出したように叫んだ。
「その袋は?」
「おねーさんが持ってるいつもの袋。採取に行くときに持っていくやつ」
あたりを見回したがそれらしきものはない。どうやら一緒に持っていったようだ。
「奥シュミッツまで往復で…」
日数計算をし、頷く。
「じゃ、あと追うよ。すぐ戻ってきたら十分間に合う」
いつもの笑顔で工房を出て行った。その足でヨーゼフの雑貨屋に向かう。
「あれ、カリン姉さん」
「テオじゃん。どうしたの?」
「そっちこそ」
「あたしはちょっと出かけるから、そのための準備」
「でかけるって、姉さんと採取?」
「ううん違う違う。あの子、今ウル様とゲルハルトと一緒になんかやってるらしいのよ。で、あたしはリリーに用事があって、その後を追う、と」
「ウル様とゲル兄貴ぃ?」
明らかに嫌そうな声。この単純な少年はリリーのことを憎からず思っていない。それは無関係のカリンにも良く分かる。だから、リリーについているのがあの二人だと知って心中穏やかではないのだ。
「オレも行くよカリン姉さん!旅には護衛が必要だろ!?」
あたしは別に大丈夫なんだけどね…。
肩をすくめたが、ここで断ったら一生テオにうらまれるだろう。
「じゃ今すぐ、今すぐ出発!」
「ちょっとまちなよ、今すぐったって限度ってもんがあるでしょう?」
息巻く少年を抑えながら買い物を済ませる。
「ヨーゼフさん、ごめんね騒いじゃって」
「構わんさ」
片手を挙げて店主に謝り外に飛び出した。そこにやってきた人物とぶつかる。
「前を見ろ前を」
「なんだ、ヴェルナーじゃない」
「なんだとはご挨拶だな」
「珍しいね。昼日中から外歩いてるなんて」
「出かける準備だよ」
「どこに」
「…お前らと同じだ」
「は?」
不機嫌そうな男はそのままヨーゼフの店に入っていった。
「なんだ、ヴェルナーの兄さんもくるのかぁ?」
テオが悲壮な声を出す。
「なんでまた。あたし達の話聞いてたのかな?」
「うー、なんか、落ち着かないなぁ」
がくりと少年がうなだれているところに戻ってきた。
「なんでまた?」
「頼まれたんだよ、楽器」
「楽器?」
「昨日あいつに雇われたって妖精が俺んとこに来て、リュートが欲しいって。出来るだけ早い方がいいって言うもんだから」
「ふぅん」
怒っているのだかそうでないのだか良く分からない表情だが、これはいつものことで、カリンはこの目の前の長い付き合いになる男をじっと見た。
「前だったら気が乗らないとか何とかいって、絶対に配達なんかしなかったのに」
くすっと笑って肩をぽんぽんと叩く。
「なんだよ」
「なんでもない」
いひひと笑いながら旅の準備をするために製鉄工房に戻っていった。
「……天使様が私を迎えに来てる気がする…」
目を回しながらリリーは呟いた。ここ数日ゲルハルトの歌声を聞き続けて、かなり神経が参っているようだ。そばに立っているウルリッヒの表情は変わらないが、良く見るとかなり憔悴しているのが分かる。
「さすがのウル様もこういう訓練はしてなさそうね…」
そう思いながらレナフォルテの音階を弾く。ゲルハルトはそれにあわせて歌っている。……はずなのだが。
「どこをどうしたらあんな声になるのよぉ…」
普段の声はいいのに、何故歌になるとおかしなことになるのだろう。普段の声だけ聞いていると絶対に想像できない声が、目の前で心地よく歌っている男から発せられていた。
「…っと。リリー、こんなもんでどうだ?」
「ゲルハルト…。あなた、普段出す声と歌うときの声、なんか変えてる?」
「そんなつもりはないぞ。普段も歌うたってるときも、俺は俺の声だ」
何を聞くんだというように返されてしまった。
「そんなことよりいつまでこんなことやってないといけないんだよ。こんな人里はなれたところで」
「人里はなれたところを選んだのだから仕方あるまい」
ぼそりとウルリッヒが呟く。
「いや、だからねゲルハルト。こういうところで練習して、それで祭りの時にはみんなを驚かせましょうよ」
「なるほど。でも、俺はリュートの弾き語りで出ようと思ってるんだ。練習するならリュートがいるんだが」
「うんうん、わかってる。だから妖精さんに頼んだから…」
「もうすぐできるのか?」
嬉々としてのどの調整を行う武器屋の店主。それを見ながらリリーとウルリッヒはそっとため息をついた。この状態が続くと、こちらの精神が持たない。王には悪いが、やはりこの依頼引き受けるべきではなかったかもしれない。
「すまないなリリー。このような無茶を押し付けて…」
「ウルリッヒ様のせいじゃありませんよ…きっと誰のせいでもない」
誰のせいでもないのは分かる。分かるのだが、やはり理不尽だ。リリーは袋の中をあさり、こういうときのためと持ってきた超高性能のはずである、リリー印の耳栓を取り出した。
「ついに…これを使うときが…」
せめてリュートが届くまで、これを使いながらどうにかごまかすしかない。いままでがんばって彼の歌声に耐えていたが、限界だ。
「ウルリッヒ様、これ…」
そっと耳栓を手渡す。
「気休めかもしれませんけど…」
「いや、かたじけない…」
素直に手を出したところを見ると、思っていたより疲労困憊していたのかもしれない。もっともリリーもかなり堪えている。
「工房で調合し続けたときより辛いわ…」
幸い耳栓は抜群の効力を発揮してくれた。しかし、今までに聞き続けただけに、頭の中にゲルハルトの歌声がこだまし続けている。軽い酩酊状態。レナフォルテのイスから降りて天幕で横になろうと動いた。
「リリー、今日の練習はこれで終わりかぁ?」
「うん…ちょっと休む」
足取りがおぼつかずよろめいたところをウルリッヒに助けられた。
「すいません…」
「大丈夫か?」
慌てて離れたところに少年の声が聞こえてきた。