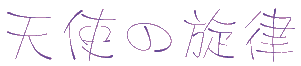
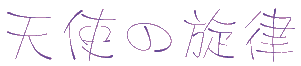
「ねぇさぁーんっ!!」
肩で息を切らしながらリリーに駆け寄るテオ。ウルリッヒに鋭い視線を向けることは忘れない。
「大丈夫?こんなところで…」
「大丈夫って、…一体なにが」
「えっ、あの、その」
しどろもどろになるテオ。その後ろにカリンとヴェルナーがやってきた。
「やほーリリー。貴女がグラセン鉱石持ち歩いているって聞いて、ここまで取りに来たよ」
「えっ、そうなの?ごめんなさい」
慌てて袋を探り、確かにあるのを確認して苦笑いした。
「いくつ?」
「二つ。それにしても…一体なんだったのかな。さっきまでものすごい音が聞こえてたんだけど」
「は、ははは」
言うまでもない。ゲルハルトの声だ。
「え…じゃあさっきのは歌…?」
「カリンはまだまともに聞いたことなかったんだっけ?」
「うん…」
「取り込み中わりぃが、注文の品だ」
このままだといつまで経っても女達の話が終わらないとばかりに、ヴェルナーが苛立った声を出した。
「あ、えっ?ヴェルナーが持ってきたの?妖精さんに渡してくれるだけでよかったのに」
「バーカ。そんなもん俺の勝手だ」
彼もテオと同じで、一緒にいるのがウルリッヒとゲルハルトというのを聞き落ち着かなくなったのだ。ただ、リリーはそんなことには気がつかない。
「バカって…人の顔見るたび言わないでよ」
そう返してくるので悔しくなった。
「バカにバカって言ってなにが悪いバカ」
「……」
ごそごそと袋を探り、耳栓をカリンとテオに渡す。それをはめるように身振りで示し、ゲルハルトのほうに向かっていった。
「お、おいリリー?」
急に不安になったヴェルナーはリリーに手を伸ばす。
「…?」
「ゲルハルト、ヴェルナーが歌って欲しいって」
「おっ?そうか?」
うれしそうに近付いてくるゲルハルト。直後にものすごいうねりが丘に響いた。
「………!!!?!!」
凍りついたように動かないヴェルナーをおいて、リリーはカリンのところにいく。
「絶対耳栓はずしちゃダメよ」
「うん…って、どうして会話が聞こえるのよ」
「私がそういう風に調合したもの。ある程度大きい音とか、雑音だって思った音だけカットするように。当然、この会話も雑音だって思っちゃったら聞こえなくなるけどね」
「すごいねぇ。錬金術って、そんなことまで出来ちゃうんだ」
「さすが姉さん。オレが見込んだだけのことはある」
なぜか自慢そうに言うテオに笑う。
「で、なんでこんなことに?」
「詳細は私から話そう」
ウルリッヒが会話に参加してきた。
「ウルリッヒ様…すごい疲れてません?」
「…それは認める」
いろいろ話を聞くうち、カリンとテオは笑い死にしそうになった。
「笑い事じゃないわよ。どうにかしないと、会場に来た人みんなあんなになっちゃう」
と、目を回して倒れているヴェルナーを指す。
「うーん。そりゃあ…」
すこしかわいそうかな、と思いながらカリンは倒れている男を見た。
「だからって…本人は絶対気がついていないと思うけどね…」
「言っても言っても分かってくれないのよぉ」
なきそうな声で親友になきつく。
「ゲルハルトも結構頑固だからねぇ。しかも、あの様子じゃ自分は上手いって信じ込んでるだろうに」
「……」
「……」
「……」
四人はリュートを持って機嫌よく歌っているゲルハルトを見て、同時にため息をついた。
「…今日って何日だったっけ…?」
「出かけるときにたしか二月の半ばすぎだったから…三月近いんじゃない?」
「…日にちごまかして、戻ってきたら芸術祭終わってたってことに出来ないかしら」
「無理だと思うよ姉さん。ゲル兄貴、結構そういうことにきっちりしてるから、多分ちゃんと数えてるはず」
「…はぁー」
ため息をつきながらカリンを送り出すことにした。彼女は彼女で工房依頼を持っており、そのためにグラセン鉱石が必要だったのだ。
「ごめんねリリー。助けになれなくて」
「ううん、こっちこそ手間取らせて。カリンにはカリンの生活があるもん」
「今度、成果を聞かせて」
そう言いながら耳栓をはずし、リリーに返す。問題の男は今度はリュートの調弦をしており、今は歌っていないのだ。
「うん、気をつけて」
受け取りながら手を振った。
「いっちゃった…カリンも忙しいのよね」
「そうだね。カリン姉さんの作った武器って、評判いいんだよ」
「私も愛用者の一人よ。それにしてもテオ、あなたカリンの護衛だったんじゃないの?」
「いや、そのえと…カリン姉さん強くて…大してオレ、役に立てなかったんだ」
頭を掻きながら言い訳するテオ。ウルリッヒは何も言わなかったがその様子を見て何かを感じたようだ。
「ふうん。まあ、カリンには冒険者としてもお世話になってるしね。強いのも当たり前か」
納得して頷くリリーに、テオとウルリッヒはそっと息を吐いた。片方は落胆の、片方は、安堵の。
「ところで、あの店主はいいのか?ずっと倒れたままだが」
ウルリッヒの指摘にヴェルナーのことを思い出す。
「…いいんじゃないの?ヴェルナーの兄さん、いつも姉さんに文句ばっかり言ってるから、たまには」
「悪かったな」
仏頂面でテオの頭を殴りつけた。いつのまにか復活していたらしい。
「ってーっ!」
「なにすんのよ」
「…お前なぁ。人が話をしようとしてるのに、その戦闘体勢はなんだ?」
言われてリリーは、初めて自分がいつでも戦えるような体勢に入っていたことに気がついた。なんとなく話は出来るようになったものの、かなり苦手意識があるのだ。それがまともに出てしまっている。
「お前にはよく蹴り飛ばされてるからな」
肩をすくめながらそんな彼女を見る。
「とにかく俺にも耳栓くれ。たまらん」
「分かったわよ」
カリンから返された分を渡した。
「ふぅん」
それをじっと見る店主。
「なんだよ、姉さんの仕事にけちでもつけるのか兄さん?」
「だれもんなこと言ってねぇだろ。なんでそういう発想になるかな」
機嫌を悪くしたときにすぐ出る眉間の皺。
「普段のことを思えば仕方がないとは思うが」
「……なんでそう、よってたかって俺をいじめるんだ」
ウルリッヒにまで突っ込みをうけてうなだれる。
「みんなどうしたのよ、大人気ない」
あきれて声をかけるリリー。それをみて男たちは盛大にため息。一番のいじめっ子は間違いなくこいつだ。そういう空気が流れる。もちろんリリーは気がつかない。
「で、一体なにが言いたかったの?」
「いやな、こいつ、作るのに手間か?」
「そんなにかからない。材料もありきたりだし…一日でできるし」
「じゃ、芸術祭参加する全員にこれ作って渡しといたらどうだ?もちろんゲルハルト以外に」
「!」
ゲルハルトの死の旋律は改善不可能だろう。それはもう、しばらくここで付き合っていたリリーとウルリッヒには良く分かっている。ならば、逆転の発想。
「なるほどな…この耳栓ならば、卒倒者が出ることもないだろう」
「ふえー。すげぇな兄さん。そんなこと思いつくなんて」
「ふふん。ここが違うんだよ、ここが」
得意げにそう言って自分の頭をとんとんと指す。
「どこが。ひねくれてるからそういう逆の発想が出てきたんでしょ」
言わなければいいのに、リリーが一言。
「ああそうかい。そういう態度かい」
言われたことが図星だっただけにすぐ機嫌が悪くなる。
「悪かったわね、こういう態度で」
ふん、とお互いにそっぽを向いているところにゲルハルトが声をかけてきた。
「みんなそろってそんなところでなにやってんだよ。そんな暇あるなら練習練習!」
ひとりニコニコしてリュートを構える。そして、全員に耳栓をする暇を与えずに歌い始めた。
芸術祭は無事に成功したとウルリッヒが知らせをもってくる頃。リリーとイングリド、ヘルミーナ、そして雇われていた妖精たちは疲労困憊で寝込んでいた。いくら一日で数個出来る単純なものとはいえ、数が半端ではなかったのだ。
「今回はご苦労だった。リリー、王は満足していたようだよ」
「そうですかぁ…良かったぁ」
満足してくれていたと聞いて疲れも少し吹き飛ぶ。
「ひいては謝礼のことなのだが」
「ああ…」
「ここにくる先にヴェルナーに会って、彼がかなりの取り分を主張したぞ」
「……はい?」
「「俺が発案したんだから俺にも取り分はある」と」
「…あの気まぐれ店主めーっ!」
立ち上がり工房を飛び出していったリリー。呆気に取られてウルリッヒ。
「…話は最後まで、聞いて欲しかったのだがな」
いくらヴェルナーの言い分が正しかろうと、実際に作業をしたのはリリーたちなのだ。そのことをしっているウルリッヒがおいそれと銀貨を渡すはずはない。
「かなわないな、あの人には」
彼は仕方がないなというように笑い、ドルニエに銀貨を渡して辞した。職人通りの坂の上からは、今日もにぎやかな言い争いが続くのだった。
ENDE
ゲル兄貴の殺人的ヴォイスの話は
一回書いてみたかったなと思ってまして…
で、こういうことになりました
天使が迎えにくる旋律、あるいは天使の戦慄という感じでお読みください(笑)
言葉遊びできるのっていいなぁ
それにしても男たち、やきもきしております(笑)
読まれて、結構イメージ崩れてると思われたと思います
特にウル様とかウル様とかウル様とか(笑)
ロイヤル系は本当に苦手で…
庶民をちくっと書いているのが一番性に合います
でも…他のメンバーも結構切れてるやうな…
一番ひどい目にあってますがヴェルナーが一番すきなんですよ、私(説得力皆無)