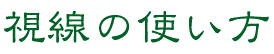
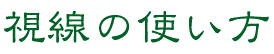
すぐに護衛の任務につくことができるだろう。どこかでそう思っていたが意に反して機甲師団の中から動けずにいた。毎日の訓練、人より多く言われているような気がする雑用、本来の通信係が「一身上の都合により」休職中なのでその仕事。あまりに細々とした用が多すぎるので次第に不安になってきた。
このままではオリビエの護衛に辿り着く事が出来ないかもしれない。
本気でそんなことを考えるようになった頃、城で騒ぎがあった。どんな騒ぎなのかはわからない。一般には公開されていないし貴族ですら田舎貴族なら状況を知る由もないだろう。それは士官クラスであっても例外ではない。そもそもミュラーが知ったのも、城に知り合いがいるからだ。
「皇子は無事。少し怪我をされたが命に別状は全くない」
「……近衛長、ありがとう」
こういうときには通信係の仕事をありがたく感じる。たまに近衛隊への連絡書類があるからだ。そしてミュラーは近衛長と不思議と気があい、初めて城に上がった時から気にかけてくれていた。またこちらも何かあれば美味い酒などを届けたりしている。
そこに何がしか作為的なものがあったのかもしれない。何をどうしても彼はヴァンダールの人間。今は機甲師団内の下士官で雑用係に落ち着いているが、いつ何時、自分を飛び越えて遥か高みに上るかわからないのだ。ミュラーとしてもそれは考えないわけではなかった。
「が、決して近衛長はそれを表に出してこない。他の者は大なり小なり、俺の出自を気にしていることを表に出す。……気にしていないことはないだろうが……」
帝国内は言うに及ばず近隣諸国にもヴァンダール家の名は轟いている。そこの息子が軍にいることは少しハイソサエティに首を突っ込んだものなら常識のようなものだ。
「少し様子を見ていくか」
今日の仕事は書類を届けることで最後だ。少しくらいオリビエの様子を覗いていっても問題はないはず。
「大丈夫か?」
落ち着いていると自分で思っていても気は急いていたのか、ノックをそこそこに扉を開くとオリビエが女性給仕を口説いている最中だった。熱っぽい瞳で手をとりじっと見つめられていた給仕は困ったようでいてまんざらでもない様子だったが、ミュラーの来訪に我に返って慌てて部屋を飛び出していった。それを見送ったオリビエが頬を膨らませる。
「もう少しタイミングを見計らってくれると個人的には嬉しかったのだけれど」
「……もう二度と見舞いになど来ない方がいいようだな」
内心を押し殺して振り返ると焦った声で止められた。
「ももも、申し訳ありませんでしたミュラー様!」
「……」
ちらりと後ろに視線をやれば半泣きで縋るようにこちらを眺めている。
「うっとおしいからその顔はやめろ」
「うーむ、給仕たちには好評なのだがキミにはもっと別の方法を考えなければならないようだね」
「……」
ちっともこちらの意図が伝わっていない。が、それ以上言うのはやめた。どこまで冗談なのか本気なのか判別がつかないオリビエの考えに付き合っていく時間はさすがになかった。
「どうなんだ、体の調子は。まああの様子ならすっかり元気になったようだが」
「うん。ボクは元気元気、いつでも元気いっぱいさ」
「ならいい。俺はもうそろそろ行く」
「もう行っちゃうのかい? 愛を深めていかないかね」
「あいにくそんなものは持ち合わせていない」
「ぶー」
オリビエは不満そうだがミュラーはオリビエに対して愛は持っていない。これは確かな事だ。その代わり全幅の信頼を置いている。ミュラー的には愛より信頼の方が重い。それにオリビエが気付いているかどうかは知らないが。
「まあいいや、そのうちタップリと愛の素晴らしさについての講義を行うからね」
「謹んで辞退する」
「今日はわざわざありがとう」
「……ああ」
軽く手を上げて部屋をでた。本当はもっといろいろな事を話したかったがまず間違いなくあの部屋には何かの仕掛けがある。壁の裏で間者が潜んでいてもおかしくない。城は古く、中世時代の、もっともっと内乱の多かった時期から使われているのだ、ミュラーの知らない仕掛けなどが施されているに違いない。自分が城に常駐する立場ならそういったこともすべて把握できるのだろうが。
「早く護衛につかなければ」
短いやりとりだがわかった。オリビエは相当心身を削られている。なかなか会えないまま時間が過ぎて、その時間は確実にオリビエから人間味を奪い取っている。そもそもの入隊動機が護衛だった為そのうち出向になるだろうが、これでは出向になった際護るべき相手が人ではなくなってしまう。
さてどうしたものかと兵舎までの道のりを辿った。途中の現状の職場である通信室の前でふと足を止める。しばし考え、中に入った。
もちろん今は下士官で雑用ばかりをこなすミュラーだが、名門出である以上人の上に立つことを考えて他人を見定めている部分も持っている。その気になればこの国の軍事力すべてを担う事ができるほどの名と地位と実力を持つのだ。ただ現状独立しているのは、どうしても政治と関わらざるを得ないから。家を継ぐ兄も政治と必要以上に関わる事を避けていた。
「あんなものは自己犠牲ができる人がやることだ。俺にはとても出来ん」
肩を竦めて城のほうを眺めていた兄を思い出す。ミュラーもそう思う。いざというときのための横のつながりは大事にするし政治家とのやりとりを行う事もあるが、ヴァンダール家は政治に口出しは決してしない。そんなことをしなくても家の立場を護る事ができる力があった。
ともあれミュラーは自分の同僚や上司を、彼らの上に立った場合という視点で冷静に眺めている部分がある。どんなに心酔し、信頼に値する上司や仲間であってもそれは同様に見ていた。おかげで彼らに対する判断を間違う事はない。例えば名門貴族出の同僚少尉は仕事はできるし部下からの信頼も篤いが、少し下に寄りすぎた考え方をする。こういう人間は現場に置いておく分には下のものとうまくやるだろうし能率向上も見られるだろうが、中枢に持ってきてしまうと意見のまとまりをなかなか見ない可能性がある。ミュラーはそんなところをすべて見抜いていた。
椅子に座り紙を取り出してまず自分の名を書き、自分を取り巻く人間の名を書いた。
「……」
機械的に名の下に所感を書き込んでいく。直接の上司の名、そのまた上の名、隊長の名。それらとつながる政界の面々。自分の同僚、貴族ならばその家柄、ヴァンダール家との関係。
しばらくすると自分を中心とした図が出来上がっていた。
「こうして書き出してみると良くわかる。どうやら俺は上の派閥争いに巻き込まれて今こんなところにいるようだ」
どこまで「上」の派閥なのかは、辿れば最終的に各皇子たちの争いにたどり着く。皇帝の体調が思わしくない今、彼らは密かに動き始めている。
「隊長とどの皇子がつながっているのかはすぐにはわからないだろうが」
最も上が皇子なら自分がここに燻っている理由は良くわかる。男として生まれてきてしまったオリビエが気に食わない。今は継承権放棄をしているが今後どうなるかはっきりしないのだ。長い帝国の歴史の中で、継承権放棄をしていたものが革命を起こして皇位についた事例があるゆえに。
だからできるなら早めにどうにかしたい。父皇帝が城に連れ帰ってしまった為下手に追い出しに掛かる事が出来なくなってしまったので、「避けようのない事故」を頻発させるしかない。その際自分が護衛に付いていれば明らかに邪魔になる。
「……あまりやりたくないことだが」
出来上がった相関図を眺めていれば、自分が意図した位置に行くまでおのずとどう動けばいいのかわかる。が、それを起こすのは彼の意識が邪魔をした。ヴァンダールの一員である自分ではなく、ただの兵である自分の力のみで動きたかった。けれどそれをしていると時間がないようだ。少々功績を上げたところでこの布陣のなかではすぐに握りつぶされてしまうだろう。
「確かこの辺に」
機甲師団独自規則がまとめられた冊子を本棚から探し当てる。目的のページを手早く見つけ一文を確認した。次に手元にきている新しい通達を眺め、そこにあった名前を先ほどの相関図に書き加える。頷きながら仕方がない、と口の中で呟いた。
実際に彼がしたことはそう多くない。一番初めにしたのは上役へ擦り寄る傾向の上司にする報告をほんの少し記述漏れをしたことと、向上心の強い部下にヴァンダールの名をほんの少しちらつかせたことだ。
上司に報告を意図的に遅らせたのは新しく赴任してくる基地上層部士官の顔写真を渡す事。あちこちに擦り寄る時間が多く、通信書類に目を通すのが二日か三日確実に遅れるのは前から知っていた。なので、赴任直前に今まで忘れていたとして添付。現状ミュラーが基地内の情報すべてを取りまとめているのでこういう荒業に出られる。上司が自分でも情報収集する性質ならば無理なことだったがそれは決してない事だった。結果、新任の顔がわからず相当な恥を掻いたらしい。新任上官も上司に対する印象を悪くしたようだった。当然添付し忘れていたミュラーを叱り飛ばそうとしたものの、前日には自分の机の上に書類を置いていた事と、部下のことは上官の責任という規則のおかげでほとんどおとがめなし。逆に上司のほうが上役から厳しい追及を受けたようだ。
部下に関しては、常に成り上がりたいと必死になっているためか上司の受けは悪い。ミュラーから見てもその渇望具合は恐ろしく感じるほど。そこでミュラーは兄に連絡を取った。
「仕事ができる奴がいる。そちらで検討してみたらどうだ?」
「お前の紹介なら信頼がおけるだろう。わかった、考えてみる」
それだけの短いやりとりを書簡で行い、しばらく時間が経った後部下からギラギラした部分が消えた。ミュラーと目が合うと軽く会釈までしてくる。何がしか兄からの接触があったのは言うまでもない。決して具体的に表には出なかったがミュラーの周りに人の流れが出来た。それに対して何をするわけでもない。とはいえ上はその動きに対して何がしかの意図を汲み取った。何せヴァンダールの直系、どういう風に出てきてもおかしくない。部下たちをまとめ上げて基地内で一大派閥を作り上げる事もできれば逆に一気に外に放出してしまう事もできる。しかも現状は一介の通信兵という立場。伝統的な機甲師団の規則、「部下のことは上官の責任」がいやに大きく上官たちに響き始めた。
「急状況変わってない?」
城に顔を出した際には必ずオリビエのところに寄る。出し抜けにそんなことを言われたがミュラーはそ知らぬ顔で通した。いかにも自分は何もしていないというように。現状の打破はミュラーの問題であって、オリビエが手を回してどうこうするものではない。そもそも今のオリビエにミュラーの配置換えを指示できる力はなかった。
「とくに変わっていないと思うが」
「そうかな。最近キミの周りが騒がしいって聞いた。あまりムチャはしないほうがいいんじゃない?」
「無茶な事はした覚えはない。が、肝に銘じておく」
「うんうん、それがいい」
基地への新任上官は弱腰そうに見えるが実はかなりの名門出で最終的な度胸はあると昔から言われてきた人物だった。どうにもだらけがちな基地へ新風を巻き起こしてくれとの期待を込めて上層部が配属させており、期待通りに基地内を替え始めた。最初に不興をかったミュラーの上司は別場所に転属、その他の澱となっている部分にもそれとなく興味を示し始めている。すぐに変わることはないだろうしもしかすると全く変わらないかもしれないが、そういった姿を下に見せることが目的だとばかりに上官は働いていた。
ミュラーは周りがざわめき始めたことを知りながらいつもと同じように訓練や仕事を必要以上にきっちりとやりつづけた。新しい直接の上司と話したときも普段通り、勤勉実直を地で行く態度で応じた。そもそもはそちらの方がミュラーの本質である。部下が周りに集まり、本人は上昇志向はないが超名門出。次第にミュラーは基地内において、最初とは別の意味で特別視され始めた。こうなってくると上層部も放置しつづけるわけには行かない。そのままにしておくと必ずこういわれるのだ。
「なぜあんな人間を通信兵にしておくのだ」
と。
しばらくしてからミュラーは基地司令官の部屋に呼び出された。
「招致に応じました」
「休んでいいぞ。早速だが君の処遇についてだ」
「は」
敬礼を解いて休めの体勢になる。
「上層の決定で昇進が決定した。まずはおめでとう。そのうち内々に通達が行くだろう。で……君が以前から出している出向願いだが」
「はい」
きた、と表情を変えずに唾を飲み込む。以前までは決してなかったこの話。これだけでもずいぶんと自分を取り巻く環境が変わったのだと実感した。
「残念だが今回も却下させてもらう。が、落胆することはない。今君の立場が少尉だと言う事と、やってきた仕事内容が問題になっただけだ。今回昇進をすることと、伴って転属してもらう事でそれは解決するだろう。そしてすぐに要求は通るはず」
「はい」
「以上だ、質問は?」
「ありません」
「ではこれで」
「失礼いたします」
さっと敬礼をして部屋をでた。歩きながら、本当に自分の環境が変わり始めているのだとしみじみと思う。やはりまだ護衛には慣れないがそれも時間の問題だ。この調子で行けば一年以内には通ると部屋を出るとき司令官が示唆していたではないか。ずいぶんと進歩したものである。
「もうすぐだオリビエ。だからお前は人のままいてくれ。あの魔窟に飲み込まれ、人でありながら修羅に身を落とすな」
城は魔窟。貴族たちの間では公然の秘密として伝えられている。城の毒気に当てられて人ならざるものになったり、人であることを選んだが為この世から消えたものも数知れず。消されずに人であることが非常に難しい場所。
「城に入れば俺はお前を全身全霊で護る。だからそれまで待っていろ」
だがもう二度とこんな方法は取るまい。あまりに上手く行き過ぎて何かの罠にかかっているのではと思うほど、とんとん拍子に話が進んでいった。うっとおしい上司はいないし人は自然に集まってくる。これ以上もう何も望むことはない。あとは自分の実力次第、腹の底に力を入れ、低く呟いた。
Ende.
意外と少佐のほうが本気で立ち回ったらオリビエより上手く回りまわせるんじゃなかろうかと思ったり。立場としては少佐のほうが磐石っぽいですし。出自で色々言われることもあったでしょうが、軍人として護衛するならどうしたって軍に入らないといけないけど、そこからどうやって護衛に行ったのかなと思いつつ。部下としての視線、後に地位が上がった時の視線。どっちもきちんと使うと恐い。
とりあえず敵に回すと恐いのは多分少佐のほうじゃないかな。