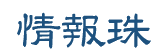
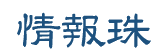
貴方も遊撃士であるなら、『情報』という名をもたされたクォーツの存在を知っているかと思います。そのクォーツに収められている『情報』はいったいどこからきたのか。どこからそれだけのものを持ってきたのか。今から語るのはそんな『情報』にまつわる、些細なお話です。
昔々、今の女王の治世よりもはるかに昔。現在知られている街の名前も現れていないような時代。小さな川沿いに集落と、そこから少しはなれた山中に修道院がありました。両者はほとんど交流は無くそれぞれの生活を保ち続けており、特に集落の人は山中にひっそりと静かに建つ建物に近寄らないように暮らしていました。
修道院は廃墟同然で、そんな建物に出入りするのは胡散臭そうな男たち。長ったらしい布をまといその色も暗く冴えないもの。朝に晩に不気味なうなり声を上げ、朝の早い時間や夜日が落ちてから集団で外に出てきます。そしてしばしの間山の中をさまよい戻ってくるということを繰り返していました。
いったい何をしているのだろう、気味の悪い儀式でも行っているのではないかと街の人々は噂し、たまに街に修道士が降りてきたときには邪険に扱うのが常でした。修道士たちとしては常々もっと交流をしたいと考えていたのですが、そういった街の人たちの冷たい態度が続いた為に、積極的に交流を説くものはずいぶんと少なくなってしまいました。
さて、ある男がいました。彼は山に入り、燃料になる枝を拾い集めては日銭を稼いでいました。普段は大して裕福ではなかったものの、時折きらきらと輝く透明度の高い石を拾うことがあり、それを売るとたくさんのお金が手に入りました。そのおかげで妻を娶り子を成しささやかな家庭を築いていました。病一つすることなくすくすくと大きくなった男の子は父親が大好き。男の方もそれを嬉しく思い、水浴びをしたりどこかに買い物に出るといったときには必ず連れて行きました。けれど、それまでどんなに泣いてもわめいても許していないのは山に入ること。
ある日、男の子が父親と一緒に山に入りたいと言い出しました。困ったのは両親。確かに言葉もしゃべり始め、簡単なことであれば一人でできるようにはなりましたがまだまだ山遊びをするには不安の方が大きい。
「お山は恐ろしいところなんだ。おまえを一口で食べてしまうような大きな大きな動物や、一回迷ったらもう二度と出て来れないような暗くてふかーい森や、何を考えているのかよくわからん奴らの住処なんかがある。お父ちゃんは慣れてるからそういうものを避けて通れるが、おまえにはまだまだ早い」
大丈夫だと言い募る子をなだめすかし、結局母親が食べ物で気をそらしている隙に父親は出て行くことになりました。
なんとか出かけたはいいけれど、最初は晴れていましたが途中から段々雲行きが怪しくなってきました。またよい枝もあまり見つからずどうしたものかと切り株の上に座って考える。帰りたいのはやまやまだけれどそうするとお金が稼げない。稼げなければ妻も子も飢え死にさせてしまうことになる。
「なんか変な声まで聞こえてきた」
風で葉が擦れ合い動物たちが鳴く合間に、それまで聞いたことのない甲高い叫びが混じりました。その上雨もぽつりぽつりと落ちてきたので、仕方がないと今日は帰ることにしました。
男はこの山に入って長いとはいえ全てを知っているわけではありません。きっと知らない獣がいるんだ、出会わないうちに早く帰るんだとぶつぶつ呟きながら次第に早歩きに。雨は急に強くなり、頭の上に張り出している枝や葉が多少肩代わりはしてくれるけれど、男の不安をあおるのには十分すぎるほど。おまけに甲高い声は先程より近くなったような気がします。
「気味が悪い。街に近くなっているはずなのに」
街に近づけば近づくほど甲高い音も近づくのは気のせいではありませんでした。片側が崖になっている獣道を歩いていると、その崖の底から聞こえてくるのです。一体どういうものがいるんだろうと次第に興味がでてきました。どういう種類のものがいるのかわからないし仲間を呼んでいるのかもしれないとは思えど、生来好奇心が強く、初めに山に入ったのも生活に困っていたわけではなく何か新しいものを見つけたいという冒険心からだった彼。今なら雨で自分のにおいも消されると思い、ほんの少しだけ覗いてみることにしました。
それはなんの導きだったのか。山に宿る大きな力なのか、それとも別の何かの力なのか。後から男が語るのを聞いたものはそんなことを思ったといいます。とにかく、そこで甲高い声を発していたのは、崖から落ち、大怪我をして僅かにも動けなくなっている、自分の子どもでした。
それに気付いた男は崖を転がり降りそばに飛びつきました。腰に巻きつけていた袋からその辺りの草を煮詰めた、薬ともいえないような薬を子どもの体中に塗りたくり、血がでてくる傷口には自分の着ていた服を破って巻きつけました。それが効いたのかはよくわかりませんが、血は少しずつ止まってきたような気がします。代わりにどんどんとその体が熱くなってきました。
怪我に対する知識なら多少は持ち合わせている男でしたが熱はお手上げ。このあたりからどれだけ歩けば街につくのか、街についたとて治せる人間がいるのか。混乱しきってしまってもはやどうすればいいのかわかりません。知らず知らず涙を流して我が子の名を呼び叫んでいました。
「……もし! そこにいるのはどなたか!」
呼ぶような声が聞こえます。気のせいかと思いましたがそうではないようでした。薄暗い森の中を見回すと、崖の上から人影らしきものが見えています。
「子どもが……わしの子が、ものすごく熱いんだ!」
「なんですって!」
もうわけもわからず叫ぶと反応がありました。そのまま人影は崖を滑り降りてきます。
「どんな状況なのですか?」
慌てた声でやってきたのは。
「……あ、あんたは」
街の人間が薄気味悪がって近寄らない、廃墟の住人。
「これはいけない。傷口からわるいものが入って熱を出しているようです。……あいにくとすぐには薬は作れないのですが、院にもどればもしかすれば作り置きがあるかもしれません」
男よりも年上に見える廃墟の住人は余計な心配をかけまいとしてか、おだやかに話し掛けてきます。そのためなのか、それとも子どものことでまともに頭が動いていないせいなのか、街で流れる噂の数々はすっかり飛んで消えてしまっていました。
案外に近いところに修道院はありました。いつもこれを横目に見ながら山を降りているというのにと頭の端で思いはしましたが、すぐに腕の中の子どもに意識を戻しました。真っ赤な顔をして粗い息を吐く子どもにしてやれることはないのかとまた涙がでてきます。
「院長、大変なことが!」
修道士が部屋の一つに飛び込んで、男も勢いで飛び込んで。あっけに取られたような初老の男は、明らかに様子のおかしい子どもをみてすぐに状況を察し寝台を用意するように他の修道士に言いつけました。
「これをどうぞ」
何かの治療をされる子どもを心配そうに見守っていると最初に出会った修道士が温かい飲み物を持ってやってきてくれました。ぼんやりと受け取ると不思議な香り。一口飲むと甘く、芯から温まれそうです。
「これ……は」
「よくわからないのですが、この本を見ながら作ってみました。心を落ち着けるのに昔から私たちの間では飲まれています」
ボロボロの本を差し出してきました。なんとなく受け取ったけれど男は字を読むことが出来ません。
「しかし驚きました。あのような場所で私たち以外の誰かに会うとは」
「そういや確かにそうだ。……あんたこそあんなところで何してたんだ?」
不意に警戒心が蘇ってきました。こうなると今飲んだ飲み物も得体の知れないものに思えてきて、少し乱暴に近くのテーブルに叩きつけようとしました。けれど今は子どもの件があります。治療になるのかどうかは定かではないにせよ街まで行かずとも休ませてくれていることには変わりありません。
「私たちの修行の一環です。自分たちで食糧を調達しなければ。この院の近くに畑は作っておりますが、それだけでは賄いきれませんので」
「へえ……普通に飯を食うんだな」
「もちろん。私たちもあなた方と同じ生き物ですから」
「ふうん。そうか、飯食うのか……」
当たり前のはずなのに非常に新鮮な気がしました。そもそも、こんなに近くに顔をつき合わせて修道士と話をするなんてこと、男の人生では初めてのことです。気味の悪い習慣を持っている人間だと思っていましたが、実は案外にそうでもないのかもしれないとふと思いました。
数日後、男は再び修道院にあの修道士を訪ねました。子どもの容態が落ち着いたことと、そのときのお礼を言いにです。街の人々は「行く必要などない」と口々に言いましたが、一回受けた恩はきちんとしておきたい男は聞く耳を持たず門を叩きました。すぐに再会をし御礼を言うと、とんでもないといいながら少し嬉しそうでした。
「……ところであんた、山歩きをするんだよな? 子どもが怪我しそうなところとか知ってたら教えてくんねぇか?」
「いいですよ」
この道は汁が痒くなる草が多いから遊ぶのは駄目、この池には凶暴な獣が住んでいる、木の上から落ちてくる双頭の蛇には気をつけて、しびれてしばらく動けなくなる。こんな風な情報をいちいち指差して教えてくれました。もちろん男が経験上知っている知識も幾つかありましたがそれを上回る知識に目を丸くしました。
「よくもまあそんなに知ってるもんだ。どれだけ歩いてるんだい」
「歩いているというか、院に書物があるのです。ここに居を定めてからずっと、先人たちが持っていた知識を書き溜めた。だからこそいろんなことを実体験することなく理解できるのです」
「へぇ……すごいもんだな、本ってシロモノは。どうでもいいやって思ってたけどそうでもないのか」
しばらく考え込んでいた男はふと顔を上げ、修道士を見ました。
「なあ。できれば、できればでいいんだ。山歩きすんのに危険な場所や獣の話、街でもしてくれねぇか? 何人もが山で怪我してるんだ」
今度は修道士が目を丸くする番です。いきなりの申し出にどう答えたものか、かなり長い間迷っていました。
「……私たちはあなた方街の人々とは交流がありません。私たちを街に呼ぶのは、あまりよいことではないのでは?」
「そんなのわしが説得するさ」
この修道院とやらに眠っているいろんな知識は、自分たちにも有用なものだ。今にも朽ちそうな建物の中に宝物を押し込めておくなんてもったいない。しかもこの宝は、人に教えても減らない宝だ。ぜひとも街に広めてほしい。そう思った男は力強くうなづいた。
「……院長と相談をしてみますが、私としてはいい案です。我々も街の方々と交流していかなければならない」
「そうだな。じゃ、その前にわしにひとつ教えてもらいたいことがある」
「なんでしょうか?」
「あんたたちのやってることだ。最初に街のやつらに言う時、何をやってるのかわからなかったなんも言えねぇだろ?」
にやりと男は歯を見せます。修道士も、確かに、と笑いました。
その後、修道院と街の間で少しずつ交流がなされていきました。薬の書置きから山歩きの極意まで様々な知識と、そして七耀教の理念が少しずつ街にもたらされました。街側にとっては有効な知識と、心のよりどころとなるかもしれない宗教が、修道院側にとっては、ゆっくりとは言え確実な布教活動と、なにより街の人々に受け入れられて街の一員になることが。双方に得がたい宝として伝えられました。
あるとき、獣たちから自衛するために若者たちが警備隊を作りました。そのなかのメンバーにあの時の子どもがいました。父親から聞かされていた教会内の知識について思い出し、念のためにと聞いてみるとでるわでるわの山ほどの本。これら全てが近辺の獣たちについての本で、一つ一つの項目には多彩な事実が記されています。火を見ると近寄ってきたり、自然では極僅かにしかとれないキラキラした色つきの石を隠し持っているものがいたり、挿絵を見るだけでもなんだか楽しくなってきます。いいものを手に入れたと早速仲間にそれを見せ、結果効果的に自衛することが出来たといいます。
その警備隊は長い間を経て遊撃士と名前を変えましたが、魔獣と名前を変えた獣たちについての書物は変わらず、むしろもっといろんなことを付け加えられて存在していました。そう、その本こそがクォーツに収められてるものそのもの。現在、遊撃士たちが当たり前のように使い、死地を切り抜けるきっかけとなっている知識は、廃墟の修道院と偏狭な街が交流をして初めて現れたかけがえのない宝物だったのでした。
Ende.
「空の軌跡で『知られざる伝説』はできないか」。これがコンセプトです。こういうの考えるのがたまらなく好きです。
『知られざる伝説』ってたぶんかなり古いから知らない方も多いんじゃないかと思いますが、DQシリーズの書籍にオムニバスなお話を幾つか集めた本というのがありました。内容はその名のとおり知られていないエピソードを紹介するもので、公式による二次の一環でしたね、今考えると。メインキャラがでてくることは滅多になし、『アイテム物語』や『モンスター物語』なんかのカテゴリ特化した本もありましたが、基本は「キャラメインじゃない外伝話」です。これがもう好きで好きで。その好きが高じて軌跡でもそういうネタできないかと思い書いてみました。すっごく楽しかったです。