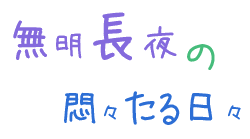
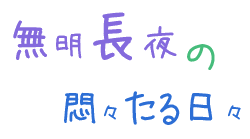
1.
「……」
アガットは黙って木の根元に腰を下ろした。今日中に峠超えをしてしまいたかったが無理のようだ。仕方がないと野営の準備を始めた。
いつも持ち歩いている小さい鞄から魔獣避け用の導力灯を二つ。スイッチを入れるがどうもうまく点かず、しばらく格闘してようやく小さな明かりを放ち始めた。
「そろそろ買い換えないとならねぇか。このサイズのはもう売ってないから直せたらいいんだが」
ルーアンの工房にとりあえず持ち込むこと。手帳の端に荒っぽく書き付けて糧食を取りだす。手早く食事を済ませて横になった。
蒸し暑い。もうそろそろしたらきっと地面が冷えてくるだろうが、まだその気配が見られない。
「……ふん」
こんな夜はやはり嫌いだ。あの夜を思い出す。胸元にある無骨な飾りを無意識の内に握り締め、その記憶を頭から追い出そうとした。
火の雨は熱いというより痛かった。そんな痛みなど忘れてしまいたいのに、彼を嘲笑うように何度も復活してくる。昔ほど過剰に反応することはなくなったが。ヨシュアには悪いが今でもあの剣帝という男は大嫌いだ。近親憎悪と呼ばれようがなんと呼ばれようが自分はこれからも嫌いつづけるだろう。だが、狂気じみた執着を多少殺ぎ落としていったのは間違いはない。
「ここで魔獣でも出てくれりゃ、考えずに暴れられるのに」
イライラしすぎて眠りにつくことができない。やはりペンダントに触れつづけながらいろいろなことを考える。環の事件以降こうやって考え込むことが多くなってしまった。
寝返りを打つと目の前に手帳があった。先ほど書き付けてその辺りに置いたらしい。なんとなく繰ってみる。
「へえ……こんなことしてたのか」
今使っている手帳は三冊目で、手配魔獣退治が八割を占めている。が、時折違う依頼も受けており、自分もこんな仕事をするのかと純粋に驚いた。よっぽど資金に困っていたのかなんなのか、少し前の自分自身のことが良くわからない。
「まあ、そういうもんなのかもな」
手帳を閉じて仰向けになる。自分自身でも少し時がたてば違う生き物のように見えてしまうのは仕方がないのだろう。刻一刻と思考は流れ変わるものだから。
相変わらず蒸し暑い。先ほどまで微かにあった風もとまってしまっている。ざわざわと葉が擦れて立てる音もない。だからこそ余計に聞こえてきた小さな水音。
「あ?」
耳に届いたその音に嫌な予感を覚える。次第に数が増え、自分の顔当たる冷たさを感じ、服の色を変えていく。
「マジかよっ! 冗談じゃない!」
飛び上がって周辺に散らかしていた私物をかき集めて鞄に放り込む。立てかけていた得物を掴み、もう少し雨宿りできるところはないかと駆け出していった。
2.
「あ、降ってきた」
「本当ですね」
城の一室でエステルが雨に気付いた。窓際で外を眺めているとカップを二つ持ってクローゼが脇に立つ。差し出された紅茶にエステルは礼を言った。
「ありがとクローゼ。ほら、さっき降りだしたばっかりなのに凄い大降りになっちゃった。明日晴れるかなぁ」
「そうですね……こればかりは明日にならないと、わからないですね」
クローゼも空を見つめる。明日はボート遊びをしようと約束していた。晴れた空の下、湖の上で釣に興じたりクローゼとずっと話したりと、いろいろ計画していたのがだいなしになりそうだ。
「この蒸し暑さはもしかして、と思っていましたが……もしも明日ダメならば、また次の機会にしましょう」
「でもクローゼが身動き取れなくなるじゃない。せっかくあちこちに根回しして時間作ったのになぁ」
がっかりだと足元を見た。王城を駆け回り、離宮まで走り、果てはレイストンまで走り、文字通りあちこちに根回しをしてクローゼと過ごす時間を作ったのだ。雨は仕方がないがなにもこんな時に、と思う。
「それにあたしもう少ししたら旅に出るし」
「あ……」
一瞬驚いた表情をしたクローゼだが、すぐに得心した表情に変わる。エステルも無言のやりとりの意味はわかっていた。
「うん、そう」
ヨシュアに付いて旅に出る。これはリベル=アークから戻ってきた時から決めていたことで、エステルにとっては曲げることができないことだった。
「ヨシュアさんがうらやましい。エステルさんが傍にいることが当たり前なんですね」
「クローゼ?」
諦めか嫉妬か、よくわからない感情が声にこもっている。はっきりと理解はできないが、次期女王の目を見たときなんとなく理解した。自分もこの目には覚えがある。何度情けないなぁと思いながら朝、姿見の前に立ったことか。
いなくなったヨシュアを思って鬱々と過ごす夜。そんな過ごし方をすると次の日は必ず情けない目をしていた。冷たい水で顔を洗い、朝食を勢い良く食べるとなんとかそれが治る、気がする。けれどどこかではやはりヨシュアのことを考えていて、結局考え込む夜が続く。
「あたし、元々そんな考え込むの好きじゃないのにさ。ぜーったい、この仕返しするんだからって思ってたのにさ。結局まだできてないや」
「?」
「でもそんなもんなのかもね」
突然のエステルの言葉にクローゼはついてこれていない。けれど気にせず笑った。
「細かいこと突付くの苦手だし」
「ふふふっ、なんですかそれ」
吊られてクローゼが笑う。これでいいや、理屈はわからないがエステルはそう直感した。何も全てを白日の下に曝すばかりが全てではない。いえないことを胸のちょっとした痛みとして抱えていくことも、生きていくことなのかもしれないと思う。
「止むかなぁ」
「止まなかったら、お茶会にしませんか? 実を言うと最近お菓子を作っていないので、ちょっと欲求不満なんです」
「お手製のお菓子かぁ。うん、それもいいね。あたしも手伝う!」
「え、あ、はい」
少し引きつり気味の表情が気になる。けれどそれよりも、明日はどう過ごそうかということで頭が一杯になった。
3.
雨音が入り口から聞こえてくる。降り始めのころは大慌てで客が店に飛び込んできたが今はもう出歩く人間もいないようだ。ジンもしばらくはここにいるかと一杯あおる。
「で、これをどうする?」
「うーん、どうしよっか。まさかこんなになるとは思わなかったけど」
明るい声で笑うシェラザードと、机の上で突っ伏して動かないヨシュアを交互に見る。
「さすがにあの酒一気のみはヨシュアといえど轟沈なのね、勉強になったわ」
「せっかくの酒なのに一気のみなんかさせるなよ」
「ヨシュアが勝手に飲んだんだもの。止める間もなく」
「……まあな」
最近シェラザードの飲酒量が前より増えており、心配になったヨシュアが酒場に探しに来たのは雨が降りだした直後。肩で息をしながら駆け込んできたヨシュアは水をすぐ頼んだが、置かれた水と最初から置かれていた酒を取り違えてしまった。
「あたしだってせっかくなのにゆっくり飲みたかったわ。この辺では珍しい、お米使った醗酵酒でしょ? 東のほうじゃこれが主流だっていうじゃない」
「俺が持ち歩いている酒もそれだぞ。まあ、さっきのやつみたいにいいもんじゃないが」
「へぇ。味がすっごく変わるんだ。同じ材料なのに。……これだからお酒は止められないわ」
顔を赤くし半眼で上機嫌なシェラザード。これさえなければと思いながら、付き合っている自分も同類だということに気がつかないジン。
「とりあえず雨もまだひどいことだし、もう一回頼もうっと」
嬉々としてマスターに声をかけ、視線をまたヨシュアに戻した。
「カクテルとかは行けてたみたいだけど」
「あんなものは甘い水だろ。酒とは認めん」
「よねー。やっぱり苦味の奥になんていうのか、うまみって言うのがね……」
二人は酒談義を繰り広げていたが、しばらくしてどちらも黙った。他の客の声が良く聞こえてくる。シェラザードの視線は眠るヨシュアの頭に向いていた。
「……ふふっ、あたしもまだまだバカなまんまなんだなーって思うわ」
「どうした急に」
「んー? この間起きたことが、あんまりにも馬鹿げてでっかすぎた……って感じになるのかしら。放心したままで次にすぐ移れない」
ジンは女の言葉を聞きながら酒をあおる。そして頭の中で反芻。
「……自分は自分、他は他。言い聞かせてるってことは、自分はそう納得してないってこと……バカのままなんだわ」
「そうか? バカって自覚してるヤツと、してないヤツの差はただ事じゃないぜ」
「……」
ジンはそれ以上何も言わず、シェラザードも黙って杯を重ねる。雨は最初ほどの勢いはなくなったが、いままだ降り続いていた。
4.
なんなんだろうな、と夜、ベッドに潜り込む時に思う。お父さんかお母さんに聞いたら教えてくれるだろうか。ほんのりとくすぐったいこの感じ。
屋根からの雨音は一定の間隔を保ち、普段ならばティータを緩慢とした眠りへ誘う。ご飯も食べて、工房につめているラッセルへ夜食を届けて、ほんのちょっとだけお手伝いをして。今までだったらそのまま一緒に朝まで工房に詰めてしまうことも多かったが、今日はなんとなく戻ってきた。
「……寂しくなんかないよ」
今までだってそうだったんだから。少しの間だけあんなに賑やかだったんだから。誰もいない家が当たり前だった。
「……」
何度目かの寝返り。こうなるのならばいっそ工房にいればよかった。寝にくいけれど誰かはいる。けれどラッセルはティータが工房で夜明かしすることを好まない。
「寂しく……ない」
ここしばらくはずっとエステルやヨシュアたちと一緒にいた。夜寝るときもエステルかクローゼが傍にいてくれた。朝起きるとアガットやジンが笑顔で迎えてくれ、オリビエの行動に驚かされて目が完全に醒めた。
それが楽しかった。痛いときもあったし、悲しいこともあったけれど。
「……」
瞼をぎゅっと閉じる。他の人もこんな風に眠れない夜を過ごすことがあるのだろうか。そんなことなんかないよという風に笑う仲間たちを思い出す。自分はまだそんな風になれない。早くなりたい。
枕元においてあったぬいぐるみにぎゅっと抱きつく。明日になったらきっと元気になるからと。雨は静かにティータを眠りへと誘い始める。
5.
毛足の長いカーペットなので本来なら足音はほぼ消される。なのに給仕は、彼がどういう風な経路を描いて移動しているのかが手にとるように分かった。さすがにもう寝ている人間もいるので一階だけだが。
「まだなのか!」
時折聞こえてくる悲痛な声。だがもう慣れてしまっており、あまり驚きも覚えない。それよりも明日晴れないと、洗濯ができないなと思う。
「……?」
玄関で警備をしている兵士が、怒りを隠せずに歩き回っているミュラーに手紙を渡していた。
「こんな夜に一体何が……」
足音が止まって怪訝に思った給仕はその現場に鉢合わせた。夜遅く、もう大使館の門限が過ぎているタイミングでの連絡は、今まで一度たりとも良いものではなかった。不安になりミュラーの傍らから手紙を覗き込んだ。
『……というわけでまたしばらくしたら連絡するよ』
すぐにクシャクシャにされてしまったので全文目を通すことはできなかったが、どうやらまた出かけてしまったようだ。
「……あ……」
「何がボースだ……何が食の祭典だ……」
ぶつぶつと呟くミュラーに何かしらの恐怖を覚えて思わず身を離す。
「この雨の中を……お出かけになられた……のですね、オリビエ様……」
時計を確かめるとボース行き定期便の最終時間だ。時間も遅く、外は雨でほとんどの人間が出歩いていないというのに。
すぐにオリビエの携帯用通信機へと連絡をとるミュラーだが、いつものように徒労に終るんだろうなと溜息一つ。
「やっぱりいい知らせじゃなかった」
必死になって通信機にしがみ付くミュラーを眺めていてもあまり面白くない。明日もまた早い。寝るに限る。
「では、わたくしめはこれにて」
「ああ、すまないなこんな時間に」
給仕は聞いていないだろうなと思いながら声をかけた。だから返事があったことに驚く。言いながら外していた視線を元に戻すと、ミュラーはまた通信機で何かをしていた。
「……」
これだからここの仕事はやめられない。意外なミュラーの律儀さに嬉しくなりながら給仕はその場を辞した。
Ende.
雨音に紛れ、雨音に誘われみんないろんなことを考える夜。そして眠れぬ夜を明かす。特に一番最後の人w
一晩の間に思考は流転する。とどまらない思考は人の生き様、時の流れに通じるような気がしてならない今日この頃。止めてしまうとそこで終わりだとは前から思ってました。あの事件を経て、何も変わらなかった人はいないはず。そんなところが書いてみたくなりました。