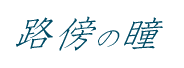
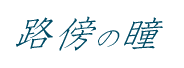
戦役が終って五年経ち、それなりに戦災復興も進んできた。未だに片付けきれていない瓦礫や廃屋があるがずいぶんと数も減っている。だが、そういったこととは別に問題ができていた。人の問題である。
出征したまま帰ってこなかった兵もいる。もともと少ない人口に、戦死者もそれなりの数に上った。そうなるとどうしても働き盛りの男たちが足りなくなってしまう。それを見てとった近在の国から一気に労働者が流れ込み、当時におけるリベール人口の三分の一に匹敵するとも言われたほどだ。最初は気にならなかった。いなくなった男たちの代わりに外国人たちは働き、日々の糧を得ることができていた。しばらくすると仕事にあぶれるものができてきた。その数は日を追うごとに確実に増えていく。結果、路銀が足りずに祖国に戻れず、もともと祖国にいられないからリベールに流れてきたこともあり、各地方で貧民街のような場所が形成されていった。
それでもまだよかった。とある貴族の屋敷に貧民街出身の人間が押しいるまでは。それまで触らないように近寄らないようにという態度だったリベール人の不満が噴出し、結果国としても放置していられなくなってしまった。もちろん女王はこの状況を憂慮し、国内優先とはいえそれなりの支援もしていた。その支援も含めて仇になってしまったといえる。
そんなわけで、ツァイス分隊を中心に、王都警備隊や親衛隊の下っ端からも手助けが出て、混成部隊が作られていた。ツァイス地方にある貧民街の一つに窃盗団のアジトがあるという。一斉摘発のために結成された部隊の中に、地方を転々として経験をつみ、ようやく親衛隊に入ったユリアの姿もあった。
「シュバルツ君じゃないか。久しぶりだね」
「分隊長殿……」
ツァイス分隊に所属していた頃の上司が手を振る。敬礼を返す姿を目を細めて眺めていた。
「うん、似合うな、その青は」
「もったいないお言葉です」
「事実だよ。そちらでも活躍をしているとか。噂はよく流れてくる」
いきなり隊最強と言われていた相手に勝利しただの、空き巣を湖に投げ込んだだの、相変わらずの武勇伝だと舌をだす。こういう、とても隊長とは思えない行動をするが信頼篤い人間だ。
「……志願したのかい?」
「いえ、自分が所属する小隊は全員参加しております」
「そうか……」
分隊長は内心ほっとした。自分の部下だったころも、危ないといわれる作戦が展開される時に必ず志願してきたものだ。それだけに、危険なところに出て行くにもかかわらず、志願ではないときいて妙に安心する。
「今までも言っていたが、またこの言葉を君に言う事になるとはな」
「……」
「命令系統は違うがそこは目をつぶること。……生きて帰れ。以上だ」
「はっ!」
火中に何らの対策もせず飛び込もうとする様はすぐにわかった。比例して怪我も絶えない。
「そんなところで散るには惜しい人材だ。ぜひとも上がっていくがいい」
「もったいなきお言葉、感謝いたします」
深々と礼をしたところで集合の合図が入った。身を翻して自分の部隊に戻る後姿を見送る。自分も自分が率いるツァイス分隊をまとめなくてはと思うが、結局ユリアが人ごみに隠れてしまうまで見送った。
第一隊の奇襲、第二隊が裏に待機。第三隊は目的外の人間が巻き込まれないように、実際は自分たちの邪魔をされない為に警備。ユリアは第一隊に行きたかったが、なぜか上司に却下されて第三隊にいた。同僚たちと一緒に壁を作り、野次馬たちや係累が現場に踏み入るのを阻止する。後ろでは大捕り物が展開されている気配がした。
「……何故却下されたのだろう」
今自分が携わっている仕事が劣っているとは思っていない。とはいえ、理由もなく却下されれば気になるというものだ。実際は親衛隊のもっと上層からユリアは第三隊に入れろといわれていたからなのだが、本人はそんなことはあずかり知らぬこと。少し気もそぞろになっていたところがあるのかもしれない。
「オヤジっ!!」
一陣の風がユリアに向かってきた。いや違う。まだ十代ごろの少年。一瞬判断が遅れたユリアの脇をすり抜け、拘束されている一人の傍に駆けた。
「こいつっ!」
「何事だ!」
気がついた他の兵たちが行く手を阻み、結局目的地にたどり着くことはなくユリアのところへ連れ戻されてくる。
「貴様かっ! 自分の役目ぐらい果たさんか!」
「申し訳ありません!」
怒鳴られるが自分のミス。一撃を歯を食いしばって耐え、少年を壁の外に追い返した。けれど少年は傍から離れず、中に入ろうと機会をうかがいつづけている。
「さっさと帰れ!」
誰かが口を開くが利く耳を持たずにあちらこちらを往復。見かねたユリアが声をかければ。
「……お前の父親なのか?」
「オマエに何がわかるってんだよ!」
薄汚れた顔がユリアに向き、その目がきつくにらみつけている。
「ええっ!? 何がわかるんだ!」
「……」
格好の的を見つけたとばかりに敵意を露にしてくる。軽率だったかと拳を握り締めるが、つとめて毅然とした態度を崩さないようにした。
「話さなければ何も解らん。自分が知っているのは、お前の父親は少しばかり度が過ぎたということだ」
「はっ!」
言葉が終るか終らないかのうちに少年が笑い出した。これ以上おかしいことはないとばかりに。気に食わないが黙って収まるのを待つ。
「アンタ、わかるのか!? 外国人だからってこんなトコに押し込められて、仕事も取り上げられて! 本気で明日飢えて死ぬかもしれないって極限を!」
「……」
「その服、親衛隊だろ!? 親衛隊につぎ込まれる金は毎年増えてるんだって、その金の一部でも俺らみたいなのに回してくれりゃって、いつだってオヤジもオフクロも飲んだくれてたさ!」
「……それはっ」
あわせて口論になりかかるところを隣の同僚が止めた。何を言っても無駄だと。眉をひそめ少年を眺める。気が触れたのかと思うほどに笑い、どこでそんな言葉を覚えるのか、ひどい単語を羅列しつづける少年。ふと気がついた。周りがそういう言葉をしゃべる環境なのだ。
地方勤務時にもこういった捕り物に参加をよくした。今考えればこんな人間もいたのかもしれない。だがユリアは知らなかった。ずっと、突入部隊にばかり志願していたから。
「……」
「オマエなんか嫌いだ! 親衛隊なんか嫌いだ! 大嫌いだ!」
「それ以上言うと誹謗中傷の罪で捕らえるぞ!」
隣の同僚が黙って動かないユリアの代わりに拳を振り上げれば、すばやくその場から逃げ出していった。
「……ま、気にすんな。良くある話だ」
「良くある、話なのか?」
「ん? しらねぇのか? 大抵働き手不足を補うからああいう奴らは大家族だ。それが悪く働いて一家立ち行かなくなって、生きるために犯罪に手を染める。……確かに、今のこの国の状態じゃ、他を受け入れる力はまだ無いよな」
「ちょっと……そんなこと私たちが言ってどうするのよ」
苦笑しながら別の同僚が肩をすくめた。
「ここだけの話にしてくれよ。……まあ、あのガキの言うこともわからんでもない。確かに親衛隊に流れてくる金は毎年多くなってるって噂はあるな。本当かどうかはしらない」
「それ、親衛隊じゃない。新しい部を作るからそっちに流れてる。なんで親衛隊になってるの?」
「そこまでは知らんぞ」
ユリアもその話は聞いている。新しい部は国防の根幹にかかわり、大事なことであると
。
「……大事なことなのだろうが」
こういう民をおいてまで、優先されるべきことなのだろうか。そんなことを一瞬だけ考え、また任務に戻った。
次の非番、先ごろ作戦を展開した貧民街にそっと出かけた。あの時には任務第一であまり回りの建物や雰囲気には気が付かなかったが、リベールにもこんなところがあるのかと思わずにはいられない。ツァイスには長くいたが気が付くことができなかった。
「一体私は何をみて過ごしていたのだろうか」
丁度ユリアがツァイスに着任した時にここも大きくなり始めたという。犯罪の温床とまで言われてしまうようになったのはつい最近だった。
雨が降ればすぐに泥だらけになりそうな道の両側に、何もすることが無いとばかりに何人かの老若男女がぼんやりとしている。かと思えば母親らしき女の横で幼い子どもが赤ん坊を子守りをして、耳元で大泣きに泣く赤ん坊に釣られて自分も泣いていたりする。
「……」
帽子を深く被り流れ者を装って歩く。見慣れない人間がいても何らの反応を示さない。毎日違う人間が来ては出て行くこの街、余所者は慣れているのだと気が付くには少々時間がかかった。
「……何も知らない」
国を捨てて出てきたもの。国に仕送りをしながら暮らすもの。時代の流れに取り残されて、どうしようも動けなくなったもの。挙句、昏い仕事に手を出し、そのまま命を喪ったもの。たまらなく痛かった。
涙が溢れようとする。往来で泣くわけにもいかず足早に街からでた。ツァイス市街が目に入る頃、ようやく感情が落ち着いてきた。
「何を見てきていたんだろう」
周りに目を向けてもっといろんなことを見ろ。士官学校時代、剣の師がそんなことを言っていた。以後、そうであるように努力してきたつもりだった。どうしようもないほどつらいときも、できるだけ周りを見るようにした。決して平坦な道を歩んできたわけではないユリアだが、あんな目は知らなかった。似たレベルの暮らしをしている人々に出会ったことはあるが、皆、目は生きていたから。日々貧しくとも自信を持ち、楽しそうだったから。
頭の中でいろいろなことを考えながらツァイス市に入ろうとしたところで、何がしかの集団がいることに気が付く。一人二人を集団が取り囲んでいる構図だ。
「……貴様ら、何をしている!」
一喝に取り囲んでいた人間がこちらを見た。大人になりきれていない、子どもでもないそんな年頃。ユリアも取り囲んでやろうと近寄ってきたが、通常の人間では出せない気配を感じたか、舌打ちをしながら散っていった。
「……この偽善者め」
一人が横を駆け抜けざまに一言吐き捨てていった。顔は見えなかったが声には覚えがある。あの時、父親の元に行こうとした少年の声だった。思わず振り返ると、街道と脇道の分岐点で向こうもユリアを眺めてきている。いや、睨み付けてきている。今まで捕まえたどんな犯罪者よりも鋭く、そして哀しい視線。
「……!」
追いかけようと動いた瞬間に脇道の奥へ消えていってしまう。ユリアと理解して投げつけてきたのか、わからないままその日は暮れた。
いつか理解したいと思いながら日々を過ごしていたせいなのか、何かとその少年と顔を合わせた。決まって犯罪が行われそうな場で、その度に罵られ、何も問えないまま物別れ。憎悪の瞳というのだろうか、あの視線で射抜かれた。捕まえることができず射抜かれ、それが悔しくて情けなくて仕方がない。
「彼らのことをもっと知れば、あの視線に対抗できるだろうか」
分かり合えるのなら、その上で彼らの暮らしが向上できるのならばこんなにいいことは無い。決めたその足で各地方の陳情係に連絡を入れた。そこならば何がしかの手がかりが得られるかもしれないと。
要塞の一室でただじっとユリアは待っていた。目の前の上司が紙の束から目を上げるのを。じっくりと時間をかけて話を聞き、実際に見、考えたことを纏め上げた報告書をすみからすみまで読む上司に少し不安になってくる。やがて書類を調えて机の上に置いた。
「……この報告書は、確かに良くできている」
「それでは……」
「……シュバルツ隊士。お前の気持ちはわからんでもない。あそこのやつらも、もはやこの国の民なのだろうな、この報告書どおりに」
「……」
上司の言いたいことが図れない。
「だがおそらく、会議にかけてもやつらの為に今以上のことはできんと結論されるだろう」
「何故ですか!」
「時間が要る。やつらはまだ、自身がリベールの民であると思っていない」
「え……」
思わぬ言葉に力が抜けていく。
「どこかにあるのだろうな、自分たちは異邦人なのだという意識が。……もちろん我々側も歩み寄らなければいけない。今以上に。だが、解るだろう? 手を差し出しても、掴むところがなければ意味はない。無理矢理鉤で引きずり出しても良い結果にはならんだろう」
女王もこの件には頭を痛めていると付け足す。各地方で摘発が行われた頃ぐらいから、国から出る補助金を受け取ろうとしなくなったのだと。
「時が来ればこの報告書、陛下に提出しておく。時間が要るのだ。傷を癒すには」
「……は!」
力なく敬礼をして部屋を出た。そこへ慌しく兵たちが駆けて行く。最近世間を騒がせていた窃盗団の主格を捕まえ、レイストンの牢に護送してきたそうだ。なんとなく予感をして牢まで降りれば。
「……お前は」
「フン……」
あの少年だった。いやもう少年とは呼べない。牢の中と外で、分かり合えぬまま相見えることになってしまった。
「何故……」
「アンタに解ってもらおう何ておもわねぇよ、偽善者」
言葉が詰まる。結局そこから進むことはできないのか。牢から上がる階段途中で不意に涙が溢れた。
「……」
偽善者と呼ばれるのは構わない。解りあえないことも構わない。ただ、自分以外の人間も彼らのことを考えている。それを理解してくれないのが哀しかった。
牢を行ったり来たりする少年と、レイストンに詰めていることが多くなったユリアは、よく鉄格子越しに対峙した。少年の瞳の鋭さは変わらず、ユリアも何も言わず牢の前に立つだけのことが多かった。もちろん説得もするのだがすべて徒労。何度目かに牢で対峙した頃には、少しずつ国と外国人の関係も良くなっていたものの、二人の関係は相変わらずだ。
そんな日々は急に終わりを告げた。次第に犯す罪の度合いが酷くなってきており、次に何かを起こせばもう外には出ることはできない、そんな犯罪者になってしまった少年。外にいる時間よりも牢にいる時間のほうが長いのではないか、どんなに尋問をしても何もしゃべらない彼は、いつしか「牢名主」とまで影で呼ばれていた。
そんな「牢名主」は何を思ったか脱獄を図った。
「大扉を封鎖しろ! 脱獄だ!」
「牢周辺の兵は最大警戒! 相手は武器を所持している!」
騒々しく放送が鳴り響いて、外の訓練場で部下たちを見ていたユリアも即座に身構えた。牢の建物は少し離れたところにあり、そこへ一般兵が集まってきている。
「ぐあっ!」
鉄材のようなものを振り回して飛び出してくる少年。
勢いに弾き飛ばされて円陣を崩す兵たち。
何かを叫びながら大扉へ向かい、駆けつけてくる兵たちを交わし、そして、響く音。
振り回していた鉄材が手から飛ぶ。胸に続けて数発銃弾を撃ちこまれ倒れた。
「……」
確かにそれが最善だったのかもしれない。鉄材でまともに殴られた兵数名は意識不明だ。一部始終を眺めていたユリアは少年が運ばれていっても、その最期の場所を見つめていた。
名も知らない少年はその後、身寄りの無いものばかりが集まる墓所へ埋葬された。何も刻まれていない墓碑がずらりとならぶそこは、管理をしている教会の人間以外、個人的に訪れるものはいない。入り口でユリアも逡巡していた。
「……あの時の言葉はお前の祖国の言葉だったな。戻れぬ故郷でも故郷か」
何をどうしても、解りあう事ができない人間は存在するのだ。それはその人自身がどうこう、という問題ではなく、自分とは決定的に違うとしか言いようが無い事なのかもしれない。それでもそういう人間がいるということは理解したし、彼を通じて外国人の待遇をよくしようというユリアの気持ちはあちこちに伝わった気がする。まだまだ問題は山積みで、今もまだ外国人は増えつづけているし、王国人との軋轢は解消していないけれど、そう思いたい。
「お前には気に食わないかもしれないが、私は解りあうよう努力したい人間だ。偽善でも構わない。そこから変わることだってある」
手にもっていた花束を、墓所入り口の碑の前に置く。いつかは参ることをかすかに思いながら、今はだめだときびすを返すのだった。
Ende
そんなことも、あるかもしれない。作中で親衛隊は基本的にベタ誉めだったのがちょっと気持ち悪かったもんで。王国人だと嫌う理由はあんまりなさそうですが、視点を変えたらどうなるか。作中でよく知るユリアさんになるまでにはいろんなことあったんじゃないかな。最近それを埋めてみたいと思ってたり。
どうにもならないこともあろうさ。いかにして彼女は彼女足りえるようになっただろう。