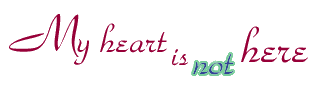
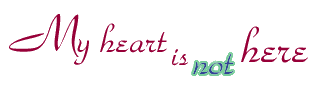
その国のことは知識として知っていた。城でも誰かが噂をしていたし、城下に出ればもっとたくさんの人間が話題に上らせていた。けれども自分が出かけていくとはほとんど考えていなかった。自分がそんな表舞台に出ることはないだろうし、もしも出るならば切っても惜しくないところに投入されるはずなのだから。
帝国とリベールの関係は、まあそれなりにいいほうだといえようか。何がしかが表面に噴出しそうではあるのだが。
「まぁ、国内に比べたら微々たるものかな」
「またそういう不穏な発言を……」
外は大雨、少しだけ暖炉に火を入れて温まった部屋の中で二人差し向かい。相変わらず勝負は続いているがオリビエは劣勢だ。盤面を睨むふりをして、ついつい別のことを考えてしまう。
「キミは行った事があるかい?」
「あるな。一応」
「へぇ。いつ行ったんだい? ボクは記憶してないんだが」
「現女王陛下のご子息夫妻……皇太子ご夫妻の葬儀の時。父が葬儀に出席した。それについていった程度だ」
「なるほど。ボクは行かなかったけど、兄上たちは何人か行ったって言ってたな」
どんな国だった? 問いかけに盤面から目を上げ苦笑するミュラー。
「残念ながらほとんど覚えていない。まだ国際飛行船も就航していない時期だ、当然陸路になる。ほとんど眠っていたが暇な旅路だったと思う」
遊びに行っているわけではない。父はすぐ葬儀に出席、ミュラーは兄ヨハネスと一緒に控え室で待っていただけだ。なんで自分もついていかなければならないのかが全く判らなかった。今では顔つなぎの意味も含めていたのだろうなとは思う。それでも、自分のことを覚えている人間はあの城にもういないだろう。
「どうして? 古株なら覚えてるだろう?」
「他にも近隣の貴族がきていた。俺は苦手だから部屋の隅のほうにいたしな。誰とも目を合わせた覚えはない。それで覚えていたらすごいだろう」
「うーん、まあそうかも」
ということはミュラーもかの国のことはほとんど知らないということだ。一体どんな国なのだろうか。
戦役をひっくり返した英雄カシウス。奇想天外な着眼点で全てのきっかけを作ったラッセル博士。訓練された飛行部隊に大変な士気。圧倒的優位だった帝国軍を押し返した国。産業も、国の規模としては比較的大きい方で、特にオーブメント系の輸出業は他の追随を許さない。
ここ近年のデータを抽出すればそれなりの事はわかる。けれどそれは、その国を本当に知ったことにはならない。
「良く聞くのは……人を変える国だというな」
「ああ。ボクもそれは聞いた」
こっそりと城下に遊びに出た時、馴染みの店主からそんな話を聞いた。リベールに旅行をすると、なにか気分が変わると。
「それに賭けてみたい、かな」
「俺もだ」
「……何が変わるのを期待しているんだね?」
「皆まで言わせる気か?」
ジロっとミュラーがにらみつける。いいです、と小さく呟いて、盤面のナイトに指を置いた。そのままどこへ動かそうかと悩む。
しばらくの時間が経つ。相変わらずナイトに指を置いたまま、ミュラーは少し飽きたのか、暖炉の様子を観にいったりしていた。その背を見ながらどうにかしてごまかしたいと一瞬思ったが。
「ああもう、リザインリザイン! 投了!」
参ったなぁと自分のキングをはじいた。それは盤面に快い音を立てて転がる。
「ようやく認めたか。そろそろ夕食の時間になるが、その間もずっと悩みつづけるのかと思ったぞ」
「いやぁ、空腹もある。おなかがすくとちゃんとものは考えられなくなるね」
「満腹でも考えられんものだ。程々がいい」
ミュラーは、勝ったのにもかかわらずそう嬉しそうな表情ではない。転がっている白いキングをみて、オリビエの顔を見た。
「……俺に負けてどうする」
「だねぇ」
肩をすくめて笑った。
「でもさ、勝負は時の運だと思うよ。そのとき一生懸命やって、それで負けたなら悔いはないさ」
「確かに。……が」
盛大に溜息を一つ。
「今回は何回もイカサマをした挙句にこれだ。それにイカサマは、俺にしたら何が何でも勝ってやるという気になる。それでは逆効果だ」
「うん、今度はばれないようにする」
「……もはや何も言うまい」
頭を掻き毟りながら大窓へ。大分雨は落ち着いた。開くと冷たい風が部屋を引き締めていく。
「この分なら今日の夜間訓練は実施できそうだ」
「寒そうだね。常々兵士たちはすごいと思うよ。ボクはとても感謝している」
「一般兵どもはご苦労だな、確かに。俺はよくない上司だ」
「そうかな。常に上官がそばにいたら、美味しいご飯も美味しくないものだ。だからキミはしばらくボクと愛の語らいをするのがいい」
「……」
親友が肩を落とすのを見て若干満足。だが、出かける前の一戦、と内心決めていた戦いに敗れたとは、あまり幸先の良いものではない。
知らない国。知らない相手。知らない会話。本当に「英雄」と自分は渡り合えるのか。「英雄」であったのは十年も前、今はその片鱗もないのかもしれないと頭の端によぎる。軍から出て遊撃士となり、そこでも活躍を続けていると情報は入っているのにだ。
「……ボクの方が「英雄」にいいようにされる可能性のほうが高いかな?」
「貴様は何のためにリベールへ出向く気だ?」
呟いた弱音に厳しく詰問された。顔を上げるとミュラーがいつものように腕組みをして窓際に立っている。
「何のためだ?」
言葉が喉に詰まる。何のためだ。そう、この国を変えるための一歩を。
「この国を、変えたいから」
「何故だ?」
重ねられた詰問。あっけにとられてしまった。そして、次にはミュラーから視線を外す。何故だ? 何故? 見つからない。いつもならもう十分だと言うほど流れ出してくる言葉が。虚ろで、何もない言葉が。自分はそれほどまでに、自分を語っていなかったか。深く長い息を吐く。
「……ボクは」
「……」
心の奥底に、何か大きいものがある。それを表す言葉も知っている。けれどそこに自分自身が乗らない。乗っているのかもしれないが、それが確信できない。
「……my heart is not here」
「何?」
ミュラーの口から何かが零れた。そちらを見るとニヤリと笑っている。
「My heart's in the Erebonia……。少し変えてみたが、どうだ?」
「ああ……ああ」
どこかの国の詩人が、故郷を強く強く思い、その一端を迸らせた一節。そのままミュラーは暗唱を続ける。聞きながら目を閉じ、自分の心を深く探った。雑多なことやうわべだけのことを全て取り除いた底に。
「My heart's in the Erebonia, wherever I go」
「My heart's in the Erebonia, wherever I go」
最後の一節が重なった。余韻を楽しみ、ゆっくりを目を開ける。視界に飛び込んできたのは、上がりかかった雨と差しはじめた夕方の太陽光。それに照らされ、心なしか満足そうなミュラー。
「貴様の答えはわかった」
「……ん、そうだね。単純すぎて言葉が見つからなかったよ」
「あんなに毎日給仕たちに投げかけているのにな」
「やきもち? キミにだって何度も贈っているじゃないか」
「いらん」
一刀して部屋を横切る。そろそろ副官に任せていた部下の訓練が終わるのだとか。
「すまんが後片付けは任せた」
「ほいほい」
見送り、閉まった扉に向かって一礼をする。深く。そして万感の。
「ありがとう」
本人に伝えるのは恥かしいし、態々口に出して言うような仲でもない。こういうものは本当にここぞという時に取っておきたい。例えば、全てが終わった後に。
「どこにいようとも、我が心はエレボニアにあり……か。なるほど、しばらく肝に銘じてみよう」
これ以上ないというほど、愛して止まない国。だからこそ憎まずにはいられない。まさに今の自分にぴったりだ。
「これなら、「英雄」と渡り合うこともできるのかな」
それなりに黒い部分も見てきたし、自分が関与し、生殺与奪の場面に出くわしたことだってある。だが絶対的に足りない年齢を重ねることでの熟考や知識。そこだけはどうにもならない。
「まずは認めてもらう。そして、出来るならば知恵を借りよう」
リベールという国は人を変えるという。今まで何人も、そんな人間を見た。自分もそうなれるか。良き方向へ変わっていけるか。変われる。流転する流れの中で少しでもいい岩を掴んでみせる。
「いざさらば北の国よ、私はもう少し強くなって戻ってくる」
必ず。
Ende
何気に『Watte』と続いていたりします。間空けすぎw