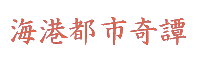
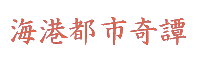
ギルド入り口で右往左往している女がいた。ドアノブに手をかけては離すの繰り返し。
「あの……遊撃士に、御用ですか?」
ツァイスへ行かなければならないが、目の前に困っている人間がいるのなら最優先だ。シェラザードが後ろで成長したな、と頷いている。声をかけられた女は怯えた様子でエステルを見た。
「あなた……遊撃士?」
「ええ」
「……」
視線をあちこち動かしながら考えていたが、やがてエステルを手招きして路地へ向かった。慌ててシェラザード、クローゼ、オリビエが後を追う。
市長選のにぎやかさからはかけ離れた空間。静かな路地では年寄りが日光浴を兼ねて昼寝をしている。。
「木が、生えてきたのよ」
エレオノールと名乗った女はようやく切り出したが、その内容がよくわからない。
「木なら、いくらでも生えるんじゃない?」
シェラザードの疑問ももっともだ。エステルたちが頷いていると女は憤慨した様子を見せる。
「普通に生えるなら問題なくってよ。考えてみてちょうだい。ある日突然、昨日まで何もなかった庭に若木が生えてきたことを」
「家族の誰かが庭師を呼んだのでは?」
「私は一人暮らしよ」
オリビエの問いを一蹴。週に三回手伝いが来るが、木が突然生えた日は手伝いが来ない日だったそうだ。
「ほうほう、それはミステリーだね」
「貴方、面白がっているのではなくて? まったく……」
興味深く見るオリビエをにらみつけるエレオノール。
「でもさ」
黙って聞いていたエステルが声をあげた。
「何かそれで困ったことになってるの?」
「うかがったお話だけだと、何もない、あるはずのないところに木が突然生えたという薄気味悪さはわかるのですが……。何か、木というものにいわれがあるのですか?」
クローゼが疑問を挟む。言われた女は先ほどまでの勢いはどこへやら。肩を落として俯いてしまった。
もともとそれなりの階級であり、幼少の頃には遊び相手がいた。付き人として連れてこられた少年。その彼が好きだったのが、今突然庭に生えて来た木だったと、ぽつりぽつりと語る。
「じゃ、きっとその人が貴女にわかってもらう為に植えたのだよ。うーん、ロマンティックだ」
「……もう、いないわ」
浮かれたオリビエの声を流して呟く。
「一年前に、海難事故にあって」
「……」
さすがのオリビエも黙る。
「酷い嵐の日があって。私も、私の家族も、もちろん彼も一緒に船に乗っていたのだけれど。……結果は、私一人」
静かな路地に彼女の言葉が響く。どういえばいいのかエステルが考えているところに、とりあえず現場を見てみようとシェラザードが提案した。ぞろぞろと一行がたどり着いた先は市長の屋敷にも匹敵する敷地。
「こ、これのどこがそれなりの階級、なわけ?」
「ルーアンには、下手をすれば王家よりも裕福な方々が多いですから」
「趣味のいい庭だ。ボクの創作意欲を掻き立ててくれるよ」
「……ちょっとあんたたち。何しにここにきてるかわかってるの?」
渋面で少し遅れてきたシェラザードがたしなめる。そうだった、と開いていた門からエステルは庭の片隅へ。そこには彼女の背丈ぐらいの若木があり、地面は確かに最近掘り返したようだ。
「うーん。木に詳しいわけじゃないんだけどさ、別に変わったとことか、ないよね?」
幹に手をやりながら振り返るエステル。
「そうねぇ。ありがちな話としては、こっちの方とか」
言いながらシェラザードが足先で柔らかい土を軽く踏む。
「……掘ってみる?」
「私は依存はないですがエレオノールさんの意思次第ですね」
「もし掘ることになるのならボクはこっちの方で応援させてもらうよ」
「何言ってんの。男手は貴重なんだから、働いてもらうわよ」
ああでもないこうでもないと言い合っているうちに、エレオノールの表情が引きつっていることにクローゼが気がついて騒ぎは落ち着く。
「ええと、そういうわけなんだけど、掘ってみようか?」
苦笑いをしつつエステルが尋ねると、相変わらず引きつった表情のままで女主人は頷いた。
「シェラ君、一つ意見を言わせてくれないか?」
「なんとなく言いたいことはわかるけれど、どうぞ」
「……もう掘っても無駄な気がする。地上が遠いのだけれど、引っ張りあげてくれるのかい?」
「あら、そんなことするより、こっちにある土を元に戻していくから、その上を登ってくればいいのよ」
土を被って見上げるオリビエに微笑みかける。
「えーと……ボクって……」
「骨折り損、ってことね」
オリビエの隣でエステルがショベルを投げ出して座り込む。
「エステルさん、オリビエさん。エレオノールさんから梯子を借りてきました。埋め戻しますので上がってきてください」
言いながらクローゼが梯子を穴の中に立てかける。オリビエが上がり、次いでエステルも地上へ戻ってきた。梯子を抜いてクローゼとシェラザードが土を元に戻していく。丸ごと抜いて脇に置いていた木も戻して一息つけば全員土塗れ。
「ううっ、芸術家のボクがこんなに土塗れになるだなんて……」
「そんなのどうとでもなるでしょ。それより、結局何にも出なかったね」
「そうね。可能性はほとんどなくなった。掘ってる間に話を聞いてきたんだけど、正確にこの木が突然生えてきたのは11日前。朝起きて、庭いじりをしようとしたら知らない樹が生えてきてたそう。これは確かみたいね、土が新しく掘り返されてた感じしたから」
シェラザードが考えをまとめようと声に出す。
「少し私、周りで聞いてきます。何か変わったことはないか」
「あ、あたしも行く。クローゼに頼ってばっかりじゃだめだもんね」
歩き出そうとするクローゼの後を追う新米正遊撃士。二人の少女を見送ってから残った女も立ち上がる。
「おや、どこへ?」
ようやく息が落ち着いてきた、と座ったままオリビエが伸びをする。
「あたしはここの主人にもう一回ちゃんと話を聞いてくる。あんたは……そこの木でも見ててちょうだい」
もういちど埋めなおした木を顎で指してから屋敷へ向かった。残ったオリビエは言われるままに木を見上げる。
「……別に変わったことは、ないよね?」
なんとなく声をかけてみる。別に反応はない。ただ風に若い枝を揺らすばかりだ。木から視線を外して屋敷を眺めると、ふいに暗くなった。何の気もなしに顔を上げると、隣家に植えられていた大樹の枝から何かがオリビエめがけて落ちてくるではないか。慌てて避けようとするも間に合わず、直撃にあってその場に昏倒するのだった。
川辺で夕涼みをする老女にエステルは声をかけた。始めは面倒そうにエステルを片目でねめつけたが、エレオノールの名を聞いて急にさめざめと泣きはじめた。
「えっ!?」
思わずクローゼと顔を見合わせる。
「エレオノール殿……哀しいことだのう……」
一年前にあった海難事故で一家と小姓が死んだ。仲が良い家族で、その小姓も忠実で実直だったという。現在は当主の、年の離れた妹が住んで屋敷を管理している。
「ちょっとまって。あたしたちエレオノールって名乗る女の人に会ったわよ、ねえクローゼ」
「ええ……おばあさま、本当なんですよね、その事故の話……」
「疑うなら市長の家の図書室に行ってみぃ。当時の新聞がのこっとるだろうよ」
半目で二人をにらみつけて鼻をすすり川辺から離れていく老女。なんとなく嫌な予感に襲われてエステルは親友の腕にしがみつく。
「ねねねねえ、ももももももしかしててて」
「エステルさん、そうと決まったわけじゃないですから。動揺しすぎですよ」
苦笑しながら遊撃士を見るが、腕を振り払うことはせずに市長の屋敷へ向かった。
「ルーアン地方の新聞は、この部屋にすべて置かれています。年代順になっているのでごちゃまぜにしないで下さいね」
司書の言葉を聞き部屋に入る。一年位前だったよね、と手分けをして探すこと数十分、エステルがその記事をみつけた。
「確かに生存者なしだって」
「エレオノールさんの家はルーアンでも大きいので、後日の話も書かれていますね。……妹のナタリーさんがあの家に住むことになったのですか」
「……ものすごく嫌な汗がでてきちゃった……」
半泣きでエステルは記事を手帳に写し取った。その間になんとなくクローゼは他の新聞に目を通す。
「ふぅ。気は進まないけどシェラ姉とオリビエが待ってるか……クローゼ、いこっか」
「……」
「クローゼ?」
「えっ! あ、すいません、行きましょう」
「どうしたの?」
「なんでもない、と思います」
「歯切れ悪いなぁ。このエステルさんに悩みは言っちゃってごらんなさいよ」
内心怖くて堪らないが、クローゼが不安そうな顔をしているのはそれより嫌だ。わざと茶化すといつもの笑みが戻ってきた。
「ちょっと、ひっかかった記事があって。何がひっかかったのかはよくわからないのですが」
「ん? ええと、新種の魔獣がルーアン市街で目撃……?」
小さな小さな囲み。幾度か目撃されるも捕獲できず。
「……気になるの?」
問いかけに小さく頷くクローゼ。どうしたものかとエステルは頭を掻く。
「……とりあえずギルド行ってみよっか。あそこなら魔獣の情報は必ずあるから」
「すいませんエステルさん……」
「気にしない気にしない。クローゼのカンは、他の何よりも信頼できるんだからね」
笑うエステル。つられてクローゼも笑い、二人はギルドへ急いだ。
屋敷へ向かったシェラザードは勝手口付近でエレオノールに出会った。
「ああよかった。あなたに聞きたいことがあるのよ」
「聞きたいこと、ですか?」
「そ。……なんで迷ってるの?」
「……え? 意図がわからないのですが」
困った顔でシェラザードを見つめてくる女主人。問われた銀閃は何も言わずにただエレオノールを眺める。
日は傾き、二人の女の影を長く伸ばす。
「何を迷っているの、エレオノールさん。あなたはここにいるべきじゃない」
「仰られている意味がわかりません。私はここにいる。何がいけないのですか?」
「……あっちゃあ……」
神父でも呼んでくればよかったかしら。自分の説得でどうにかできるかしら。
眉根を寄せながらシェラザードは「エレオノール」を見た。
『何を、私が、迷っているとでも』
「あなたは死んだのよ。お屋敷に来る前にちょっと回りで聞き込んでみたけどね。一年前からずっとここに住んでるのは、あなたと同じ姿をした女性だけど、ナタリーさんという名前だってこと」
「エレオノール」が奇妙な光を発し始めた。
「多分、海難事故で一人生き残ったんじゃなくて、あなたも一緒に……。ねえ「エレオノール」さん。何を、迷っているの?」
『迷ってなどない。貴女こそ何を仰るの? 人のことを死んでいるだなんて……失礼にも程がある』
言い切ったところでシェラザードに向かって凶暴な風が吹き付けた。咄嗟に小さな風を巻き起こして相殺させる。
「戦術オーブメントも操作せずにそんな真似ができる時点で、只者ではないってことだわ」
露出している肌に浅い切り傷が付く。
「シェラ姉!」
「ご無事ですか!」
エステルとクローゼが駆けてきた。それぞれ得物を構えようとするのを制す。
「待ちなさい! ナタリーさんを傷つけてはダメ!」
「じゃあどうやってこの状態クリアするのよー!」
風にあおられながらエステルが叫び返した。「エレオノール」の瞳は黄色く光り体中から怪しい妖気が漂っている。対するこちらの武器はどうしても寄り代のナタリーを傷つけてしまう。せめても、と凶風を緩和する為に風を巻き起こす程度だ。
いっそ神父でも呼んでくればと思い、少女たちに声をかけようとすると急に風がやんだ。
「……え?」
「シェラ姉、あれ……」
半ば呆然とするシェラザードに、これまた驚いているエステルが指した。「エレオノール」と、猫に似ているがそれとは明らかに違う生き物。背中に固い鱗が見え、尾も三本だ。その生き物は「エレオノール」の足に噛み付き悲壮な声で鳴いていた。
「気が付いたらあの子がボクの枕もとに座ってるんだ。一瞬猫ちゃんかと思ったけれど全然違うね」
「オリビエ……」
いつのまにか隣に立っていた金髪の青年をちらりと見る。その間に生き物の尾が発光し始めた。警戒しつつも好奇心には勝てず、じっと何もせずに見守る。見る間に人の形を取った。
「……誰だね?」
「あたしたちに聞かないでよ」
オリビエの呟きにエステルが反応。シェラザードとクローゼは光景に魅入られている。
尾からの光は男のようだった。「エレオノール」に何かを伝えているようだが音は聞こえない。そして、男がそっと上を指したかと思うとそのまま消えた。同時に「エレオノール」もその場に崩れ落ちる。慌てて抱き起こせば気を失っているだけだ。シェラザードはほっとして息を吐く。
「……で、コレはなに」
「知らない。あの木のところにいたら上から落っこちてきたことだけは確かだけれど」
「役にたたないヤツ……」
「ヒドイなエステル君。ボクだって協力員なんだから」
「ああもううるさいうるさい」
耳に栓をするしぐさをしてエステルはシェラザードのところへ行く。ちょうど、女も気が付いたようだ。
「……ええと……」
「すいません、ナタリーです。姪っ子が迷惑をかけていたようで……」
「気が付いていたの?」
「うっすらとは。この家に住むようになってから、意識が飛ぶことがあったのです。そして、無性に不安感が押さえられないままずっといました」
「神父様にでも相談すればよかったのに」
「もしかして、と思ったのは、ガストン……この屋敷の小姓ですが、彼が好きだった木を植えてみてからです。教会に行こう、と思ってもその度に意識が飛んで……とりあえずギルドまでは行くことは出来たのですが、そこで体が言うことを聞かなくなりました……」
エレオノールが嫌がったのかもしれない、と寂しそうにナタリーは呟く。
「今は、お体はいかがですか? おかしなところはありますか?」
「いいえありません。ありがとう、王立学園のお嬢さん」
言いながらナタリーは立ち上がる。もう夜が遅いので泊まっていけという誘いを断りきれず、一行は後について屋敷へ向かう。ふと後ろを向いたエステルは、あの不思議な生き物が、エレオノールが消えた場所から動いていないのを見た。もう後少しで暮れる庭で、長く長く影を伸ばしながら、まるで守護獣のような神々しさ。思わず見とれてしまう。
「エステルさん、どうしましたか?」
「……ん。いや、あの子みてたの」
「ああ……ガストンさんか、エレオノールさんかが可愛がっていたんじゃないでしょうか。あの木に誘われて、このお屋敷へ来たのかもしれませんね」
「だね。きっとさ、ルーアンで目撃されてた謎の魔獣ってあの子のことだよ。ギルド資料に幻がどうのこうの、ってメモ残ってたもん」
やがて日は沈み、最後の朱が紫に侵食されていく。二人が見ているうちに素早く立ち上がり、一声鳴いていずこともなく走り去っていった。
「これでエステルの幽霊嫌いも少しは落ち着いてくれたらいいんだけど」
あてがわれた部屋でシェラザードは杯を空にした。すぐさま、なぜか部屋にいるオリビエがお代わりを注ぐ。
「シェラ君の怖いものってなんだい?」
「聞いてどうしようって言うのさ」
「いや、エステル君はわかりやすかったけれど、キミは幽霊ごときで動じるわけはないし。ミミズとかも別に大丈夫だろう?」
「あんた、あたしをどういう風にみてるのよ」
「ああ、一杯の酒が怖い、だなんて言うのはやめてくれよ?」
「……」
にこりと微笑むとオリビエがもっていた酒瓶を奪い取る。まだ半分以上残っている。はっとなったオリビエが抵抗する間もなく、彼のグラスにはなみなみと酒が注がれた。
「はい。グラスに入った分は飲む、それが今日のルールでしょ」
「か、カンベンしてください」
「だぁめ。まだ酒瓶5本も行ってないじゃない。じゃんじゃん行くわよ」
空けばすぐ足す。それを繰り返してオリビエはいつものように机に突っ伏した。それをみて自分のグラスを空にし、自分で注ぐ。意識朦朧としているオリビエをその場に残し、窓際にグラスを持って近寄った。
「……怖いもの。……そうね、今の幸せな生活を奪われることが、きっと一番怖いんだわ。……あんな思いは、一度だけでたくさん」
心の中でそっと思う。そんな彼女を星明りとラングラントの明かりが柔らかく照らすのだった。
Ende
だいぶん前から書いてて、どうしようかなーと思いつつ、結局いつもの如くのまあいいかであげてみました。男勝りだけど幽霊はダメというエステルのギャップが結構好きです。で、隠れたテーマはシェラさんの怖いもの。本当に「一杯の酒が怖い」とか言って、オリビエに大量の酒を持ってこさせる、と(まんじゅうこわい)。