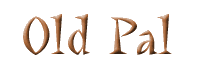
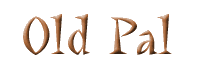
夕暮れが近くなると、風向きによっては下町の方から夕餉の匂いがしてくることがある。屋敷では使わない食物、香辛料。食べたことがない味を想像しながら窓から外を見るのが好きだった。
普段はそれだけで、使用人が食事の時間を告げに来て、想像の時間は終わり。厨房から食卓まで届く間に幾人もの毒見役の手を経て、すっかり冷え切った食事が常だった。料理長にこっそりと熱々のスープを飲ませてもらうのだが、それが一番美味いと思うのに、なぜそんな手間を踏まなければならないのかと少年は思う。父親や兄はそれで納得しているようだが、彼にはどうも納得できなかった。
「あれ、あそこ……」
使用人の誰かが置き忘れたのか、梯子が高い塀にかけられていた。外からは変わらず夕餉の匂い。誘われるように庭に出た。
梯子を昇り、眼下の様子を眺める。高台に彼の屋敷はあり、皇城を除いてすべての家を見下ろすことが出来た。
「よっと……」
梯子持ち上げ今度は外側に立てかける。しばしののち、彼は一人、帝都の下町を歩いていた。
露店で立ち食いをする仕事帰りの男。真剣そうな目つきで芋を眺める若い女。みずみずしい葉野菜を、粋な口上で売り上げる商人。屋敷でいるだけでは見ることができない、生の暮らし。何もかもが珍しく、また興味深い。
帝都には多種多様な人種が住んでおり、実は純血の帝国人はあまり住んでいないのだとか。家庭教師が教えてくれるのを話半分に聞いていたが、実際にこうやって人の集まるところを歩けば実感できる。ぱっとみただけではどこの人間なのか良くわからない。
「おや、あんたどこのお坊ちゃんだい?」
恰幅のいい中年女が声をかけてきた。
「ええと……向こう……」
「向こうって言ったら、皇室護衛のヴァンダールさんとこがあるだけじゃないか。じゃ、なにかい? あんた、そこのお坊ちゃん?」
どう答えようか迷っていると、
「そんなはずないよね。あたしらとは無縁の人たちさ。こんなところにいるはずない。ところであんた、お父さんやお母さんは?」
と、自己完結したようだ。
「家に、いないから……」
父は常に帝国軍の元帥府に詰めているし、母は母で各所の晩餐会に呼ばれてほぼ毎晩留守だ。それがあたりまえだとおもっていた。
「あらま! こんな可愛い子おいて、どこほっつきあるいてるんだろうねぇ。よし、あたしがなんか作ってあげるよ。ほら、遠慮せずおいで」
にこりと笑う。丸い顔や、少しやつれた表情や、白いものが混じっている髪は、母とはまったく違う。それなのに、母親に見守られている安心感をもった。
その日から、機会があればその女のところに行った。そっと戸を叩くと笑顔で迎え入れてくれるのだ。年老いた夫の両親と彼女の子どもたちが四人。夫は徴兵で共和国の前線基地に行っているという。
「ほらミュラー、こいつなんかどうだ?」
「なんだこれ」
「ミソ、っていうらしいぞ。カルバードより東の方ではよくつかわれてるんだって」
香辛料屋を営むそこには見たことがないものが多くあった。ミソ、というものを指先にとり、舐めてみる。
「……塩辛い」
「ぶはは! お前、そんなに一気に舐めるなよ! 香辛料ってーのは、ほんの少し隠し味に使うのが筋ってもんだぞ!」
「そういうことは早く言ってくれよディーター」
水をもらいながら往来を眺める。一般家庭用にかなり値を下げてはいるが、それほど減るものではないのが香辛料というものだ。店は比較的静かで、子どもたちが騒いでも叱られない程度だった。
ふと、ミュラーは店の入り口から視線を感じた。鏡に映しながらそちらを見ると、金髪の少年が中をうかがっている。
「?」
入ってくるのかと思えばそのままいなくなってしまった。
帰り道、少し冒険をして行った事がない裏路地を選んだ。いかがわしい店が散見できるが、ミュラーにはまだ意味はわからない。涼みに降りてきていた女たちがミュラーを見つけ手を振る。なんとなく手を振り返せば、疲れきった顔がほころぶのがわかった。
「……」
意味はわからないのだが、ただ無性に哀しい。たまらなくなってそこから駆け出す。
気が付けばよくわからない道に入り込んでいた。途方にくれて回りをみると、あの少年。姿を隠す前にミュラーが声をかけた。
「お前、店の前にもいただろ?」
「……」
「なんか用事か?」
「……」
「……この辺りの道知ってるなら、教えてくれないか?」
ばつが悪いが、戻れなければ大変なことになる。顔を赤くしながら問えば、金髪の少年は笑顔になった。
後から考えれば真っ直ぐ帰ったのではなかった。あちこちの郭を通り、顔なじみらしい遊女たちと一言二言声を掛け合う。ミュラーはあでやかな格好をした女たちに気圧され顔を赤くしながら後を付いていく。ようやく見慣れた大通りに出たとき、ミュラーの頬には赤い口紅の後さえついていた。
「……拭きなよ」
そっと差し出されたハンカチを受け取る。
「お前さ、名前は? 俺はミュラー」
「……オリビエ」
「ありがとう、オリビエ。どうしようかと思ったよ」
「キミは、いつもあの店にいるわけじゃ、ないよね?」
「ああ。外に出られるときと出られないときがあるんだ。本当なら毎日でもいたいんだけど」
「……どこからきてるの?」
「あっち。オリビエは?」
「ボクは……ボクもあっち」
「なんだ、一緒の方向か。じゃ、一緒に帰ろう」
ミュラーは笑い、戸惑いながらもオリビエは彼について歩き出した。
オリビエはミュラーの屋敷手前でいつも別の道をたどる。その先には確か皇城とその係累しか住んでいなかったはずなのだが、あの裏路地を抜けたようにそれが近道なのかもしれないと、さして深く考えなかった。隠した梯子は見つかることなく、時間が出来た時彼を外へ連れ出す手段となる。剣の稽古や勉強の隙をみては下町へ遊びに出かけていた。ディーターとその仲間、時折オリビエも混じり、くだらないことで笑いあう日々が続いた。
ただ、オリビエは心底笑っていない。直感でミュラーはそう思っている。ごくたまに父親について領地視察に行く時があるのだが、その際領民が見せる笑みに良く似ていた。内心では何を思っているかわからない、うわべだけのそんな笑み。
「ミュラー様、お館様がお呼びです」
今日は何をして遊ぼうか、どうやってオリビエを笑わせようかと考えていたところに給仕が入ってきた。
「父上が?」
珍しく屋敷に戻ってきたのか。何の用事だろう。疑問符が頭を飛び交うが、今日は遊びに行けないだろうということだけはわかった。
「わかった。今行く」
長い廊下を歩み、重厚なドアの前に立つ。両脇には彫像のように警備兵が佇んでいる。
「父上、ミュラーです。入ります」
応えがあり、そっとドアを開ける。使い込まれた机の上で何か書き物をしている父親が居た。
「何用でしょうか」
「……勉強や剣の稽古は進んでいるか?」
「あ、はあ……それなりに」
「それなりに、では困る。お前もそのうち皇族の誰かの護衛になるのだから、腕も頭も磨くように」
「心得ました」
「よし。今日はそれで呼んだのではない」
引出しの中を探る。
「こっちにこい。これだ」
古ぼけた姿絵だ。そこに描かれているのは。
「あ……」
「覚えがあるな? いわんでいい、どこで知り合ったかは」
父親の言葉が頭に響く。
「庶子で末席だが帝位継承権保持者だ」
「庶子……帝位……」
ああ。だから。彼は心底から笑えない。皇帝の血をもつがゆえに宮廷にいなくてはならないが、半分しかその血には意味がない。見たくもない、聞きたくもないことを、10歳にも満たない身ですべて見てしまっている。
「これからお前がどう接するかは任せる。だが、そういう人物だ。覚えておけ」
「……かしこまりました」
辞していい、といわれ父の執務室を出る。溜め息をつきながら廊下を歩いていると、兄に出逢った。
「どうしたんだ。元気ないじゃないか」
「兄さん」
「悩みか? 好きな子でもできたか? 最近外によく出て行ってるみたいだしなぁ」
「え!」
聞けば屋敷内の半分くらいは知っているとのこと。
「気にするなよ。誰も止めてないのが答えだ。この際堂々と正門からでていったらどうだ?」
「それじゃ面白くない」
「確かに」
二人して高らかに笑う。ふと、オリビエはこんな風に笑いあうことはあるのだろうかと思う。
「やっぱり元気ないなぁ。なんかあったのか?」
こっちにこい、と兄の私室へ連れて行かれる。もっと小さい頃は良く入り浸ったが最近はご無沙汰だった兄の部屋。あまり変わっていない。
「どうしたんだよミュラー。ん?」
「うん……実は」
父親から聞いたこと。自分が思ったこと。足りない言葉で言い表せない胸のうち。すでに領地管理の実務を行っている兄にどれだけ伝えられるか。さぼっていた修辞学だがきちんとやっておけばよかったと今更に後悔。
「……なるほど。それはまた面白い人間と友だちになったな」
「知らなかった。ただ、すごく寂しそうだと思って。俺たちと遊んでいても、どこも見てない感じがしてた」
兄はミュラーの頭に手を置く。
「お前はお前が思ったように行動しろよ。俺みたいに、身動きが取れなくなってからじゃ遅いんだ。お前は、そいつを笑わせてやりたいんだろう? なら、今後もそうすればいいんだ」
「兄さん……うん、わかったよ。俺ちょっと行ってくる」
頭に置かれた手をとり握り、部屋から飛び出していった。
それから数年。まだ本当のオリビエの笑みは見ていない。が、少しは安らぎになっているのか、安心しているような気がする。それとともに見えなかった性格に振り回されるようになったが、半ばそれは覚悟していたし、本気で迷惑になるようなことはしていない。……口以外は。
幾度か注意はしたものの一向に直す気配はない。ミュラーが、どんなことがあってもオリビエを見捨てるはずがない、ということを知っているからだ。
「少し甘やかしすぎたかもしれん」
腕組みしながら父の呼び出しを待つ。大事な用事があるから部屋にいろと言われ、こうしてずっとまっているのだが何も音沙汰はない。
「今後も俺はこの苦労を背負うのか?」
渋面だ。容赦なく拳を落とし、反省の言葉を口にしようとも、その数分後にはまたくだらないことで脱力させる。
「ある種の才能だな、あれは」
そんな才能、自分で実験して欲しくなかったと最近特に思う。
場を和ませようと一生懸命なのだ。それはわかる。わかるのだが。往々にして行き過ぎるきらいがある。
「ミュラー様、お館様が」
「ああ、わかった。今行く」
ようやく呼び出しか、と短く息をはいて給仕に礼を言う。あまり父の執務室へ行くことはない為、そこまでの道のりが重い。
「父上、参りました」
「来たか。最近、お前の剣の腕の上達振り、目を見張るものだと聞いた。よくがんばっているな」
「まだまだです。今後も修練あるのみ」
「その意気だ。……お前は、我が家の仕事を知っているな?」
「……皇族の守護と領地運営、北方の外敵侵入の阻止……」
「そうだ。うち、領地運営と北方警備はお前の兄が勤めている。お前は皇族の守護の任につけ」
「……」
いつかは言われると思っていた。そのために剣の腕を磨いた。皇族と渡り合えるよう、したくもない勉強もたくさんした。
「現状の候補としては第三帝位継承者、エーデルトラウト皇子殿下だ」
「!」
誰かの専属護衛になるということは、その護衛の対象の障害になるものはすべて排除することになる。特に、同じ皇族は。また、自分の親戚と剣を交えることも多々あると聞く。それは構わない。ヴァンダールの名をもつ、しかも直系であるということはそういうことだから。
オリビエを、斬ることになりかねない。だが、家長の命は絶対。選んだ相手には理由がある。複雑な心境。自然、顔が下を向く。
けれども、いつかの時のようにうなだれて帰るようなことはなく、すぐに顔をあげた。
「父上。申し訳ありません。自分には、もう剣をささげたい相手がいる」
「……お前は、私の命がきけない、そういうことか?」
「絶対です。曲げられません」
「…………」
「…………」
黙って視線を絡ませあう。窓から入る夕日が長くなり、光が届かない位置にいたミュラーが照らし出される。その光が弱まり、ほの暗くなったころ、父が降参というように手をあげた。
「いいだろう。そういうと思った。断っておこう」
「申し訳ありません、父上……」
「構わん。エーデルトラウト皇子殿下の一派はライン地方を狙っているという噂がある。味方に引き入れるか、噂など聞かなかったことにしてつかず離れずで行くか迷っていたところだ」
「ラインは……我が領地の中でも一番裕福な……」
父は頷く。
「お前が了承するなら懐柔策をとろうと思ったが、あまりいい噂は聞かない。それよりきな臭くなってきているから、戦死の可能性も高い」
何かしらないが宮中では戦争の機運が高まっていると聞いた。皇族は全員戦場に出るので、そのために内乱を起こすことが歴史上よくあった。
「お前が決めたんだ。祝福まではしてやれんが、行くところまでいってこい」
「ありがとうございます、父上」
「で、これからどうするんだ? 前々から軍隊に入りたいとは言っていたが……」
「はい。次週、試験を受けます」
「そうか」
もう外は暗い。手元の明かりをつける。あまり精度のよくないオーブメント灯で、ぼんやりとした光に親子が浮かぶ。
「そろそろ新しいものに変え時か。リベール製のものがいいのだが、なかなか手に入らん」
「市井ではまだランプが主流です。贅沢はいっていられません」
「お前に諭されるとは。だが、そのとおりだ」
しばらく明かりを見つめ、やがて小さく、いってこい、とだけ伝えられた。
「今度もどったら、ディーターの店に顔をだすか」
オリビエから、ヨシュアが戻ってきたのでそろそろ帝都に戻ると通信があった。ようやく戻ってくるかと安堵したと同時に、これでリベールの食事ともお別れかと寂しさを覚える。帝国とは違い、魚料理がたまらなく美味い。
「ディーターに教えてやろう。流行るんじゃないだろうか」
香辛料屋をもとにして一人立ちし、帝都の市で食堂を営む昔馴染み。リベールの味は絶品だと教えてくれたのは彼だ。
「もう、来ることはないかもしれない」
小さな、女王が治めるこの国。精一杯両隣の大国に飲まれないように生きるこの国。だがその基盤は危うい。できれば残っておいて欲しいとは思うが、何が起こるかわからない状況だ。
読んでいた本を置きのびをする。窓から見える空港の喧騒は、いつにもましてにぎやかに見えた。
Ende
話を書けば書くほど地雷を増やしていっている気がするしりあです。多分、他の人がイメージするよりももっと年齢が上な感じで出会ったかな、と私は思ったり。多いのは乳兄弟チックに書かれているのですかね。ただでさえ反乱気味なのにそこにも異を唱えるか俺は……(タメイキ)。ただこの辺りは、個人的な設定のページあたりでちらっと書いたような気がするからいいか。ほぼ宣言してたようなもんだし。この話で少佐は十三歳程度。おにーちゃんは一つ違いの十四歳。すでに実務の一部をになっていたりするすごい人。あ、おにーちゃん名前決めてないや(笑)。やっぱりライン地方の特産は金糸工業と絹織物工業かしら。
最後で「もうリベールにはこないかもしれない」とかほざいてる少佐ですがその後呆れるほど(以下略)。