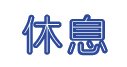
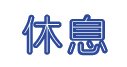
「自分の責任です。いかようにでも罰してください」
女王の前に黙って立ちユリアは言葉を待った。つい先ごろ、湖に住む魔獣が何を思ったか、大挙して王城に襲撃をしてきた。陸側からの襲撃には強いが湖側からになると途端に状況が逆転してしまう。最後の砦になるはずの女王宮が敵に向かって曝されてしまっている為だ。当然それはわかっているので親衛隊と王都警備隊とで連携しながら湖に繰り出し退治は行っていて、今回も念入りにした。
それでも見過ごしが出てしまった。生き残りが城内に入り込んだと知らせが入った時には既に数人の給仕と隊士が傷を負っていた。それが焦りにつながったのか、出す指示出す指示が上手くいかず。結局小隊程度の軍人と五人ほどの給仕が怪我を負った。大怪我と言うほどではないが完治にしばし時間がかかるだろうとの侍医の言葉に、ユリアは自分の至らなさに唇をかんだ。
「……少し、そうですね、一週間ほどゆっくりしてみては」
「御意に」
提案のかたちを取った命令だった。その間にどうするかを決めるのだと薄らと思うが、自分の行く先がどうなろうとどうでも良かった。ただ、自分の失策で怪我を負わせてしまった人間に対する悔恨の思いのみ。部下たちもそうだが一般人を守りきれなかったことが何より辛い。
女王が辞してからユリアは立ち上がる。詰所に戻ると一瞬冷たい空気を感じた気がしたが、それも当然だろうと右腕を強く握り締めた。誰も彼もがユリアの失策でこの事態になったことを知っている。
ユリア自身も襲撃で傷を負っており、もう少しで腱が切れていたかもしれないという酷いものだった。けれど本人はそれを酷い怪我とは思っていない。自分自身はまだ自由にあちこち歩き、少し痛みはあるが剣も握れる。
「怪我などしていなければ、仕方ないと言うようには見られなかったな。いっそ剥き出しの敵意をぶつけてくれる方がいい」
自分の執務室に入り、そのままドアに寄りかかった。こんな怪我などしたから、同情と敵意のまぜこぜになった、中途半端な意志を向けられるのだ。中途半端な意志を向けられるとこちらとしても中途半端な対応をしていかざるを得なくなる。それは酷く苦手だ。
「……」
右腕を掴むのをやめ腰に手をやった。カチリと鞘を支えるベルトを外し、剣を執務机の上に置く。普段なら書類が問答無用で置かれているこの机だが今日は一枚もなかった。薄く笑って部屋から出た。ずっと掴んでいた右腕には薄らと血がにじんでいたが、詰所にいた誰も声をかけることはしなかった。
自宅の窓という窓を全て開け放ちよどんだ空気を入れ替える。昼と夕方の境目、中途半端な時間の風は少し生暖かい。普段ほとんどハウスキーパーに任せてある家の中だが、せっかくなので自分で掃除をすることにした。
「買うだけ買って少しも触れないというのも悔しい。結局その間に触りたい欲求が消えていってしまう」
まさか兵舎や詰所に置くわけにいかない私物は自宅に送ってもらっているが、問題はそれに触れる時間がないということだ。流行の本を頼んだとしても結局すぐに廃れていってしまう。意を決して流行の服を買っても同様。結局最低限のもの以外はあまり買わなくなってしまった。
「……また剣舞の本を詰所から持ってくるのを忘れた」
自分が必要なだけではないので剣舞の本だけは詰所に届くよう手配をしてあるが、それがユリアにとってお守りのような存在となっていた。一番自分がいる時間が多いところに置いておきたい。そんな馬鹿げた考えが心のどこかにある。だがいい加減に本を持ち帰らなければ向こうの書架はいっぱいだ。それに今回のことで任を解かれる可能性もある。そうなった時一度に移動させることが難しくなるかもしれない。
「……自分らしくない、か」
一通りの掃討が終わった後、警備隊長に言われた言葉が戻ってきた。確かに戦いのさなか、他のことを考えて判断が鈍るなど今までなかった。
「引退時かもしれないな」
軍務など長期間続けられるものではない。ことに前線に立つ可能性のある部署にいるならばなおさら。体力、判断力の衰えはそのまま死に直結する。
それはまたおいおい考えることにしよう。一通りの片づけを終わらせて自分の寝台に横になった。かすかな風で窓のレースカーテンが少し揺れる。なんとなくそれを眺めつづけていた。その向こう側には昼下がりの空。
「こんな時間にこんな風に空を見上げるなど、何年ぶりだろう」
なんともいえない感情が不意にこみ上げてくる。枕に顔を伏せて目を閉じた。閉じれば一人、浮かぶ男がいる。今の自分を見たらなんと思うだろうか。数日中に会う約束はしていたが見られたくない。だが連絡の取りようがない。
「……仕事中に貴方のことを考えてしまった罰、となるかな……」
本当はいつだって考えている。自分の思いに気付いてから偶々大きな襲撃がなかっただけという僥倖に支えられて、ユリアはミュラーのことを考えていた。すぐに振り払って、女王やクローゼ、部下の顔を思い出し自分を戒めているだけで。
「……それでも……私は」
柔らかい寝台と時折吹く風がゆりかご代わりとなり、ユリアの思考は少しずつ鈍り始める。そのまま眠りに落ちるのも時間の問題だった。
自然の目覚めではないようだった。その証拠に、もっと眠っていたいと頭も体も悲鳴を上げている。
「……呼び鈴が鳴ったような?」
深い眠りに落ちていた為か、それで起きた気はするのだがはっきりとわからない。気のせいかともう一度目を閉じようとしたところに、呼び鈴。これに起こされたか、どこの家への来訪者だろうと寝ぼけている頭で考えて。
「この階には私の家しかないじゃないか」
慌てて飛び起きて玄関まで行くとやはり自宅への来訪者。一体誰だろうと警戒をした。今自分がこの家にいることを知るのはほとんどいないはず。城から出るときも行き先は告げずに出てきた。まあ少し考えればここにいるとはわかるが、ここにいることを感づける人間がわざわざ尋ねてくるはずがない。肌身離さず持っている護身剣を抜き放ちながら扉の外の人間に声をかける。
「どなた?」
「俺だ」
耳が今聞いたことを拒否しようとした。どうして? 何故ここにいるの? 疑問符がこれでもかと言うように頭の中を飛び交う。あまりに驚きすぎて扉を開けることさえ忘れたほどで、もう一度呼びかけられて慌てて扉を開く始末。開けたそこには私服のミュラーが立っている。
「久しぶりだな。元気にしていたか?」
「あ、はい……ではなくて」
立ち話もなんなので居間に招き入れる。薄暗くなった外に合わせて部屋の中も暗いのだが、それにすらユリアはすぐ気付かなかった。
「何故……こちらに? 約束の日はまだです、よね?」
護身剣をまた鞘に収めて問い掛ける。
「着いたのは今日だ。せっかくだからと王城を訪ねてみたら今日から休暇という。クローディア殿にこちらの住所を教えてもらって来た」
「……王城に寄られたのですか」
「ああ」
それならば聞いただろう。なぜユリアが仕事をせずここにいるのかを。だが確認してしまうのは怖い。そんなユリアを眺め、ミュラーはぽんと手を打つ。
「そうそう、クローディア殿から、忘れ物を届けてくれないかと言われた」
ずっと何かを持っていたのは知っているが気にしていなかった。差し出されたそれは剣。鞘に収まった細身の剣は紛れもない自分の剣だ。
「忘れていったのだろう? 得物を置いていくなど、貴女らしくもない」
「……」
今の自分にこの剣を持つ資格がない。あの日、初めて親衛隊士になった日、女王から直接拝領したこの剣が重い。その手から滑り落ちる。
「重症だな」
床に落ちた剣をテーブルの上に置き小さく呟いた。
「あ、あの……」
「何を、考えていたのだ?」
優しい問いかけに目が潤みそうになる。しばらくそれと格闘していたがすぐに無駄と悟った。涙が流れるなら流れるままにしておけばいい。今更この男の目の前で泣き喚いても動じないだろうから。
「貴方の、ことを」
「……」
「悔しいくらいに貴方のことを思う。書類を見ていても、訓練をしていても、眠る前にも。どうしているだろうかと……考えて、しまいます」
一筋涙が落ちる。ミュラーはそんな様子に息を少し吐いて、零れた涙を拭くように頬へ手を添えてきた。
「俺は……それを聞いて正直、かなり嬉しい。だが……」
一旦言葉を切った。どういう風に切り出せばいいのか悩む様子にユリアは不安になる。
「これでは、俺は貴女の枷になっているだけだ。いや、こうなることが怖かった。自惚れと言ってくれて構わない」
「……一体、何を仰って」
「今回はこの腕で済んだが……いや、それすらも俺は嫌だが、何か他に気を取られることが出来、その挙句貴女が取り返しのつかないことになってしまうのが恐ろしい。その気を取られることが俺のことだと言うのならなおさら」
包帯を巻いた腕をそっとなでる。
「傍にいられるのなら。俺が貴女の背を守れるのなら。こんなに気をもまずに済むのかもしれないが……」
薄暗くてはっきりと顔を見ることが出来なかったがどうやら少し照れているようだ。ここに至って初めて、ユリアは明かりを灯していないことに気付いた。だが今動く気はない。頬に添えられた手が暖かく何よりも安心する。
「思っていてくれるのはたまらなく嬉しい。だが、それが枷になるような思い方は、互いに辛い」
「ミュラー殿が、辛い?」
「今貴女がここにいる理由が、俺なのだろう? 確かに城にいるより気軽に会えるが、もちろん嬉しくてたまらないが……それでも何か違う気がするのだ」
頬から手が離れた。
「俺は、そんな風に貴女を縛り付けたいわけじゃない。ただ……」
寄り添いたいだけだと、引き寄せられたついでに耳元で囁かれた。そのまましばらく黙る。ユリアはそっと男の背に手を回した。
ややあって互いに体を離す。気恥ずかしさを打ち消すように声を発したのはミュラーから。
「少しは落ち着いたか?」
「……多分、落ち着きました」
「ならよかった」
小さく笑っていると、開け放っている窓から夕餉の香りが漂ってきた。そういえばもうそんな時間だと思い、せっかくなので手料理をと思うが次の瞬間肩を落とした。
「どうした? 表情が変わるのを見ているのは面白いが、そうがっかりされると心配になる」
「そんなところをじっくり見ないでください! ……食糧の買い置きがないことを思い出したのです。普段ここにいるわけではないので」
薄暗いのにそんなところまでわかるのかと若干驚きながら言い返すと、なら外に食べに行こうと誘われた。
「この辺は不案内だから貴女に任せる」
ユリアが応える間もなく既にいく気満々な様子に、仕方がないなと肩を竦めた。
一週間ほど休暇でのんびりと家で過ごした。ミュラーはまたすぐに帝国へ戻っていったが、少なくとも一人でいるよりはずいぶんと気が楽だったと思う。ホテルに戻る姿を見送りながらそっと礼をしたのはさすがに気付いていないだろう。
まず一番に女王のところへ行き、その言葉を待った。だが特に何を言われるでもなく、休みを取っていた間のことを淡々と告げられただけで拍子抜けした。その後、けが人のところへ見舞いに行ったがこちらも何を言うこともなく、むしろユリアの見舞いを熱烈に歓迎してくれた。
「お久しぶりですユリアさん、ゆっくり休めましたか?」
先に見舞っていたクローゼに声を掛けられてはっとなる。
「殿下……」
「お元気な顔になられましたね。よかった、やはりミュラーさんに頼ってよかった」
「それは一体……?」
クローゼがしまったという表情をする。だが仕方がないと、ユリアを自室へ呼んだ。
「ユリアさんがどう思われていたかは知りませんが、皆……もちろんあの怪我をされた方々も含めて、誰もユリアさんのことを悪く思ってはいない。けれど、多分、ユリアさん自身はそれを許せないのだろうと思いました。そしてそれは私たちの誰も触れることが出来ないのだと」
きっと自分の責任を感じ沈み込むユリア。わかっているけれどどうしようもできないもどかしさが、嫌になるほどの沈黙を作り出していた。だから女王は、本当の意味で休息をしてほしいと思ったのだという。
「そうしたら、幸運なことに偶々ミュラーさんが訪れてくださって。申し訳ないとは思ったのですが、ユリアさんのことをお願いしました。剣も届けてくださったようで、あとでお礼をしなくては」
「……」
にこにこと笑っているクローゼを前に何も言うことは出来ない。けれど確かにこのおかげでいつもよりほんの少し、立ち直りが早かったような気がする。
「でもユリアさん、皆は特に気にしてはいないのですが、仕事はそうは思ってくれなかったようです。昨日詰所に行ったら、机の上がすごいことになっていました」
「……そ、そうですか」
「できることがありましたら手伝いますので、仰ってくださいね」
笑うクローゼに深々と礼をして辞した。最強の敵が待つ、自分の机へと向かう為に。
Ende.
「失敗した時にどう立ち直るんだろうか」の一つの答えな感じで。少佐がいない時にはもうちょっと時間を掛けるか、わざと仕事を山ほどして忘れるか。どうなるにせよ完治せずいつかは暴発しそうな、そんな気がしてます、ユリアさんって人は。