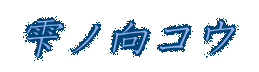
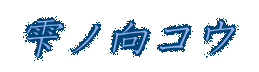
最近気がついた。雨が降ると嬉しそうに外を歩くことが多いが、ふとした拍子にここでない何かを雨の向こうに見ているようだった。
例えば樹の下で雨宿りをしている時、傘を差しかけても気がつかないほど深い思索に入っていたり、例えば窓際に座っている時、窓に当たって流れ落ちる雫の筋をいくつも追ってみたり。雨が好きかと問えば決まって微笑み返し、好きですと付け加えられる。けれども、「好き」という表層に出てくる単語では賄いきれぬ何か。良い記憶なのか、悪い記憶なのか、計れぬままその答えを信じられないミュラーがいた。
「雨に何か記憶でも?」
一転俄かに空掻き曇る。誰かが冗談めかして言っている、雨宿りの喫茶店で切り出してみた。いつもならば、好きですと言われたときの表情が堤となる。それ以上は問うなと無言で続けてくるのだが、今日は最初の問いはしていなかった。
唐突に聞かれたユリアは窓から目を離し、心配そうな目をしながらカップで手を温めているミュラーを見た。
「雨?」
「ああ、雨だ」
反芻してユリアの顔を眺める。ここのところ忙しくて、あえてもあまりちゃんと顔は見ていなかったかもしれない。
「たいした思い出はないですよ。大通りを泳いだくらいでしょうか、話の種になりそうなのは」
「なんだそれは」
「昔……そうですね、20年ほど前の話でしょうか。それはもうひどい雨が降ったことがあったんです」
グランセル地方はあまり雨が降らない。一つ隣のロレントはよく雨が降り、その恵みの産物が穀倉地帯となっている。逆側になるツァイスはグランセルよりもっと雨は降らない。小さな国の中で多様な気候が同居していることが不思議でならなかった頃だった。
朝はまだ晴れていて、懇意で家事をしてくれているギゼラと共に洗濯を干していた。青い空にはためく洗濯物を眺めては、まだ邪魔にしかなっていないのにもかかわらず誇らしかった。
様子が変わってきたのは午後。急に空が曇ってきて、慌てて洗濯物を取り込んだ。
「丁度今日みたいな勢いで急に曇って土砂降りです」
「で、大通りが川になるほど降った、と。そんな危ない時に外にいるとは……貴女らしい」
「用事があったんです」
ミュラーが溜息をつきながら相槌を打てば、正当な理由があるのだと少し機嫌が悪くなった。
「ほう……どんな?」
「母の命日でした。毎年父と一緒に、花を手向けに行くので」
「……」
「これくらいの降りならたまにあるのですが、まさかずっと降り続くとは思ってなくて……」
街道沿いにひっそりと作られている墓地から戻ってくると王都が水浸しだった。特にギルド前辺りの治水は非常に悪く、小さい湖のようになっていたという。
「今では直っていますが、あの光景はちょっと忘れられません。父に抱えられて渡りかかったのですが、どうしても自分で歩いてみたくて」
「……結局貴女の好奇心が原因か」
「そうとも、言うかもしれません」
少し頬を染めて皿の上に残っていた砂糖菓子を口に含む。
「……今日の雨は小降りになってきたようだ」
「そうみたいですね」
二人は会話を途切れさせ同時に外を見る。ややあってミュラーが口を開いた。
「行ってみるか?」
「……どこへ?」
虚を突かれた表情で視線を男に移してくる。
「貴女の、ご両親の墓へ」
「なんでまた。行けないことはないですが……まだ大門が閉まる時間ではないし」
「俺は貴女のご両親に挨拶をしていない。折角話題に出たのだ、案内を頼めるか?」
テーブルに置かれているナプキンに手を伸ばしたところを捕らえ、握り締めながら聞いてみる。少々の間を置いて握り合った手の上に、あいていた手が重なった。
「わかりました。けれど長居はできませんよ。大門が閉まると王都に入れなくなりますので」
土砂降りからしとしと降りへ。常緑樹の葉が久々の水を受けて生き生きしているように見える。そんな中にその墓地はあった。木々が上手くその存在を隠し、知らない人間であれば気がつかない道を入る。主道の真横ではなく少し奥に入っているためか、静かなものだった。
黙って古いが手入れをされている墓の前に立つユリア。墓碑銘は辛うじて読めるものと、比較的読みやすいものの二つが刻まれていた。
「父はつい六年程前にようやく母と同じところに眠ることが出来ました」
「……戦役でなくなられたのでは? それならば十年前では」
「国内がかなり混乱しまして。父がなくなったことを知らされたのは直後なのですが、遺品をどこに保管したのかがわからなくなっていました。遺体は他の仲間と共に荼毘に付したとか。まだ戦争中だったので仕方のないことですが……」
「……教会は火葬を禁じているからな……」
「正式に軍に入ってからあちこち掛け合いました。確か遺品が残っているから、それを取りに来いと言われていたはずなのに、ようやく動けるようになったら戦後処理に圧されて……」
「それで六年前にようやくここに葬ることが出来たのか」
「そういうことです」
言いながら場所をミュラーに譲る。一歩踏み出し、その墓の前で片膝立てて座った。刻まれた銘を指で辿る。くぼみに溜まった水を掻きだし、その文字を体で感じてみる。見たことのない二人に思いを馳せ目を閉じた。
「……」
不意に雨が顔にかかることに気がついた。僅かに引いてユリアが傘を差しかけてくれていたはずなのに。見回せば傘はすぐ傍にあったが、全く見当違いのところに差しかけられている。それをもつユリアはただ何も言わずに雨が降る空を見上げていた。自身も傘を差さずに、ただじっと空から降る水滴を追っている。
「……ユリア?」
幾度か呼びかけてようやくミュラーの方を向いた。その目は普段と変わらない光がある。はず。
「あっ、すいません。傘が……」
「いや、貴女の方こそ」
「……」
「……」
慌てて傘をミュラーに差し出す。その姿を見て、不意にユリアの両親に強く願った。
この人をこの世界に送り出してくれて本当にありがとう。けれど、まだ、連れて行かないでくれ。
雨が降る。時折晴れそうになるも結局しとしと、しとしと。時間が合えばユリアと会っていたミュラーだが、限られた時間の逢瀬なのに、自分と話をしながらその向こうを見ていることに気がついていた。
あの雨の日から。ぼんやりと雨の向こう側を見ていることが多くなった。クローゼにそれとなく聞いてみても仕事中は特に変わったところはなく、非番の時もいつもと変わらないという。けれど、若干語尾が不安そうだった。
「姫殿下も確信が持てずにいるのだな」
王城のバーカウンターで一人カクテルを煽る。近日中に帰国の為オリビエと共に挨拶に来ていたが、会食の場から抜け出した。
「……おや、貴殿は」
「先客がいるのか? 私はそれでも構わん」
既にもう酔っているのか、デュナンが上機嫌で席についた。その後に従いフィリップが一礼。ミュラーも椅子から降りて軽く返礼をした。
「おお、君はあれだ、ほら、帝国の皇子殿下の傍仕えだね?」
「は」
短く敬礼をするとデュナンがうんうんと頷く。
「この間彼とお話をしたよ」
「……え」
「いやあ、非常にこちらも為になる会談だったよ。是非また機会があればとお伝えできないかね?」
「御意」
いったいいつの間に何の話をしたのだと冷や汗が背中を流れていく。幸いにしてボロは出していないようだが。
しばらくデュナンが上機嫌でグラスを空にしていたが、やがてその場で眠り始めた。小さく息を吐いた彼の侍従は、カウンターの奥に置いていた毛布を借りる。
「失礼ですが……そのような程度で宜しいのですか? お部屋にお連れしたりなどは……自分もお手伝いいたします」
「何もかもをわたくしがしてしまうことが殿下の為になるとは限らない。……そう、最近考えるようになりましてな」
せめて風邪を召さないようにと毛布を常備しているのだと、老練な侍従は優しく笑む。
「貴殿も同じ理由から、ここにいらっしゃるのでは?」
「……」
笑い、一杯頼んでフィリップに差し出した。
「いや、わたくしはまだ仕事中なので」
「ノンアルコールですよフィリップ様。こちらもよくわかっていらっしゃる」
バーテンダーがミュラーを指差していた。
「そうですか。では少し頂きましょう。実は少し喉が渇いておりました」
ミュラーの横に座り、透明な色の向こうに世界を映しながら少しずつ嚥下。その洗練された飲み方から、若い頃にはさぞ火遊びをしたのではないかと思ってしまう。半分ほど開けたところでグラスをおき、ミュラーに視線を向けた。
「何か、気になることでも?」
「……誰かがそんなことを?」
「いいえ、誰も。ただ、この年になると知りたくなくてもわかるものです、いろいろなことが」
片目を閉じる姿が年を感じさせない。
「たいした事では……」
「そうですかな?」
「……」
フィリップは残りのカクテルを飲み干す。カタン、とグラスをカウンターに置いた音がした。
「実は、僅かに気になることが」
この先達になら相談してもいいかもしれない。そう思い口を開くと、バーテンダーが用事があると言って出て行った。それを見送り、ミュラーは続ける。
「……シュバルツ殿のことで」
「彼女が、どうかなさいましたか?」
「王太女殿下も言葉の端々で心配なさっていましたが、どこか……遠くを見ているような」
それ以上言っていいものか。だがこの老執事にはお見通しだろう。その証拠に、ふと見た彼の目は笑っている。
「この間の土砂降りの日、自分とあの人とで、あの人の両親が眠る墓地へ行きました。その時からもうずっと遠くを見ている気がしています」
とっくに空になっている自分のグラスを握り締めていると、フィリップがカウンターの向こう側へ回った。
「多少は心得がありますのでね。今の貴殿にはお酒が必要そうだ」
言葉どおりに数々の道具を手に取り、しばらくして小さなグラスに濃い青の液体が満たされる。
「名前は……ありません。今即興であわせましたので」
「……ありがとうございます」
「お好きに付けていただいて構いませんよ」
「しかし、それはフィリップ殿の権利では?」
いいから、と促されたが、若干酒の回った頭で気の利いた名など思いつかない。オリビエがいれば進んで付けてくれたかもしれないが。
「いつでもいいですよ。レシピも書きましょうか?」
フィリップの言葉に生返事をして、たった今出来たばかりのカクテルを眺めた。濃い青。青。青。それはユリアの色。
飲むことが出来ずに手元に収めて眺める。フィリップはそんなミュラーをカウンターの向こう側から眺める。外の雨は今少し強くなっているのか。遠くから水音が聞こえるほどに。
「わたくしも気になっておりました。しばらく気をつけてみることにしましょう。ヒルダ夫人にもそれとなく伝えておきます」
「あ……ありがとうございます……」
自分はずっとそばにいて見守ることは出来ない。いっそ、自分がただの一般兵で、この国に来るのも自由であればと。
「彼女は、雨が好きなのですよ」
不意の言葉に視線を上げると、フィリップが道具を片付けていた。
「父親と交流がありまして。少しは彼女の事を知っています」
「……」
「貴殿にならお話をされているかもしれませんが、彼女の父親は優秀で、わたくしが親衛隊にいた頃引き抜き対象にしたとかしないとか……」
聞いたことがある。何度か打診をされ、その度に断って王都警備の任を全うしたらしいが。
「結局親衛隊に引き抜くことは出来ませんでしたが、気が合って数回ほど個人的に話をしたこともあるのですよ。稀に彼女もその場にいたのです」
あまりに微か過ぎる記憶だが、少女のユリアは語った。暖かい手があったのだと。そのぬくもりに包まれる時にはよく、雨の音がしていたと。
「父親に聞くと、どうやら彼女の母親が赤ん坊の彼女を抱いていた時のことだろうと。あの頃、雨の日は警備隊も若干弛緩しましてな。早めに帰る輩も多かった。あの男も、体を壊した妻と幼い子どもを家に置いているということで、すぐ帰っていったそうです。当時の隊長も事情が事情だからと許していて……多分、その記憶がぬくもりとして残っているのでしょう」
「……家族全員揃った、暖かい記憶が雨音から……」
「そうなるのでしょうな」
ミュラー自身はあまり雨が好きではない。雨が降ると外でやっていた稽古が中止になり、それがそのまま机の上の勉強へ替わってしまうからだ。
「人はそれぞれ、基盤となる記憶を持っています。雨音は彼女にとって、思い出すきっかけの一つなのでしょう」
執事の言葉が一つ一つ頭に入ってくる。そうなのかもしれないと思いながら、自分の男の部分は納得していない。
俺のぬくもりでは駄目か? いつでもとは行かないかもしれないが、望む時できるだけ与えてやりたいと思っている。俺はここにいる。俺はここにいるから、貴女も俺を見てくれ。
ぬるくなったカクテルを飲み、かなり強い酒だということを知った。ユリアはそんなに酒は強くないので、この点は少し違うかなと考える。今度はぬるくならない内に飲まないと申し訳がないと感じながら、結局一切酔うことは出来なかった。
帰国日は晴れて、そして忙しかった。結局何もユリアに伝えることがないまま母国に戻り、毎日忙しく過ごしている。けれど決して忘れたわけではない。手紙の返信を書く頻度も上げた。もっともこれに関しては、オリビエに言わせるとまだまだ足りないらしいが。
そんな日々は緩やかに過ぎる。そして一通の手紙が届いた。ユリアからではない。フィリップだ。嫌な予感がして慌てて封を切る。
『貴殿の力が必要です』
簡潔にそれだけ書かれた手紙を握り締め、オリビエの執務室へ飛び込んだ。数分後、主を説き伏せたミュラーはその足で空港まで行き、グランセル便に飛び乗る。その横には、あまりの勢いに振り回されて目を回しているオリビエがいたとか。
おりしも雨のリベールに着いてから、王城まで飛ぶように走った。門番が何事かと詰め寄ってきたが、その気迫とオリビエの口添えでなんとかつなぎをつけてくることになった。
「いったい何があったんだね?」
「……」
問い掛けてくる男に答える余裕などない。ホールにフィリップの姿を認め、変わらず握ったままの手紙を振りかざした。わかっている、ついて来いと帝国人二人を案内し始めた。
王城から少し離れたところに兵舎が建っている。湖沿いの細い道を歩いてたどり着いたそこの一室に。
「し、少佐殿! それにオリビエ殿まで……」
「!」
ベッドでゆったりと休む女がいる。張り詰めていた意識が一気に和らいでいった。
「やあユリア君。どうしたんだい?」
「情けない話なのですが、疲れすぎてしまってちょっと」
「駄目だよ。たまには休まないと」
なお何かを言い募ろうとしたオリビエをフィリップが手招き。じゃあ置いていくねとミュラーの背中を押してきた。
「……大丈夫、なのか?」
戸が閉まる音を聞いて近くの椅子を引き寄せる。
「実は大丈夫じゃなかったようです」
「……ようです、とは?」
「覚えていなくて……十日ほど倒れこんでいたようですが……」
「十日!?」
それは相当だ。フィリップでなくても手紙を送りたくなる。また降ってきた大雨に誘われて空中庭園を気晴らしに歩いていた時から記憶が飛んでいるとあれば。
「もう雨の中を一人歩くのは禁止だ」
「……禁止、ですか?」
拗ねた口調で返してくるのを聞くと決心が萎えそうになるが、雨の中倒れたという話を聞かされておいそれと許可はできるはずがない。
「俺がいないときでもフィリップ殿や姫殿下に頼んでおくからな。絶対に駄目だ」
「……」
少し不機嫌そうな顔でうつむく。はいと小さく聞こえてきてほっとした。
「……で、雨の中に何かが見えたか?」
声のトーンを落とし柔らかく聞く。うつむいたまま、しばらくしてから小さく首を横に振った。そしてまたしばらくしてから今度は首を縦に振った。
「……どういうことだ?」
「見えました……雨の中に」
何がと問う前に、ユリアの指がミュラーを指している。
「貴方が」
雨音を聞くとなにか優しい気持ちになるのは昔からで、そこから記憶が零れようとしてくる。あまり過去に浸りすぎるのは前を向いていないことになりはしないか。普段はそう思ってできるだけこぼれないように考えないようにしていた。
けれど、ミュラーが墓参りをするといったあの日、ただただ自分にはどうしようもないくらいの記憶の波がユリアを取り込んだ。堰を修復しようにも何らの手立てもなく、昔知ったぬくもりを心が求めだす。
「それをどうにかしないとどうも浮ついてしまい……殿下や陛下たちにはわかってしまったらしく、酷く心配をしてくださいました」
もはや手に入らぬことはわかっている。そう言い聞かせながら雨音を耳に入れないようにしていたが、心がどうしてもざわめいて仕方がない。そんなときにまた土砂降りがあり、気がついたら庭園に出ていた。
「そのとき、雨粒の向こう側に灯りを見た気がしました。手を伸ばせば届きそうなところに私の記憶があった……」
それがどんなものか、ミュラーにはわからない。ただ、語るユリアの表情を見ていると、とても大事なものだということはわかる。
「実際手を伸ばしましたが届きませんでした。それどころか、庭園の手すりを乗り越えようとしてしまっていたので、慌てて離れました」
「……それは」
「なんだったのでしょうね。人は緩やかに壊れる時があると聞きます。自分もそのときはそうだったのかもしれない……」
階下に降りようとした辺りから記憶が途切れがちになる。ただ雨の中を歩いていたような、あまりはっきりしない。
「ちょうど意識を取り戻す寸前くらいでしょうか……声が聞こえました」
ゆっくりと視線を窓に向けた。雫が伝うのを目で追いながら続ける。
「ここにいる……ただそれだけ……けれどその声は」
また視線がミュラーに戻ってきた。何を言いたいのか、それはわかった。
「そして目を覚ましたら十日経っていた、と」
「ええ。で、それからしばらくして貴方が来てくれた」
それまで寝込んでいたせいか、若干顔色はよくないが、今日初めてみた笑顔がまぶしい。
「ありがとうございます」
「ん……いや、礼はオリビエに言ってくれ。ここにいることを許可してくれた……もっとも、ついていくと言われるのは想像していたことだが……」
男は手を伸ばし、ユリアの頭に置いた。そのままゆっくりと撫でる。
「前に言おうと思って言えなかったことだ」
「え?」
「……俺がいる。ここにいる。貴女の求めるぬくもりとは違うだろうが、俺なりのものを貴女に与えることはできる……はず」
そういう相手としてみてくれるか? 雨の向こうの幻影に僅かの嫉妬をこめて。
「でも……私は貴方に何もお返しができない……」
「何を言う。きちんと貴女が生きていて、こうやって俺に笑いかけてくれる。……それが一番だ」
「……」
頬を染めて目を閉じる。
「はい、がんばって生きます」
「あまりがんばり過ぎなくていい。今のままでも過ぎているくらいだ。でないと、俺は何回も帝国から飛んでこないといけなくなる」
一瞬だけ口付けを交わして二人は笑う。外は雨、これからもユリアは雨の向こうにぬくもりを求めるのだろうかと自問する。
「雨の向こうに負けないように、もっともっと貴女にぬくもりを。そうして、腕の中で微笑んでいてくれ。俺は、ここにいる」
心の中で誓い、興味深そうに見つめてくる蒼い瞳を見て思い出した。
「そういえば、フィリップ殿がカクテルを作ってくれた」
「なんと。あの方は多才だ」
「即興で作ったもので名は俺に決めて欲しいと。が、そんなセンスはないから、貴女にお願いしようと思う」
「私が? でも何故?」
「……俺が貴女の様子に悩んでいた時に作ってくれたからな」
「……そんなにも私は不安定だったのですね。後でフィリップ殿にもお礼を言わなくては」
ややあって頷いた。
「『雫の向こう』というのはどうでしょうか?」
「それでいい。かなり強いカクテルだったから、貴女には少しきついかもしれないな」
「そうですか……でも、飲んでみたいですね」
貴方と。付け加えられた言葉に口角が下がりそうになるが、慌てて取り繕った。
ユリアの雨好きは変わらず続いたが、その雫の向こうに見るものがいつしか変わっていたことをミュラーが知るのは、もう少し先のこと。
Ende.
サイズ的に一ページが大きいですが、要するにそれぞれページを作る意味がないかと思ってこんな感じです。『Patriots』以外は連載じゃないですし。PCで見る分には問題はそれほどないと思いますが、携帯から見るとサイズ大きい方なのかもしれない。
人にはいろんな姿があって、壊れたところもある。それを全部まとめて愛せるのならば。