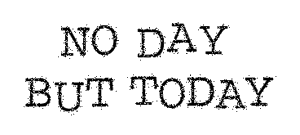
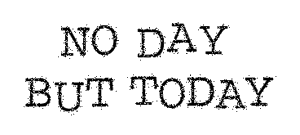
「永遠とは、なんだろうな」
目の前を流れていく大量の水を眺めながら呟いた。
「さあ、なんでしょうね」
どんな人間にとっても、問われてすぐに答えがでる問いではない。短く息を吐いてユリアは返した。
「例えばこの水の流れ。何がしかの理由で枯れればそこでおしまい。永遠に流れつづけるわけではない」
「そうかもしれませんね」
「貴女は信じているのか?」
何を、と瞳をひらめかせるユリア。年齢の割に子どもっぽい動作だとミュラーは口元を緩めた。
「永遠を」
久々の休暇で、しかも二人とも同時に休みが取れた。どこか遠くへ行こうと持ちかけたのはミュラーで、ここがいいと笑ったのはユリア。オリビエに言わせると「なんでまたそんなところに」とのことだがあまり深く追求はしてこなかった。
帝国を超えてなお北、もはや極に近いほどの小さな村。付近にある毎年氷で閉ざされる泉は透明度が高く、晴れた日には鏡になるという。最初は共和国にあるという遺跡めぐりをしようという話だった。が、共和国に帝国人が入るのはいまだ規制が厳しく、手続きだけで数ヶ月がザラ。仕方がないと諦めて泉を見にいこうということになった。
「よく知っていたな。俺ですら知らなかったのに」
帝国北部はヴァンダールの領地が多い。周辺の情報も多く入ってきていたが、その泉のことは知らなかった。
「どこか遠くへ行きたいといろいろ聞きました。今の時期なら凍らないかと思いまして」
何万年もかけて氷に削られてできた谷を鉄道が進んでいく。だが鉄道の終着点からなおまだ山へ分け入る必要がある。帝国側を出発して実に二日かけてようやくたどり着いたそこは、小さな宿が一軒あるだけのつつましい村だった。普段は狩人相手の宿は素朴で暖かい。
「どうやらここは特定の時期だけ、人が戻ってくる村のようだな」
「そのようですね。山が開いている時期だけ狩人たちが集まってくるのでしょうか。冬にはきっとそれぞれの家に帰るのでしょう」
「おそらく。そういう成り立ちなら俺が知らなくても無理はない」
ずっと定着しているものならば管理もできようが、流浪の民に関しては自己申告に任せている部分がある。ずっと以前からミュラーが問題点として兄に提起はしているもののどうにもならない。逆に兄に、「山には山の理があって、それにしか従わないもの達もいる。宗教観の違いというのかもしれないが、そういうことも理解しながら土地を治めるのも当主の役割だ」と返されてしまった。
「というわけで、一応書類上ではこの辺りはヴァンダールの領地ということになるが、実際は定住しないものたちの無法地帯に近い。まあそれでも上手く出来ているらしいからいいが……」
「お兄様の意見、なんとなくわかります。陛下も似たようなことを仰られていました」
「貴女まで兄の味方か。俺の肩身が狭くなりそうだな」
冗談めかして片目を閉じる様が子どものように見えた。
一日目は長距離移動の疲れを癒す為ゆっくりと。女将に道を聞いて、そこから流れてきているといわれた川を遡れたのは二日目だ。幅は狭いが水量は多く、エア=レッテンみたいだなとミュラーは思う。だからこそユリアが行ってみたいと思ったのかもしれないと、深読みもする。
「先ほどの問いですが」
「あ、ああ」
一休みをしながらなんとなく切り出してみた永遠について。雑談にするには少々重いかもしれないと考えていたが、ユリアはそうは感じなかったらしく興味深そうに口を開く。
「例えば、ここの川で遊んだ子どもたちが自分の子どもたちにその楽しさを伝える。そしてその子たちがまた遊んで、自分の子孫たちに伝える。例え川がなくなっても、そこで楽しく遊んだということはずっとずっと伝えられていく可能性もありますね」
「……確かに。それを永遠と呼ぶのも、ありかもしれないな」
「それが元で枯れた水源に水を取り戻そうと運動が起きることもあります」
そしてまた語り継がれていくのかもしれない。
「結局は、人が人である限り、何かを伝えようとする限り」
「そこに永遠はある、か?」
「……ええ」
自分で言いたかったと口を尖らせる。ミュラーから離れて小走りに先へ行ってしまった。しばらくその背中を眺めて男も歩き出す。辛うじてできている道を獣に気をつけながらのぼっていると川が消えた。どうやら地下に潜ってしまったらしい。
「この道沿いに行けばいいのだろうが……少し不安だ」
ユリアはもうとっくに行ってしまったのか、影も形も見えない。少しは待ってくれても良いだろうのにと立ち止まって体を伸ばした。常緑樹の深い緑が目を刺激する。普段、比較的帝都でも緑の多い皇城に詰めてはいるが、庭師の手入れが行き届いたそれと現生の樹は違う気がした。
『樹は、樹です。どんな樹でも一生懸命生きていますよ』
不意にユリアの声があたりに響いた。どこにいるのだ、心を読めるのか。葉の擦れる音と獣の声が邪魔をして居場所が特定できない。
『さあ、私はどこでしょう?』
「からかっていないで出てくるんだ!」
『すぐ近くです。ほら、答えないと……』
何が起こるというのだ。聞こえてくる笑い声に若干いらだちながら顔を上げると、高枝の向こうに浅葱色がひらめいた。
「!」
そのままミュラーに向かって飛び降りてくる。なんとか受け止めたがそのまま尻餅をついてしまった。
「上がおろそかですよ」
これ以上楽しいことなど無いという表情でユリアが笑っている。
「全く……なんということをするのだ貴女は」
「ふふふ、こういう人間ですが、お忘れですか?」
そのままミュラーの額に口付けをしてしがみ付いてきた。
「どうした。先ほどまでの余裕は」
男の髪に顔をうずめる。
「……探してくれなかったらどうしようと、一瞬だけ思いました」
「…………馬鹿なことを」
「そう、ですね」
たまには相手の出方を試してみたくなる時はある。固く信じあっていても不意に不安になるのは、想像力というものを持ってしまった人の業なのだろうか。滅多にそんな行動をとらないユリアだが、やはり離れているということで不安もあるのかもしれない。
「もう少し大人しい方法で試してくれないか? 少し体を打ってしまったぞ」
「あっ、すいません!」
慌てて上からどこうとする腰を抱き寄せる。
「いくら俺でも、堪忍袋の尾が切れたら何をするかわからんぞ。閉じ込めて二度と外に出さないかもしれないな」
「……気をつけます」
二人して起き上がりまた湖を目指す。今度は硬くつながれた手。互いの存在を確かめながら一歩、また一歩。常緑樹の森を抜ければ。
「……」
「……ここか」
風に遊ばれて波立つ湖面が光を乱反射。それ以外はただの水。いや、周りの景色を逆転して映している。名残惜しそうに風の残滓が消えれば、そこにあるのは大きな大きな鏡だった。
しばらく二人とも何も言わなかった。言うことができなかった。どれだけ技術が発達しようと、こういうものを何気なく作り出してしまう自然には。そして、いろいろなことにまみれてしまった自分たちが、まだこういう景色を見て感激できることを噛み締めて。
少し鏡の色が赤みを帯び始める。はっとなって回りを見ると夕暮れになりかかっていた。
「まさか何も言わずに時間があっという間に過ぎてしまうとは」
「確かに。早く戻らないと夕食に間に合わなくなる」
帰らなくてはといいながら鏡から目が離れていない女。それはミュラーも同じで、いっそ色変わりの様を全て見届けたいと思ってしまう。こうしようと考えていたことを全て白紙にしてしまいそうなそんな景色。
「負けてなるものか」
呟きを聞いてユリアが首を傾げる。頭を振って頬を軽く叩き。
「永遠、か」
「……え、あ、先ほどの話の」
「どちらかといえば永遠など、日々で意識はしない。その日、その場ごとに精一杯生きて。それをきちんとこなしていくことが何よりも楽しくてな」
「そういうこともありますね。私もどちらかといえばそうでしょうか」
お互い軍人、そして護衛でもある。何かがあれば命を散らすこともある。
「そのときの行動が何かの間違いで永遠に残る可能性はあるが……そんなことはどうでもいいのだ。いや、それこそが本当に望んでいることかもしれない」
ユリアの右手を取り甲を撫でる。
「だから、なんだ。ああもう、言葉にできん」
言いたいことが音にならないもどかしさ。慌て気味に女の手袋を外す。現れた薬指に小さな金属の輪を滑らせた。
「……?」
ユリアがそれを何かと理解する前に体ごと抱き寄せてしまう。夕暮れでよかった、顔がもし赤くなっていてもわからないだろう。
「……あの、ええと……何か言ってください」
「察してくれ。無理ならもう少し待ってくれ」
「……それはいいですが間違って……えっ!」
言葉に疑問が乗っている。しばらくして息を飲む音が聞こえてきた。
「……お願いです、何か、言って……」
「だから少し待ってくれ。俺も情けなくて仕方ないのだ」
ん、と小さく頭を預けるユリア。恋人の意図することを理解してそっと涙が零れた。それを肩で感じたミュラーはようやく女と向き合う。
「……常に共には在れないだろう。離れれば二度とあえないかも知れない。それでも、俺は貴女を束縛したい。永遠は、信じてはいないが、このときこのためだけに信じたい……」
小さな金属の輪が意味するのは明らかに一つ。不変絶対の契約。
「これを見て、嫌なら投げ捨ててくれて構わない」
言いながら自分も右手の手袋を外す。ユリアに渡したものと同じような指輪が薬指に収まっていた。ユリアは黙ってその手を眺めていたが、不意に視線を男の顔に向けてきた。
「……ずるいです。いつも、いつも貴方は」
「……」
「でも、だからこそ、いろんな貴方を知ることができるのかもしれない」
眦から際限なく雫が零れ落ちる。思わずミュラーは手を伸ばし、少しでも止まれと拭った。
「これから……もっといろんな……貴方を、知ることができますね」
「俺もな。さぞ、波乱万丈な暮らしになるだろう、いろんな意味で」
「それでも、毎日精一杯……生きましょう、ね……ミュラー」
「ああ、約束だ、ユリア」
囁きあい、名を呼び、やがて静寂。湖面はそんな二人を余さず映しつづけた。
永遠は信じたい。けれどそれは夢想であることは嫌というほど知っている。けれど、多分今後どんなに辛く悲しい事態になっても、この時のことだけは自分に残り続けるのだろうなと、愛しい人を腕に抱きながらミュラーは思うのだった。
ENDE.
ナンダコリャ。馬鹿文章の最高峰に君臨しそうだ。一応六万時にヒゲダンスの導きの先にあったお話。らくがきは出す予定はないですがこっちだけ。ヒゲダンスの導きって辺りがなんとも永遠海らしいことで。
とりあえず形式抜きの合意婚がしっくり来るのでこんなイメージ。『Patriots』は踏んでるというか、あの設定で別次元みたいなそんな感じ。
後は、帝国では婚約は左、婚姻は右の薬指に嵌めるという風習で書いてますので、間違ったわけじゃないです。一応念のため。ドイツがこの風習です。リベールは名前ドイツ風ですが国風はイギリスと感じるので風習も違うでしょう。てか(離す言葉はいきなり通じてるけどw)違う国なんだからいろいろ細かいこと違ってて当たり前じゃんー。なんだかよく解らないことをされて一瞬戸惑うユリアさんを書きたかったならそうと言え。全てをおいて自分の下にいて欲しいから、と感じたのであえて風習分けてみましたです。