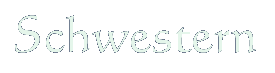
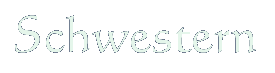
灯カリヲ トモセ
誰かが夜の街中で叫んでいた。先ほどから外で何かを言っていたのは知っているが、ようやく書類仕事が一段落したからこそ入ってきた意味。
「灯かり?」
歩哨に立つリベール兵に聞けば、オーブメントが使えなかったときのことを忘れないようにと、街の大半の導力を落とす日なのだとか。ああ、そういえばそうだったとミュラーは納得した。
「両大使館と王城は任意ですので、そのままですけれどね」
礼を言って二階に上がる。そのまま窓から街を見ると、いつもは明るい外が頼りない灯かりで照らされていた。この街が導力以外に照らされているのを見るのは初めてだ。しばらく上から眺めていたものの、自分もその灯かりに照らされてみたくなった。もう一度門番のところへ戻ると。
「お勤め、お疲れ様です!」
と、敬礼をしてくるではないか。
「何のことだ?」
全然事態が理解できないが、続けられた言葉のせいで眉間に皺が寄ったのを感じた。
「オリビエ殿が先ほど出ていかれました。そろそろ門限になるというのに耳を貸していただけず……。お連れ戻しにいかれるのですよね?」
「……善処する」
「はっ!」
生返事に敬礼する気配を後ろに感じながら通りに出た。導力以外の、例えば炎で照らされる街並みを知らないわけではない。自分が幼い頃、帝都はまだランプが主流だった。野戦訓練に参加すれば携帯用のランプで火をつけることもある。決して見慣れていないわけなのに、場所が違うと新鮮に映るものだと頷きながら歩いた。
誰かが変わった試薬を放り込んだのか、赤や黄色以外の炎を発しているランプがある。何気なく近寄ると、見た顔がそこにあった。小さい体で一生懸命手伝いをしているのはティータだ。
「あっ、こんばんはミュラーさん! よい夜ですね!」
「ああ、こんばんは。君がこの色を作っているのか?」
他のランプよりも大きめのそれは様々に色変わりをし辺りを染め上げる。
「いいえ、おじいちゃんです。実はおじいちゃんの発案なんです、この「導力のない日」は。言い出した人間なら何かしないと、って」
「……そうか。あの博士が……」
彼なら導力のない時代を生き抜いて、導力をこの世にもたらした人間だ。そんな人間の発案ならば上層も飲むだろう。
「じゃ、ミュラーさん、わたし次のランプを見にいかないといけないんで、失礼します!」
ぺこりとお辞儀をして去っていく。確かに他にも幾つか同じような灯かりがあった。感心だなと後姿を見送る。ややあってから、周りに人が増え始めた。
ただ導力を落とすだけではなく、こういう風に変化をつければ人の噂になる。実際、この巧妙な色変わりを目当てに観光客も増えていると聞いた。帝国からも多く観光に来ているがその分トラブルも増え、事後処理等がまわってくる大使館員にとっては頭が痛い話らしいが。
「……」
不思議な光景。ゆれる炎に合わせて人の影もゆれる。手に灯かりを携えているものもいて、歩く度に炎が消えそうになればまた盛る。基本は白で作られている建物が千差万別の色に分けられて佇む。常にこれでは日常も過ごしにくいだろうが、たまにはいいと思っているのが住人の気配から解った。
なんとなく大通りを目指しながら、時にランプの灯かりで満たされている酒場を覗き込み、オリビエを探しながら、それ以外の何の目的もなく。
「以前に皇城も導力が落ちたことがあったが、あの時のイメージと今のこの街のイメージはまた違う。本当に不思議なのは、受け取り、感じる人の心か」
あの時には生死の境を彷徨った女がいた。今は何も悩むことがない。まあ、欲を言えばオリビエが見つかればいいし、隣を歩く人がいればいいと思うが、その望みは女神も叶えられないだろう。自重気味に笑ってまた歩き出すと、ミュラーの視界から隠れるように動くものがある。
「オリビエか!」
建物の影に回りこんだそこにいたのは、少なくともオリビエではなかった。が、ここにいるのが意外で、次にそうかも知れないと思う人物、クローゼだ。
「見つかってしまいました……今日ならきっと誰もわからないと思ったのですが」
「……姫殿下」
「あ、その呼び方は今はちょっと……」
手を合わせて頼むクローゼに苦笑し、わかったとばかりに頷く。明らかにほっとした表情。
「向こうからミュラーさんがくるのが見えて、見つかったらあまりよくないかなと思って隠れたのですが……」
「隠れないほうが宜しかったかと。あれでは不審に見えてしまう。そのまま堂々とされていれば、自分はきっと気がつかなかった」
「そうなのですか。では今後に備えます」
この答えにどう反応していいかわからず黙っていると、クローゼが座りましょうと手招きをした。少し影になっているところで、ランプの明かりもなかなか届かない。花壇の端に腰掛ける姿をよく見ると、普通の街娘の格好で、不穏な動きをしていなければ、この暗さもあってきっと見過ごしていただろう。
「何故また? 王城は……そろそろ門限では?」
「エステルさんと約束をしていまして。「次の導力のない日は一緒に回ろう」って……」
まだ待ち合わせ時間には少し早く、けれどちょうど人の目を掻い潜れたのでそっと出てきた。これからエステルとあちこちを見て回る事が楽しくて仕方がないのか、心底から微笑みつつミュラーに説明をした。
「……護衛の立場としては褒められることではないですが……」
「そうですよね。解ってます、軽率だって」
「だが、自分も貴女ぐらいの年齢の頃は、似たようなものだった。それを知っているから、今夜自分は何も見なかったことにしましょう」
「すいません、ありがとうございます」
軽く頭を下げるクローゼ。
「今ごろ城では大騒ぎでしょうね。特に今夜は用事はないのですが……帰ったらユリアさんやヒルダさんに叱られるのは覚悟しています」
「ユリア殿なら貴女を探しに出てきていそうだ」
「確かに」
不安な表情で、人が溢れる薄明かりの中を駆けるのだろう。自分がオリビエを探すのと同じように。
「……ところでオリビエを見かけませんでしたか?」
「オリビエさんですか? 教会前の広場のほうで、ダンスコンテストの伴奏をしていらっしゃいました」
「……感謝します」
幾度かグランセルに訪れるうちに、妙にオリビエの名前が通るようになってしまった。毎度の奇行や所構わずの演奏会のせいだが、それを見込まれてコンテストの伴奏を頼まれたと、自慢そうに語ったらしい。
「まだまだコンテストは終りそうになかったです」
「……頼まれてやっていることを途中で連れ出すわけにもいかない……」
大きく溜息をついて肩を落とすとクローゼが背中を軽く叩く。それがまたミュラーを情けない気分にさせるのだが、それを口に出しては言える筈もなく。
「でもミュラーさんにあえて、ちょうど良かった。お伺いしてもいいですか?」
少し硬くなった口調に顔を上げる。
「何なりと」
「……どう、されるおつもりなのですか?」
「……それは」
それまでの和やかな笑顔は消え、人を見ることを知っている瞳がきらりと揺らめいた、そんな気がする。
「あの人は……私のお姉さんです。幸せに暮らして欲しい人です。そして、ミュラーさんはそれを満たしてくれそうだと思いました」
「恐れ入ります」
「けれど、私はまだ聞いていません。どう、されますか?」
「……」
そのうちに聞かれるのではないかとは思っていたが、こんなに早くに言われるとは思っていなかった。しばらく口を開いては閉じるを繰り返す。本物の姉以上に慕う相手のことだ。気になるのも当然で、もしミュラーが同じ立場であればクローゼと同じように問うのは目に見えている。
「申し訳ありません。今の自分では、それを断言することはできません」
ようやく音になったのはそんな情けない言葉。
「……」
「いまだ帝国は揺らぎつづけている。その揺らぎの渦中にオリビエと、自分はいます。今それを貴女にお伝えしてしまうと、嘘をついてしまうことになるかもしれない」
今すぐにでも王城から連れ去ってしまいたいのは確かだ。しかしそれは、自分の仕事に誇りを持つユリアを壊してしまいかねない。なにより、揺らぎつづける自分ではふさわしくない。
「ですから、宿題ということにしていただけないでしょうか。お約束します。何があろうと、生きてその宿題を片付けると」
「……私に約束するのは違いますね」
「ああ……では、貴女の姉上殿に誓いましょう」
力強く言い切り、視線を外さないクローゼに真っ向から立ち向かう。ミュラーにとってはどんな魔獣に立ち向かうよりも人間に立ち向かうほうが恐ろしい。ましてや、全てを見透かしてしまいそうな次期女王だ。ただそこにいるだけなのに、自分と十以上も年が違うのに気圧されそうになる。
「はい、ではそうしましょう。でもなるべく早くに宿題は済ませてくださいね。でないと、ユリアさんはずっとずっと待っていそうですから」
「それが一番自分にとって痛い言葉です」
ぷっと吹き出したクローゼに、仕方がないと頭を掻くミュラー。
「あ」
何かに気が付いたようにクローゼが立ち上がった。
「ミュラーさん。私のことは今晩は見なかったことにしてくださるんですよね? なら、私の追手も止めておいてくれますか?」
「そういうことになりますが……」
「ではお願いします。それではまた」
言い置いてクローゼはその場から駆け出していった。何のことかよくわからないまま座っていると目の前に誰かを探す人間が来た。
「……」
「……こちらに居られたと思ったのだが……」
肩で息をしながら周囲を見回すのはユリア。なるほど、と内心クローゼに感謝をしながら声をかけたら、相当に驚いたのか目を丸くしている。
「そんなに驚かれても困るが……探し人か?」
「……ええ」
「俺もだ」
わざと大仰に手を上げて見せるとユリアの表情が和らいだ。
「俺はともかく、貴女が探し人というのも珍しい」
「せめていらっしゃるところだけでもわかればいいのですが……」
「……一緒に探しに回るか?」
「あ……」
幸か不幸か今日は普段ほど明るくない。一緒にいてもきっと解らないから。それを理由にもう一度問い掛けてみる。
「……その辺はやはりオリビエ殿に影響されているのでしょうか? それとも、もともとそういう風に強引なのでしょうか?」
「知るためにもっと一緒にいないか?」
「……ふふ。王都を一回りする程度でしか時間はないですが」
「十分だ」
立ち上がって手を差し出す。軽く重ねられた手を握り、込み合う街の中へ、いつもと違う王都の灯かりの中へ。ゆっくり、ゆっくりと消えていった。
Ende.
単に私がランプの炎が好きでして。この宿題はいつ片付くんでしょうか。インスピレーションの源は「音速パンチ」(Cocco)。「明かりをともせ」の一文でできました。