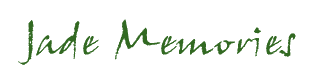
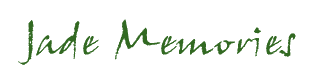
「囲まれたか」
もう少しで城内へ駆け込める。門が大きく開いて、その奥から配下の兵や傭兵たちが飛び出してこようとしていた。追っ手を牽制しながら男坂を駆け上がってきたが、これまでとばかりにミュラーは足を止めた。
「諦めるのかい!? もうすぐそこだ!」
驚いたオリビエが立ち止まった親友を引っ張る。だが男の瞳はオリビエを見ずに周りを鋭く見据えるばかり。少しの間を置いて得物をそれぞれ抱えた集団があたりに現れ始める。
「諦めてなどいない」
部下たちに指示をしながらオリビエにも視線を投げかける。
「最期のそのときまで手を伸ばすつもりだ」
一瞬だけニヤリと笑って、猟兵たちの中へ突入していった。
見るからに重い大剣を自在に振り回し血路を開く。剣先で切り裂き、剣の重みで払い飛ばし、柄で得物を弾き飛ばす。軽快なステップを踏みながら返り血を浴びる男がいる。だがそれも限界が近いことは、腹心の部下やオリビエには見抜かれているだろう。そう思いながらミュラーは両手で剣を握り締める。
普段であれば片手で扱う剣。が、夜討ち朝駆けが繰り返され、連日の果てしない戦いで磨耗されていく体には、ほんの少しばかり彼の愛剣は重かった。気が付かず、むしろ気が付くまいと今日まで来たが、頭はともかく体はもう悲鳴をあげつつある。
「どうした剛剣使い。ほら、後もう少しだぞ」
猟兵を束ねる長らしき人間が笑う。オリビエの傍に影のように付き従うミュラーの存在は、半端な腕では太刀打ちできない相手として猟兵たちの間で囁かれていた。オリビエとは別枠で高額の懸賞金がかけられているらしく、オリビエを守りながら自分自身の身を守る生活。
「貴様に心配されるいわれはない!」
長の持つ短刀のすばやさに何とかついていく。しかし次の一手を繰り出すまでにかかる時間に違いがあった。幾度となく短刀から身を守ってくれる大剣に感謝をしながらも、力の配分が思うように行かず地面に刺さるまで振り下ろされてしまうのにいらだつ。
刺さり、動かない剣を蹴り上げ続けた軍靴の先は、保護用の金属板がほぼ取れかけてしまうほど。金属板の下まで刃が到達したか、踏み立てるごとに鈍い痛みを放つ。
「少佐殿! 後ろ!」
「!」
長だけを相手にできれば今のミュラーでも勝利を得てオリビエを守り通すのも容易だ。けれど猟兵たちは集団の闘い方を知っている。時代がかった騎士風の名乗りなどない。部下の声に背後から振り下ろされた鉄棒を必死で避けてまた長と相対。そんな調子でどんどんとオリビエから離されてしまう。戦いの合間に様子をうかがうとなんとかやっている。彼の部下たちも精一杯庇いながら城へと近づいていっていた。
「余所見しているひまなどあるか?」
「ないな。失礼した」
「オレたちはあんたの賞金だけでももらえると向こう十年は働かなくても生きてけるんだ。そりゃアッチの皇子さんだとプラス15年ってところだがね」
「毎日勤勉に働く方が、生活に張りが出るぞ!」
「どうだろうな……ほらまた地面に喰らわせてるぞ」
「くっ」
完全に猟兵たちのペースに巻き込まれてしまった。足元が不確かになるほど汗で視界は悪くなり、後ろから呼びかけてくる声が部下のものかオリビエのものか猟兵のものか判断できない。
「こんな時に言うべきでは、ないのだろうが、いい腕しているな、貴様」
「確かに、こんな時にんな暢気なこと、言ってるばあいじゃないな。でも褒められたら嬉しいぜ」
双方共に肩で息をしながら軽口をたたきあう。命の取り合いをしているのに奇妙な感じがする。もちろん他の猟兵たちはミュラーに容赦なく襲い掛かってくるし、長も隙あらば致命傷を狙ってくる。
「ミュラー!」
一際大きいオリビエの声に一瞬気をとられる。視界に入っていた猟兵が数人その場でうめき始めた。攻撃の手を休めずにオリビエの方を向くと銃に弾丸を込めなおしている最中。その背後にはもう扉。
「さっさと中に入れ! 名乗りまでのリミットはもうないだろう!」
「そんなものは済ませた! 扉を閉めるから、早く!」
その声を聞き心底から笑う。これで一つの試練は終った。皇子として名乗りをあげ、この国に関与していくことを宣言した。これからも自分はそれを支えつづけなければならない。
「ちっ……プラス15年はムリか」
長がパチンと指をならす。すると、ミュラーでさえ気取れなかった猟兵たちが次々に姿を見せた。ミュラーとオリビエの間にも割込み、それまでの混戦に拍車をかける形になった。
「向こう十年。よろしくな」
ニヤリと長も笑った。
報告を聞いたのは全てが終った後だった。平静を保てたのは訓練の賜物だろうか。そんなときぐらい取り乱してもいいのにと思うが、部下たちの前ではいつものとおり冷静な顔。
「……それは壮絶な闘いだったのだろうな」
「猟兵一個中隊を相手に……ですか。それは……」
傍らの部下がうめく。ユリアは報告書を机の上に置いておくように言い、また手元にあった自分の書類と向き合う。そうしなければ自分が壊れる。上に立つ者としての自分を要求されている時に、感情を剥き出しにしたただの女としての自分を晒してしまう。
「どうした。この山も確認したぞ。もっていくのだろう?」
報告の内容に呆然となっていた部下に処理済の書類を持っていくよう促した声は、発した本人ですら何の感情も読み取ることができなかった。
おそらく、あまりに唐突過ぎて理解できていない。ミュラーはもういないのだと。あの生真面目な顔は見られないし、少し強引な提案や、その割に紳士的な行動を見ることももうない。
ようやく書類から開放されてその事実に向き合わなければならなくなったのは明け方に近い深夜。視界に入れないように、できるだけ自分から離しておいていたその報告書を手に取る。
「……貴方も私も軍人。こういうこともあるだろうと、覚悟していたつもり」
同じ軍でも部隊が違えば最期の瞬間傍にいられるとは限らない。ましてや違う国の士官同士。リベル=アークでのように、共に闘うことを願っても叶わない。
「ここでは涙も出ない」
執務室では自分は士官。リベールの軍人。そして上官。ここでは自分の為はおろか、部下の為にも涙を流すことは許されなかった。
報告書を何度眺めてもかかれていることは同じ。一個中隊規模の猟兵に襲われ、部下たちを庇い、城に向かおうとしていたオリビエを護衛し、自分は剣を構えたまま絶命。ミュラーの最期を淡々と告げていた。薄らと空か明るくなる頃には文章を暗記してしまう程見直した。
どこかで大門が開いたことを知らせる鐘がなった。報告書を握り締めたままユリアは部屋を出る。不寝番以外まだ誰も起きていない時間の城内は静かで、そして自分の居場所ではない錯覚を起こす。
「……」
門番に何か言われた気がするが覚えていない。朝もやが薄らと掛かる周遊道へ。王都の大門は開いたが、隣接地方への関所は開いておらず、離宮方面へ向かうしかなかった。かといって離宮に行きたいわけではない。凍りついた感情を抱えて歩き、気が付けば翠輝石の広場。もやの中に薄い翠を見つけ手を置くと鉱物の冷たさを感じた。
「あ……」
そういえば、ずいぶんと昔にここで抱きしめてくれた。途端にそのときの表情や声、存在のありようが思い出されてくる。石碑にもたれかかるようにしゃがみこみ、その思い出を必死になって抑えようとしても、一度流れ始めた感情だけはどうにもならない。呼吸すらままならずに目の奥が熱くなる。しかし、熱くなるばかりで涙は一向に流れない。
「こんなところにいたのだね、ユリア君……」
「!」
がさりと植え込みの音を立てて現れたのはオリビエ。正式に、正統後継者の一人として名乗りをあげることを決意し、帝国にきちんとした形で介入していこうと決めた男。その名乗りの為の儀式に出るには、特定の日、特定の時間に皇城にいなければならない。そこに向かう途中の襲撃だった。
「ああ……すまない。ボクも眠れずに城から出てきたクチなのだよ」
一睡もしていないということが見ただけでわかる。決して簡単にリベールにいてはいけない人間なのに。
「護衛たちにムリを言ってここまで来た。ボクはね、伝言を頼まれたよ。……酷なことをするよ、彼も……」
ボクにとっても、ユリア君にとってもね。音にならない言葉がユリアに届いた。視線を合わせることができず、目の奥の痛みと戦ってはオリビエの言葉を待つ。
「……『手を伸ばしつづける』ってさ。……はっきりと、伝言と言われたわけじゃないけれど、あれは彼からキミへの伝言だったと思えてならないんだ……」
声が震えている。ああ、この人もまた認められないのだと、ぼんやりと女は思った。
「手を……」
なんとなく伸ばしてみる。何も変わらない。もっともっと伸ばしてみる。やはり何も。一体何を自分に伝えたいのだろう。せっかくの伝言でも、自分には理解ができない。それが悔しくて悔しくて、それでもオリビエの前で涙を流すことはできなかった。
「……じゃあ、ボクはこれで」
ユリアに背を向け、一歩進んだところで立ち止まる。
「ねぇユリア君。ボクからお願いがあるんだ」
「何……でしょうか?」
いつもと変わらない声にする気力がなく、感情などない事務的すぎる声になったのがわかった。
「……ボクの代わりに……彼のために、たくさん、たくさん泣いてくれるかい?」
「……」
「それだけ。じゃ、今度こそ」
結局一度も視線をかわすことなくオリビエはどこかへ行った。ユリアはオリビエの言葉を幾度か反芻し、ふと思った。オリビエは泣いてはいけないのだ。
「友のために涙を流すことは……今のあの方には、許されないのだ……」
ユリアと会うだけの、ごく私的な時間でさえもう涙を流すことはできないのだろう。寂しさに浸って涙を流すには他にやることが多すぎる。そんな涙をミュラーは許さないことを知っている。親友でありながら親友ではない、主人と侍従という冷徹な関係を嫌というほど理解もしている。
「冷徹と噂が立つかもしれない……だが、それすらも利用してしまえる方なのかもしれない……」
付き合いはそれなりになるが、ユリアはオリビエという人間はいまだはっきりと掴めていない。ただそれぐらいのことをやってのけるだろうと思っていたので、意外なことだとは感じなかった。
「……ミュラー殿。貴方は、ご自分で思う以上にいろいろな影響を与えていたのですよ……」
口に出してみた。目の奥がまた痛くなる。ずっと握り締めていた報告書に雫が一つ、二つ。後はもう何もわからないまま、後から後から涙が湧き出してきた。
結局その日は全く仕事にならなかった。というよりも城にそれから戻ることもせず、石碑の影でぼんやりと過ごした。報告書だったものは皺だらけになり、文字も所々にじんで読みにくくなってしまった。けれど、もう一度書けといわれれば書けるなと、現状を冷静に見詰めている部分があることに驚いたのを覚えている。
報告があってから数日後の月夜。
「……お慕い、申し上げて、おります……」
あの白い月夜に意を決して伝えた言葉をもう一度。まだ自分はミュラーのことを思っているのだ。どちらかがいなくなる可能性を認めながら、それを否定したくて。結局、護衛であり軍人であるということに落ち着いてしまう。いつものユリアならどんなに大切な人間であれど、それで無理矢理にでも納得をした。
「……その最期のとき。貴方の視界には、私も、いましたか?」
護衛であること、戦死の可能性が常に付きまとい、それも受け入れなければならない職業であるということ。そんなことよりも、ユリア自身のことを考えてくれただろうか。自分でも驚くほど、納得ができない。けれど、クローゼやフィリップ、ユリアとミュラーのことを知る人間が皆、ユリアをみて寂しそうな目をする。
それは嘘だと言ってもらいたくて、オリビエが帰国する際にユリアも同行させてもらった。しかし淡い期待はすぐに雲散、淡々と刻まれた墓碑銘と、その横に立てかけられたミュラーの剣が全てを語っていた。そこでまたユリアは涙腺が壊れたように泣き叫ぶ。他の墓参りの人間が何事かと驚くほどに。
「か、必ず……迎え……っ……来るって……!」
嗚咽に混じる言葉は途切れ途切れで、何を言っているのかユリアにもわからない。ただ、果たされなかった約束を死人に向かって責めるのは良くないと思っていた。
しばしの時間を置いてオリビエが声をかけた。
「……ユリア君?」
「あ……申し訳ありません……」
墓に目を落としながら立ち上がる。
「少しは落ち着いたような、全然落ち着いていないような……よくわからないですが、もう涙はでません」
自虐的な笑みを浮かべてオリビエに向き直る。
「よかった。すこしは、光が戻った……かな?」
「それほどまでに?」
「うん」
自身の悲しい瞳を癒せないオリビエは、わざとらしいほど軽く返事をする。
「ミュラーも果報者だね。こんなに思ってくれる人がいたんだ、幸せだったに違いないさ」
「……」
いくらオリビエがそう言ってくれても、ミュラー本人の言葉ではない以上本当はわからない。それに今はまだその言葉はユリアに届きそうもない。だからあいまいな笑みを浮かべるだけにしておいた。
「……そろそろ帰国いたします。もういい加減に……仕事に戻らなくては」
「そう、だね」
「帰れば、きっと、山のような仕事。でも、今の私には、それが一番癒しなのかもしれません」
ざわざわと潅木が風に揺られる。
「手を、伸ばしつづけようよ、ユリア君。彼もきっと、こちらに伸ばしているはずだから」
「ええ、そのつもり、です」
たどたどしく答えながら目を閉じた。知っている人間は限られるだろうと思える優しい笑み。微笑みながら自分に手を伸ばしている。いつか掴めるときがくるだろう。
「私も、伸ばします。また貴方を思い出して泣き叫ぶのは見えていますが、それでも」
声をかけて欲しい。抱きしめて欲しい。口付けて欲しい。それ以上も欲しい。そうやって泣く日も必ずある。すぐに壊れてしまう気もしている。けれど夢の中でしか生きられないようにはしないでくれと願った。
「なりそうだったら、怒ってください」
小さく呟いた言葉にオリビエが怪訝そうに首を傾げる。なんでもないと微笑み、しばらくはまた自問自答をくりかえすのだろうなと心の中で続けるのだった。
Ende.
いわゆる死にネタ、とゆーヤツです。ユリアさんも少佐も死亡確率は通常の人間より跳ね上がるし、その状況を互いは嫌というほどわかっている。その時かたっぽいなくなったら……で、少佐がいない場合はこんな感じ? なんかまとまりきってない気もしますが、この後ユリアさんがゆっくり壊れていくのかもしれないし、最期まで夢見の人にはならずにいるのかもしれない。
逆パターンは『Ever Blue』。