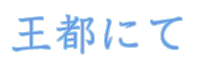
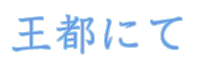
黙々と夕暮れの王都を歩く影を追う。長く伸びたそれを見失うこともないだろう。それに、行き先は一つしかないのだ。朱に染まった王城へ。
「ユリアさん、アカンて! きっとまだ封印解けてへんから!」
ミュラーの後ろからケビンが走ってきた。
「大丈夫か?」
「大丈夫やけど、少佐さんなんで止めてくれへんねん! あの人足速いわ……」
息を切らしてミュラーを恨めしそうに見る。
「そう言われても」
「ケビン、無茶は言わないの」
更に遅れてリースが追いつく。こちらも肩で息をしていた。
「こんなことになったら、きっと誰も止められないと思うから」
「そりゃそうかもしれへんけど……あーもう、見えんようになる!」
まずいとばかりにケビンとリースは街路樹の向こうに消えたユリアを追う。一呼吸置いてミュラーも追った。
「行き先に関してはそう心配することもない。一つしかなかろう」
「私もそう思う。けど、一人っていうのは心配。……じゃない?」
リースに追いついて呟くとそう返された。問いかけに答えず足を進めるスピードを上げた。返事がなかったことに多少拍子抜けしたが、リースもすぐに走りじめた。先をいくケビン、そしてユリアが視界に戻る。
「少佐さん、走ってや。そしたら追いつくやろ? オレらは軍人の歩き方にはついていかれへん。なんで歩いてるだけであんなに早いん……」
「そう訓練されるからな。大尉が歩いているのは大尉なりに自分たちのことを気にかけているからだろう。でなければとっくの昔に置いていかれている」
「冷静に分析してる場合ちゃうで。何や見えてる」
「む」
確かに半透明の何かがユリアの歩いた後を辿るように現れている。体が自然と戦闘態勢に入り、どういう動線を描いて落としていくかシミュレーションを開始すれば。後ろからすぐ脇を高密度の水流が疾っていく。だがそれより先にユリアが振り返り、手にしていた抜き身のままの剣を一閃、ニ閃。そのまま再び王城への道を辿り始めた。ワンテンポ遅れて魔獣が消滅し、散ったセピスを水流が押し流してしまう。
「リース! お前、撃つの一言ぐらい言えや!」
「そんな暇なかった。でも大尉の方が早かった」
「まあ確かに……ってそんな問題ちゃう!」
「活躍できなかったからってひがまないの。少佐はちゃんと黙っている」
「ううっ」
恨めしそうな視線をミュラーに向けてきた。正直に言うとミュラーもケビンの心境とあまり変わらない。ただ、少しだけ、この戦闘気分をどうすればいいかと考える程度で、ケビンほどはっきりと外に感情を出すこともない。集団の中で闘っていれば良くある話である。
「それに、そんなに若くないしな」
ケビンぐらいの頃なら、行き場のない破壊衝動を外に出すこともあったが。黙って剣を収めて、今なお言い合うケビンとリースをおいてユリアの後を追った。
白い石を芸術的なまでに研磨し、そして積み上げられた建造物。グランセルの基本構造は白であるが、この建物は一番白かった。晴れた昼であれば、背後に遠く見える常緑樹の山と見事に対比し、月夜となれば、暗い水面と光に照らされ一層白くなる。それ以外の夜に沈む時は、夜の色に染められ、控えめにそこにあることを主張する。
「ここぞという時に存在感を表してくる国だ。城もそうなるか」
正門前で佇むユリアに追いつき、夕暮れに染まった城を見上げた。何度か夕暮れの王城を見る機会はあったが、今の城は一言でいうと不気味。打ち寄せる水音だけが耳障りに思うほど響いている。
「普段ならこの音など聞こえん。普段聞けたら感慨深いものがあるかも知れんな」
無関係なことをわざと呟きながらユリアの背後に立った。振り向きもせずにただ正門を眺めつづける女。
「……」
「……無慈悲やな……」
ようやく追いついた二人が扉から目をそむけた。
音もなく、知らない言葉や知らない円陣で施されている封印。最初にケビンが触れてみたら、熱は全くない。ただ、押したら押しただけ反発する力があった。幾つか教会に伝わる解呪の法を発動してはみたが完全に徒労だった。
「……」
何かユリアに声をかけようかと思うがやめた。冷静さを欠いているのは見ただけで解る。だが、それを指摘して何になるというのか。頭でわかっていようと本当に理解するまでには時間がかかる。
きびすを返して少し離れたところに立っていた聖職者たちのところに行く。
「ほうっておいてええのん?」
「自分に何ができるというのだ」
「そりゃまあ確かに」
悲しそうなリースと目があう。すぐに外してオレンジ色の湖面を見た。彼女の大きな瞳に映る、どうしようもなく悲しい表情の自分自身を見たくなかった。
どれほど水面を眺めていただろう。先ほどからリースは近くの長椅子に横になっていた。それをやめろとケビンが起き上がらせようと悪戦苦闘。ユリアは変わらず扉の前。時折ミュラーとケビンの視線があう。くだらないやり取りを続けている二人は弛緩しているようで周りを見ており、不測の事態に備えて周囲の気配を探っている。ミュラーも考えられる事態を想定しながら、自分が剣を捧げた相手のことを思う。一体何がどうなっているのか、少しは解けてきたような気もするがほとんどわからない。
「敵の仕掛けたことならば何故我々は石の形でこの世界にいるのだろうか。あの庭園で聞こえた声の主のおかげなのか?」
とにかく情報が少なすぎる。今、どこでどういう状態なのだろうか。おそらく本人は、自分もそうだったように、直前の状態のままであろう。凍り付いていたというか、そういう風に動けない時間が存在したということが理解できないというか。
「少ない情報のままで動くことは破滅につながりかねん。……奴なら大丈夫だろう」
多少の襲撃など一人で乗り越えるだろうから。長く共にいる間にそんな確信が育った。ミュラーも一歩間違えばユリアと同じ状態になりかねないのだが、ならないのはその確信のおかげである。
「……俺たちと同じになれるはずなのに。性格の違いといえばそれまでだろうが」
本当にそれだけなのだろうか? 何かが足りていないのではないか? なんとなくユリアに視線を投げかけた。
「……?」
視界の中でゆっくりと体が動く。剣を構えて封印へ突進していく。
「何を!」
リースも気がつき椅子から飛び降りた。封印の反作用ではじき返されてたたらを踏むユリアに手を伸ばすが、掴んだと思ってもすぐに振り払って改めて突進。その勢いが強ければ強いほどはじかれる勢いも大きい。幾度も地面に叩きつけられては封印に向かっていった。
「ユリアさん、やめて!」
ケビンが必死になって止めようとするがつかめない。ユリアの力に簡単に振り払われてしまっている。
「大尉!」
ミュラーも駆けより腕を掴む。剣を無理矢理奪い取り説得を試みるが聞く耳をもとうとしない。力いっぱい掴む男の腕を振り払って、今度は自分の拳で泣きながら封印を叩き始めた。
「しっかりしろ大尉!」
「なんや変や! ユリアさんの……戦術オーブメントが暴走してる!?」
封印を殴りつけながら起動でもしたのか、アーツ発動時特有の空気のゆがみ。だがこれは通常のアーツどころのゆがみではない。もっと巨大な、兵器が主砲に導力を収束するような。
「馬鹿がっ!」
ユリアに体当たりをかけてオーブメントを奪う。地面に叩きつけるように放し、次いで、いまだ封印に執着を見せるユリアの頬を容赦なく叩いた。小気味良い音が夕暮れの正門前に響く。
「……嘘や……するんや、そんなこと……」
地面に落ちた衝撃でクォーツが外れ、異常な空気のゆがみも薄まっていく。
「何を考えているのだ!」
「しかし!」
馬乗りになったまま、先ほど叩いた頬と逆側の頬を容赦なく叩く。
「もしあのまま暴走させていたら、どうなるかわからないほど呆けたか大隊長! 城ごと壊すような真似を貴様がするのか!」
「!」
自分とオリビエの関係と似て異なる決定的なことを見つけた気がする。
「自分たちに盲信は必要だ! だが、盲信しすぎることは許されんのだ! 信じることに全てを置いて、考えることを放棄するな!」
「……」
クローゼとユリアの関係もきっと自分たちと同じものになる。けれど、いま少し時間が必要だった。昔は自分も、ただ信じてついて回ることが仕えることと勘違いしていた。
「……申し訳ありません、少佐殿」
「……」
小さく謝罪を聞き、謝罪をするのは俺ではないと返事をしてユリアの上から移動する。起き上がったユリアは、顛末を見守るケビンたちに一礼をした。
「申し訳ない……不意に、本当に不意に思考が飛んだ」
「別にオレはええよ」
「私も。むしろ、怪我は?」
優しく待っていた二人の声に心底か悔やんでいるのか、唇をかんで下を向く。ミュラーはその間に先ほど放り投げたオーブメントを拾った。
「……む、壊れてしまったようだ」
「そうなん?」
ミュラーから借りたケビンがリベール紋章が刻印された蓋を開く。確かに発動しようとしない。
「ありゃ。どないしようか」
「……」
頬を抑えながらユリアも様子を見る。
「確かに、壊れているようだな。少しぐらいなら自分でも直せるが……」
裏蓋をこじ開けると幾つか部品が落ちた。
「これでは自分の手には負えない」
「すまない、頭に血が上っていた」
謝るミュラー。
「いえ、自分が悪かったのです。少佐殿は止めてくださった。……神父殿、申し訳ないが」
「わかってるて。一旦戻ろう」
「はい、直せますよ。これくらいならすぐです」
輝ける滝の前で考え事をしていたティータに壊れたユリアのオーブメントを見せる。しばらくまんじりともしない時間が経ったが、すぐにティータからは明るい答えが返ってきた。
「さすが中央工房の秘蔵ッ子……」
「よく知っているな」
「ボクたちの仕事は情報も運ぶんだよっ! いちいち軍人バカの癖に突っ込みいれないで!」
「……」
ジョゼットにやり込められているミュラーをみてリースが微笑んでいる。それを横目に、ケビンは柱の影に立つユリアに向き直った。
「あの、ユリアさん」
「解っている。しばらく頭を冷やすことにしよう。あんなことをしでかした人間をつれて回れるほど、事態は緩やかでもないだろう」
「……すんません。でも解ってくれてありがとうございます。何かあったら必ず知らせますんで」
「……」
目を閉じて頷き、以降はもう何も言わなかった。ケビンもそっとユリアから離れてテーブルに戻る。
「神父殿、大尉は」
「少し休むと」
「……そうか」
賑やかな少女から開放されたミュラーはケビンと柱の影のユリアの様子を見てなんとなく状況がわかった。
「はい、直りました!」
精密作業に使う細いドライバーを片付け、ティータがオーブメントを空にかざす。
「ユリア大尉さん、終りました!」
「あ、ああ」
影から出てきてティータからオーブメントを受け取る。その手が微かに震えていることに気が付いたミュラーはケビンに告げた。
「すまないが、俺も少し休ませてもらって構わないか?」
「……わかりました。ほな嬢ちゃんとティータちゃん、ちょっと付いてきてくれへん?」
「はーい」
「えぇぇ? エセ神父についていくの?」
「エセちゃうって……ホンマに神父やって」
かなわんわと大仰に肩をすくめて見せてから、そっとミュラーに目配せをした。応じて軽く頷くと、ほないってきますわと暢気な声を残して光に消えて行く。次いでティータ、リース、ジョゼットも消えていった。それを見送ったミュラーが振り返ると、ユリアは既に滝の前に立ってる。
「……少しは落ち着いたか? 頬は痛くないか?」
「久しぶり、でした。あそこまで見事なまでに叱られるのも」
「……」
少し赤くなった頬を撫でている。こちらも頭に血が上って容赦なく叩いたが、冷静になると少し力を抜いても良かったかもしれないと思う。
「しばらく考えてみます。少佐殿の仰られたこと。ありがとうございます」
「俺は何もしていない。ただ自分と貴女は似ている、そんな気がして思わず口に出した。あまり気にするほどのことでもない」
いいえ、ありがとうございます。小さく礼をしてミュラーに微笑みかけてくる。その目がすこし濡れているのを見て取り、しばらく一人がいいのかもしれないと気が付いた。
「俺は向こうの書架にいる。何かあれば遠慮なく呼んでくれればいい。手合わせでも何でも、スッキリするのならつきあおう」
「そのお心、お気遣い。もったいないほどです」
背中に言葉を感じながら水辺を後にする。不自然にならない程度のスピードで歩くが、書架までの道のりが果てしなく遠く感じた。螺旋階段を下りて長椅子に座り、ようやく息を吐き出す。
「……なんなんだ俺は」
気の利いたフォローはオリビエの役割で、自分は基本的に突っ立っているだけだ。それしかできない。ユリアに対して何もいえなかったことを反省しながら、もう少しあの生真面目過ぎる軍人が、肩の力が抜けてくれるようにと願う。
「……なあオリビエ。俺はこれで構わんだろう?」
今ここにいない男に問い掛ける。庭園から見える星々は変わらず、闇を蒼く彩りつづけていた。
Ende
非常に私にとって痛かったです、3rd二話。少佐が復活してきて嬉しくないわけではないのですが、それ以上にユリアさんの狼狽振りが。そんなわけで、普段使っている『Patriots』設定じゃなくて、3rdのまんまを自分なりにお話化アレンジしたらこういうことになりました。ケビンやヨシュアの余裕っぷりと対比するあて馬っぽい感じがしてならない。主人公補正には負けます(苦笑)。
少佐はユリアさんをちゃんと叱れる人。対等でありたいと思ってる人。ユリアさんは『Patriots』でも、少佐より一歩後にいる人。自分よりもっと上だと思ってる人。この辺の意識の違いって結構大きいと思う。