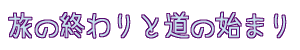
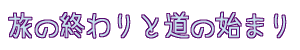
風を感じるのが好きで、どこにいても窓を開けてしまう。一晩中あけていたらしい窓から優しい潮風が入ってきた。その、いつもとは違う香りに薄く目を開ける。辺りはまだほの暗く、だがもう夜が明けきる、そんな時間のようだった。
「……ん」
走り込みを、と寝台から降りるが、いつもと感覚が違う。
「ああ……ルーアンにいるのだったか……」
本来ならエア=レッテンで滝の音を聞きながら眠り、滝の音を聞きながら目覚めるはずだった。予定はどうなるかわからないものだと息を吐く。寝台に座りなおし、すでに活気付いている朝市の声を聞いた。
「……もう少し、横になるか」
滅多に飲まない酒が効いたのか少し体はだるい。そのまま背中から寝台に倒れた。
「ぐっ!」
何か硬いものがある。それは奇妙な音を発した。慌てて振り向くとまだ目覚めきっていない表情のミュラーがいた。
「……あ?」
「いくらなんでも、そういう起こし方は、ないだろう……」
真っ白だ。何が自分の身に起きたのか。全身を探りながら必死で昨夜の記憶を洗い出す。が、思い出せない。花火をみながらワインを飲んでいたのは覚えているが。
「なんだ、忘れてしまったのか。半脱ぎで俺に迫ったのに」
「!!?」
「さすがにあそこまでされたら、据え膳食わぬはなんとやらだ」
「ほほほ、本当ですか……?」
涙目かつ真っ赤になって問い掛ける。すると、
「冗談だ」
と、あっけらかんと答えが返って来た。咄嗟にユリアは寝台のカバーを掴み、一気に持ち上げる。当然笑っていたミュラーは床に転げ落ちた。そのままカバーを頭から被り、寝台の上で丸くなる。
「機嫌を直してくれ。真っ赤になった貴女が面白いので、ついからかいたくなった」
「……ミュラー殿……そのあたり、オリビエ殿に感化されてませんか……?」
半眼でカバーから顔をだしたユリア。まだ赤い。
「ううむ。そうかもしれん……」
床の上で腕組みをしていたが、ふと思い出したように寝台に上がってきた。相変わらず丸くなったままのユリアは緊張で何がなんだかわからない。
「まだゆっくりしたい。傍にいても、構わないか?」
「……」
「ああ、嫌だと言ってもいるつもりだからな」
「……何のための問いですか……」
「一応、礼儀として」
言いながら丸くなっている女の布を取りにかかる。ユリアは抵抗したが、耳元に息を吹きかけられて力が抜けてしまった。その間に覆っていた布は脇へ。
「はい……あきらめました」
「よろしい」
教師のような物言いで男が笑う。ああ、自分はこの笑顔に弱いのだと懐柔されてしまう。体をのばしつつ、まだ緊張しているままで問い掛けた。
「何故、ここに? 部屋はもう一つ取っていたと記憶していますが」
「……俺の我侭、だろうな」
夢の時間は終わる。今日は王都に戻る。もどればまた逢えない。そう思うと、ただ傍に居たくなった。
「……そう、ですか……」
「子守唄は歌えなかったが。横になるとすぐに眠ってしまったからな。唄は今度の機会に」
「いや、そんなに気にされなくとも」
「子守唄を歌う時は……」
仰向けになる。少し口篭もったがそっと囁いた。
「……貴女をもらう時……だといいが」
それを聞いた女は、脇にあったカバーを再度頭から被ってしまった。
うとうとしたようで、次に目を覚ました時はすでに往来の人も多くなっていた。ユリアにしては珍しく寝過ごしたといえよう。逞しい腕が体に巻きついているが、彼女自身の服が緩められた気配は無い。
それがいったいどういう精神力を必要とするのか。だからこそ、次に逢えたなら、と思ってしまう。
「今はまだ、少し怖いから」
あれほど恐れたのに、かなり薄まっている。とはいえまだ固い。起きているのかいないのか、目を閉じて頭をユリアのほうに傾けている男を見やった。
「もう少し。待っててください」
その鼻先に唇を寄せる。どう反応するか見守っていると片目が開いた。
「了解、マム」
冗談めかして応じた様子に、ユリアも知らず微笑んだ。
身支度をしているとあけていた窓からジークが飛び込んできた。脚に通信筒がついている。手にとると、オリビエからだ。
「オリビエ殿?」
内容は簡単なもので、ミュラーがそこにいるかいないかを問うだけだった。だがそこに行くまでに山ほどの修辞を超えなければならない。
「通信文を書くのは、さすがに慣れていらっしゃらないようですね」
肩をすくめながら手早く返事を書く。
「ジーク」
読んでいる隙に飛び出していたようで、しばらく待つと戻ってきた。
「ジーク、殿下のところまでこれを頼む。今日王都に戻ると、つたえてくれるか?」
わかったというように鳴く。その頭を軽くなでてやると擦り寄ってきた。
「いてくれて、ありがとう。感謝している」
「ピューイ」
嬉しそうに鳴いてから、外に飛び出していった。見送り、朝食をとるために部屋をでる。階下では何組かの泊り客がすでに席についている。割り当てられたテーブルにつき、出された水を飲んでいるとミュラーがやってきた。
「……どうされたのですか?」
朝にはなかった傷。
「いや……俺は貴女のナイトには嫌われているようだ」
「え?」
「あのリベル=アークにいるときも、彼にはよくつつかれた」
「まさか、ジークですか?」
眉を寄せ傷に手を伸ばす。たいした事はないと手をあげ、椅子に座った。
「俺が貴女といるのがよっぽど気に食わないらしい。朝、着替えていると突然窓から飛び込んできてこれだ」
と、腕を見せる。そこにはあざがいくつか。
「目だけはつつかれては敵わないからな。なんとか死守したが腕はこの通り」
「すいません……言い聞かせておきます」
「きっと、俺が貴女を連れて行くと思っているのだろう。ジーク君ほどの男に嫉妬されるのも悪くない」
にやりと笑う。
「ジーク君に伝えてくれ。連れて行きたいのは山々だが、今しばらく君にナイトを勤めていてもらうと。いずれ決着はつけるぞ、と」
「ミュラー殿……お戯れは……」
顔を少し赤くしながら溜め息を盛大についた。運ばれてきた朝食が目に入る。
「……食べますか」
「そうだな」
焼かれた卵を口に入れ、少し熱かったので舌を出しながら水を飲む。気を取り直してまた卵に向き合う。カリカリに焼かれたパンをちぎっている時、ふとミュラーがじっと自分を見ていることに気がついた。
「あの……何か」
「……」
なんでもない、というように自分も食事を始めた。よくわからないが、なんでもないことなのだろうと話を変えた。
「今朝方のジークですが、実はオリビエ殿からの手紙を運んでくれました」
「オリビエから?」
目に見えて嫌な顔をする。よっぽどかの御仁には振り回されているのだろうと内心思う。
「ミュラー殿が私と一緒にいるのか、といった内容でして、一応所在は知らせておきましたが……」
「それだけか?」
「いるなら伝言を、と。『ボクが王城の給仕全員に振られる前に帰ってきてくれ。そうしないとブロークンでセンチメンタルなボクは、とてもじゃないけど帝国までの帰路になんかつけやしないんだから』とのことでした」
飲んでいた水をまともに噴出す。慌ててナプキンで拭くその顔は、どうにでもしてくれと言うような。
「オリビエ殿らしいというか……その二点を書くのにものすごい量の修辞がついていまして、一瞬何を読んでいるのかわからなくなりました。通常、ジークが運ぶのは簡便かつ合理的な通信文だけですから」
これです、とポケットに入れてあった紙を出す。受け取ったミュラーはちらりと眺め、溜め息をついた。
「一時期、軍で使う書面に華がないと言って、無理矢理にわけのわからん修辞をつけた文面が飛び交ったことがあった。猛反対したおかげですぐなくなったがな。本人は何もいわんが、多分奴のせいだろう」
「それはまた……災難な……」
申し訳なさそうな顔をしつつも、どうしても笑いがこみ上げてくる。自分に置き換えてみたら笑い事ではないのはわかっているのだが、小刻みに肩が揺れた。ごまかすようにトマトを口に放り込む。
「本当に、思っていたよりよく表情が変わる。この数日は驚かされてばかりだ」
「嫌ですよ、そんなところを見ていたのですか」
「無表情な堅物より俺は好きだぞ」
「……」
わかっていて言っているのだろう。笑いながら放たれた言葉に返事が詰まる。ここは気にしないに限る、とばかりに残っていたスープを口にするのだった。
王都行きのチケットを二枚買い、あたりのベンチに座る。旅の終わりはなにかしら物悲しく、宿をでてから口数が少なくなっていた。それだけ楽しい時間を過ごしたということだ。
今度はいつ逢えるか。下手をすればもう逢えないのではないか。心の底から不安が吹き上がる。
「……今度は、俺が帝国を案内する。貴女のぬくもりを忘れないうちに、来てくれないか?」
「あ……」
ベンチの上に置いていた手の上に男のそれが重ねられた。顔は変わらず、正面の管理ゲートで忙しく働く職員の様子を眺めていた。
ユリアは自分の足元に視線を落とす。
はい、と答えたい。けれども即答できない自分。行ってしまうと、もうリベールに戻って来れない気がしてならない。すべては自分の薄弱な意志のせいだ。
ミュラーの手が答えを待つように握られた。その力強さを感じながら、この人は酷い人だと思った。いとも簡単にユリアの心に居座り、彼女が大切に思う女王やクローゼ、部下やリベールという国自身を脇に追いやってしまった。それらを捨てて、隣で一見不機嫌そうに辺りの様子をみている男とともに在りたい。自分がこんな感情を持つとは思わなかった。
世の人々は多かれ少なかれ、このような感情と闘いながら生きているのだろうな。
目を閉じた。
「そうですね。努力してみます。帝国の良い場所を見てみたい」
「まあ、俺か貴女か、どちらかがそわそわしていたら、俺たちの主がそれを見つけるだろうからな。全く、かなわん。クローディア殿はもちろん、オリビエも」
「そうかもしれませんね。なんだか悔しいですけれど。あの方々の手の上にいるようで」
驚いた、というように目を丸くしてユリアをみた。
「貴女でも、そのようなことを?」
「離宮のような行き過ぎになりかねませんからね」
肩をすくめて応じる。
「確かに……」
「なるべく、自分の意思で帝国へいけるようにします。だから、貴方へ一つ、お願いがあります」
「どんな?」
「今後も剣舞の本は送ります。その都度とはいいません。でも一度ぐらいは返事……くださいね、ミュラー」
満面の笑みと、最後に呼ばれた、尊称のない自分の名。ミュラーは頭を振る。
「ああ、ああ。わかった。努力しよう。貴女も努力してくれているのだから」
「お褒めの言葉、光栄です」
一拍置いて高らかに笑い出す。道行く人は何事かと二人をみるが、その幸せそうな笑顔に何も言わなかった。
「ミュラー、一体全体何事なんだね。この! ボクを! 一人異国に置いておくだなんて!」
「何を言うか。どうせ貴様のことだ、行き先など検討がついただろうが。ジーク君にまで頼みおって」
定期船の中ではほとんど一緒にはいられなかった。偶々非番だった親衛隊士がユリアの姿を見つけたからだ。グランセル空港で軽く会釈をし、話し込むユリアとわかれて王城へもどってきたらこの出迎えだ。
「ジーク君はクローゼ君の案だよ。ボクがあまりにキミ恋しそうにしているのを見かねて」
「それ以上戯言は聞きたくない。帰国は明日だ。少し休ませろ」
「やだ」
邪険に扱うのも関わらずついてくる。望まずして大型犬に懐かれたような気分だ。割り当てられていた自分の部屋に荷物を置くと伸びをする。
「で、どこまでいったんだね」
「は?」
何食わぬ顔で部屋の椅子に座るオリビエ。
「何の話だ」
「その腕。そんなに痣になるくらいなのかい?」
ニヤニヤしているその顔面に、鞘から抜き放った切っ先を突きつける。
「ちょっ! ここで騒ぎ起こしたら大変だよ! ユリア君だってせっかくの休暇を呼び出されるだろう!」
「卑怯な」
舌打ちをしながら剣を元に戻す。
「言っておくがこれはジーク君に突付かれた跡だ。下世話な想像は止めろ」
「えー。そんなの信じられないよー。だって、四日も一緒にいたんじゃないか。その間ほったらかしにされたボクとしては、それくらい聞いたって罪はないんじゃない?」
芝居がかった様子で言葉が流れ出す。
「いつかこうリベールから通信がくるかもしれないね。ユリア君が子を成した、とかさ」
「いいかげんにしろ! そんなことはしてない!」
「本当に?」
「くどい!」
「ほんとにホント?」
「そんなに俺が信用ならないのか!」
真っ赤になって怒鳴る親友をみて、ようやくオリビエも信じるようになったらしい。
「……それは男としてどうかと思うんだが……。はっ! もしかして! ボクのことをやはり愛しているんだねミュラー! そうとなれば」
「貴様の基準で何もかもを考えてくれるな、頼むから」
気は済んだだろう、とばかりに話を遮り部屋からオリビエを追い出す。ようやく一人になり、ベッドメイクされた寝台へ横になる。扉をカリカリと掻く音がするがもうすでにオリビエのことなど頭の彼方へ。代わりに初めて尊称をつけずに自分の名を呼んだ、あの瞬間を思い出す。
「やはり不意打ちは貴女の方が得意だ。最後の最後で俺の完敗だったな」
けれどそういう負けなら悪くない。むしろ歓迎していることに気がつく。
「帝都に戻ったら手紙を書く練習でもするか」
自分からの手紙を受け取ったらどんな顔をするだろうか。そんなことを想像しながら眠りにおちていった。
Ende
……ゑ……一応リベールを観光しよう、うまいもんを食おう篇は終わりですよ(そんな副題だったか)。帝国料理を改善しよう篇は、続くんですか? 続けてイイデスカ?(笑) ボース、ロレントもまだ回ってないし。
人がいるところで寝れない性質ですので、ユリアさんがちょっと……いやかなり羨ましい。