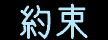
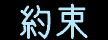
ようやく動力が戻りオーブメント灯がつくようになったが、なんとなくランプに火を入れる。物心ついたときには家にオーブメント灯がついており、ランプを使うのは野戦訓練の時ぐらいしかなかった。
「炎は、不思議だ」
生き物のように揺らめく様を見る。オーブメントにはない力強さと変化がある。
「まぁ、オーブメント灯に慣れていると、この明るさで読書はできないが……」
日中は誰かがそばにいるので落ち着いて本は読めない。だが、心配してきてくれる兵や給仕たちがいることはうれしい。それが帝国の人々であることがもっとうれしさを倍加させる。手元に置いてあった本をサイドボードに返した。
「つつ……まだ無理はできないな」
以前は火傷だが今度は穴が開いたか。軍隊にいるということである程度は覚悟の上だが、なるべくなら大怪我は控えたい。
「考えるより先に体が動くところは、やはり治らないのかもしれない」
部下を持つようになってからはだいぶんましになったのだが、基本的に前線で動きたい人間なのだ。
しばらくランプの明かりを眺めていると部屋の温度が下がってきた。開けていた窓を閉めなければならないが、体を動かすのが億劫だ。しかし、夜露でシーツが湿っても気持ち悪いので意を決して起き上がる。
「やれやれ。本国に戻れるのはいつのことやら」
あまり長居する気がないのは最初から。自分の果たすべき役目はリベールにある。だが今のままでは戻っても何も出来ないこともわかっている。
「とにかく早く治すのが一番だな。…………ん?」
ようやく窓に手が届いて閉めようとしたら、少し離れたところに生えている潅木が揺れている。風の揺れ方ではない。人為的な揺れ方だ。つい先ごろ城内に侵入者があったばかりだ。身を固くする。
「……戦えない」
薄手のローブを着ているだけの自分。護身用の短剣も、傷を負ったとき失っている。剣は近くにあるもののとても振るえる状態ではない。最悪のことを予想した。
しかし、潅木の動きを見守っていると、見慣れた人物がそこから出てきた。あまりに意外で声をかけることも忘れる。その人物はついた葉を落としながらユリアの部屋の窓を見、驚きを隠そうとしない彼女とまともに目が合った。
「……これはまた、みっともないところをみられたものだ」
「……ミュラー殿? 何故?」
「今の時間にならないと、貴女の周りから人が消えないからな。そちらに行っても構わないか?」
「え……あ、はい」
ユリアが窓から離れたのを確認し窓枠に手をかける。軽く息を吐き、身軽に部屋に滑り込んだ。
「まったく、部屋の前にフライハイト侍従長が陣取っているから、まともに部屋も訪ねられん」
「そういえば、何かあるといけないから、すぐ近くにいるとおっしゃっていましたね……」
「道理なんだが、昼あまりに貴女のところに人間がくるものだから、その反動なのか今は全く入れさせないようにしているようだ」
「はぁ……」
フライハイトが給仕や兵を追い払っている姿を想像する。おそらく、その中にミュラーも含まれるのだろう。
「笑い事ではない。話も落ち着いて出来ん」
笑うユリアは、そうですねと返すが、やはり笑う。なんともいえない表情でミュラーはランプを見た。
「気に入ったのか?」
「ええ。野戦訓練のときでもない限り、わが国ではランプを使うようなことはありませんからね。せっかくなので」
「なるほど。帝国では、帝都はともかく、地方に行くとまだランプが主流だ」
ベッドの端に座り、ランプを見る。ふと気が付けば、炎に合わせて自分やユリアの影が躍っているのに気が付く。
「基本、俺も帝都にいることがほとんどだから、ランプの明かりがどのようなものか忘れていた。なかなか面白い」
壁や天井に映った影を見ながら続けた。
「……いつ、俺のことを?」
「さあ。いつでしょうね? 自分でも、よくわかりません」
ユリアの位置からは男の横顔しかわからない。赤い炎に照らされているから良くわからないが、少し赤面しているようだ。
「ただ、貴方の眼が、とても澄んでいるから。……いうなれば、初めて会ったときから、かもしれません」
「……そんなに澄んだ眼などしていない」
「いいえ。不機嫌そうな顔でごまかそうとしてもだめです。見る人は、見るんですよ」
「貴女のように、か?」
答えず笑うユリア。炎が揺れる。
「では、ミュラー殿は?」
「……おそらく、舞」
「え?」
「決定的に気が付いたのは、生死の境をさまよう貴女についている時だがな。その前の日に、言葉に出来ていればと、心底思った」
気の利いた言葉をすぐ返せるほど器用ではないのだ。抱きしめたのは、近づくことで気持ちが伝わらないかと思ったからだった。
「そうだったのですか」
何故自分を抱きしめたのか。答えが聞けて少しほっとした。
「それにしても、何故あの時泣いていた?」
「……言わなければいけませんか?」
「無理に、とは言わないが」
月明かりに照らされた涙目のユリアが思い浮かぶ。思いがけず刺激を受けたのは事実だ。凛々しいユリアしか知らなかったから余計にその涙の理由が気になる。
「……」
どう言おうか思案する。
「今は、筋違いの感情、ということにしておいてください」
「??」
不思議そうな表情をするミュラー。が、それ以上詮索することは止めた。その気になればユリアが話してくれるだろう。
「しかし、よく礼服まで持っていたな」
「あれは、こちらでお借りしたものです。オリビエ殿の招待で、急遽出席することになりましたから。礼服は持ってきてはいません」
「……なるほど」
あの日、オリビエが彼に好みの色を聞きにきたのはこういうことか。オリビエの手に引っかかってしまったのかもしれない。だが、それもいい。きっかけの一つだろう。
「ところで……、この状況、世間一般では、夜這い、といいませんか?」
意地悪な笑みをユリアが浮かべている。この表情も自分が知らないものだな、と思う。
「まあ、そうなるか」
否定してもそれ以外の言葉で今の状態を表すことは出来ないので、おとなしく納得することにした。
「なんと。そんなこともされる方でしたか」
「だから言っただろう。及第だが十分ではない、と」
「確かに」
「侍従長が通してくれればこんな妙なことをすることはなかったのだがな。どうしても話がしたかった」
とりあえず侍従長に責任を押し付けてみる。ユリアも気が付いただろうが何も言わなかった。
他愛のない話をしているとランプの炎が小さくなってきた。油を補充し損ねていたので普段より燃焼時間が短くなってしまったようだ。
「明日は、入れてもらわなければ」
動けたら自分でするのだが、今は歩くのは難しい。
「そうだ、約束をしてくれないか?」
「どのような?」
「……いや、たいしたことではない、と思う」
小さくなりつつある炎を眺めながら口篭もる。なんだろう、と興味深そうにユリアは男をみた。
「……あまり、舞うのは控えてくれないか?」
「……?」
「これ以上、貴女の崇拝者ができると、俺が近づけなくなってしまう」
早朝、朝日を浴びながら舞う姿をミュラーもみていた。傍らの侍従長が話し掛けてくるまで、彼の部下と同じように圧倒されていた。
「それが不思議なのですよね。リベールでも同じように訓練場で良く舞いましたが、それほど注目されたことなどなかったのに」
首をかしげる。
それは、貴女が上官だからだ。
親衛隊の中にもユリアに心酔している人間はいる。口には出さないが、想っている人間もいるだろう。アルセイユに行きがかり上乗った時気が付いた。ただ、上官だけに、何も言わないのだ。
「それは……いや、約束をしてくれるか?」
「どうしましょうか。舞いたい、という気持ちはかなり衝動的ですからね。空中庭園の時など、その最たるものでしたし」
「では、なるべく、で構わん」
「……」
ミュラーを見ながら考える。少し悪戯をしてみたくなった。
「はい。では、なるべく、ということで。でも」
貴方の前では、舞ってもいいですか?
体を伸ばし耳元に囁く。
「……」
この不意打ちに眼を丸くするミュラー。してやったり、という顔のユリア。ランプの炎が、一瞬だけ光量を上げ、ジっと音を立てて消える。一呼吸置いて、答えた。
「歓迎する」
「どうも」
「やはり、十分ではなかったな。俺の知っている貴女のイメージに、悪戯好きも加えておこう」
「では私は、意外に積極的、と」
二人同時に笑った。フライハイトに聞こえるといけないので声は落としているが。
今日は薄雲がかかっており、あまり強い月の光は入ってこない。ようやく眼が慣れてきたら、思っていたよりユリアの顔が近いところにあることに気がついた。体の中でなにかがはじけそうになるが、とりあえず抑える。
「そろそろ、横になった方がいい。すまないな」
「いいえ。楽しかったですよ」
顔を離しゆっくりと横たわる。枕に頭を預けると、薄雲が晴れ、ユリアの顔をてらした。なんともいえない美しさだ。
「また、時間を見つける」
「お待ちしています」
ユリアの頬に手を添えた。あの日と同じように、ユリアも眼を閉じる。今度は邪魔は入らないだろう。そう思ったのだが、戸の方から小さく声が聞こえる。
(……少佐殿、少佐殿。お戯れは程ほどに。シュバルツ様は、まだ安静が必要なのですからね……)
フライハイトだ。彼女は、部屋の中から話し声が聞こえてくることに気が付いていた。ただ、今回の経緯を一応オリビエから聞いている。少々不本意ではあるが、話ぐらいならユリアの気も安らぐだろうと、それまで大目にみていたが、それ以上となると話は違う。
「……やれやれ。この城は落ち着けん」
「そうかもしれませんね。まさかもう、襲撃はないと思いたいですが」
「巡回を厳しくしている。もう、大怪我などさせん」
「ありがとう、ございます」
にこりと笑った。
「せめて、ここにいる間でも、ジーク君の代わりを勤めたいのでな」
「こうやって傍にいていただけるだけで、私は十分です。お慕い申し上げております、ミュラー殿」
「……また不意打ちか。不意打ちが得意、も追加だな。この借りはかならず返すぞ」
「お手柔らかに、お願いしますね」
上目遣いに男を見上げながら呟いた。いまだ頬に添えられている手はごつごつしており、いかにも剣を使う武人の手だと思う。だが、暖かく、大きい。堪能するように眼を閉じた。
「……」
「……あ」
そっと唇が重なる。柔らかな唇。重ねるだけのものだが、ユリアは頭の奥が痺れるような感覚を覚えた。
そして、初めて口付けを交わした時よりは長く重ねる。
「ゆっくりと、眠れ。お休みユリア」
「はい、お休みなさい」
就寝の挨拶を交わし、ミュラーは名残惜しそうにユリアから離れた。そっと戸に近づくと音もなくひらく。戸の外側には渋面のフライハイト。そっと戸を閉めじろりとミュラーを見る。
「……少佐殿」
「……」
「少佐殿もシュバルツ様も大人ですから。何をしようとそれは別に関係ありませんけれどね。大人だからこそ、シュバルツ様の容態を気遣うべきでは?」
「いや、わかっているが」
「いいえ、わかっていらっしゃりません。それにしてもどこからお入りに?バルコニーへの扉は鍵を掛けたままのはずですし、まだシュバルツ様は満足に歩けないはず」
「…………窓から」
「!!」
侍従長はその答えにあきれ果てた。
「窓! 帝国軍少佐ともあろう方が、よりにもよって窓! まったく……。殿下の悪い影響を受けましたね」
「侍従長が通してくれればそんなところからはいることはなかったのだが……」
「言い訳は聞きません! なんですか。このような夜遅くに、安静が必要な程の大怪我で臥せっている御婦人の部屋に、はいそうですかと殿方を部屋に入れる人間がどこにいますか!」
「いや、先ほどと言っていることが違うぞ。何をしようと関係ないのでは?」
「それとこれとは話が違います! 時と場合をお考えください。もう……少佐殿はもっとそういうことをおわかりになられていると思っていたのに……情けないやらあきれ果てるやら……」
これはすぐには終わりそうにない。覚悟を決めなければ。そっと溜め息をつく。
その後ミュラーは一時間ほどフライハイトの小言を聞く羽目になった。外でフライハイトに叱られている声を聞きながら、ユリアは幸せのうちに眠りに落ちるのだった。
Ende
フライハイトさんにこっぴどく怒られるミュラーさんを書きたくてできた一品。つか、叱られる少佐にハマッた奴がここにいる。ずーっと城の中を取り仕切ってる年上の女性には、オリビエもミュラーさんも敵わないんですね(笑)。つーか、夜這いなんぞせんでください少佐。ユリアさんも受け入れんでください。気持ちよくバカップル化してきたな……。
フランス製ランプの中にミュラーランプってのがありまして、硝子粉をシェードに使ってるとか何とか。名前見たとき吹きました(笑)。