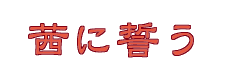
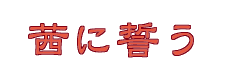
鐘の音が聞こえる。吹く風がいつのまにか冷たくなった。うっかりすると道端でスープを振舞っている露店に誘われてしまう季節。人恋しくなるのもこの季節で、寄り添いあう恋人たちや夫婦の様子を見てユリアはそっと視線を外した。
「決して寂しくなど」
女王やクローゼの前では「ない」と言い切る。言い切ることができる。言い切らなければならない。自分の瑣末な感情で君主たちを煩わせることはならない。だが今は一人だった。口に出しては言ったものの断じることは出来なかった。
おりしも年の変わる直前で、新しい年を迎える為忙しく立ち働いている。今忙しく働いて、年末から新年にかけてをゆっくりと過ごすのだろうと眺める。彼女自身も、旅行に使えそうなちょっとした小間物を売る店の前で、たまには長期休暇を取ってみるのもいいかもしれないとふと思った。休暇を取って、帝国行きの便に乗って。ミュラーも忙しいだろうからほとんど顔など合わせられることはないだろうが、それでもより近くにありたい。そこまで考えて、やはり自分は寂しいのだと痛感した。
「……陛下や殿下がいるから大丈夫……であったはずなのに。この感じは、やはり寂しさなのだろう」
手に取っていた小さな瓶を棚に返して歩き始める。本来は買い物目的ではない。
聞こえていた鐘の音が大きくなった。あの角を曲がって少しいけば目的地だ。冷たい風に押されながら少し早足気味に歩く。他に数名似たように同じ目的地へと向かう人間が散見できた。
熱心な七耀教徒ぐらいにしか浸透していないが、新年を迎える十日ほど前には七耀教で重要な聖人の為の祝祭日がある。当然ユリアはこの祝祭日を知っており、よほどのことが無い限り祈りに参加をしていた。教父に聞けば、聖地アルテリアでは敬虔でありながらも一年のうちでもっとも賑やかな祝祭となるそうだ。一度はそれを見てみたいと思いながら古い石段を登った。
古く重厚な扉を押し開ければ百や二百ではきかない蝋燭が堂内を照らすのが目に入る。その火のおかげなのか外よりも大分暖かい。ありがたいと思いながら見渡せば数人がもうベンチに座っており思い思いの時間を過ごしていた。邪魔にならないよう足音を立てずに歩き、あいているベンチの端に座る。ちょうど近くに蝋燭があり、ゆらゆらと揺らめく炎をなんとなく眺めた。
『信仰というものはどういうものなのだ?』
かつて恋人が発した疑問が不意に浮かび上がってきた。ミュラーは神は特に信じていないという。元々帝国、特に帝都は多種多様な人種民族が集まっていることもあり、どこか特定の宗教が強いという場所ではない。それは大陸最大といわれる七耀教でも同条件であった。幾度か教主が秘密裏に帝国の国教扱いにするよう圧力をかけたというが、歴代皇帝はこれを受け入れずに信仰は個人の赴くままとしてある。本音を言えば、異国の宗教を信仰するが帝国のそこかしこで幅を利かせている商人たちの不興を買いたくないということであった。それに何より、皇帝自身が民のよりどころとならなければいけないのに、他に心のよりどころとなるものができてしまうと分裂しかねない。もちろん七耀教会の力は侮れないのでないがしろにするわけではないが、その一点だけは決して譲れないものだそうだ。
『多少は七耀教の勉強をしたが……どこの宗教でも国でも同じだ。大きくなる為にはその背後に血の道を作り屍の山を積み上げている。その教義ほど彼らは綺麗ではないぞ』
あまりといえばあまりな言葉をミュラーは淡々と音にした。一瞬息を飲んだユリアは一回深呼吸をする時間を置いてゆっくり口を開く。
『もちろんそれは知っています。多少はそういう部分を見る羽目になったこともあります』
『だったら何故?』
『ただ……自分自身を赦してもらいたい為。これは私だけに当てはまる理由なので、他の敬虔で立派な方には当てはめないでくださいね』
『……』
微妙な表情をするミュラーに笑いかけた。
『そういった血生臭い側面。教会側は必死で隠しておきたくて仕方がないようですが、少し調べるといろいろ出てきますよね。今でも自分たちに都合の悪いものは速やかに処刑しているとか……まことしやかに囁かれるときがあります。そして、自分の経験上それは八割は確実なことだと思っています』
一旦言葉を切ってミュラーの目を覗いた。一体次は何を言うのだろうと好奇心に満ちた瞳を自分に向けてきている。心の奥が波立つのを感じながら続けた。
『けれど……そういったことは、個々人の信仰に関係あることなのでしょうか』
『そういわれれば確かにそうだな』
『私の場合は、ただ心の安息を得たい為に信仰をしています。あまり純粋に神を信じているかと突っ込まれると少し怪しいこともありますがね』
冗談めかして締めくくれば、だいたいは納得したと言うようにミュラーが頷いていた。
過去の会話を思い出しているうちに礼拝の儀式は始まっていた。目を閉じ、深く低く堂内に響く教区長の声に神経を集中する。目を閉じても闇に落ちることはなく、辺りを照らす炎が瞼を伝わってほんのり暗い程度にしていた。それがもう少し強くなってきたので目を開けると、ちょうど横に作られている飾り窓から夕方の光が差し込んできていた。経典の一幕を意匠化した飾り窓で、淡い茜色の光と手を広げている女神がよく合う気がする。暖かさの象徴である茜色の光と、全てを包み込もうとする女神。この上も無く安心できる光景にまた目を閉じた。
「……あの方にも、この暖かさ、届けたい」
往来で感じた人恋しさだけはどうにもならないのか、せっかく凪いだ心もミュラーのことを思い出すとまた落ち着かなくなった。けれど、この暖かさ、自分が感じている幸福さを分かち合いたい。どうしてもそんな考えが離れない。
「教会は、苦手なのかもしれないけれど」
あの会話の様子を思い出すに、どうもそれほど近寄りたい場所ではなさそうだ。それならば無理をしてつれてくるわけにも行くまいと小さく笑った。
気配が変わったのはその瞬間。先ほどまで暖かかった空気は急速に冷えて灯かりも無くなった。目を開いて警戒をしていると、蝋燭の炎が一つ一つ消えていく。最後の一つが消え去った後も警戒を怠らずに辺りを見回す。闇に目が慣れてきた頃気が付いたのは、見知らぬ窓がそこにあることだった。
「……?」
どこかの屋内。雰囲気自体は先ほどまで自分がいた大聖堂とまったく変わらない。
「ここも……教会か?」
大聖堂なら祭壇のある方へ目をやると見たような装飾を施された台がある。近寄るとやはり七耀教の祭壇。どうしたのかと慌てて後ろを振り向くと、見知らぬ人間が一人二人、祈りを捧げていた。
肌寒さを感じ脱いでいた上着を着込む。祈りの邪魔にならぬようそっと歩いて外に出る。きっとこれは何かの間違いだ。ここを開けばいつもと同じ光景だ。目の前にはグランセルの街並みがあるはず。そう信じたのだが。
その希望は目の前に積もった雪でまず砕かれた。次いで知らない街並みの為にばらけ、見覚えの無い人種で散っていく。
「どこ……なのだ?」
上着の袷を強く引き多少でも冷気が体に届かないようにする。けれど雪の冷たさに応じた服ではないので時間の問題だ。背中にゾクリと冷気が昇ってきたような気がした。
空を見上げると降ってくる雪の奥は浅い夜。先ほどまで自分がいたはずのグランセルでは夕方が始まったばかりだった。往来の人間は不審者を見るようにユリアをちらりと眺め歩み去っていく。明らかに場違いなことは自分も自覚してはいるが行動できるまでには今しばらくかかった。
近くに服屋があったのでとりあえず厚手の上着を買った。その際、ユリアの持つお金が通用しないということで一悶着あったが、万が一の為に持ち歩いていた装飾用クォーツを幾つか渡すことで落ち着いた。オーブメントに使うことは出来ないが装飾としては一級品のもので、万が一お金が通用しないところへ突然出かけることになっても問題がないようにと所持していたものだ。店の主人は喜んでそれを受け取り、家族の為に指輪にでもすると笑っていた。なにがなんだかよくわからないもののその笑顔を見ていると少し落ち着く。
「それに買い物をしたおかげでここがどこだかわかった。わからないのは何故ここに来てしまったのかということだが……」
店の主人にそれとなく聞いてみれば帝国領の最北端。訛りが酷すぎて聞き取りにくかったがおそらくそういうことを言っていたように思う。上着に袖を通し雪の降り続く往来に出て周りを観察すれば確かに帝国風の建物を見かける。
「鉄道駅もこの場所からは遠いという。さてどうやって帰ったものか」
空港などないので陸路を行くしかない。どこかで地図を調達しようかと思って歩き始めた。しばらくいくと正面から集団が歩いてきている。周りの様子からするにそれなりの身分の人間のようだ。他の人間が避けているのでユリアも避けた。なんとなく一行を見ているとどこかで見たような横顔。その横顔がふとこちらを向き、向こうもユリアと同じように驚いている。急に止まった人間に驚いた一行。うち一人がユリアを見ている男を突付くと、男は呆然としたままユリアを指差した。
「……」
「な、に?」
突付いた男も呆然。ユリアはなんとか金縛りから抜け出してぎこちないながら笑いかけた。
「お、お久しぶりです、オリビエ殿に少佐殿」
「やっぱり……ユリア君なんだ……視界の端に何かどこかで見たような顔があったから、失礼だとは思ったけど見てしまったよ……」
オリビエも多少表情は硬いが挨拶を返す。
「どうしてこの街へ? ここはリベールとは何ら交流を持っていない街なのだけれど……」
「話せば長くなる……のかどうなのか。正直な話は、自分でも良くわかりません。とりあえず帰る方法を模索している途中です」
「そうなのかい?」
怪訝そうにしているオリビエ。長い話なのかすぐに終わる話なのか。判断ができない。
「まあいいや。ミュラー、ユリア君がこの街から無事立つことができるまで見送ってくるといいよ」
隣に立つ男にさらりとそんなことを言う。言われた本人もユリアも目を丸くして顔を見合わせ、そしてすぐ視線を外して真っ赤になる。
「ボクはこのまま街の視察を続ける。護衛は大丈夫だ、皆とても誠実で頼りになる」
周りに控えている屈強な男たちを示す。
「しかし」
ミュラーが何かを言い募ろうとしたところ、オリビエがミュラーの襟首をつかんで無理矢理耳打ち。一言二言呟いてそのままユリアが来た方へ歩いていってしまった。何も言わず護衛たちも続く。しばらくしてまた活気が戻り、いまだ立ちすくんでいるミュラーとユリアを気にする人間はいなくなった。
「……ええと……」
「その格好ではこの街は辛い。これを使うといい」
話を導切り出そうかと迷っていたところにミュラーが被っていた帽子を差し出してきた。断ろうとするより先に頭に被せられる。暖かさもそうだがそれより男の匂いが残っていることがユリアを落ち着かなくさせた。
「さて、何時の乗り合い馬車で駅に向かうつもりだ? もうそろそろ最終便が出るとは思うが……」
「あー……馬車、ですか」
「ここに来るには馬車が一番楽だ。……どうした、頓狂な顔をして」
「……」
赤くなったユリアの顔を覗き込んでくる。優しい笑みの形になった瞳と間近で出会い血が上る。
「と、とりあえず歩きませんか?」
「それもそうだ。皆の邪魔になる」
そういうと当たり前のようにユリアの手を取って歩き始めた。
街灯に入れられた火が赤々と燃えており、それに競うような形で各店の明かりも揺らめいている。降って来る雪がそれらの灯かりに照らされて暖かい火の色に染まっていた。不意にユリアはグランセル大聖堂で見た窓からの灯かりを思い出す。
「……信じていただけないと思うのですが、私はつい先ほどまでグランセルにいました。聖堂で礼拝に参加をしていました」
「……」
何を言い出すのだろうというようにミュラーはユリアを見た。だが何も言わず、代わりに繋いだ手を強く握る。
「不思議な気分でした。女神に祈りを捧げ、これ以上ないほどに心が安らいでいるのはわかるのに、その舌の根も乾かない時間で貴方のことを思い落ち着かなくなる……恥ずかしい話ですがそんな状態でした」
「それは……その状態だからこそ、ではないか?」
「え?」
意外な言葉にミュラーを見る。
「普段の貴女ならそんなことで心を惑わすことはない。それは確かだ。だが普段は、女王陛下や王太女殿下、そして部下や国のことを考えて決して凪いでいるとはいえない状態。……そうだろう?」
手が離されたかと思うとそのまま腰に回ってきた。突然の動きに驚くが足取りは変わらないしミュラーは淡々と言葉を紡いでいる。
「色恋の話で心が乱れるということはそれだけ貴女の心が平穏だということだ。……俺もそうだからな」
「……それは、そうなのかもしれませんね……」
恋人も同じということを知りなんとなく嬉しくなった。腰に回された手も、外で恥ずかしいのは恥ずかしいが今日はまあいいかと肩に頭を預ける。
「話を元に戻しますね。とにかくそういう状態で、心を落ち着けようと目を閉じていました。大聖堂の中は蝋燭が灯っていて暖かく、外の光も茜色でとても暖かかった。けれども急に暗くなり寒くなり……気が付いたらこの街の聖堂にいました」
丸い広場に出た。通行や商売に邪魔な雪があちこちに寄せられている。人自身はそれほど居らず目抜き通りらしき場所なのに静かだなと思う。
「そういうわけでどうやってきたのかさっぱりわからない。また、出国審査をきちんとしていないから戻れるかどうかも定かではない。どうしたものだかと頭を悩ませていたところにオリビエ殿やミュラー殿が通りかかられたのです」
「そうか」
乗り合い馬車の待合所へ向かおうとしていたミュラーが足を止めた。そして方向を変えて歩き始める。
「あの、どちらへ?」
「帰れるかどうかわからないのなら今しばらくここにいても問題はあるまい。珍しい飾り付けをしたところがあるから行ってみよう」
こういうときのミュラーには逆らえない。逆らう気も無いというのが正直な話かも、とユリアは心の中で呟いた。
広場から少し離れたところでは灯かりがたくさん灯され、その中央の常緑樹には様々な飾り付けがなされていた。確かに樹に飾り付けをするのは珍しい。
「なかなかないと思って、次の手紙にはここのことを書こうと思っていた」
「……では、手紙に書くことがなくなってしまいますね」
何気なく呟いた言葉にミュラーの体が固まった気がする。そちらを見れば、しまったとありありと表情に描いていた。その様子が面白く肩を震わせて笑う。灯かりと、雪と、灯かりで溶けた雪と、様々な色の飾りがいっせいにきらめいた。暖かい茜がユリアの視界一杯に広がる。これもあの時と似た感じだなと思っていると不意に足が地に付いているという感覚がなくなった。驚いて恋人の方を見ると腰を抱く手の形のままでユリアを見つめている。
「それは……一体……」
「よく、わかりません。けれどなんとなく逢瀬の時間の終わりな、そんな気がします」
「おい、ユリア!」
自分の体の端が揺らめいているのがわかる。奇妙な気分だった。何もかもわかっていて、何もこれ以上望むことなどないほどの凪ぎ。
「また会いましょう。今度はグランセルか……帝都か……どこでもいい、会いたいと思ったときに」
ミュラーが手を伸ばすがユリアの腕を通り抜けていった。
「一つだけ聞かせてくれ。これは、貴女がどうにかなったとか、そういうことではないな……?」
男の瞳の奥に言い知れぬ恐怖と悲しみが満たされている。
「そんなことはありません。ただ私が、貴方に会いたいと思っただけ。不思議ですね。人を思う気持ちというのはこんなこともできるのか……」
「わかった。だが俺をこんなに驚かせたことについては、いずれ仕返しをさせてもらうからな」
まだ動揺は収まっていないようだがその言葉は紛れもなく普段のミュラー。
「はい。茜色の光と共に、お待ちしています」
男の頬に手を添え唇を寄せる。感触を感じることはもうなくなっていたのだが、あわせた唇の熱だけは伝わってきた。
肩を揺らされて頭を上げると見慣れたグランセルの大聖堂。蝋燭の明かりが灯っていて暖かい。
「お疲れのようですね、シュバルツ様。礼拝の途中で居眠りをされる方は数多くいるのですが、まさか貴女もその中の一人に数えることになるとは」
「教区長様!」
「そろそろこの中も冷えてきます。ほら、日ももう落ちかかっている」
言われ窓を見ると茜色はずいぶんともう暗くなっているようだった。
「すいません……」
「いえいえ、いつものことですから。今日は堂内が暖かいせいか、他にもまだまだ仕事が残っていますよ」
穏やかに笑う教区長。辞しながら辺りを見ると確かに居眠りをしている人間が多い。
「来年はきちんと礼拝に参加します……」
「いえいえ、ここに来てくださっただけでも私たちは嬉しいものです。どうぞ、そのお心を忘れずに」
きた時と同様に大きな扉を開き、今度は外に出る。冷たい風がユリアの体に吹き付けるが、先ほどの夢で見たほどは寒くない。あの寒さを思うとグランセルの寒さなどたいしたものではないような、そんな気がした。
帰ろうと石段を降りていると子どもたちの集団が家に帰ろうとして走ってきた。子どもたちのはしゃぎ様をみて、何故そんなにはしゃぐようなことがあるのだろうと考え、そして思い出した。
「女神の贈り物の日だ……」
グランセルの子どもたちの間で囁かれる伝説。新年を控えた寒い寒い冬の日、その年に良い子であれば女神が贈り物をしてくれるという、ありきたりな伝説。誰かが贈り物をもらったといって、その直後に嘘がばれて大騒ぎするようなその程度の。いつしかそんな伝説に一喜一憂していた子どもの心を忘れて大人になったのだ。
「どうやら、まだその伝説は生きているのだな」
はしゃぎながら家路につく子どもたちを見送り笑った。そして、先ほどの臨場感のありすぎる夢を思い出す。
「場所が場所だけに、そして内容も考えると、もしかしたらあれは女神の贈り物……?」
教会の飾り柱に彫り付けられている女神像を見上げる。時間的に最後の茜の光に照らし出されているが、それを見ていても誰も答えるはずはない。
「まさか、ね」
けれどもしそうなら最大級の感謝を。心で呟きながらせわしなく動く目抜き通りに戻っていった。
ENDE.
季節っぽいネタ。女神様は神様という超常の存在である為、人ごときではその真意を測ることは出来ないのですw 思いは人の体という束縛を抜け出し魂だけ望む場所に飛ぶ。好きな人が夢に出てくるのは、それは自分に会いに来てくれているのだという話も聞いたような聞かないような(逆パターンも)。