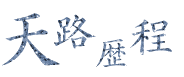
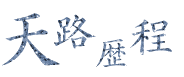
「最後のワガママ。つきおうてくれてありがとうな」
「別に構わないわ」
ちらちらと舞い降りてくる雪の欠片。緩やかな傾斜の坂道。古い門扉を押せば蝶番が悲鳴をあげた。
「……こんなとこまで再現されるんか……」
「それだけケビンさんのイメージに、鮮烈に残ってるってことじゃない?」
「ああ……そうやろな姐さん」
敷地内へ。正面には教会。左手には少し大きめの建物。かつて紫苑の家と言われた場所。
影の王は星層に居ないことは確かで、もうこの幻影には何らの意味も無い。だから、ケビンがもう一度ここに来たいといったとき、辺りの一同は目を丸くした。最初は一人で行くと言い張ったものの、何があるか分からないというクローゼの意見が通った。
とは言え、最後の出発を控えて仲間たちは慌しい。どうしたものかと考えていたところにシェラザードが同行を申し出た。それなら、とオリビエも一緒に行くことになり、護衛兼見張りのミュラーもついて行きたそうにはしたが、結局こないことになった。
『打ち合わせとか何とか言ってるけどね、実は別の理由があってだね』
ケビンに嬉々として話し掛けてきたオリビエの後ろから、こちらに視線を向けていないにもかかわらず異常な殺気が漂ってきたという瑣末な話もある。別の理由も聞いてみたかったがあまり突付くとどうにも修羅場になりそうだったのでお茶を濁しておく。なんとなく察しはつくが、いずれオリビエから聞いてみようと思いつつ、方石を掲げた。
「ほなちょっと行てくるわ」
ケビンは何をするでもなく敷地内を歩いた。時折何か考え込んでいるがシェラザードには知る由がなかった。
考え、歩き、建物を見上げ、また考える。同行者がいることをすっかり忘れてしまったかのような振る舞い。だが、女には何をしているかなんとなく判った。
「決別、ね」
不意に懐かしい記憶の扉を開かされたが為、予期しない望郷の念に駆られた。そういうときに限って強くなる。そして簡単に障りとなる。しばらく好きなようにさせるのがいいだろうと、黙って建物の中に入った。
外と違い暖かさに包まれる。その差に体が一瞬ついていかず、僅かに震えた。すぐに平静を取り戻して部屋を見回した。薪をくべるものもないのに燃え盛る暖炉。誰も必要としていないのに赤々と点るランプ。誰もいないのに誰かのために点く灯りたちに寒気がした。
誰もいない? 本当にいないのか。何かヒトには計り知れない存在がいるのではないか。
「!」
暖炉の炎の形が変わる。ランプから異常な量の光が溢れる。光の波はそのままシェラザードに巻きついた。
「熱っ……くない?」
炎は炎。天井まで焦がす勢いで燃え盛る。その柱のありようも炎そのもの。けれど熱くない。
「姐さん!」
「シェラ君!」
シェラザードの叫びに外にいた男たちも部屋に飛び込んできた。炎は彼らも巻き込みつつんだ。
「熱い熱い熱い……あれ?」
「熱ぅない……」
一瞬はその勢いに押され、そしてその明らかに炎としか思えない色の変容に錯覚をするが、巻き付かれても微塵も過剰すぎる熱は感じなかった。しかし消せない。振り払おうとしては、消えたところからまたすぐに次の炎が巻きついてきた。
「なんやこれ」
「あたしに聞かないで。あのランプがいきなり大きくなっただけ」
指差した方にはもうランプの形をしたものはない。差しながら見たシェラザードはそっと肩をすくめた。
「少しあったかいね。全く熱がないわけでもないのか」
「こいつは……」
ケビンは奥歯を噛み締めた。視線が集まる。だが愕然と炎を見るばかりで何もそれ以上は言わない。
「どうしたの?」
促され、ノロノロと視線を上げる。
「姐さん……ウチの教義。知っとる?」
「興味ない」
「……皇子さんは?」
「ボクも覚束ない。あまり教会には縁がなくてね」
「そうなんや。まあ、ええんやけどね。あんまりこう教会に興味あれへんってことハッキリ聞くとちょっと切のうなったりもするわ……」
少しだけ切なそうに溜息をついて、いまや部屋全てを飲み込んだ炎を見据えた。
「多分火の再生を模してるんやと思う」
ケビンの言葉にオリビエが苦笑いを浮かべた。
「もしかしてだね、物語とかでよくある定番に「炎で燃やして全部浄化して、そこからまた始めよう」というのがあるのだけれどね。これと何か関係あったりするのかい? 知識不足で見当違いならそれはそれでいいのだけど」
「ああ皇子さん、ほぼビンゴや……」
「……」
「……」
厳密に言えばもっと宗教的な意味をもっているのだが大体似た思考なのだという。
「なんてこった。このままだと三人まとめて真っ黒焦げになっちゃうね」
「そんな暢気なこと言っている場合じゃないでしょう。ケビンさん、どうにかならない?」
言われるまでもなくケビンもこの状態をどうすればいいのか探っている。だが、彼の数奇な経験をもってしてもこんな事態は初めてだった。
「……姉さん……なに思って……もうここにはおれへんのやろ?」
遠く、どこともしれぬ場所に行ってしまったルフィナに問うがもちろん答えはない。千差万別に形を変える炎はまぶしく、あまり目を開けつづけてもいられなかった。目を閉じるとほんのりと暖かい炎が安らかな眠りに引き込んでいくのだった。
幾ばくかの時が過ぎ、オリビエはふと目を閉じ安らぎを得ていたことに気がついた。
「もしかしてこれは酷くよくないことじゃないか?」
ケビンもシェラザードも目を閉じたまま、表情は穏やかだ。
「いや、いいことなのだろうけれども」
炎に体を持ち上げられ、僅かにゆれる振動が心地よい。遠い昔過ごした胎内のような揺らぎは、考え込むことをしなくていいと、もう一度元に戻れと言う。
「シェラ君! ケビン殿!」
その幸福な呼び声を振り払い、必死に声をかけ続けた。眠っているのか起きているのか判断できない状態から、次第に意識がはっきりとしてきているのがわかる。
「起きてくれ! この状態を回避しなければ、ボクたちは帰れない!」
シェラザードが視界の端で跳ね起きた。
「オリビエ! あんた予備のチャージ持ってない!? さっきから風で吹き飛ばせないかやってみてるんだけど、大きいの一発撃ちこんでやらないといけないみたいだわ!」
「わかった! これを!」
何とか隠しから引っ張り出してシェラザードに投げる。ありがと、と微笑みシェラザードはエネルギーの切れ掛かったオーブメントを再起動した。オリビエも現在可能な、もっとも大きな風を起こそうと操作を開始した。複雑な手順を踏み、一つ一つの部品にエネルギーを行き渡らせる。もう少し調整おけば起動も早くなただろうにと内心舌打ち。だが今はそれどころではない。
「神父さん! 早く起きないとまとめて吹き飛ばすわよ!」
「カゲキだね……」
「あんたもシャキンとしなさい!」
怒られて一瞬だけ舌をだし、その合間にようやくオーブメントが待機状態に入った。
「いっけえぇ!」
なんの合図もない。後ろにいるシェラザードを振り返ることもしなかった。けれどほぼ同時に放たれた大風は互いの勢いを高めあい、部屋の中一杯に広がる炎を駆逐するように膨れ上がる。嵐の一瞬が通り過ぎて、体中に切り傷を作ったオリビエとシェラザードがいた。
「なんとか……体からは離れたみたいね」
肩で息をしながらシェラザードが自分の体を一瞥。炎に巻きつかれていた部分にはまだ暖かさが残るがやけどはない。
「神父さんは? ほんとに吹き飛ばしちゃったかしら」
「まさか。それはきっとないんじゃない?」
目立つ傷に適当に薬を塗りこみつつ警戒。
「姐さんも皇子さんも、その言い方は酷いんちゃう?」
テーブルの上でまた大きくなろうとしている炎の向こう側。多少よたつきはしていたがケビンが自分の足で立っていた。
「これでも鍛えられとるで。一気に畳み掛けよか」
「諒解!」
「具体的な作戦は?」
「ない!」
やる気が一気にそがれた。オリビエは盛大にすべり、シェラザードは呆れて溜息。
「この手のは取り込まれたらアカン。これが火の再生を模しとるもんやったら必ず「元に還れ」って思考を受けるはずなんや。原罪を負っていなかった頃へ還れと」
「ちょっとそれは還りすぎね。その途中に戻らないといけない場所があるから、それは却下!」
「ボクも同じく」
「その調子でよろしく頼むわ。もうちょっとヨワなったらオレがとばしちゃる」
その背から青白い陣が浮かび上がる。炎の赤と対比したような、目の醒めるような青。ニヤリと歯を見せて笑うその姿は、少し前まで聖痕の力を解放しきることを恐れていた男ではない。
もう一度ぐらいなら大風を放てる。シェラザードがオーブメントを掲げれば、やはり同時にオリビエもオーブメントを掲げた。一瞬だけ目配せをしあい、後は自分の間合いで風を放つ。時間差で広がる空気の流れは部屋の中のものを全て吹き飛ばし、炎は自分の体を千切りとられる。その大きさは最初のランプ程度にまでなっていた。
「二人とも下がっといてや! まとめてぶっ飛ばしたらスマンですまへん気がするわ!」
軽口をたたき、背負った陣からより強い光が放たれる。
「さっきの仕返しってわけね! いいわ、今回は不問にしてあげる!」
「冗談を言えるなら大丈夫さ。ほら、また大きくなる!」
声を聞くまでもなく、風が収まると共にまた大きくなろうとしているのはわかっていた。躊躇うな。心を一点に絞れ。応じて光が矢のように降り注ぎ始めた。
「ま、なんとかなったわね」
庭に出てようやく一息つきながら傷に薬を塗りこむ。オリビエがシェラザードを手伝いたいようにしていたが、その視線に心配以外のものが見えた気がするのでとりあえず却下はしておいた。
「アレはなんだったんだい? わかる?」
オリビエの言葉に女は頭を横に振る。そのままケビンに視線を移す。
「まあアレやろ。ここが教会の孤児院やってことと、オレのせいやろな。「全てに還れ」……か。求めとったんかなぁ」
手近な草を抜いては脇にどける。
「浄化は結構。だけど時と場合を考えて欲しいわね、神父さん。殉教なんかする気もない」
「殉教……って、姐さん知っとるやん」
「興味ないとは言ったけど知らないとは言ってないわ」
七耀教会において炎は浄化であり、共和国のごく一部ではそのための儀式も行われていることをケビンは知っていた。それゆえ、「炎=浄化」の図式は教会に興味がない人間でもそれなりに広まっている。だが「殉教」の意味まできちんと理解している人間となれば数は減る。
「へえ……勉強になったよ。ボクももう少し宗教に目を向けておくべきだね」
「そうやで皇子さん。教会味方にしてるほど強いモンはないわ」
キミが言っていいのかと肩を叩く。ケビンは困っているような、心から楽しんでいるような、ぱっと見ただけでは判別できない。
「せやけどありがとうお二人さん。お二人とも原初に還りたいとか、そんなことは思えへんかったんやな……」
トーンが落ちた声にオリビエとシェラザードは顔を見合わせる。
「じゃ、神父さんは還りたいの?」
「……わからんのや……」
「わからないからこそ今、ボクたちがここにいるのだと思う。ここまで回り道をしたのだ、もう少しケビン殿が落ち着くまで待っても、まず問題ないと思うのだが……どうだろう?」
「そうね。でもまあ正直なところ、ちょっと体痛いから少し休ませてもらいたいのは事実」
腕の傷を見ながらシェラザードが同意をした。
「……ありがとう。ほな、もうちょっとだけ、な」
それだけ言うと教会の建物を見つめたまま何も言わなくなった。シェラザードとオリビエは少しだけそんなケビンから離れる。
何をするでもない、いつもと同じやりとりをしていたが、オリビエが女の過去を問い掛けてきた。傷を診る手を休めて薄暗い空を見上げた。
「……なんでまた」
「いや、なんとなく」
「なんとなくで人の過去なんてもの聞かないでよ」
「なんだったらボクの過去も洗いざらい、全てキミに告白するよ?」
「いらない」
シェラザードの即答にオリビエがわざとらしくうなだれる。
「だって、誰のものであろうとあたしは過去なんてもの、全く興味ないから。もちろん反省の材料にはするけど、その程度でいいの」
「その人が辿ってきた半生を知って、よりその人を知るということもあるけど」
「その人を知るってことは、別に過去なんか聞かなくても知ることができる。よほど喧伝したいなら別だけど、今のその人をみたら、過去からの積み上げで今があるわけなんだから」
「うん、まあそうかもね」
「興味はないけど大切には思ってる。大切に思ってるからこそ、興味なんか持つべきじゃない。ただそれだけよ」
にこりと笑ってまた傷を診はじめた。オリビエはしばらくその様子を見ていたが、やがて誰にも気付かれないように満面の笑みを浮かべる。
「……うん、決めた」
「何さ」
「ん? 後で飲みながらでも」
「飲む? いいわねそれ」
なんだかよくわからないなりに、飲めるということだけで機嫌がよくなるシェラザード。そこに、もう行こうとケビンが声をかけてきた。
「もういいのかい? ボクたちはまだ別に構わないけど」
「ええ、大分スッキリしました。こうやって悩んで悩んで、それにまつわる苦労も仰山して、いつか求める場所に行くもんやしね」
「あ、いまの神父っぽいわね。得心した?」
「ひどいな姐さん。オレ正真正銘神父やってば」
苦笑い。一呼吸遅れて、三人の笑いが孤児院に響いた。
Ende
完全にタイトル先行。というかこのタイトル、『Patriots』と悩んだくらい昔から頭にあります。が、抹香臭くなるのでやめました。宗教ってどうなんだ、の一環でもあります。このタイトル使えるお話できるかなぁと思っていたら3rdにあったという感じ。あの場所は炎の地獄、煉獄に落ちる場所だしまあいいでしょう。女神信仰に神父はいねぇとツッコミたい。