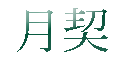
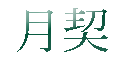
前を行く背で長くなった髪が揺れた。それほど気にかけて手入れはしていないが艶のある、少し波うった黒髪。
「長くなったよね、髪」
「そうだな。切りたいんだがなんとなく伸ばしてみるのもいいかと思って。子どもの時以来だ」
「へぇ、小さい頃は髪長かったんだ。僕と出会ったときにはずいぶん短くてびっくりした。旅人ならわかるんだけどちゃんと家で過ごしてるのに短い年頃の女の子がいるんだ、ってさ」
「……なんだよそれ」
顔にかかる髪を後ろにやりながらレイラがじろりと男をみた。悪びれず掌を振るフォディニーに疲れきった表情を見せる。
「僕が初めてレイラを見たのはアリアハンの劇場で、その後噂色々聞いたんだ。だから驚いた」
「ああそう」
「レイラぁ、そんなつれない声出さないでよ。僕泣いちゃうぞ」
「勝手に泣け。というかお前、ほんとに変わらないな……」
「レイラだって変わってないからおあいこさ」
軽く女は肩を竦めて街道をまた歩み始める。昼下がりだが少し天気が悪く、時間にしては人通りは少なかった。この道の先はルプガナ。
「セニアス、どんなになってるかな?」
「前にあったのは三ヶ月前だっけ。きっとびっくりするくらいおっきくなってるんだろうね」
「今度の投宿は少し長くしないか?」
「賛成」
セニアスは半年ほど前に妊娠がわかり、そのままルプガナに留まっている。ヴィッターは真面目に働いているのだがどうも今までの言動からしてレイラにはからかわれ続けていた。フォディニーは意外に適材適所だな、とオークショニアとなったヴィッターを少しうらやましく思う。目利きは当然できるし口上も上手いという。
自分は何ができるだろう。劇場で出し物? 多分無理だろう。そもそも情報収集がやりやすいからこそああいった世界にいただけで、栄枯盛衰の激しいかの世界に居続ける気はもとよりない。レイラにはそれを言ってはいないが、最近の路銀の貯め方は劇場出演より魔物退治や傭兵家業で賄うようになってきた。
「たぶんそれが、レイラの答えだ」
そんなことを考えていると前を行くレイラが頭を揺らした。当然のようにフォディニーも頭をレイラと同じ方向に傾け、一瞬後に光弾が飛び過ぎて行く。
「大丈夫……そうだね」
「ああ」
声をかける前に抜き打ちで分断された巨大な蜻蛉が落ちる。男は街道掃除の意味もこめて死体に火をつけた。
「最近ぼんやりしすぎてないか? そっちの方こそ大丈夫か?」
「うん、ごめん心配かけて。僕は大丈夫」
死体が燃え尽きたところで水をかける。レイラはいつものように不思議そうにそれを眺めていた。
「もう見慣れたかと思ったんだけど、相変わらず気になる?」
「そりゃな。ああ、でも仕組みがどうたらって説明はいらない」
「ははは、そこは慣れちゃったか」
他愛無い事を話しながら続ける旅をして三年になる。レイラは少しだけ丸くなった。荒い言葉は怒ったとき以外はあまり出なくなり前にセニアスと会った時にはひどく驚かれたものだ。とはいえ通常の女性言葉というわけでもなく聞く人によればぶっきらぼうすぎるらしく、それで幾度か揉め事になりかかったことがあった。都度フォディニーがフォローしている。
フォディニーのほうは傍からはほとんど変わらず。相変わらず目立つ髪は金色に変えているが元の髪自身は一時に比べてかなり短くなった。手慰みの奇術を披露して酒場で小金を稼ぐこともあるが回数は減った。レイラに言わせると「魔法を使えるのに奇術はヘンだ」だそうだ。実は種も仕掛けもあるからこそ人に通用するしその種を芸人志望に売ってみたりもしているがその辺は彼女には言っていない。ただそれよりもやりたいことが一つ出来ていた。
間を強めの風が吹いていく。歩いて少し汗ばんでいた二人には心地よい。
「いい風だ」
「そろそろ風に潮の香りが混じり始めたよ。海が近い」
「やっとたどり着くな。ちょっと強行しすぎたかもしれない」
「僕はまあいいけど、他の人なら付いて来れなかったろうね。レイラ足速いもん」
「そうかな?」
「うん」
そんな二人を潮風が歓迎した。
「おおお、すっげ、こんなになるんだ」
宿の予約もそこそこにヴィッターとセニアスの家へ。残念ながらまだヴィッターは戻っていなかったがセニアスが大きなおなかを抱えつつも歓迎してくれた。
「時々蹴るようになってきたんだよ」
「蹴る? 蹴るって、おなかの子どもが?」
「うん」
心底珍しいという表情でセニアスの話を聞くレイラ。
「人の体って不思議なもんだな。私もセニアスも、こうやって生まれたんだろうね」
「そうよ。ヴィッターもフォンも、他の皆も、お母さんから生まれてくるのでした」
部屋の隅で二人の女の様子を眺めていたフォディニーに軽くウインクするセニアス。その意味がなんなのかは良くわかっていたが、彼は軽く肩を竦めるだけにしておいた。
「そろそろヴィッターも戻ってくると思うんだ。今日はもちろんここで泊まるでしょ?」
「あ、いや一応宿はとってるんだ。ちょっと長く居ようかなって思って」
「そうなんだ! わー、嬉しい。レイラもフォンもいてくれるんだ」
真っ直ぐ微笑むセニアスに、心から幸せなのだなとレイラは感じた。子を宿すというのがどういうことなのかいまだに良く分からない。けれどそれもいいかもしれない。そんなことを感じさせる。
「おっ!? 誰かと思ったらお前らか」
「お帰りヴィッター。久しぶりの来客二人もだから、今日はお料理たくさん作らなきゃ」
「だな。お前は座ってろ。俺がやるよ」
「ちょっとは運動しなきゃ」
台所に立とうとするヴィッターを押しのけてセニアスが料理を始めた。仕方がないなと客人のところへ来る。
「よぉ。お前ら相変わらず旅してるんだろ? なんか変わったことあったか?」
「いや別に大して変わったことはない。ラダトームに少し寄ってみたけど特に変わり映えせず、ってとこだな」
「あ、でもメルキドが街として機能し始めてた。あの街すごいよ」
「そうなのか……」
広い通りを二人で歩く。散々騒いで、けれど泊まる事は遠慮して宿に戻る道。フォンがレイラを港に誘った。単調な波の音がほろ酔いの頭に心地よい。
「気持ちいいな。海の傍ってのも悪くない」
「だね」
「……どうしたんだ?」
軽く視線を送りレイラはきく。ややあって苦笑いを返す男。
「レイラにはわかっちゃうか。ちょっと考え事」
「多分私にも関わる事だろ?」
「……そうあってほしい、ことかな」
「まあ言ってみろ。じゃなきゃわからない」
しばしの沈黙。
「どのぐらい滞在する予定?」
「決めてないよ。後で決めようって事だったろ?」
「僕は……勉強をしようと思うんだ」
「何の?」
「……前にセニアスの様子を看た時から考えてた。医を志そうと思ってる。僕にできることはそんなに多くなくて、腕っ節もないしろくな仕事しか今までしてない。傭兵を続けられないとは前から思ってたんだ」
「……」
「ただ、勉強を始めると一月や二月でどうこうなるものじゃなくなる。それに勉強したい街は、ここからずっと南の街なんだ」
「ルプガナから定期船が出てるベラヌールって街、か」
「え……」
仕方がないな、と腰に手を当ててレイラはフォディニーを覗き込む。
「前に来た時、定期船の案内板で考え込んでただろ? ベラヌール行きの。何でだろうって思ってたけどそういうことか」
「……うん」
「別にいいんじゃないか? 私は……似合うと思う。それでどうせお前の事だから、医者のいない地域に庵を結んで暮らすとか、怪我をする旅人のためにロンダルキア大山脈に住むとか、そんなところじゃないか?」
「驚いた。そこまで当てられるとは」
「何年一緒にいるんだよ」
「……そうだね」
ここで双方共に黙った。何を言えばいいのか悩むのは男でそれをレイラはただ待っている。
「レイラには……無理に付いてこなくてもいいって言おうと思って」
「お前はそれでいいのか?」
間髪いれずに言われた言葉に顔が熱くなる。そんなはずはない。声に出そうとするがこんな時に限って何も出てこないのだ。
「ああもういいよ。分かったから」
困った顔でフォディニーの手を取る。
「修行自身に完全に付き合うのは難しいかもしれないけど、ベラヌールには一緒に行く。もちろんその後も」
「レイラ……」
「私としてはそういうもんだと思ってたんだが、違うのか?」
思わずレイラを抱きしめるフォディニー。強く強く。
「ううん、ううん……ありがとう、ありがとうレイラ」
「なんか照れるじゃないか。たいしたことじゃないよ」
「たいしたことなんだよ、僕には」
いつだって不安だった。だから確かめるのが怖かった。あてどなく旅をして数年、レイラの気の向くまま足を向けるばかりだったからこそ自分の意見を言うのが怖くなっていたのかもしれない。
薄い雲が切れ月の光が強く降りてきた。その強さに思わず見上げる男。
「……そうか。今日は満月なんだ」
「ん? そうみたいだな」
「……」
今なら。小さなつぶやきがレイラの耳に届き怪訝そうに月を見たままの男に目をやる。と、髪色が金色から彼本来の、青銀色に戻った。
「どうしたんだ? いやいつみても月とその髪はすごく合ってて綺麗だと思うけど」
「……」
答えず目を閉じる。少し不満を顔に出した女だがすぐにそんなことを考えていられなくなった。音もなく何も気配もなく自分たちは宙に浮かんでいる。思わずフォディニーに強く抱きついた。
「お、おいフォン、浮いてるよ浮いてる!」
「うん」
「うん、ってそんな……」
「レイラ、大丈夫」
見れば優しく笑っている。不思議とその笑顔と落ち着いた声に心が凪ぐ。
「足場あるから。ほら」
さすがににそれにはまさかと思い恐る恐る下を見ると確かにフォディニーの足はキラキラと光る石の破片のようなものに乗っている。よく見れば爪先立っていた自分の足の下にも同じものがあるではないか。
「えっ? えっ?」
「空気の中には水があるんだ。それを部分的に凍らせて強度の維持時間を延ばしてみた。実は前からこっそり練習してたんだけど失敗ばっかりで、上手く行ってよかった」
「ちょ、ちょっと待て。理屈はどうでもいいんだけどその後半の物言いって……失敗したらどうするつもりだったんだ」
「上手く行くって信じてたんだ。レイラの魔力は君が自分で思ってるより大きいんだよ」
目を白黒している女に少し肩をすくめた。体を離しより一層近くなった月に視線を向ける。
「僕の村にはね、伝説があったんだ。紅宝珠の伝説とは違うもっと身近なもの。「その時が着たら月までいける」って。もう記憶もずいぶん薄れたけど確か、昔の人が月まで歩いていってその向こうにある永遠の楽園にたどり着きずっと幸せに暮らしました、って話。それは伝説じゃなくて本当にあった事じゃないかって、月まで歩いていけないかって方法を模索するようになった。もちろん全然出来なくてねー。よほど大きな魔力が必要なんだってことで落ち着いた。大体なんでもそうだけど時代が下ると魔力でも何でも廃れるもんなんだ。伝承自体に力があることが多くてその伝承が正しく伝えられなくなったら伝承が持ってる力も正しく伝えられないし」
「うん……」
おっかなびっくり、話を聞きながらレイラは足を進める。フォディニーの服をつかんで離せないのに男が歩き始めたのでそうせざるを得ない。けれど少しずつ怖さは持ち前の好奇心に駆逐されていく。一歩進むごとに小さな光が零れ、風に吹き飛ばされてしまいそうなほど小さく涼やかな音を立てるのが気持ちいい。
「それが時代を下るにつれてどんどん意味が変わってきてね」
「うん、それで?」
「……ちょっと話はずれるけど、魔力は共鳴するって知ってる?」
「え? 共鳴?」
「共鳴というか共振というか……重ねがけが出来るのは知ってるよね? 大規模な魔法をかけるときは複数人で掛けるでしょ?」
レイラが頷いたのを確認し、服を握る手を外して自分自身の手のひらで握った。
「つまり二人以上なら月に歩いていける。けど、それはよっぽど気が合った人じゃないと無理だった。だから親友や、家族や、恋人。不思議なほど相乗して普段と考えられない力がでた。それでも魔力と親和性の高い満月じゃないとダメなんだ。もともと僕の村は月の力の落し物っていわれてたしね、あの辺では」
「……」
「いつからか伝承はこう変わったんだ。「満月の夜、月まで歩ける相手は生涯の友であり恋人である」ってね」
「それは」
レイラの言葉に応じず男は握った女の手に口付けを落とす。
「故郷は魔力的にすごく立地が良かった。だからあそこでしか出来ないと思ってた。けど、レイラの魔力はそれを補ってくれた。むしろまだ僕を助けてくれてる」
「そうなのか? 全然そんな自覚はないけど……」
少し頬を染めるレイラ。
「うん、レイラらしい。無自覚に大きな人」
そしてささくれ立った心にまっすぐな瞳で入り込み、そしてすぐに癒して行った。心の中でそう続ける。
「じゃあレイラ、伝承を確かめてみよう。月まで。そのまた向こうの楽園まで。今なら行けるよ」
「……ああ!」
そして手を堅く握り合い、細かな光を降らせながら二人は歩いた。
数日後にニヤニヤしたヴィッターがレイラの頭をつついた。
「なぁレイラ。俺さっきこんな話聞いたんだが」
「なんだよ」
「酔っ払いの戯言っちゃ戯言なんだがな? こないだ夜に港で光が降ってきたって言い出しやがったんだ」
ちょうど酒を一口のみかかったフォディニーのほうがむせ込んだ。レイラも思い当たることがあり目が泳ぎだす。
「おまけにな? 精霊が二人いたってよ。光の階段を上って月まで行っちまったって。片方は良くわからなかったらしいが一人は青い青い髪で思わず何回も見返したってよ。酔いがさめてから思い出したらやっぱり幻だったかもしれないとは言ってたがな」
ニヤニヤ笑いを崩さないまま自分の酒をあおる。
「ってお前ら隠し事下手だな。レイラはともかくフォン、テメェこいつとのんきに旅してる間に牙なくなったんじゃねーか? 俺に脅しかけたあの気迫はどこ行ったよ」
「今そんな必要まったくないからね。お望みとあればいくらでも戻るけど?」
言うなりフォディニーの視線はかつて仇を妄執的に追っていた頃のものに戻る。ヴィッターはニヤニヤ顔のまま冷や汗を流した。そこにまた一人加わる。
「やめてよフォンもヴィッターも。せっかく気持ちよくご飯食べてたのにさぁ」
憤慨した様子でセニアスが腰に手を当てる。ごめんね、とすぐにフォディニーはその視線を引っ込めた。原因の男はまだ固まっているが。
「それにしても決心したわねフォン。ベラヌールって、大山脈挟んでなお南にある島でしょう? 一度は行ってみたいって港に行く度に思ってたけど船旅だけで軽く二月かかるって言うじゃない。そこじゃないといけないの? この街にもお医者様はいるけど」
「うん。いろいろ噂話を集めるとそこが一番なんだって。でもまずはこの街のお医者様に話を聞きに行くよ。だからしばらくこの街に居るからね。あっちに渡れるようになったらもちろん手紙書くし会いにくるから」
「楽しみにしてる」
セニアスとフォディニーが話している間にレイラは二人から見えないようにヴィッターの腹に拳を入れた。
「馬鹿野郎。せっかくあそこまでになったのに。あいつの本質はあっちなんだからな」
「……悪い」
「もう言わないでくれ」
「ああ」
短い間の後にヴィッターがつぶやく。
「でも良かった。お前以外に執着が出来たみたいで。妄執は駄目だが何か執着することは複数あることがいいと俺は思う」
「私もそう思ってる。今までだともし私自身に何かあったとき、フォンがどうするか火を見るより明らかだから。そうやって、世界には他に人がいるってこと思い出してくれたらと思うんだ」
一緒に旅をしながら、いつか自分自身の望みを見つけてほしいと願っていた。幼くして家族、故郷をすべて奪われ仇をとることのみを目標として生き続けてきた男。本人はどう思っているか知らないがレイラの目には時折ひどく歪に映ることがある。
だからこそフォディニー自身からその望みを切り出してくれたことが嬉しい。
「さて私はどうすっかな。フォンが医者になるのはいいし似合ってると思うがこっちはなんもとりえがない」
「壊すことなら得意だけどな」
「……お前なぁ、どういう意味だ?」
「深い意味はない」
悪びれずに言ってのける様は以前と変わらず。レイラが軽く頭を叩いていつも話題は終わり、今日もそうなった。名残惜しいが泊まることはやはりやめて宿へ。
その道すがら。
「レイラはレイラにしか出来ないことあるよ。これからどんどん見つかると思ってる。だからあせらずにね?」
「なんだ、聞いてたのか」
「最後のほうだけ」
不意に何かいいことを思いついた、というように満面の笑顔になった。
「なんだよ」
「うん。僕のお嫁さんになってくれたら問題解決するって思ったん……」
言い終わる前にレイラが足払いをかけた。見事に転んだ男を置いてさっさと行ってしまった。それを見つめていたがやがて立ち上がり、苦笑いをしながら後を追った。
END
傍からみたらまとまってるようで本人たちとしては全然まとまってない二人。たまに書きたくなる。あと、1の世界前のアレフガルド外の国がどんな風になってたのか想像するのが楽しい。にしてもルプガナからベラヌールまで船旅は厳しいだろうな。
「勇者」って称号だから手に職もって生きていくにはつらい存在じゃないかな。だから勇者は職業:盗賊だったり職業:魚屋だったりするんだと思う。魚屋勇者も盗賊勇者も大好きだ。
2010.4.9