

好きだった絵本がある。だから、その結末が大嫌いだった。話が好きだったから、余計にその結末がつらかった。今はもう開かれることはなく、普段は思い出すこともなくなった。
「…クラーラさんが、結婚?」
「そうらしい。村長が酒場で漏らしたとか」
「…」
ヴィオラートが入れてくれたお茶の入ったカップを力なく置くバルトロメウス。
「まぁバルテル、決まったわけじゃないんだ。またいつものように勢いじゃないのか?…あ、ヴィオ、もう一杯お茶をくれるかな」
親友に声をかけながらちゃっかりお茶のお代わりをもらう。
「はーい。…あれ、お兄ちゃん…」
熱いお茶で満ちたティーサーバーを持ってきたヴィオラートは、兄の様子が妙なことに気がつく。
「ああ、ありがとう。…あまり気にしなくていいよ、バルテルのことは。自分で蹴りをつけるだろう」
「そう…ですか」
不安になりながらもカップにお茶を注ぐ。さわやかな香りが立つ。
「うん。お茶を淹れるにも腕がいるけれど、ヴィオは上手だね。それにこの焼き菓子もおいしい」
「誉めてくれてうれしいですけれど、実はこのお菓子はクラーラさんが持ってきてくれたんです。この間一緒にお菓子作って…。そういえばクラーラさん、なんだか意気消沈してたなぁ?」
中空を見ながら考え込む妹を見て、バルトロメウスはふとあることに思い至る。
「…クラーラさん、やっぱり」
「お兄ちゃん?」
さすがに鈍いと言われるヴィオラートでも、数年兄と二人きりで生活をしていれば、クラーラに心底ほれ込んでいるのはよくわかる。
「ねぇロードフリードさん。一体何があったんですか?」
「酒場の噂。…あてにならない、といいたいところだけれど、ね」
「…結婚の話…ですね」
「知っていたのかい?」
「よく依頼とか、流行とかを知りたいから酒場には行ってるんで。そのときに、どこかで聞いた気がします」
そのときには村長のいつもの勢いだと思った。しかし、ついこの間クラーラの表情が沈痛なものであったのが引っかかる。
「お兄ちゃん、聞いてこようか?本人に直接」
「…うん」
妙にしおらしいのが不気味だが、いつも一緒に暮らす兄のために少しでもなにかしてあげたい。こういう問題に関して自分ができることは、これぐらいしかないのだから。
「クラーラさん、いますか?」
「あらヴィオ。どうしたの?」
居間で何かを見ているクラーラが微笑む。その笑顔に、兄でなくても好きになる人間がいてもおかしくないな、とふと思った。
「なに見てるんですか?」
いきなり結婚するんですかと聞くわけにもいかず、内心冷や汗を流しながらクラーラの手元に目をやる。と、男性の姿絵が視界に入った。
「ああこれ?結婚の、相手」
「結婚!?」
「ええ。おじい様が見つけてきてくださったの。最初はどうなることかと思ったんだけれど。ほら、貴女とお菓子を一緒に作ったその日の朝に言われて。一体どんな人が相手なのかって不安でね。でもそのあとすぐこの姿絵が届いて、昨日会ってみたらとても素敵な方だったの」
「…」
「確か、ハーフェンの古い家柄の、貴族だって聞いたわ」
「それで、しちゃうんですか?」
「まだはっきり決めてない。でも、向こうは私のことを気に入ってくださったみたいで」
幸せだというように笑いかけるクラーラに、何もいえなくなった。
「…はぁ」
お兄ちゃんに、なんて言おう。そう思いながら村長の屋敷を辞すと、ロードフリードとブリギットが巨木の前に立っていた。
「ヴィオ、どうだった?」
「うん…」
「まぁ、とりあえず私のうちに来て。こんなところで立ち話も邪魔になるし…」
病気もすっかり治り、健康的な肌色になったブリギットがヴィオラートの肩を押す。その言葉に甘え、二人はお茶をご馳走になることにした。
「最近あまりお菓子はないのだけれど。よければ食べてね」
ハーフェンから送ってもらったという高級菓子を綺麗に並べて出され、思わず手を出すヴィオラート。それを眺めながらロードフリードはお茶を一口もらうが、心の奥でヴィオラートが淹れてくれたほうがおいしいように感じた。
「で、クラーラさんはなんと?」
ひとしきり味わった後でロードフリードが訊ねた。
「うん…ハーフェンの貴族さんと、結婚するかも」
「へぇ。ハーフェンの…。なんて方?知っている方かもしれないわ」
ブリギットに名前を告げると、感心したように息を吐く。
「うん。うちと並ぶくらい名門で、事業も手堅く、でも手広くやってる、やり手の家ね。村長もそんな人間と知り合いだなんて。案外、くわせものかも知れないわ」
髪をいじりながら呟く。
「はぁー。お兄ちゃんになんて言おう」
兄思いのところがあるこの妹は、テーブルの上にあごを乗せて目を閉じた。これをそのまま伝えれば確実に兄は落ち込むだろう。それこそ、何年もクラーラのことを想ってきたのだ。
「でも、言わないわけにはいかないよね…」
「そうね。元気を出してヴィオラート。私も一緒にいてあげるから」
「俺も、バルテルのヤツがショックで暴れだしたら止めないといけないしね」
「二人とも、ありがとう…。仕方ないか。家に帰ろうっと」
戻ってくるのを今か今かと待ち構えていたバルトロメウスは、広場の奥からやってきた三人を見て突然どきりとした。嫌な予感とでもいうのだろうか。店の中に戻り、とりあえずカウンターに座る。
「ただいま…」
ウインドベルが鳴り、ヴィオラートが顔を出した。その表情でわかる。やはりクラーラは結婚をするのだ。
「……」
カウンターに思いっきり頭を打ち付けたが、そんなことも気にならない。
「お兄ちゃん!」
駆け寄る妹だが、どうすることもできないのは感じていた。
「…世の中…報われないことって、多いよな…」
「……」
とりあえずロードフリードがバルトロメウスを部屋に連れて行った。ヴィオラートは参考書を並べてある棚に向かう。
「ヴィオラート、何をするの?」
不思議そうにブリギットが聞く。
「好きだった絵本があるの」
「えっ?」
「何年も王子様が好きだった女の人だけど、その王子様は結局女の人の気持ちに気がつかなくて、ほかの国の王女さまと結婚して。女の人は海に身を投げて泡になってしまった…」
「ああ、私も読んだわ。とっても悲しくて、泣いた」
「私も泣いた。挿絵がすごく綺麗で、大好きな絵本だった。でも、その結末は大嫌いだった。大好きなお話だったからこそ、その結末が許せなくて、自分で勝手に女の人が幸せになれるお話を続けてみたりしたの」
「どこも一緒ね。私も、おんなじことをした」
懐かしむようにブリギット。
「一緒だと思ったの。お兄ちゃん、クラーラさんにとても気を使ってた。失礼がないように、自分のことを気に止めてもらえるようにって。かなわないなって思うくらい」
穀潰しで放浪癖があって、それでも自分を守ってくれている兄。幸せになって欲しかった。
「そうね…。物語がここで終わってしまうのは、つまらないわ。で、貴女は錬金術でどうにかできないかと?」
「うん」
「…まさか、そんなことができるわけ、と言いたいけど」
ヴィオラートの隣に立ち、自分も参考書を手にとる。貴族の娘として高等教育を受けてきている彼女だ。多少はわからないところもあったが、内容がどんどん頭に入り込んでくる。
「貴女は私の病気を治してくれた。絶対に治らないといわれていた、不治の病を。またその奇蹟、みせてもらいたい」
人にとって何が一番幸せなのか。店を経営し始めて、そういうことをふと思う。人が集まれば打算があるのは当然で、いろんな思いが交錯する中、全員が幸せになる道を選ぶのは不可能だった。一人が幸せになれば、誰かがその犠牲になる。そうやってこの世の中は成り立っているのだから。
だから、兄の失恋もそのなかの一つとして見なければならないのだろう。けれども、兄だからこそ、彼女が一番幸せになって欲しい人の一人だった。
「肉親の、わがままかな?」
「いいんじゃない?そういうわがままも。たまには、ね」
ウインクして笑ってくれたブリギットの存在がうれしかった。
「クラーラさんね、私がお屋敷出るとき、なんだかほんの少しだけ悲しそうな顔してた。これ以上ないってくらい幸せに恵まれて、それでもなにか引っかかることがある、そんな顔。もしかしたら、クラーラさんは…って思った」
「…間違ってたら?」
「そのときはそのとき。だけど、何にも聞かないままじゃ、ダメだと思う」
「でも…さっきの様子じゃ、とてもじゃないけど聞くなんてことできないでしょうね」
「…」
話し合っていると二階から声がかかった。
「ようやく落ち着いたよ。どれだけ本気か、俺も思い知らされた。これじゃしばらく後をひくだろうな」
やれやれと、手を振りながらロードフリードが階段を下りてきた。
「すいませんロードフリードさん。不肖の兄で」
「慣れたよ。いつだってこんなものだろう。で、二人で仲良く参考書を読んで、一体何をしようとしているのかな」
「物語を、幸せにするためですよ」
にこりと笑ったヴィオラートに、意味はわからなかったがつられて笑った。
「物語?」
「お兄ちゃんは、一つの物語をちゃんと終わらせないまま、次の物語を始められるほど器用じゃないから。終わってないなら、おわらさないと」
自分で聞いて確認して、そうすれば納得できる。納得できなければ、物語は終わらないまま、この後もそれに引きずられるだけなのだ。
「ヴィオは兄貴思いだと思ったけど、これはなかなか厳しい兄貴思いだね」
「本当」
二人に言われ、そうかなぁと頭を掻いた。
「はいこれ」
小さな石のようなものを兄に渡し、出かける準備をする。
「あ、おい店は」
「どうしても手に入れなきゃいけない材料があってね。クラーラさんに2日だけお店番頼んだの。お兄ちゃんはちゃんと畑に行ってよ」
「お、ヴィオ!」
「行ってきまーす」
元気良く飛び出し、待ち合わせていたブリギットとロードフリードと合流し、さっさと村から出て行ってしまった。入れ替わるようにしてクラーラがやってくる。
「おはようございます、バルトロメウスさん」
「あ、あああ…おはようございます…」
鍬を持つ手が震える。
「ヴィオも大変ね。お店と、酒場の依頼と両立するのも」
カウンターに座りながら話し掛けるクラーラに、なんの返事も出来ない。逃げるように畑に出て行った。
「…二日、って言ったよな。まったくヴィオのやつ、なにもクラーラさんに頼むことないじゃないか…二日ぐらいなら俺が店番するってのに…」
当然畑に出ても気もそぞろで、まともに畝を作ることも出来ない。結局、夕方までぼんやりと畑の真中で座っていたに過ぎなかった。
「か、帰ったらクラーラさん…」
痛い。痛すぎる。帰りたくはないが、酒場に寄れるほど金はない上、親友は妹の採取についていっている。
「……くうぅっー!」
あきらめて家の戸を開けば、片づけをしている女性と目が合う。
「お帰りなさい。今日もご苦労様でした。とりあえずヴィオちゃんに頼まれていたので、お食事の準備はしておきました」
「あ、あの…どうも」
「それにしても、もしかしたらこんな風にお店番できるのも、今ぐらいかもしれません…」
「…それは」
「……」
じっとクラーラがバルトロメウスの顔を見ている。何かを言いたそうに、見ている。
今なら、後少し勇気があれば、何か言える。それはわかるが、声が出てこない。たった一言、名前を呼ぶだけでもいい。そうすれば、体の中を駆け巡る思いが一気に言葉になって出てくるだろう。
黙っていれば、クラーラの口から最悪の言葉を聞くことはない。だが、彼の心は蹴りを付けられぬまま苛まれ続ける。自分が黙っていれば、この人は無駄な思いを知ることはない。だが、行き場のない思いは彼の中に留まり、災厄となるだろう。
「…じゃあ、帰りますね。また、明日」
「……はい」
長い間の沈黙の後、バルトロメウスが先に視線をはずした。それにあわせてクラーラがカウンターから動き、ドアに手をかけた。そのとき。
「クラーラさん、待ってください!」
バルトロメウスの声がそこで響く。はっとして振り向けば、同じく驚いているバルトロメウス。
「あ、あの…なにか?」
遠慮がちに聞く声に頭を振り、何かを決心した。
「クラーラさん…結婚してしまうんですか?」
「…まだ、はっきりとは」
「俺は…クラーラさんに、この村にいて欲しい」
「…バルトロメウス…さん」
「クラーラさんのこと、ずっと…」
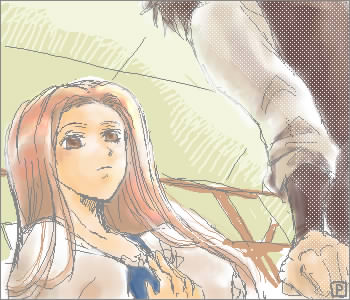
「言ったな」
「うん、言った言った」
「やるじゃない、結構」
わずかに開いた窓の外で三人が声を潜めて囁きあう。採取に出かけた振りをしてブリギットの家で時間を潰しつつ、兄が畑から戻ってくるのを見計らってこっそり戻ってきたのだ。
「さ、行こう」
「このまま行く先を聞いておかないのか?」
「うん。明日になったら、きっと教えてくれる。お兄ちゃんのことだから、すっきりした顔で、ね」
笑うヴィオラートにはかなわない。
「それに、私たちは知らないはずなのに、ニコニコしながら戻ってきたらおかしいじゃない」
「確かにそうね。じゃ、また私のうちに来て。いいのよ、遠慮しなくても。前、ヴィオラートは私を泊めてくれたから、今日はお返しね」
「俺は家に戻るよ。でも…」
歩きながらふと疑問をはさむ。
「一体、あの時クラーラさんに声をかけたのは…?」
「あれはね、お兄ちゃんの寝言」
「寝言だって?」
「ここのところものすごくうなされててね。私なんか寝れなくて困っちゃった。クラーラさんのこと呼ぶのよ。とっても悲しそうな声で。それを、記憶石に記憶させてみた」
「記憶…石」
ブリギットが不思議そうに頭を傾ける。
「うん。アイゼルさんといろいろ相談もして。惚れ薬なんて案もあったんだけど、人の気持ちを薬でどうのこうのするのは気持ち悪いから…。要は、きっかけがあればいい」
決心を実行に移すには、多かれ少なかれきっかけがいる。最後の最後で怖気づいてしまわないための、後押しというきっかけが。それに気がついた妹は、兄自身の声に、きっかけを作らそうと思った。本当に、その声が必要になったとき、反応するような仕掛けにしておいて。
「それで、どこかの古い文献に載ってる、記憶石に登場してもらったの。アイゼルさんが殆どやってくれたんだけど、もともとから不完全な記述だったから一回覚えさせるのが限界。もう、今お兄ちゃんのポケットの中で壊れてるんじゃないかな?」
「そんなものまであるのね、錬金術って…」
「ん。そうかも」
「そうかも、って貴女…。ま、いいわ。これで少しは貴女のお兄さんも、落ち着くでしょうし」
「そうなってくれるとうれしいがな。とにかくこの間みたいなのはごめんだ。…どんな結果になっても、今回ならさっぱりしてそうな気はするが」
「してますよ。私のお兄ちゃんだもの」
ロードフリードと別れ、ブリギットの屋敷へ向かう間、ヴィオラートはなんだかうれしかった。
「早く明日が、来ないかな」
どんな結果であれ、きっと兄はすっきりした顔をしているだろう。今日ほど明日がくるのを待ち遠しいと思ったことはなかった。
ヴィオやブリギットが読んだのは人魚姫と思ってくれれば幸いです
往々にして世の中は自分の思うとおりにはなりませんが
それでもじっと黙ったまますごしてしまうのはもったいないと思います
私自身もなかなか行動を起せない
起したら今までのことが壊れそうで怖いです
でも…少しは兄貴みたいに変われたらいいな、と…
ほんのわずかのきっかけが一番大事だって
ヴィオは一体いつ知ったんでしょう(笑)
でもそれって、一番難しいんですよね…
途中のイラストはペン子さまより頂きました
こんな拙い文章にこのような素晴らしい挿絵がつくなんて…
文章を書いてて本当に良かったと思う瞬間です
この場を借りて御礼申し上げます