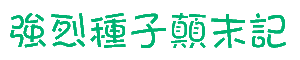
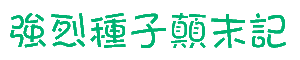
その日の兄は少しだけ不幸だった。普段も決して幸福とはいえない。ヴィオラートが調合するのに実験台になれだの、見るからにあやしい物体な、自称チーズケーキを味見してみろだの、気の合わない貴族のお嬢ちゃんが店番でやたらと痛い視線をうけたりだの。ただ、それは日常なのだ。彼を不幸にしたのは、たとえば家に戻ろうとしたとき、解けていた靴紐を直したかそうでないか、それだけの違いだった。
「きゃーっ!」
突然開いた戸に、ヴィオラートが奇声を出す。状況からして、急いで何かをどこかへ持っていこうとしていたのだろう。その、手にもったものがまともにバルトロメウスに向かってくる。
「うわっ!」
綺麗にフタがされていなかったそれの中身は兄にかかる。
「な、何だよこれは!」
頭から見事に濡れた彼は眉をひそめながら匂いをかいだりする。
「…あちゃー…」
「だから、何なんだよこれは!」
「……」
言っていいものかとしばらく頬を掻いていたヴィオラートだが、ため息を一つ。
「…育毛剤」
「なんっ…」
先月の美人コンテストのことが思い浮かぶ。戸惑いながらも化粧が似合っていた、恐ろしい彼の幼馴染の姿を思い出す。
「…なんだってそんなもん作ってたんだよ!ハゲブームでもなし!」
「そんなこと言われたって…。依頼があったんだから…」
「誰だよ!?」
「それは言えないよ。守秘義務ってものがあるもん」
口を割らないヴィオラートにバルトロメウスもため息を一つ。
「気持ちはわかるが…でも、どーいうもんを作ったかくらいはいえるだろ?どーせこれ、持っていくわけにはいかねぇもん」
「…だから、育毛剤。ただ…前に作ったのよりものすごーく強力で、ものすごーく即効性」
「……そんなに悪いもんじゃ…ないか。伸びれば切ればいいだけだし」
「…そう、そうだよね」
一瞬だけ間があったのが、妙に気になった。
その兆候はそれから半刻後に現れた。前髪が目に入りだしたのだ。
「お、効いてきやがったな。さすが「ものすごーく即効性」と言うだけのことはある」
切ろうかと思ったが、どうせまだ伸びるだろう。
「効き目が切れればさっぱりさ」
と、なにやら参考書を読み始めた妹を見た。
「…そんなに急ぐ依頼だったのか、この育毛剤」
「ちがうの。効き目をとめる薬できないかと思って…」
「そのうちとまるだろ?」
「確かにそうなんだけど…ぬけちゃうから」
「……」
申し訳なさそうに付け加えられた一言に硬直した。
「なんだって…?」
きき間違いであって欲しい。若干20代でハゲになぞ。しかも、部分を飛ばしてスキンヘッド。たまったものではない。
「……抜けちゃうの。全部。気持ちよく。それはもう。…だから、止める薬…」
「なんでそんな物騒なもん作るんだ!」
「作ったときはよくわからなかったんだよ!とりあえずものすごく強力だってことはわかったけど…。後から本を見てたら、あんまりに強力すぎる、みたいに書いてあって…」
ヴィオラートの説明を聞く間にもどんどんと伸びてくる。掻き分けなくては前が見えない。
「どれくらい効き目が続くんだよ!?」
「多分、もって三日」
「三日…」
三日後にはスキンヘッドが待っている。毛根が死ぬわけではないから再び生えてくるだろうが、外を歩けない。頭が殴られたような気がした。
「ヴィオ、さっさと作れ!さー作れ!ほれ作れ!」
「あんまりうるさくしたら手元が狂っちゃうよぉ!」
急き立てる兄の気持ちはよくわかるが、急かされて直ぐ出せるようなものでもないのだ。なにより、まだ彼女にはどういう理屈で髪が伸びるのかわからない。それがわからなければ、伸びるのをとめるのも無理というものだ。だから先ほどから参考書を見ているのだが…。
「さっぱりだよぉっ!」
当然だ。育毛剤が必要になる背景には、伸びないのを伸ばす、という願望がある。そのために存在する。逆など考える事はなかったはずなのだ。
「そうだ、アイゼルさん!」
彼女の師なら教えてくれるかもしれない。店を飛び出した。
いつもは酒場付近にいるのだが、夜が結構遅いこともあり宿で休んでいるようだ。休んでいるところにたずねていくのは気が引けるが、兄のために仕方がないと部屋を聞き、ノックする。
「…?」
返事はない。もう一度。
「……」
やはり返事はない。
「い、いないの?」
酒場にきてマスターに話を聞けば、少し興味深いところを見つけたといってしばらく出るとのこと。心の中で涙が滝のように流れる。
「き、きゃーっ!!」
突如上がる悲鳴。飛び込んできたのはクラーラだった。よほど恐ろしい目に会ったのだろう。涙で顔がぼろぼろになっている。
「クラーラさん!?どうしたんですか!?」
「ヴィオ…っ!あなたのお店…モンスター…」
「モンスターっ!?」
過呼吸になりそうになるクラーラをなだめながら聞いたところ、買い忘れのものを分けてもらいに行こうとして店に入ったら、いままで見たことのないような毛むくじゃらのモンスターがたたずんでいたのだという。
「けむくじゃらっ…!」
「多分、村の有志…退治しにいってくれてる…」
「!!」
くずおれる彼女をマスターとクリエムヒルトに頼み、慌てて外に出た。と、男たちが店の前で牽制しあっている。
「ちょっと、通して…通してください!」
掻き分けて扉の前にやっとでると、ロードフリードに制止された。
「ヴィオ、危険だから入るな。俺たちがまず突入する」
「いやあの」
「行くぞ!」
掛け声と共に店の中に突入したが、誰もいない。何もいない。ただ、窓が全開になっている。
「窓から逃げた!そちらに3,4人回れ!」
「だから」
「ヴィオ、ここに残っているとモンスターが戻ってくるかもしれない!酒場で待っていてくれ!」
「話を」
「逃すな。二度とこの村に足を踏み入れられぬようにするぞ!」
「…聞いて…」
言い置いてロードフリードは華麗に窓から飛び出した。その姿に、そういう場合ではないのだが思わず見惚れる。
「じゃなくて!」
我に返ったヴィオラートは兄を探しに飛び出した。いつもの畑はもちろん、兄がいると思われるところを探し回ったが見つからない。
「こうなったら…クラーラさんに頼んでみよう」
いくら鈍いヴィオラートとはいえ、兄の態度を長い間見ていればよくわかる。彼女に頼むのが一番効果的な気がした。
「…クラーラさん?」
「ヴィオか。今さっき村長が迎えにきたよ。相当怖い目にあったんだろうね」
酒場に顔を出したヴィオラートに向かってオッフェンが心配そうにつぶやく。それを聞いてガクリとなった。そんな様子なら、頼みごとなどとてもできやしない。ほとほと困り果てて村はずれまできた。
「村にモンスターが出たって言うのに、なんで貴女こんなところでうろうろしてるのよ?」
少々きつい物言いで誰か直ぐにわかる。
「ブリギット…」
都会から来た友人の顔を見つめ、突然泣きついた。
「ブリギットぉぉぉ!」
「ちょ、放しなさいよ!往来でみっともない!」
「うわわぁぁん!」
しがみついてくるヴィオラートをなだめながら自分の屋敷につれて帰り、お茶を一杯だしたところでようやく落ち着いた。
「実は…」
事の次第を聞くにつれ、心配そうだった表情があきれたものへと変わる。
「…で、どうしようかと思って…」
「……」
めまいがするとばかりに頭を抑え、紅茶を一口飲んで息を整える。
「ほんっと。貴女って、どんくさいわね…」
「そんなこと言わないでよ。本気で困ってるんだから。みんなはモンスターだと思って追いかけてるし、お兄ちゃんは見つからないし」
「……貴女のお兄さん、そんなに頭悪くはないんだから、案外に自分の部屋にいるかもよ?窓だけとりあえず開けておいて」
「…!そうかも」
そういえば家の中にいるなんて思いもしなかったので、ろくに調べもしなかった。
「揃いも揃って本当にここの人は単純なのね…」
ため息をつきながら肩をすくめるブリギットだった。
「…お兄ちゃん?」
そっと部屋の戸を開ける。薄暗がりの中になにやら毛の塊がうごめいていた。
「ちょっと、お兄ちゃんってば」
「うー」
本当に毛むくじゃらだった。髪の毛だけではない。薬剤がかかった部分の毛が全部伸びているのだ。
「ほらやっぱり。もう少しまわりに注意を払った方がいいわね」
行きがかり上付いてきていたブリギットが軽く厭味を言う。が、ヴィオラートはそんなものに気がつくはずもない。
「そうだね、うん。ブリギット。心配してくれてありがとう」
「…もう。少しは骨のある反応してよ…。からかう意味もないじゃない」
「え、からかってたの?」
「…もういいわ。この毛の塊を先にどうにかしましょう」
ダメだとばかりに頭を振り、近くに置いてあった鋏で手早く切り落としていく。かなり長く伸びた毛がばらばらと落ちていった。
「お掃除…大変だろうな…」
「なにのんきなことを言っているのよ。貴女は早く育成をとめる薬を作りなさい!」
「はいっ!」
部屋から飛び出して階段を転げ落ちる音がした。
「……」
何が起こったのか簡単に想像はつくが、この際気にしないことにする。
「…だいぶましになってきたわね」
「すまねぇな」
「本当に。まったく、貴方達は一体なにを思って生きてるのかしら」
「…後は自分でできる。ヴィオの様子でも見てやってくれ」
「……いいわ。ここに置くから」
ブリギットが出て行って、鋏を手に取る。しつこく伸びつづける髪を見、ため息をついた。
「クラーラさん…俺って、わかってないよなぁ…」
彼女の悲鳴は文字通り彼に突き刺さったのだ。どうか、自分と結び付けてませんようにと祈った。
さすがに山狩り捜索隊までは作られなかったので、ロードフリードはヴィオラーデンにやってきた。クラーラが人事不省に陥っているだけで、これといった被害は出ていない。ただ、ヴィオラートの店がどういう状態なのかはわからなかったので、様子見も兼ねて戸を叩く。
「ヴィオ、そちらの様子は…?…ブリギット…さん?」
「あら、ロードフリード様」
「なぜ貴女がここに?」
「ヴィオラートが泣きついてくるものだから…」
ブリギットの視線を追って顔を動かせば半分なきながら参考書と格闘する少女がいる。
「…?一体」
「…ヴィオラート、ロードフリード様にはちゃんと言うわよ」
騎士に向かってではなくヴィオラートに向かって告げ、返事を待たずに二階へ上がるように言う。彼女についていけば、あたり一面毛だらけの床と、その真中で座る悪友。それで今晩の出来事の合点がいった。
「バルテル…お前か?」
「……文句はヴィオに言え」
ぶすっとした顔なのだろう。前髪らしき髪の毛で隠れて見えないが、声の調子でわかる。
「ふっ…はははっ…」
突然笑いがこみ上げてきた。始めは抑えていたが、こうなると波が去るまでは収まらない。やがて青年の笑い声は部屋中に響いた。
「笑うな!」
「いや…しかし…くっ…。これじゃあ、俺たちがガキのころとまったく変わってないじゃないか!」
体を折り曲げて笑うロードフリードに、バルトロメウスは飛び掛るまねをする。
「少々…迷惑度は上がったがな」
「確かに」
「あとは、ヴィオが薬を作ってくれるのを待つばかりだな」
「それはなかなか難しいようよ。まだ参考書に埋もれてないてたわ」
やってられないとばかりに腕組みするブリギット。二人の青年は顔を見合わせ、肩をすくめた。
「…で、どうなったの?」
「どうもこうも…ヴィオラートがそんなもの作れるわけもなく、まだ本を読んでるから私がアイゼルさんを待つことになったんです」
なかなか面倒見のいいブリギットはアイゼルが採取から戻るのを宿兼酒場で待っていた。一日経って戻ってきたアイゼルは事の顛末を聞き、しょうがないわねという表情をする。そして、遠い思い出がよみがえる。
「あの時は街中が凍りついたわね…」
縦ロールまでされた日には聖騎士部隊も真っ青だった。口元にわずかに微笑を蓄え、弟子の店を訪れた。
「ヴィオ。調合は気をつけないと」
「アイゼルさん」
一睡もしていないためクマが濃く出ている。
「ごめんなさいっ!」
「謝るのは私じゃないわ。ただちょっとだけ注意力がなくなってただけね。誰も悪くないと思う。で…発育を止める薬だけど…。ないことはない。でもね、このあたりでは手に入らない材料なの」
「代替も…できないんですか」
無言でうなずく師。
「そんなぁ…お兄ちゃん、スキンヘッド…ぶっ!」
思わず想像してしまい、慌てて笑いを押し殺す。
「そうね…。バルテルさんの髪の毛、一体どれくらいになったの?」
「え?…あそこの箱のなかにとりあえず入れてるんですが…」
「まだ伸びてるのよね?」
「効き目が切れるのが多分明日だから…」
「じゃあ、切るのを止めて抜けるのを待ちなさい」
『えっ?』
その場にいたヴィオラート、ブリギット、バルトロメウスが調和して返答をした。
「抜けた髪を私に預けて。しばらく風邪だと言って、外に出ない方がいいわね」
「…あの、どうするんです?」
「鬘。とりあえず成形はするから、あとで誰かにちょうどいいくらいまで切ってもらえばいい。そうすればわからないわ。髪がまた生え揃えば必要はなくなる。それに、もっと穏やかな効き目の育毛剤も作ってあげるから」
「アイゼルさん…ありがとうございます!」
気にしない、と手を振って店から出て行った。
「よかったね、お兄ちゃん」
「良くない!」
「なんで?別に抜けたことを知っているのは、私と貴女のおっちょこちょいな妹と、アイゼルさんにロードフリード様だけ。別に支障はないでしょう?」
「もし突風が吹いてみろ!それはそれは大いなる悲劇だぞ!」
「そこまでは責任もてないわ。帽子でもしっかり被っておけば?」
少し冷たく突き放し、今度こそやってられないと店を出て行くのだった。
「ブリギットって、結構面倒見がいいよね」
「…だぁーっ!」
そんなこといってる場合か!まともに口を開く気力もなく、ただただ叫びが口から出てくるのみであった。