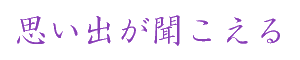
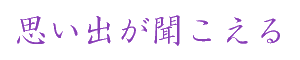
彼が店番を始めて一月になる。店の構造上仕方がないのだが、カウンターの真隣で爆発音を聞かされるのはあまり心臓によくない。かといって、必死になって村おこしのために調合を続けるヴィオラートを見ると、文句も言えなくなってしまう。
「…甘いと言われればそれまでだろうけど」
プラターネ兄妹は面白い。昔からそうだ。悪戯が好きで、少々怠け癖はあるが憎めない兄と、にんじんが大好物で、人を疑うと言うことを知らない妹。そして自分。幼いころは野原を駆け回った。ことあるごとに、しかも他人からみると本当にどうでもいいことで大喧嘩をしたかと思うと、その半刻後にはニコニコとお菓子を分け合う。バルトロメウスが大抵悪戯の火付け役で、ヴィオラートが被害者。そして怒られるのは彼。子どもながらに釈然としないと、何度も悪友に文句を言ったが結局聞いてくれなかった。
「思い出…か」
カウンターで時折接客しながら、昔のことを思い出す自分がいる。田舎で、他にすることがなくて、それでも楽しいと思っていた。
夕方になり、客足が途絶える。今までの経験から言うと、そろそろ店を閉めても支障はない。
「ヴィオ、ちょっといいかい?」
調合が一段落したのをみてとり、そっと声をかけた。
「なぁに、ロードフリードさん」
屈託のない声が、笑顔と共に返ってきた。
「いや、そろそろ店を閉めても支障はないんじゃないかと思って。少し、練武がしたいから早めに上がらせてもらえるかい?」
彼女は調合器具を机におき、窓をのぞく。そして店の中の状況を見、ロードフリードの顔を見た。
「そう…ですね。もう夕方ですか。お店の品物ももうあまりないみたいだし。はい、今日はありがとうございました」
きっと彼女ならこういう。そんな気がしていた。
「ああ。雇われている身でわがままをいうのも心苦しいけど」
「そんな。ロードフリードさんは、村を守れる力がある人です。そんな人を店番に使っちゃう私の方がわがままですよ」
舌をだしながら頭を掻く。ロードフリードはヴィオラートの頭をぽんぽんと軽く叩き、笑った。
「…じゃ、また明日」
「はい」
戸を閉め、名残惜しそうに出来たばかりの店を見上げる。と、中から強烈な爆発音が響き、バルトロメウスがなにか怒鳴るのが聞こえた。
「…だ、大丈夫よな…多分」
明日来たら、店がないなんてことは…。わずかに肩をすくめながら村はずれへと向かった。
村はずれにはブリギットが住む屋敷がある。なぜ彼女が首都からここに越してきたのかは詳しく聞いていないが、何かと彼を頼ってくるのでそれなりに話をするようになった。ロードフリードが近くで練武をしているのを知ってからは、よく屋敷の外へ出てくる。
「ロードフリード様」
「ああ、ジーエルンさん」
「あら、水臭い。ブリギットで構いませんわ」
にこりと微笑む彼女は、ヴィオラートとは違い洗練された香りがする。基本は田舎育ちのロードフリードには、少し苦手だった。が、そんなことはおくびにもださない。
「今日も練武…ですか?お茶でもどうかと思ったのですが」
「お気遣いどうもありがとうございます。けれど、待っていただく必要はありませんから。気が済むまで練武をすると、夜遅くなりますし」
「…まぁ、熱心なのね…」
感心して、剣を振るう姿を見ていた。しばらく黙っていたが、
「…もったいないわ。こんな村でなく、ハーフェンにいれば竜騎士団にも入れたでしょうに」
「そうでしょうか…?」
「そうですわよ。素人目にも貴方の腕のすごさ、わかりますもの。田舎で埋もれさすには惜しい気がします」
「…なら、この村は誰が、守るんでしょうか…?」
自信なさげにぽつりとつぶやいたが、ブリギットの耳には入っていないようだった。
ヴィオラートが近場に採取に出ているので、ここのところ留守番ばかりが続いていた。そんなに長くならないと聞いていたので、そろそろ戻るかと戸に目をやる。まだ開く気配はない。
「……この村を、守る」
本当にそのために、自分はここにいるのか。規律化され、集団化された中での期待と重圧。苦しい訓練の中でよく思い出したこの村。精錬所を卒業すると共に、逃げるようにして戻ってきた故郷は相変わらずのまま。
「本当は…逃げてきたのかも」
人から思われるほど強くはないのだ。村を守るのならば、村にいる男たちがやってのけるだろう。お金がなくて無理だったと言うだけで、騎士になれる素養を持った人間は多いのだ。
「うがー。ヴィオの奴、まだもどんねぇのかよぉ」
「バルテル、そんなに腹が減ったのなら、自分で料理すればいいじゃないか」
階段上から情けない声が降ってきて思考が中断した。
「お前、そんなこというけどよ、ヴィオの飯、結構美味いんだ。そんなの食ってたら俺の飯なんぞ、食えたもんじゃねぇ」
「………自慢にならんな」
まったくこの悪友は。
「あとでマスターに言って、美味いものを届けてもらうように言っておくよ」
「すまねぇな、親友」
「都合のいいときだけ親友にするな。代金はお前持ちだ」
「…前言撤回」
「たっだいまー!」
先ほどまで死人のようだったバルトロメウスが階段を駆け下りてきた。
「飯、飯、めしーっ!」
「…お、お兄ちゃん…おかえりも、なし?」
飯、を連呼しながら揺さぶられるヴィオラートをみて思わず声を出して笑う。
「お帰りヴィオ。疲れたろう」
「ただいま、ロードフリードさん。お店番ありがとうございます」
律儀に礼を言う少女に微笑みかける。
「で、君の兄はどうやら餓死寸前のようらしい」
「そうですね。ってお兄ちゃん、いい加減揺さぶるの止めてよ」
「めしー」
「わかったよ、作ってあげるから。もう…。あ、ロードフリードさんもいりますか?」
「いや、俺はいい」
断り、また客の相手を続けていると食欲をそそる香りが鼻腔をくすぐる。空腹ではないが、この匂いをかげばどんな人間でも空腹感を感じてしまう。
あながち、バルテルが言うのも贔屓目じゃないかもしれない。
少し、幼馴染がうらやましかった。
とりあえずの間食を終わらせ、ヴィオラートは休む間もなく調合を始めた。ロードフリードも客足が多くなり、彼女のことには気をまわせなくなる。そんな最中、カウンターの上に巻貝が置かれているのに気がついた。
「これは」
覚えている。昔、騎士精錬所に行く前にヴィオラートに渡したものだ。海の音がする、と、幼い彼女は喜んで耳に当てていた。
「ヴィオ、これは…」
まだ持っていたのかい?そう聞こうと振りむいたが、テーブルの上で船をこいでいる。
「……」
いつから眠っていたのかは知らないが、そっとしておきたかった。村おこしのため、彼女が見えないところで努力をしているのを知っている。
「そろそろ夜だし、店も終わらせてもいいか」
閉店の看板を出し、あたりを少し掃除する。巻貝を大事に手に持ち、眠るヴィオラートを起こした。
「…ヴィオ。ヴィオ」
「…んんー」
「起きたかい?」
「…はにゃ?」
寝ぼけた眼差しで周りを見渡し、年上の幼馴染と目が合って覚醒した。
「あ!私、寝ちゃったんだ…こんなに真っ暗になっちゃって…」
「大丈夫。ちゃんと店は閉めたよ」
「…あー、何から何まで…」
「構わない。仕事のうちさ。それより…」
そっと巻貝を指しだす。
「これ、まだ持っていたんだ?」
「…あれ?どうしてこんなところに…。ちゃんと大事なもの入れに入れてたのに」
「…?カウンターの上にあったけど?」
「変なの。でもいいや。置いておこうっと。きっと、箱の中が寂しかったんだ」
笑って手のひらに包み込む。
「もう、音は聞こえないね」
「でも宝物。音は聞こえなくても、思い出が聞こえる」
「思い出が…」
屈託なく笑うヴィオラートを見て、なぜ自分がこの村に戻ったか理解した。いや、なぜ村を離れて騎士精錬所に入ったかを。
思い出を守る力が欲しかった。ここに住む人たちがもつ思い出と、これからを。とりわけ、バルトロメウスとヴィオラートという、憎めない兄妹を。
人は思い出に頼って生きるべきではない。けれども、活力へ換えることはできる。思い出をまもる、それは悪くない人生だ。ロードフリードはそんなことを思った。
後日、バルトロメウスが壊れた巻貝にバーゲン札をつけて売り出そうとしていたことが発覚し、村中をヴィオラートに追いかけられたのはまた別の話である。
ENDE
イメージボードの一つから連想しやした
なぜか微妙に悩める人になってしまったロードフリード氏(笑)
ヴィオに追いかけられたバルト兄貴(だから違う)は
ロードフリードにも追いかけられたに違いありません
もう、兄貴ってば(爆)