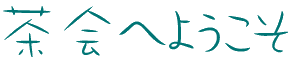
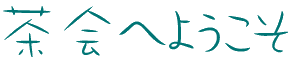
「『お茶の木』…ですか?」
三月のはじめ。シスカからの依頼を完了した際、そんなお茶を聞いたことはないかと彼女から言われた。けれど、お茶を飲む習慣すらないのにいわれても困惑するばかりだ。
「やっぱりないのかなぁ。私も、噂に聞いただけなんだけどね。南東の方で、『お茶の木』って言うものが栽培されてて、その葉で淹れたお茶はすごくおいしいって…。一回飲んでみたいと思うんだけど」
「シスカ姉さん、酒以外も飲むんだね」
「テオちゃん?それはどういうことなのかな?」
たまたま彼女達の話を聞いていたテオが口をはさみ、シスカにぽん、っと頭を叩かれている。ばつが悪そうに笑いながら、大量のザラメをもって出て行ってしまった。
「ミスティカティーよりおいしいんですか?」
「うーん。私はそれもあんまり飲んだことがないから、はっきりとはいえないんだけどね…」
肩をすくめながら依頼の品を自分の荷物に入れる。
「以前、アザミを使ってお茶を淹れたことはあるんですけど、それとはまた違うんですか?」
「違うみたい。純粋に、『お茶の木』があるんだって。聞けば、貴族とか王族とかが飲んでるとかなんとか」
「へぇー」
「酒場の噂話なんだけどね。あそこは、噂話でも馬鹿に出来ないところだし…」
そうですね、と首を縦に振る。
「リリーなら遠くから来たから、何か知ってるかと思って」
「すいません、お役に立てなくて」
「いいのよ」
にこりと魅力的な笑顔を残し、工房から出て行った。残されたリリーは、妖精や弟子達に指示を出しながら思いふける。
「南東…南…イルマなら何か知ってるかなぁ?」
確か彼女は南から来たと言っていた。なにか聞いたことがあるかもしれない。
「シスカさんに飲ませてあげたいのもそうだけど、あれだけ言われたら私も気になる」
いつも一生懸命お手伝いしてくれる妖精さんたちや、イングリドとヘルミーナに飲ませてあげたい。そんなお茶私も、飲んでみたい。
「『お茶の木』?」
「そうなの。知らない?」
今日も今日とて中央広場で占いを営んでいるイルマにリリーは近寄っていった。
「うーん。私が生まれたって所では、確かにそんな木があったとかなかったとか聞いてるけど」
「本当?」
「すごくたかーい高原でしか育たない木で、育てるのも大変だって」
「でも、実際あるわけでしょう?」
「そうね…。ってもしかしてリリー、行ってみようなんて思ってない?」
「ダメ?」
いつもの採取に出かけるような感覚では駄目なのか?そう、目が問うている。
「ダメに決まってるでしょう?一体どれだけ時間がかかると思ってるのよ」
「…どのぐらい?」
「片道最低二ヶ月。馬車でね」
「えっ…」
「それに、道はないに等しいから…。追いはぎや、獣や、そういうこと考えたら四ヶ月は考えていかないと…」
「よ、四ヶ月って」
「四ヶ月過ぎたら、初摘みじゃなくてセカンドフラッシュになるんじゃない?」
「せ、セカ…え?」
「うん、あのね。小さい頃に聞いた話だから、うろ覚えだけど」
と、前置きをして語り始めた。
『お茶の木』は一年に三回収穫を迎える。春・夏・秋だ。それぞれ、ファーストフラッシュ、セカンドフラッシュ、オータムナルと呼ばれており、それぞれ味わいが違うのだとか。中でも初摘み、ファーストフラッシュは収穫量が少なく、それはそれは高い値で取引されるのだという。
「同じ葉っぱなのに、味が違うの?」
「そういうね。私は飲んだことはないけど」
「ひゃー。世の中にはいろんなのがあるのね…。お茶ってだけでも、侮れないわ」
「で、そのお茶が一体どうしたの?」
「うん、シスカさんから聞いた話なんだけど…」
「…へぇ。あのシスカさんが飲んでみたいなんて…。私も飲んでみたいなぁ」
「でしょう?でも無理かなぁ。すっごい高いって…」
「うーん…。貴族とか、王族とかに聞けば知ってるかもしれないけどね…」
役に立てなくてごめん、とあやまるイルマ。
「そんなことないよ。『お茶の木』について教えてくれたじゃない」
「ごめんねー。せっかく頼ってくれたのに」
「うん。気にしないで」
ちょうどそこに占って欲しいとお客が来たので、リリーはその場を辞した。職人通り前を貫く坂を登っていると、見慣れた少女の姿。
「エルザ!」
「あっ…」
むこうもこちらに気がついたようで、手を振りながら駆け下りてくる。
そうだ、エルザは貴族だから、お茶を飲んだことがあるかもしれない。
「ね、今暇?」
「うん…。どうしたの?」
「工房にちょっと来てよ」
と、相手の返事を待たずに工房に連れ帰る。幸いなことに弟子達は外に買い物に出ており、妖精たちは採取に出した。エルザが貴族だというのは彼女だけしか知らないことなのだ。
「どうしたの?」
「あのね、『お茶の木』って知ってる?」
「お茶…あ、うん」
「本当?実はね…」
シスカから始まったお茶の話を聞かせるリリー。
「そっか…。普通はなかなか手に入らないものなのよね、お茶葉」
「エルザのうちにはある?あったら、買わせてもらいたいの。みんなでお茶会をしてみようかと思って」
「ええと…。実は、そういう食べ物とか飲み物とか、全部シェフが管理しててね」
その料理長が決めたスケジュールどおりでないと、絶対に出してくれることはないのだ。
「例外は?」
「だめ。一切、認められないの。それに、今やっと収穫の時期だったと思うよ。まだ市場には出回ってないの」
「そっかぁ…」
「でもさ、なにもそんなお茶飲まなくたって、リリーが淹れてくれるお茶とお菓子は抜群だと思うよ。家で飲むよりよっぽどおいしい」
笑いながら一口。多分、友達と一緒に飲んでる、という空気が良いんだと思う。そう言ってお菓子もかじる。
「うん、おいしい」
「ありがと」
てれながら頭を掻く。
「でもね。そこまで話を聞いちゃったら、飲んでみたくてたまらなくなっちゃって…。シスカさんと、イルマにも飲んでもらいたいなって」
「その気持ち、わかるよ」
ミスティカティーを一口飲んで舌を出す。思ったより熱かったのだ。その様子を見てエルザが噴出した。
「笑うことないじゃない」
「だってぇ、なんかかわいかったもん」
「かわいかったって…」
なんだか、私の周りにいる女の人って、私をからかってるのかな?
苦笑しながらそんなことまで考えてしまう。と、あることに気がついた。
「じゃあ、どこでそのお茶葉買ってるの?」
「あなたも良く知ってるお店」
「ん?」
良く知っている店は何軒かあるが、そういうものを扱っていそうなお店。確かに、一軒心当たりはある。あるにはあるのだが。
「…あそこ?」
「うん、あそこ。実はうちとお得意様なの」
だから名前は知ってて、外に出歩くようになってからはよく行っているのだと。
「あ…それで良くあの店にいるのね」
「そうなの。他にはあんまりお店知らないのよ」
「…」
「どうしたの?急に暗くなっちゃって」
心配そうに覗き込んでくる。なんでもない、と慌てて手を振りながら笑顔を作る。
「大丈夫だよ。あなた、ヴェルナーさんと仲がいいじゃない」
「どこをどう見たらそう見えるのよ」
「どこって…全部」
用事があって店に行くたびになにやら文句と言うかなんというか、とにかく妙なことを言われ、依頼品を渡せば渡したで文句を言うことの方が多い。店で二人そろって言い合いをしていることもしばしばだ。それのどこを見たら、仲がいいと見られるのだろう。複雑だ。向こうはどう思っているかは知らないが、やはりからかわれているような気がしてならない。
「…なんか、見てて面白いわ、リリーって」
「なんで?」
「すぐ顔に出るもん」
「…」
みんなそろって私をからかってる。それは間違いないと、確信をした彼女だった。
「大丈夫だって。いくらあの人だって、リリーを取って食ったりしないわよ。頼んでみたら?」
「うん…。みんなに飲んでもらいたいもんね。やっぱり」
「そのときは私も呼んでくれる?」
不安そうに聞いてくるエルザ。それをみて不思議そうな顔をするリリー。
「当たり前じゃない。エルザもシスカさんもイルマも、ほかのみんなも呼んで盛大にお茶会しよう」
彼女の言葉を聞いて貴族の娘の顔がほころんだ。やはり、どこか負い目があるのだろう。
「初摘みの茶葉だぁ?」
面倒臭そうにイスに座っている店主。雇っているメイドがぱたぱたとハタキを商品にかける音しかしないほど、人のいない店。
「ここで扱ってる、って聞いたから…。良かったら、少し多めに仕入れてもらいたくて…」
機嫌の悪そうなヴェルナーを前に、だんだん言葉が尻すぼみになってくるのがわかる。
「そりゃ確かにここで扱ってるがよ…。ありゃあ、貴族や王族のもんだぜ?」
「知ってるわよ」
「それに、一体どれぐらいするのか知ってるのか?…ほら」
「…ぶっ!」
彼が差し出した交易品のレート表を見てひっくり返りそうになった。
「ななな、なにこれ」
「なにこれって…茶葉1グラムに対して支払われる銀貨だ。もっとも、こいつは去年のだがな。今年はどうも収穫率が悪いから、もっと上がるって聞いたな」
「うー」
「いつぞやの何とかの実のときみたいに、お前が育てた方が早いんじゃないか?」
「イルマから聞いたら、高地で涼しいとこじゃないと育たないんだって…。このあたりにそんなところないもん…」
「じゃ、あきらめるか、一生かかって払うような借金抱えるかどっちかだな」
「どーしてそういう言い方しか出来ないのよ」
「知るか。俺はこういう性格だ」
わかってはいる。わかっちゃいるが、リリーはたまに、こういう人間がいることが理解できなくなるときがある。ため息をそっとついた。
「…はいはい、あきらめますよ。…お茶会したかったなぁ…」
肩を落としてリリーは店を出て行った。
五月半ば。しばらく遠方に採取に出ていた彼女は、工房に戻って唖然とした。
「…なにこれ」
覚えのない木箱がででんと、彼女の机の上に居座っていたのだ。
「あ、先生お帰りなさい」
「ただいまヘルミーナ…。…これなに?」
「あ、これですか?ヴェルナーさんが、昨日置いていきました」
「…?なんだろう…」
そっと蓋をこじ開けてみる。金属製の蓋はしっかりと木箱にはまっており、なかなか外れなかったが、ヘルミーナと協力して開けた。と。
「わあ…いいにおい」
「……お茶?」
良くみると、木箱の横に銘柄らしい単語が焼き付けられている。
「ダー…ジリン?」
茶葉の香りは新緑の香り。工房中に広がり、居眠りをしていた妖精が目を覚ます。
「んん?ボクは一体、いつ森に帰ってきたんだ?」
寝惚けた声で言うのがたまらなくおかしい。
「なんでまた…」
不意に、二ヶ月前のやり取りが思い出された。
「…あっ、お金…」
慌てて工房を出て彼の店に飛び込む。
「ヴェルナーっ!」
「なんだよ騒々しい」
「あの…お茶…ありがとう…」
ただ礼を言うだけなのに、なんだかとても恥ずかしいことを告白しているような気分だ。
「ああ。あれか」
「うん。…いくら?」
「……」
ヴェルナーは興味深そうにリリーを見る。いろいろと思うところはあったが、結局、
「いらね」
とだけ言った。
「だって…すごく高いって…レート見せてもらったじゃない」
「いいんだよ。…いつも、買い物来てくれてるからな」
意味がわからなかったのか、首を傾げる女。
「お得意様サービス、ってことだ」
それだけではないのだが、そこまで表に出せるほど彼は正直ではなかったし、子どもでもなかった。
「いいの?」
「ああ」
「本当に?」
「しつこいな」
「……ヴェルナー」
優しい声で呼ばれ、少しどきりとする。
「ん?」
まともに顔などみられないから、いつものように目だけ動かす。
「本当に、ありがとう」
満面の笑み。慌てて視線をそらして手元の紙に視線を落とす。
「お茶会するから、ヴェルナーも来てね」
うれしそうに続ける。が。
「いかねーよ」
「どうしてよ?」
それまでの雰囲気が壊れてしまったと、憤慨してリリーが問い詰める。
「店はどーすんだよ、店は。俺はお前と違って暇じゃないんだ」
「…あー、そうですか、それはどーも失礼しました!」
口を尖らして店から出て行く。それを見送る渋面の店主。
「なんでこう、俺はひねくれてるんだ…」
その答えは誰も知らない。
「へぇ。これがファーストフラッシュ、ってものなんだ」
テオがザラメを入れたカップを持って呟く。
「リリー、ありがとうね。私の言ったこと、覚えててくれたんだ」
「それにみんな呼んじゃって…。お仕事とか大丈夫なの?」
美貌の剣士と流浪の少女が声をかけてきた。
「うん、今誰の依頼もうけてないし。たまにはこういう日もないと。妖精さんたちやあの子達も休ませてあげなきゃ」
楽しそうにシャリオミルクを加えて飲んでいるイングリドたち。その様子を見ていたら、なんだかとても元気になる気がする。
広い工房にはいくつかのテーブルが置かれ、その上にはリリーお手製のお菓子とダージリンと呼ばれるお茶が置かれている。それぞれテーブルにはリリーと親しい人々が座っており、盛大なお茶会となっていた。
「たまには、こういうのもいいものだね」
人前にあまり姿をあらわそうとしないアイオロスですら、この空気が気に入っているようだ。
「今度は教会でも、子どもたちのためにお茶会を開いてみてもいいかもしれません」
クルトが静かにお茶を飲みながら呟く。
「賛成です、クルトさん。私、準備しますよ」
エルザがうれしそうに応えた。
「これはなかなかないものだな」
ウルリッヒですら門番の仕事を置いてちゃっかりと混じっている。
「以前ロイヤルクラウンを飲ませてもらったが、あれとはまた違った趣だ」
「俺はお茶もいいけど、こっちのパイが絶品だよ、うん」
ゲルハルトは何切れ目になるのかわからないが、アップルパイに手を出している。
「前はすごいの食べさされたけどな」
「ゲルハルト、それは言わないで」
今日の女主人は照れて頭を掻く。
「ところで…、このお茶の提供者は?」
製鉄工房の若き女職人があたりを見回す。
「それが、店があるから来ないって」
「付き合いの悪い奴だよな、ヴェルナー兄は」
「せっかくの誘いを断るなんて」
ゲルハルトとテオが反対側のテーブルからうんうんと頷いている。
「その件でちょっと出かけてくるね。すぐ戻るから」
と、綺麗に箱詰めされたお菓子と茶葉を包みに入れ、工房を出て行くのだった。
ふっと居眠りから開放されたら、カウンターの上になにか乗っている。手にとってみるとお菓子のようだ。なにかメモが挟まっている。
『今度はお茶会にきてよね』
それだけ書かれた簡潔なメモ。あいつらしい、と思いながら箱を開けると、彼が好きなラムレーズンをたっぷり使ったケーキだった。
「……やっぱり、行けばよかったよなぁ」
一切れ口に運ぶ。それは甘く、けれどちょっとだけラムの苦さをまとっているのだった。
そして茶会にいかなかった彼は知らない。レーズンケーキは、彼だけのために焼かれていたことを。
ENDE
2222のキリ番リクエストでした
ショウさん、こんなようなものですがいかがでしょう…
あまり甘すぎるのはかけないのでごめんなさい〜
今でこそ平和に常飲されている紅茶ですが
中世では非常に高値でした
それがらみで密輸も行われていたほど高級品かつ需要がありました
一度やってみたかった紅茶ネタです〜
私は紅茶馬鹿なので、一日にサーバー三杯飲んでます
飲みすぎだと怒られました(笑)
そして、私が抱えているキャラクターはどいつもこいつも紅茶飲みです(笑)
お茶会は好きなのでよく開いてます
なにが楽しいって、くる人に合わせてお菓子や出すものを考えるのがいいですね♪
BGM are Linger(the cranberries), To Be Free(Sol Bianca), Free Space(the Gospellers)