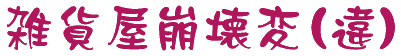
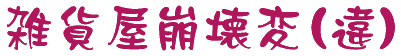
「ヴェルナー、何この匂い」
「あぁ?」
雑多に物が置かれているので普段もそんなにすっきりした空気ではないのだが、今日はそんな匂いではない。ここにはあまりそぐわない、……いつもなら金の麦亭で嗅ぐもの……そして、自分自身の工房でも嗅ぐ……アルコール臭。
「ハインツの旦那が、……蛇の抜け殻使って……酒…」
「あんた、酔っ払ってるの!?」
こんな昼日中から。
憤慨気味にリリーは腰に手を当てた。店主はといえば、いつもとそう顔色は変わらないものの、なにやらふらつき気味だ。
「これね?」
無造作にカウンターに置かれた酒瓶を手にとり、その匂いを嗅ぐ。
「ぶっ」
匂いだけでもそのすさまじい強さが想像できる。
「うげぇ…。なんなのよコレ。竜殺しよりひどいじゃない」
この間のカクテル騒ぎで懲りているので、飲んでみるようなまねはしない。
「旦那…新しい酒はいいんだが…人に試し飲みさせるのはやめてくれ……」
要するに、出来たからためしに飲めといわれたのだろう。さすがのヴェルナーも、あの剛毅な男に逆らうことは出来ないらしい。
「ハインツさん…実は最強よね…」
酒場のマスター以外したことありませんというような顔をして、実はその昔相当な腕前の冒険者であった。加えてその押しの強さ。彼に頼まれて断れるような人間はそうそういない。あの王国最強と歌われるウルリッヒですらハインツには頭が上がらないのだと、誰かが酒場で噂をしていた。ただ、それがまったく嫌味でないので、彼は人望を集めるのだ。
「本当に光る人の元には、おのずといろんな人が集まるものよね…」
妙な感動に浸っているとヴェルナーのうめき声が聞こえた。
もともと彼もそんなに酒に弱い方ではない。シスカとタメを張れるぐらい強いのだが、マスターお手製の酒にはかなわなかった。後から聞いたところによると、最強のザルだと噂されるシスカ嬢ですら頭痛を次の日引きずったとか…。
「まぁ、いいけど。で、偏屈店主さん、私売って欲しいものあるんだけど」
「誰が偏屈だ、誰が」
「ヴェルナー」
さらりと言ってのけるリリーに言い返すことが出来ない。コップにほんの数センチしかのまなかったのに、この視界の揺れ具合は何だ。しかも、そんなに悪いものではない。大体、普段どんなに飲んでも平気な顔をしている彼は、酔う、という感覚すらもあまり理解できていない。
「これが、酔うってことか」
少し新鮮な気はする。
「はいはい、変な感動に浸ってないで、今日のラインナップは何?」
「もっと優しい声ってのは掛けられないのかよ」
文句を言いながらもおぼつかない手つきで今日のリストを探す。が、かなり見当違いな所を探していたらしく、リリーのほうが先に見つけることになった。
「しっかりしてよ」
「…うるせ」
あきれた顔の彼女に悪態をつきたいものの、なんだかそういう気分ではない。
「………残念、今日は羽根ないのか」
「羽根?」
「うん。すぐにいることになっちゃって…。ないなら仕方ないから、またくる」
「おい、まだ少しあったぞ」
「本当?少しでいいのよ」
「ああ。…あんまり量が多くないから今日ははずしといた」
よたつきながらイスから立ち上がり、横の倉庫に顔を突っ込む。その様子をみて少し心配になる。
「…まあ、こんな状態でもお店開けてるのは、前よりよっぽど店の主らしいけど」
実は、ヴェルナーがどんな状態でも店を開けているのは、彼女がくるかもしれないからなのだが、そのあたりのことはまだあまり理解していない。
カウンターに座りながらヴェルナーが戻ってくるのを待っていたら、奥から声が聞こえてきた。
「ヴェルナー…?」
急に不安になって奥の倉庫を覗こうとするが、死角になって見えない。
「…手伝ってくれぇ…」
どうやら手伝いを求められているようだ。仕方がないなぁとカウンターを乗り越え、倉庫へ向かう。そこはまさに人外大魔境。わけのわからないものが多いヴェルナー雑貨店たらしめている理由がそこにある。
「ヴェルナーっ、どこーっ?」
自分の工房と勝るとも劣らないほど高く積み上げられた荷物の中を彷徨っていると、座り込んでいる彼がいた。
「何やってんのよ」
「うるせー。ほんと、お前他に言い方ねぇのかよ……」
力なく答えるヴェルナー。
「ほら…そこの袋ん中に、羽根あるからもってけ」
「そこの袋って……」
巨大な袋がリリーの腰まで膨らんでいる。
「こういうのって…『あんまり量が多くない』っていうの…?」
素朴な疑問が頭を掠めたが、彼女が求める羽根はかなりの大きさをもっていることを思い出し気を取り直した。
「あんなとこに袋の開け口がある」
手を伸ばしても届かないような位置に、かろうじて紐が見えた。少し躊躇したが、袋の上に乗るようにしてその紐に手を伸ばす。
「もうちょっと…」
悪戦苦闘していると後ろから押された。不意の攻撃にあえなく袋に沈没する。
「人んちの商売モン…上に乗んな」
「な、何すんのよ!あそこに紐があるからとろうとしてただけじゃない!」
酔いのせいで顔が赤いヴェルナー。それが、何とか体を起き上がらせたリリーの目の前にある。
「酒くさ…」
「傷モンにしたな…?」
「ちょ…ヴェルナー、目が据わってるよ…」
冷や汗を流しながらリリーはその場を退こうとしたが、ヴェルナーがいるので上手く動けない。
「退かないともっと傷物になっちゃうでしょ!……傷がついた分買うから、退いてってば」
無言でこちらを見つめている視線が怖くなって、気の弱い発言まで飛び出す。が、彼は退かなかった。ただ、見ている。
「……ヴェルナーってば…」
「……ん」
何事か呟いたような気がした。けれどそれは彼女の耳にまで届かず、その背に柔らかさを感じていた。なにが起こったのか把握する前に男の唇が彼女を支配する。何か言おうと唇を開けば、彼の吐息がリリーの中に入り込む。
「……!」
不思議な感覚。柔らかい羽根の上、それより柔らかい唇。嫌だと思った酒の匂いも、気にならない。
憧れを持っていたキスが、こんな形で実現するなんて。
戸惑いや驚きの裏にある喜び。あのヴェルナーが、私に口付けてる。
「……」
しばらくそのままだったが、不意にヴェルナーが動いた。どきりと身を固くしたリリー。いくらなんでもそれ以上はちょっと、と警戒をしていると寝息が聞こえてきた。
「…へっ?」
よく見ると気持ちよさそうに眠っている。
「なぁんだ」
はっとして自分の唇を抑える。心のどこかに残念だと思っている自分がいる。
「うそうそ!」
頭を振って立ち上がった。眠りこけている男をどうしようかと思ったが、結局そのままにしておくことにした。痩せてはいるが昔冒険者だったということだけあって、それなりに筋肉はついている。そんな彼を動かしていくのは至難の業だ。
「ここなら羽根がお布団代わりになるでしょ」
周りを見渡して、使われていない布を見つけてそっと掛けてあげた。
「風邪、引かないようにね」
耳元で囁いてその場を後にした。
「というわけで、今日こそアードラの羽根売ってもらうからね!」
「なんなんだよ、その『というわけで』、ってのは」
すっかりいつもの通りになったヴェルナーは、例の如く不機嫌なのか機嫌がいいのか分からない口調で返してきた。
「だっておととい…」
「おとといぃ?お前、来てたのか?」
「…はい?」
「旦那に新酒飲まされたあたりから、あの日の記憶ぶっとんでるんだよな。起きたら倉庫で布かぶって寝てるし。おかげでアードラの羽根、かなりダメにしちまった」
「……」
「俺が記憶飛ばすなんてなぁ…。初めてだよ。ハインツの旦那には悪いが、あの酒はまともな奴には飲めないって言わなけりゃな……って、どうしたリリー」
「ほんとに…」
じろりと睨んで聞いてくる。
「ほんとーに、覚えてない……の?」
「ああ。綺麗さっぱり」
「………」
なにも言わなかったが、リリーがかなり怒っていることはよく分かる。
「お、おい…」
「……」
「どうした?…なんか、あったのか?」
「………ない」
じっと彼を睨みつけながら呟く。
「忘れて欲しくないこと……、あったんだよ」
唇がわなわなと震えている。怒りのためか、顔が真赤だ。
「…俺、一体何をしたんだ?教えてくれよ」
「自分で思い出しなさい!!」
傍らの地球儀を持ち上げてヴェルナーに向かって投げつける。直撃を食らった彼はイスごと後ろにひっくり返った。体を起き上がらせる頃にはもうリリーはドアから飛び出していってしまっていた。
「……っつー」
打ったところをさすりながら起き上がる。
「なんだってんだよ」
憮然とした顔で転がっている地球儀を持ち上げた。すこしひしゃげている。
「なんだよもう。踏んだり蹴ったりだ」
ふと視線を和らげる。
「あの時寝ちまったのは、ヴェルナー様一生の不覚だな」
戸につけてあるウインドベルが、まだ鳴り続けていた。
雑貨屋を飛び出したリリーはその足で金の麦亭に駆け込んだ。
「ハインツさん!!」
「なんだ、姉さん顔色変えて」
「あんなお酒、絶対に、絶対に絶対に絶対に作んないで下さい!!」
「あんな酒…、ああ、蛇酒ね」
「そうです!」
怒り心頭のリリーを見て、こりゃ何か相当なことがあったと心の中で思うハインツ。
「あの酒のことしってんのはシスカとヴェルナーだけだが…シスカはずっとここにいたから、ヴェルナーと何かあったんだな」
滅多に酒場に顔を出さない変わり者の青年が頭に浮かぶ。確かに、あいつなら何かリリーにちょっかいかけかねない。
「わかったよ姉さん。まあ、シスカですら二日酔いになったってんだから、かなりやばい酒だとは思ってたしな」
「あら、でも飲んだときはとってもおいしかったわ」
常連のシスカが笑う。そんなシスカをリリーは悔しそうに見つめた。
「…やれやれ、これじゃせっかくのあのお酒、もう飲めなくなっちゃうのね」
「すまんなシスカ。なんだったらお前に全部譲るが」
「ほんと?」
顔を輝かせているシスカを見ながら、どうやらあの酒がこれ以上ヴェルナーのところに行くことはないだろうとほっとした。またあんなことが起こった日には、店を跡形もなく破壊しかねない。
「ありがとう、ハインツさん」
「いいってことよ。客がみんな撃沈しちまうような酒、出しても意味ないしな」
豪胆に笑うマスターにリリーも吊られて笑った。
実は、ハインツよりも強いのは彼女自身であることは、彼女は気がついていない。
「あーっ!」
突然の声に店の中が一瞬とまる。直後にリリーは駆け出していった。
「騒がしいねぇ」
「ま、それなりに平和だってことだ」
そして、リリーはヴェルナーのところにあった酒瓶をとりに、またひたすら職人通りの坂を駆け上がるのだった。
Ende
実は私、酒に酔うという経験がありません
飲まないわけじゃないくて…酔わないんです(笑)
父親からザルよりひどいツツの称号をいただきました(いらないなぁ)
そんなことよりハインツさんですハインツさん
大塚明夫の素晴らしいお声……
悦ですねー
メタルギアのスネークもいいですが
こんな感じの酒場のマスターでも素敵です
って、話の後書きになってないや(笑)
ツツ講座から大塚明夫を熱く語る、になってるし…
ま、いっか(よくない)